
最初から読み進めていく本ではなく、座右において間違った言葉の使い方をしないように、時々たちかえって読む本ではなかろうか。
どういうものが出ているかというと、例えば「綺羅星の如く」。これは「綺羅、星の如く」と読まなければならない。「綺羅星」という星はない。「綺羅」とは、綾織の絹と薄絹の意で、美しい衣服のこと。転じて衣服の美しい華やかさを言う。「綺羅」がきらきら輝くの「きら」と勘違いされることがよくあるようだ。
もうひとつ「夭逝」は「ようせつ」ではなく「ようせい」。「夭折」という別の言葉と同じく、若くして死ぬことだが、後者が「ようせつ」で、「夭逝」も同じ読み方にしてしまう人が多いらしい。
このような勘違いの例が、ぎっしり詰め込まれている。この本のいいところは、勘違いを指摘すると同時に、どうしてそういう勘違いが生まれるのか、その理由が明記されていることである。
「一章:意味・ニュアンスの取り違えとことばの誤用」「二章:慣用表現の言い間違い」「三章:故事・ことわざの勘違い」「四章:語法の間違い・勘違い」「五章:避けたい重ね言葉」「六章:漢字の読み間違い」「七章:漢字の書き間違い」の七章構成。

「言葉の海」はノンフィクションの歴史小説のジャンルに入りますが、この小説はこと日本語の最初の辞書作りの話なので、本ブログでは「言語/日本語」のカテゴリーに入れます。
日本語の大きな辞典といえば今では。「広辞苑」を挙げる人が多いが、ほかにも「広辞林」「言海」がある。「言海」は大槻文彦によって作られたもの。この小説は、その大槻文彦の生涯を、「言海」作成に焦点をしぼって書かれたもの。
文彦は日本語辞書の作成を明治の近代国家確立を象徴する仕事と位置づけ、生涯をかけて渾身の力を注いだ。ヨーロッパの近代国家には、それぞれの国の言葉を集大成した辞書がある。それらは文彦の目標であった。また、辞書の作成には、日本語の文法が正確に把握されていなければならない。しかし、当時、日本語の文法を体系化した仕事はまだなかった。文彦はその両方にとりくむ。
1875年(明治8年)、当時文部省報告課に勤務していた大槻文彦は、課長の西村茂樹に国語辞典の編纂を命ぜられ、この仕事を開始した。1882年(明治15年)に初稿を成立させたが校閲に4年をかけ、完成したのは1886年(明治19年)であった(収録されている語数は39103語、固有名詞などは扱っていない。本編の辞書部分の他に漢文で書かれた「言海序」、西洋文法を参考に日本語を体系化した「語法指南」、索引の仕方を書いた「索引指南」なども載っている)。
「言海」はもともと文部省自体から刊行される予定だったが、予算の関係で出版が立ち消えしそうになり、結局、文彦が算段して自費出版することになった(明治24年)。文彦没(1928年[昭和3年])後に、兄の如電(修二)によって改訂された『大言海』が発刊された。
なお、文彦の祖父は玄沢という蘭学者(杉田玄白、前野良沢を継ぐ)、早くから開国論を唱えた父盤渓は漢学者。文彦は学者の家系である。この小説では、東京の芝公園の紅葉観で開催された「言海」出版祝賀会から始まる。祖父、父との関係、友人の富田鉄之助、箕作鱗祥のこと、若くして英語と数学を学んだ洋書調書(洋学の教育と研究のための幕府の機関、前身は葉書調書)、仙台で入学した養賢堂(藩校)、横浜での英語の修業、鳥羽伏見から奥羽戦争、宮城師範創設のことなどを織り込んで、明治の国学者の偉業をいきいきと描いている。

過去から現在にいたる日本語の「ゆらぎ」を考察。日本語の奥行きの深さは、いろいろな側面から語ることができるが、言葉をひとつひとつとりあげて、その変遷をたどるという視点はわたしにとっては得難いもので、勉強になった。
たとえば、「電覧」という言葉があり、この言葉自体がいまはもう使われないもので、その意味は「人がもの見ることに対する敬語」であるにもかかわらず、「ひととおりざっと目を通す」という意味で使っている人がいる。
ときおり目につく「店がはねる」「芝居がひける」などの誤った言い方にも苦言を呈している。もともと「ツルノハシ(鶴嘴)」だったのにいまは省略形で「ツルハシ」になってしまっている。平清盛は「たいらのきよもり」で「の」が入るが、足利尊氏は「あしかがたかうじ」で「の」は省略されている。このような省略を、著者は「無用の合理主義」と呼んでいる。
他にもたくさんの指摘がある。このようなことができる能力をもった人はそうはいないので貴重だ。著者は、敏感な触角で、文献、小説などにあらわれる言葉の蒐集を行っては、辞典(『言海』『大言海』『広辞苑』『広辞林』、さかのぼっては『日葡辞書』『ヘボンの辞典』『節用集』)にそれがあるのかないのか、どのように整理されているのかを検証している。
それでは、「闇から牛」「三十一字」は、本当は何と読むか。「言語同断」は間違いだろうか。(「やみからうし」「みそひともじ」ではない)。トランプの「ジャック」は日本語ではどう表現したらよいのか(「キング」は「王」、「クイーン」は「王妃」)。正解は本書で。

本書のねらいは、著者が幼少の頃、父母によって育まれた言葉を回顧し、また家庭の外で得た言語体験を懐旧の念で記憶のなかから取り出し、それらの作業から現代の日本語の激しい変容をいかに観察しうるか、文献のなかにそれをもとめて記録する作業である。それは、言葉が変化していく現象をとらえて記録し、語誌に役立てることでもあるという。「あとがき」で述べられている詞の世界の、著者の散策法である。
構成は次のようになっている。「追憶の中のことば」「漢語の素養」「近い過去・遠いことば」「誤用・俗用・正用」「語誌探求」。著者の研ぎ澄まされた言語感覚が随所に示されている。父母によって育まれた言葉としては、「おんぼりと(何の気兼ねもなくの意)」「はがやしい(もどかしい、じれったいの意)」「はだこ(肌に直につける下着)」「飯台(食卓のこと)」などの言葉があげられている。
巷間に、「住みづらい」「生きづらい」という言い方がよくされるが、そのような言い方はかつてはほとんどなかった、「住みにくい」「生きにくい」である。「寝台」は、いまはみな「しんだい」と読むが、むかしは「ねだい」だった。最終電車を昔は「赤電車」といい、そのひとつ前の電車を「青電車」と言った。公園などにある長いベンチは、「ろは台」と言われていた。漢字・漢文の常識の退廃にも、言及している。
他にも、興味深い話がたくさん。言葉の変容が大正、昭和、平成の国語辞典の項目や記述に、また古典的小説のなかに証言をほりおこされている。
本書はエッセイ風に編まれ、それゆえに指摘が断片的だ。著者のこの分野での業績をもっと体系的に知りたいものだ。
漢字に関して、常識的なこと、例えば、その読み方に、漢音、呉音、唐音、慣用音があることなどはもちろん、あまり知られていないこと、例えば、中国の簡体字と日本語で使われる漢字の略字の考えとの相違、漢字には助詞、前置詞、関係代名詞を使わないで長い言葉を作る機能があること(一つの極端な例:県立広洋高等学校創立三五周年記念秋季大運動会準備実行委員会企画小委員会広報部会大三回中間報告草案検討会議)まで、さまざまなことが、体系的に書かれています。今後、漢字がなくなるかどうかについても論じています。著者は、そこで、「終には必ず廃せられて、久しくは存する能わざるも、暫時必ず存せられて、遽か(ニワカ)には廃する可からず」という中国の代表的言語学者の意見を引いています。面白いです。
構成は4部からなる。「Ⅰ うっかり読み誤りやすい漢字」「Ⅱ 同じ意味でもちがう漢字」「Ⅲ 漢字から仮名が生まれるまで」「Ⅳ あなたは漢字の変化についていけるか」。
全体のコンセプトは、漢字文化に囲まれているわたしたちは、それでは漢字のことをよく知っているのかと問えば、案外何もしらないのではなかろうか、と疑問を発し、それをセミプロの視点で明らかにしていこうという姿勢です。漢字はなぜ漢字と言うのか。日本人は漢字をいつごろから使いだしたのか、使いこなせるようになったのか、漢字はどれくらいの数があるのか、日本でつくられた漢字(国字)はいくつあるのか、「蟲」の字と「虫」の字との関係は。「森」はどうして日本でだけ「モリ」を表し、中国ではその意味でつかわれないのか、画数が最も多い漢字は何か、漢字と仮名をどれくらいの割合でまぜると読みやすい文章になるか、などなど。
わたしの姓名のなかの一字である「」は「崎」と微妙に違う。戸籍では「」が使われていますが、生まれてこのかた、「崎」を使ってきました。2つの漢字はどう違うのか。知らなかったのですが、この本でわかりました。
要するにアマチュアの素朴な「疑問」によりそって、それらを「Q&A」形式で安易に説明するのではなく、ある程度、体系的に、論理的に答えようとしているのがこの本です。

平成21(2009)年3月に公示された新指導要領は、平成25(2013)年から高校学校の英語の授業は英語で行うことが義務付けられた。
著者は、この教育方針に異論を唱え、日本の教育環境で英語の授業を行う場合には文法と訳読を中心にすべきであり、英語で授業を行えば、その内容は中途半端になる、英語の文章を本当に理解しているのかがはっきりしなくなり、文章の内容がよくわからないことを質問するのも難しくなり、またその質問に英語で回答されても理解できない、ことになりかねない、コミュニケーションのための英語(話せる英語)と言うことがしきりに喧伝されるが、現在の教室の規模ろカリキュラム編成で、それは無理、しかkり読めるようになってこそ、上手な英語が喋れるようになる、と唱えている。
もし、本当に英語で授業と言うことになれば、授業内容は低下し、知的訓練の質は維持できなくなる、と懸念している。このような主張をしたうえで、著者はさらに訳読と翻訳との違い、について論じていて、ここは参考になる。とくに、日本語、英語の背景にある文化の相違、それぞれの言語に固有の作法、翻訳元と翻訳先のどちらを尊重するのか、訳語の選択の問題、連語関係に着目することの重要性、など。
要するに、高等学校までの学校英語は、文法の学習、「読む」力の涵養に力を入れるべきで、「読む」力をつけるには、どのような勉強を行うべきか、教室で「読む」力を鍛える訳読とは何か、英語と日本語との間にどのような関係を考えるべきか、そもそも「コミュニケーション」とは何なのかを、考えようというのが、本書の基本的スタンスである。

幼少の頃から多彩なことば遊びを経験してきた(犬棒かるた、数え唄、百人一首、暗号解き、小説の書き出しの暗記など)著者が「日本語が危ない」との危機感から、日本語のユニークさにもっと関心をもってこの本を書いた。
しゃれ、比喩、漢字の読み、漢字の分解、回文、なぞ(二段謎、三段謎)、いろは歌、無理問答、折り句、記憶術、替え歌などさまざまな切り口で、ことば遊びを楽しんでいる。わたしたちも子どもの頃から親しんできたものがたくさんあるが(もちろん知らないものはたくさんあった)、このように分類して紹介されると、あらためてその多様性、日本語の豊かさに驚かされる。
回文(「竹やぶ焼けた」のように上から読んでも下から読んでも同じ文章になる)では、ものすごい例が紹介されている。確かめるのもめんどうな、あきれるような例である(pp.117-8)。いろは歌は、ひらかなを一度きり使ってくみあわせ、ひとつの詩歌をつくるおちうものだが、これは予想外にかなり作れるものらしく、新聞社や雑誌社がかつてコンクールをしていて、入選作が紹介されている。200も300も、否、数千も可能らしい(p.143)。たまげてしまった。
著者自身がいくつかの自作を紹介している。三段謎では、多くの自作「作品」を掲げている。たとえば、「野村野球とかけて朝鮮半島と解く。こころは長い島にまけたくない」。折り句では、この新書の出版社である「いわなみしょてん」を折り込んで「『い』ずの海『わ』たつみの青『なみ』白く『しょう』ねんの凧『てん』高く舞う」がそれである。
この種のことば遊びには、すぐれた「先行」業績があるようだ。鈴木棠三『新版 ことば遊び辞典』(東京堂出版)、篠原央憲『いろは歌の謎』(カッパブックス)がそれ。著者は部分的にその業績に依拠した考察をしているが、議論はより発展的だ。

日本語には女性に特有の言葉がある。この「女ことば」とは一体何なのだろうか。著者は本書で多くの人の常識なっている「女性たちが話してきた言葉づかいが自然に女ことばになった」という考え方の問題点を多面的(多様性の承認、規範、知識、価値)に考察している。
具体的には種々の言説をデータとして分析し(歴史的言説分析)、鎌倉時代から第二次世界大戦までの女ことばの歴史をたどりながら、女ことばがつくられてきた道程が明らかにしていく(歴史的言説分析とは、特定の言説が意味をもつようになった政治や経済的な背景を探るという方法)。
その結論は、要約して言えば、女ことばの形成はまず鎌倉時代から続く規範の言説によって女性の発言を支配する傾向が、江戸時代に強化され、さらに現代のマナー本に見られるような女らしさとの結びつきの強調につながっているということ、明治期には近代国家建設という課題のもとで国語理念が男性国民の言葉として形成され対極で「て・よ・だわ」などの具体的な語と結びついた女学生ことばがひろく普及したこと、くだって戦中期には、アジアの植民地の人々同化政策や女性を戦争に動員する総動員体制のねらいとして女ことばが天皇制国家の伝統とされ、家父長制の象徴である「性別のある国語」が強調されたこと、さらに戦後は、占領軍のもとで男女平等政策の推進、天皇制や家父長制の否定のなかで女ことばを自然な女らしさの発露と再定義する言説が普及し、女ことばに日本の伝統を象徴することが期待されるにいたったこと、である。
したがって著者によれば、「日本語には女ことばがある」というとき、それは、実際に日本女性が男性と異なる言葉使いをしているという意味の「ある」ではなく、言語イデオロギーとして言説によって歴史的に形成されてきた、ということなのである、と(結論部分を含め以上、pp.327-8)。
「第1部 『女らしい話し方』-規範としての女ことば」「第2部 『国語』の登場-知識としての女ことば」「第3部 女ことば礼賛-価値としての女ことば1」「第4部 『自然な女らしさ』と男女平等-価値としての女ことば2」。

日本語にまつわる事柄を、著者がつれづれに書いてきたものを編集してできあがった本。
「ことばは深い」「ことばと遊ぶ」「ことばの道草」「ことばの知恵」とグループ分けされているものの、全体をながれるコンセプトがいまひとつはっきりしない。
読者はこのような本に出会うと、いくつか初めて分った事柄(「転失気」「二豎(にじゅ)」の意味、「狼狽」の語源など)、曖昧だったことをすっきりとさせてくれた事柄(大乗仏教と小乗仏教の区別)、もうすでに知っている事柄、というふうに仕分けしながら読み進めることになる。すでに知っている事柄でも、こういうふうに書くとより理解が深まるものか(句読点の付け方)、と感心させられることもあった。
ひとつの事項が2ページほどでまとめられているので、電車のなかで、あるいはちょっとした開いた時間に読むにはまことに都合がよい。
最後に「小説家の眼」として松本清張の「黒地の絵」を分析し、この小説のテーマ、モチーフを浮き彫りにしている。この分析は面白く、こういう分析をもっとやってくれれば、読者としては有難い。
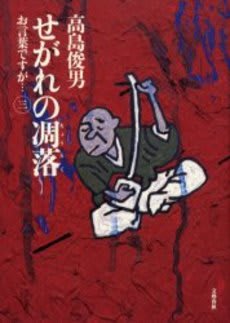
シリーズ『お言葉ですが・・・』はいずれも面白いのですが、この巻はなかでも話題が豊富です。
いくつか拾ってみると。11月3日が文化の日で、これは憲法公布の日ですが、同時に天長節(明治天皇の誕生日)、公には明治天皇誕生日と文化の日とは何の関係もないことになっているのですが、「しらじらしい」説明、とあります(「緑の日」)。
7月と8月と続けて31日が続くのはどうしてなのでしょうか、もともと1年はMARCH(日本では3月)に始まり、FEBRUARY(日本では2月)に終わるらしいのですが、日本ではJANUARYを1月として数で数えるようになっているので変なことになっています、和暦に「月」の名称が残っているので混乱するもとですが、もともと陰暦は月で数え、15夜は毎月の15日目に、3日月は3日目にというふうになっていたとか(「ジュライ、オーガストの不思議」)。
戒名は自分でつくってもよいが、わずかな例をのぞくと、そうなっていない、戒名をみるとだいたいの値段がわかる(「院殿大居士一千万円」)。墓誌銘と墓碑銘の違いは何か(「墓誌銘」と「墓碑銘」)。臥薪嘗胆という語の由来について、『史記』『呉越春秋』には「嘗胆」はあるが「臥薪」はない、「臥薪」が「わが身をくるしめてこころざしをはげます」の意に用いられ、「嘗胆」と結び付けられて「臥薪嘗胆」という語ができるのは『史記』などより千年も後のこと(「臥薪嘗胆」「日本の辞書は甘い」)。学者、研究者は「位相」という用語が好きらしいが、こけおどかしにすぎないのではないか(「『位相』ってなんだろうね」)。
他に「五十をすぎたおばあさん」「『ゲキトバ』新説」「千円からおあずかりします」「『食う』の悲運」「せがれの凋落」「みどりみなぎる海原に」、いずれも好エッセイです。そして為になるお話です。

「漢字」について、眼からウロコがおちるような思いです。
「漢字は、日本語にとってやっかいな重荷である。それも、からだに癒着してしまった重荷である。もともと日本語の体質にはあわないのだから、いつまでたってもしっくりしない。しかし、この重荷を切除すれば幼児化する。ヘタをすれば死ぬ。この、からだに癒着した重荷は、日本語に害をなすこと多かったが、しかし日本語は、これなしにはやってゆけないこともたしかである。腐れ縁である。・・・日本語は、畸型のまま生きてゆくよりほか生存の方法はない、というのがわたしの考えである」(pp.245-6)。これが著者の結論ですが、本書ではこの結論こ至る裏付けるの議論が展開されています。
簡単に説明すると、日本語はもともと文字がなかったので、比較的隣国であった漢字でそれを代行しました。これが不運の始まりでした。独自の文字が発達する可能性がなくなったのです。
漢語の音節は、英語ほど多くないらしいです(1500くらい)。しかし声調があるので複雑です。漢語の単語は原則として一音節です(だが、二音節で安定する性質をもつ)。一つ一つの単語に個別の文字があるので、漢字の読みは全て一音節(これが日本に入ってくると二音節になる)。
日本語は開音構造で、全ての音節が母音で終わります。しかも母音の前につく子音は一つだけです。日本語の発音は貧しい、くわえて、漢語は語の形が変化しない、日本語は変化する、変化する言語を漢字で書きあらわすのは至難の技です。
漢字は漢語を書きあらわしたものでした、それを日本語のなかで使うには相当面倒な加工をほどこさなければならなかったわけです。
さらに、漢字の読みの音には呉音と漢音があり、訓読みも規則性もないまま次第に定着しました。そして假名(ひらかな、カタカナ)が生まれました。
漢字は本来漢語と一体のものであり、中国の文化とも密接に結びついています。文化先進国だった中国が、そして漢字が崇拝され、それを操る人が尊敬されました。しかし、漢字は和語とは縁がなく、馴染みもないにもかかわらず、それを無理やり利用したたため、日本語の表記法は歪になったというのです。
明治に入って西欧の語を日本語に取り入れるにあたって、漢字に翻訳されて日本語になったものは物凄い数になるそうです。その際、それらがどのような音で発音されるかについては、無頓着でした。したがって、同音異義語が増え、それらは文脈のなかで漢字を想起して意味を把握するという、世界でも稀にみる不思議な特質をそなえるにいたりました。
漢字廃止論が明治から昭和にかけて根強くあったのも、ある意味で無理からぬところがあります。昭和に入って漢字を廃止をめざして当用漢字(常用漢字)が設けられましたが、その流れは現在、止まっています。
逆にワープロソフトの普及により、JIS規格が漢字文化を主導する、とんでもない流れがでてきています。著者は漢字を廃止することはもうできないので、「かな」を主体にし、漢字を従にした日本語を展望しています。

なかでは、人名用漢字の変遷が興味深かったです。内容を整理すると、当用漢字が制定されたのが昭和21年、改訂戸籍法はこれを受けて昭和23年に、「命名に用いる文字は当用漢字の範囲内」と定めました。これ以降、昭和26年5月に内閣告示の「人名用漢字別表」で92文字が認められ(「弘」や「彦」など)、さらに昭和51に法務省は人名用漢字に28字を追加し、平成16年6月法制審議会人名用漢字部会は488字追加案を最終決定しました。
この間にあった調査、エピソード、著者の意見が書かれています。国が決めても、それに従わないケースは多々あり、漢字はしたたかに生き残ってきた、というところが面白いです。(「苺ちゃん、雫くん」「法務省出血大サービス」「『人名用漢字』追加案」)。
「喧々囂々」「侃侃諤諤」という4字成語がありますが、人はときどき「喧々諤諤」と間違うことが多かったです。しかし、広辞苑もこれを認めたらしいです。間違いでも普及し、一般化すれば、市民権を得る好例です。(「ケンケンガクガク?」)
「文化の罪人岩波文庫」という指摘に留飲をさげました。。戦後、岩波文庫は現代表記を採用しました。その結果、そうしてはいけない個所まで現代表記にしてしまい、まがいものを世に広めることとなりました。(pp.139-140、pp.209-210)
他に、川端康成の「雪国」で、「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」の「国境」をどう読むのか?「こっきょう」なのか、「くにさかい」なのか?この点についてご本人の証言があって、「コッキョーのつもりだったよう」なのですが、上越線清水トンネルを抜けて新潟に入った場合、それを「コッキョウ」とはいわないのが普通、という指摘も、ひとつのエピソードとして興味深かったです。
西暦と和暦との関係を把握するのが難しく、国文学を専門としている人もしばしば誤解している例がひかれていました。正直のところ、これについては、わたしも同類でした。
というのは、私の誕生日は12月14日なのですが、それを言うときにしばしば「赤穂浪士討ち入り」の日です、と付け加えていました。そう言いながら、なんだかおかしい、とは感じていたのです。というのは赤穂浪士討ち入り日には江戸に雪が積もっていた、と言われているからです。12月14日に東京で積雪? 絶対ないとはいえないが、いくら近年暖冬傾向とはいえ、まずないことです。
そうか、赤穂浪士討ち入りの12月14日は陰暦だったのです。新暦の12月14日は陰暦では1月30日です(p.171)。それならアリです。ただし、もうわたしの誕生日とは言えません。今回、そのことがわかりました。
表題の「芭蕉のガールフレンド」は「智月(ちげつ)尼」のことです(p.100)。手紙の相手が女性であったときに、相手のことをどう呼ぶか? それが問題です。

圧巻は「これは賤しきものなるぞ」。新潮文庫の太宰治『津軽』への注釈について。太宰治の『津軽』に注釈がついているのですが(W教授による;本書には実名が載っています)、それがひどいもので、かなりの部分が広辞苑からのまる写し、あるいは意味不明の記述で、なかには『津軽』を読んでいないのでは思わせるものもあるというのです。
著者が点検した『津軽』は平成9年11月20日発行の89刷り。上記の記事を平成11年1月28日付の「週刊文春」に書いたところ、平成11年6月10日付の『津軽』93刷りでは、著者の指摘した個所が訂正されていた、ところが訂正は基本的にその部分に留まり、他の個所はそのまま。著者はいくつか「例」をあげたまでなのに、W教授ないし新潮編集部はそこだけ変更し、注釈全体の見直しをしていないらしいのです。著者は注釈をつける作業がその場しのぎのやっつけ仕事になっていることにあきれています。
「『津軽』の注釈を依頼されたからには、この作品が書かれた昭和19年の日本について、またこの作品の舞台である青森県について、またこの作品の作者である太宰治について、すこしは勉強した上で、すこしは心をこめて。書いてはどうか」(p.105)と指摘しています。世の中にはひどい仕事ぶりがあったものです。
関連して、戦前の三田村鳶魚が大仏次郎の「赤穂浪士」、土師清二の「青頭巾」など江戸時代のことを書いた小説を時代考証し、こてんぱんにやつけたことがあったのを紹介しています(「江戸博士怒る」)。
さらにベストセラーになった妹尾河童の「少年H]の中身が間違いだらけであったことを、山中亘・山中典子「間違いだらけの少年H」の指摘を借りながら、書いています(「少年Hのタネ本は『昭和二万日の全記録』[講談社]で、これをつまみ食い的に利用して話をつくったらしい[p.115])。
要するに、時代小説にしても、「少年H」にしても、今の時代感覚でストーリーを成り立たせようとするから、とんでもないことになってしまうというのだ、という。なるほど。
本書ではこの他、赤とんぼの歌詞の三番「十五でねえや」はを分析して、「ねえや」とは、また「お里の便りはたえはてた」で、便りを出していたの誰かを推測しています。この記事は面白かったです。
他に「広辞苑神話」「子供、子ども、こども」「『名前』の前は何の前?」「棒嫌いの系譜」「ヤブ医者の論」が印象に残りました。
著者は年来の主張を本書にも織り込んでいて、それは和語に漢字をあてはめてありがたがっている、あるいはそこに意味をもとめるのは、ナンセンスだということで、本書でも何度もそのことを指摘してます。傾聴に値します。

著者の「お言葉ですが・・・」シリーズ(文藝春秋)が10巻でひとくぎりとなり、そのまま終わるのかと残念に思っていたところ、別巻が出ていることがわかりました。出版社は連合出版に代わっていました。
また、内容は、従前の文藝春秋版が「週刊文春」のコラムに掲載された記事をまとめたものであったの対し、別巻は著者があちこちに書いたまま放置されていた記事、エッセイを編集したものになっています。
このため、内容は質、量とも、統一性がやや欠けています。それでも、高橋精神は健在で、面白いです。
印象に残ったのは、「向田邦子の強情」「『上海お春』と鴎外の母」、それに「むかしの日本のいくさ馬」。「向田邦子の強情」では向田さんが独特の言葉使いをしているのに著者が共感をもって、喜んでいます。「羽目板」「(貯金を)積む」「市電」「字引」「明治節」などなど。さりげないが、譲らない言葉使いがお好みのようです。
「『上海お春』と鴎外の母」では、鴎外を溺愛する母と嫁との確執に触れています。
「『水五訓』の謎」は謎解きのプロセスに興味がわきました。ある講演会で著者が「水五訓」が黒田如水の作なのか、王陽明の作なのかを問われ、即答できなかった著者がその真実を洗っていくのです。それは黒田如水でも王陽明でもなく、どうやら昭和初年ごろにいた大野洪聲という人であった、と結論づけています(p.55)。
「抔土(ほうど)未だ乾かず」「彼女(かのじょ)」に関するいつもの言葉の穿鑿も、わたしにとっては貴重な、価値のある分析がなされていて、参考になりました。

この巻では「赤鷲の謎」の章が抜群に面白かったです。内容は戦争中の歌「加藤隼戦闘隊」の歌詞をめぐる著者と読者のやりとりです。読者との応答のなかで加藤隼戦闘隊隊長加藤健夫中佐のこと、この歌ができた経緯、歌詞のなかにある「赤鷲」の意味が明確になっていくプロセスが面白かったことでした。
また、わたしがほとんど知らない戦時中の飛行機(戦闘機)に関する叙述が興味をひきました。わたしも昔、子供のころ、戦闘機、軍艦のプラモデル作成に夢中になった時期がありましたが、そういう時期が戦後昭和30年代から40年代にあったとの指摘が本書のなかにあり(p.231)、わたしはその最中にいたのでした。
この章ではのもうひとつ、土井晩翠「荒城の月」の二番にある「植うる剣」の解釈をめぐる議論があります。「植うる剣」とは何なのかで、著者の解釈、読者諸氏の理解、そして学者の見解が整理されています。結論はよくわからないのですが、著者は「守備のために城壁や陣の周囲などにさかさまに植えてある剣」ではないかと、仮の結論を示しています。
本書を読み進むうちに最後のほうになって、著者が怒っています。著者は「不戦と恒久平和を誓う」「正しい歴史認識」という言葉が大嫌いだそうです。したがって、そういう言葉が出てくる、記事、文章をコテンパンに叩いています。要は現在の価値基準で過去をさばくことに嫌悪を示しているのです。「たしかにあれは(太平洋戦争は-引用者)、無謀な、愚かな戦争であった。しかしそれは現在から見てのことである」と著者は書いています(p.278)。
表題の「イチレツランパン破裂して」はよくわからなかったのですが、内容は日露戦争の頃にはやった数え唄(お手玉)「イチレツランパン」に関する考察です。
新知識は、昔の文人は自分の「勉強部屋の名前」に室号をつけていたようで、例えば漱石は「漱石山房」、芥川は「澄江堂」、荷風の「断腸亭」などです(pp.148-149)。遠藤周作の「狐狸庵」もそうだとか。
著者は中国文学者なので、中国の古典、漢字の発音、成りたち、関連して日本語(発音)に詳しいです。呉音、漢音、唐音、入声(にゅうしょう)、和語、字音語(中古漢語[六朝隋唐期のシナ語])など勉強になりました。









