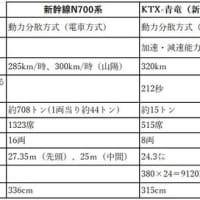今回は雑誌記事の受け売りです。
週刊ダイヤモンドに、
「大人のための最先端理科」生命科学 大隅典子
と言う記事が時々掲載されています。大隅典子さんは東北大学教授です。
2023年12月23日/30日合併号のテーマは「体外受精の『リスク』は子や孫世代に伝わるのか」です。これは、論文誌に最近掲載された京大の篠原隆司教授の論文の紹介です。ただし、この論文で行われた実験は人ではなく、マウスを用いています。人による実験をする(出来たらの話ですが)と、少なくとも半世紀の時間がかかるので、実質不可能です。
実験の結論は「顕微授精だけでなく、体外受精(IVF)のみでも、子ども世代(F1)以降の健康に関してリスクがあることをマウスで示しています。一見、正常に見えるF1世代を交配して得た孫世代(F2)やひ孫(F3)世代に携帯的な先天異常が出現する他、見た目は正常なF1世代でも行動異常は認められ、F2でも同様との結果でした」というものです。
(「携帯的な」という言葉がありますが、もしかしたら漢字変換の間違いで「形態的な」でしょうか?)
つまり「体外受精で生まれた子は、見た目は正常でも、行動異常は認められた」そうで、「正常そうに見える子を交配してできた孫やひ孫に先天異常が出現するリスク」があるそうです。繰り返しますが、これはマウスを用いた実験です。
卵子や精子を体外に取り出して操作する時に、何らかの影響を与えるのでしょうか? そうであっても、別に不思議とは思わない。
人間の体外受精は広く行われているので、他人事では無い。体外受精を職業にしている人もいるので、この論文が本当なら影響は大きい。しかし、人間で確認するには数十年かかるので、数十年先に結論が出たとしても手遅れです。これは重い問題です。
出来るなら、体外受精のリスクは避けるべきでしょう。しかし現実問題として、マウスを用いた実験を信じて、体外受精のリスクを避ける人がいるかどうか? 法律で禁止するにはマウスの実験だけでは無理。マウスよりも人に近い、より良い実験方法があると良いのですが。
2024年1月9日