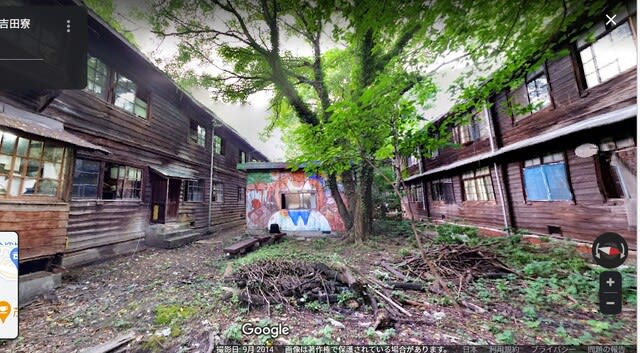中国人は穴を見つけるのが習性
最近TVを見ていたら、東大大学院の留学生の多くが中国人という話題を放送していた。中国人は隙間というか穴を見つける天才なので、直ぐにこういう情報は知れ渡る。
最近、国際免許証への切り替えが日本では容易だと言うことで、東京の運転免許試験場に中国人が並んでいるとTVでやっていた。旅行中の中国人でも切替できるらしいのが日本の役所らしい。また、ゲームPC部品の販売で、多数の中国人が並んで混乱したと報道されているが、これはたぶん転売が目的なのでしょう。私はこういう住みよい隙間を見つけて暮らしている人たちを「ごきぶり」と呼んでいます。
穴に群がる中国人ではなく、日本を貶す中国メディア
日本で発行している中国系のメディア(ネットだけ?)が、国際免許証を取りに来る中国人が列を作っている件を取り上げていた。この中国メディアは、「穴に群がる中国人」とか「日本人は『上に政策があれば下に対策有り』という言葉を知らないのか」と書いていた。そして、「日本は何故穴を埋めないのか」と他人のせいにするのは中国人らしい。
日本に住んでいるので、日本の役所は対応が遅いし、穴を作るのが得意という日本の事情を良くご存知で。特に国土交通省は、車種区分などあちこちに穴を作っている。
中国人激増の東大大学院
東大の留学生に中国人が激増している件で、「東大全体の留学生の3人に2人は中国人」「特に中国人留学生が多いのは大学院だ」「大学院は同じく約1万5000人のうち国費と私費を合わせた留学生は約5200人となり、そのうち約3500人が中国人」とデイリー新潮は書いている。この話題は、TVでもやっていた。
「東大の大学院は入り易いんだよ」
これは私の約半世紀前の経験。私が入社した時、東大の大学院卒がいたので聞いてみた。話を聞くと、彼は都内の某国立大卒で、大学院だけ東大だった。「東大の大学院は入り易いんだよ」と言っていた。それから50年、東大大学院が入り易いのは変わっていないようです。
東大の修士の定員は学部より多い
私の経験を信用しない人がいると思うので、東大の資料で示します。
なんと大学院(修士他)の定員は学部の定員より多いし、大学院生(修士他)は他大学出身者の方が多い。
令和6年(昨年)に入学した学部生は3126人
令和6年(昨年)の大学院(修士他)は3253人、その内東大卒は1619人で、他大学卒は1634人。
令和6年(昨年)の大学院(博士)は1379人、その内東大卒は885人で、他大学卒は494人。
(京大の場合)
京大の大学院の定員は学部の定員より少ない。他の大学でもそうでしょう。
令和6年(昨年)に入学した学部生は2908人
令和6年(昨年)の大学院(修士他)は2243人。(出身大学のデータは無い)
令和6年(昨年)の大学院(博士)は951人。(出身大学のデータは無い)
学部生は就職する人が多いのに、大学院(修士他)の定員の方が学部生より多いのは東大固有の事情があるのでしょう。東大は付置研究所が多く、その定員も多いので、他大学出身の大学院生が必要になる。しかし、東大大学院の博士課程になると、他大学卒は激減する。そして、東大の教師たちに他大学卒が珍しいのは、東大出身者を優先しているからでしょう。(今そのデータは無い)
東大の穴
これも「東大の穴」というか、「東大の隙間」なんでしょう。こんな住みよい隙間は他にないかも知れない。中国人は隙間が大好きだから。
日本政府の情報が洩れていないか?
東大の先生たちは、日本政府の仕事をしている人が多い。審議会の委員とか役所から委託を受けて仕事をしている場合がある。そうすると、役所の資料を大学に持ち帰っているので、その気になれば留学生も見る機会があるはずだけど、大学の先生なんて秘密保持なんて気にしていない。大丈夫かな?
2025年2月14日