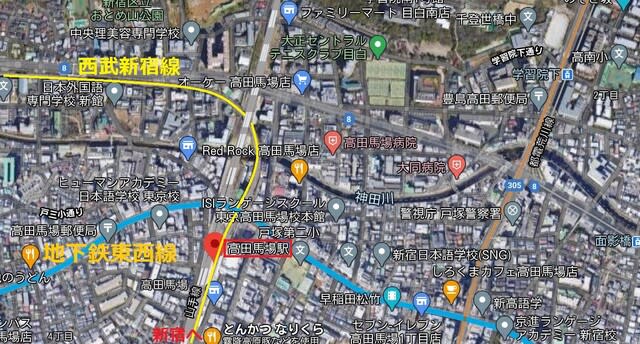2020年6月14日の「近鉄のフリーゲージ・トレインは成功するか? ㊤買収された奈良電とJR奈良線の悲哀」
2020年6月17日の「近鉄のフリーゲージ・トレインは成功するか? ㊥吉野へ行くには標準軌と狭軌を通る」
の続きです。
日本の「フリーゲージ・トレイン」は、新幹線と在来線の直通用として開発していたが、ギブアップした。耐久性が問題と報道されている。
タルゴの「フリーゲージ・トレイン」
2016年09月10日のブログ「サウジアラビアの高速鉄道その1~サウジアラビアをタルゴが走る~」では、スペインのタルゴ社の高速列車について書いています。
スペインのタルゴ社と言えば、私の学生時代から「フリーゲージ・トレイン」で有名な鉄道車両製造会社でした。そのユニークな技術を使った車両は興味を引きましたが、キワモノという感じで日本では使えないという印象でした。
タルゴ社製の高速列車の特徴は、何と言っても下図に示すような二つの特徴がある。

タルゴの編成
①「連節台車」
「連節台車」は、車両を繋ぐ連結器の下に台車がある。カーブを曲がり易いのが特徴。
②一軸の独立した車輪
新幹線などの高速鉄道の車体は、普通は2軸の車輪を持った台車が2台ある。一般的な連節台車も2軸の車輪を持った台車が多い。しかし、タルゴの連結器の下にある台車は一軸の車輪であり、しかも車輪は左右独立して回転するという独特の構造です。

一軸の車輪のイメージ図
一軸で左右独立した車輪
この一軸の左右の車輪は車軸で繋がっていないので、左右の車輪の行程差を補正しなくて良いので、カーブを曲がり易い。つまり、脱線し難いし、カーブでのキーキー音がうるさくない。左右の車輪が車軸で繋がっていない構造は、車輪を左右に動かし易いので、結果として「フリーゲージ・トレイン」をやり易い構造になっている。
このように左右の車輪が車軸で繋がっていない一軸の車輪を使うとメリットもあるが、車体を支える車輪の数が少ないので、車両の重量を軽くする必要がある。そのため、タルゴの車両はかなり短い。
タルゴは機関車(連節台車ではない)を連結しているので、軌間が変わった場合、機関車をどうするか?
①機関車も「フリーゲージ・トレイン」にする
②軌間の違う(フリーゲージ・トレインではない)機関車を外したり付けたりする
タルゴは、場合によって①か②をやっているようです。
「スペインのタルゴは昔からやっているのに、日本はなぜ出来ない?」という意見の人もいるかと思います。タルゴはユニークな技術に固執してここまで発展させたのはすごいですが、日本が流用できる技術は無いと思う。
日本では標準軌⇔狭軌の「フリーゲージ・トレイン」ですが、タルゴは標準軌⇔広軌なので床下の機器の配置に余裕があり日本よりやり易いという意見もある。それにタルゴは機関車がけん引する客車なのに対して、新幹線は電車なのでモーターが付いているので、余計にやりにくい。(スペインでは、電車の「フリーゲージ・トレイン」もあるようですが、詳細不明です)
タルゴが日本の「フリーゲージ・トレイン」の参考になるとしたら、世界に「フリーゲージ・トレイン」が存在しているということぐらいでしょうか。
「フリーゲージ・トレイン」に吉野特急は丁度良い
既に書いたように、日本の「フリーゲージ・トレイン」は、新幹線と在来線の直通用として開発していたがギブアップした。ギブアップした本当の理由は発表資料が少なく詳しくわからない。
しかし、新幹線より低速、かつ短距離で使用すれば何とかなるという意見もあるので、近鉄はそれに賭けたと思う。確かに新幹線と近鉄の吉野特急を比べると、吉野特急に有利な点がある。
①吉野特急は、1日に1~2本(私の推測)と少ない
②最大4両編成(私の推測)と短い
③長崎新幹線用は、新大阪乗り入れが前提なので、〈新大阪-博多間〉約620Km+〈博多-長崎間〉約145Km=約765Kmに対して、京都-吉野間は約84Kmと大幅に短いので技術の壁は低くなる。
④新幹線は最高時速200Km以上必要だけど、吉野特急は最高時速120Km程度とより低速なので、技術の壁は低くなる。
まとめると、京都-吉野間の特急でフリーゲージ・トレインを使うと、近鉄としても目が届くので、メンテナンスや故障時の対応はやり易いという良い点がある。
この吉野特急で本当に「フリーゲージ・トレイン」を実用化出来るのか、私は疑っていたが、こうして見直してみると何とかできるような気がしてきた。
この吉野特急が日本初の「フリーゲージ・トレイン」になったとしても、その後に長期にわたる改良が必要になるはず。そういう意味では、京都-吉野間の特急に「フリーゲージ・トレイン」を使用するのは丁度良い。
2020.09.16