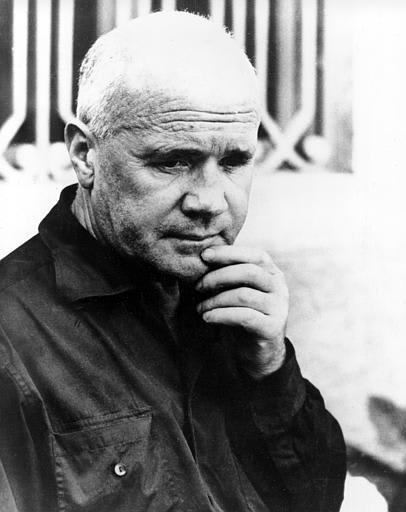★ ジャン・ジュネは、自己を変身させる驚くべき力を持っていた。伝記を書くという作業はしばしば、ある一人の人間が一つの明確な方向へと踏み出す小さな歩みの跡を追うことだと思われている。だが、ジュネがその人生の最初から最後までを通して行った尋常でない跳躍を論理的に摑まえることなど、誰にも出来ない。
★ だが再び、今度は政治的な行動主義者の姿で、この不死鳥は甦る。下層階級から出てきた作家は大抵の場合、自分をそこからすぐに切り離そうとするものだが、ジュネは世界の悲惨な人びとの使途となった。1970年代から1986年の死まで、彼は囚人や移民労働者の権利を護ろうとした。そしてとりわけ祖国を失った人々、すなわちブラック・パンサーとパレスチナの人たちの大義に係わっていく。時折発表するエッセイとインタヴューを除けば、彼は堅く沈黙を守り通したが、それは死の一ヵ月後に刊行された、それまでにもまして驚くべき「想い出」の分厚い一冊の著作を作り上げた。しかもこの『恋する虜』は、それまでのもの全てを超えた最後の作品となっている。
★ 彼は新しく、誠実で静謐な調子(トーン)を用いているのだ。彼はまたそこで、自分の周囲の世界に対する新たな関心――歴史、建築、政治、さらには小説の中では避けてきた女性に対するものまで――も示している。
★ 彼は放浪者であり、荷物は小さなスーツケース一つに納まってしまうほどのものしか持っていなかった。たいていは鉄道の駅の近くのホテルを宿とした――これは、すぐに逃げられる場所を確保しておこうとする、泥棒としての長年の習い性だった。
★ 無神論者サルトルは、大いなる皮肉を込めて彼のことを「聖ジュネ」と呼んだのかもしれないが、ジュネ自身は一種の現世での至福というものに憧れを抱いていた。彼は自分の人生を立派なものにするために、物質主義、世間的な出世の仕組み、友人関係を支えるための義務、さらに芸術的な達成にまつわる虚栄心までも否定した。このように性的、社会的に偏向した者が(略)人々に一つの規範を与えることが出来ると思う人はまずいないだろうが、この伝記はどのようにしてこうした変身が形作られたのかを示すものである。ジュネの一生のように驚くべき、そして多様な人生は、柔軟に記述する必要がある。本書の目指すところは、ジュネの人生が描きだしている複雑な文様の痕跡を追うことであり、それを単純な一つの枠にはめることではない。
★ ディジョン南西のアリニィ=アン=モルヴァンでの少年時代、ジュネは家の外の便所で長い時間を過ごすのが好きだった。便所は二つあって、一つはスレート葺きの屋根の大きな石造りの家の近くに、もう一つは野菜畑を横切って二十歩ほど行った小学校の壁の脇にあった。彼が何時間も夢想に耽ったり本を読んだりしたのは、二つのうちの遠くて不便な方の便所だった。
★ フランス語で「ジュネ」というのはエニシダを指す語で、その黄色い花はフランスの田園地帯を広く彩っている。母親が自分を捨てた野原の花に因んで自分は名付けられたのだ、と彼はコクトーと俳優ジャン・マレーに語っている。
<エドマンド・ホワイト『ジュネ伝』(河出書房新社2003)>
★ 徒刑囚の服は薔薇色と白の縞になっている。
★ わたしはそうした婚姻を高らかに歌いたいと思い、そのために、すでに徒刑囚の服が暗示している、自然界の最も甘美な感受性の形式――花――がわたしに差出すものを用いるのだ。徒刑囚の服の布地は色彩以外の点でも、そのざらざらした感触によって、花弁にうっすらと毛の生えたある種の花々を連想させる。この些細なことは、それだけでも、力と汚辱という観念に優雅と繊弱という性質をごく自然に結びつけて考えさせるのに十分なのである。
<ジャン・ジュネ『泥棒日記』(新潮文庫1968)>