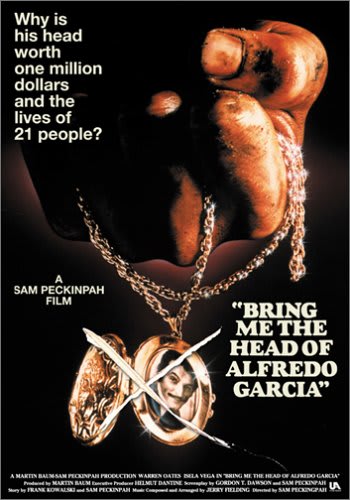★ あらたな虚構の介入とはどういうことか。それは武藤が制作したひとつの8ミリ短篇映画を見た唯生が、そこにいままで見知っていたはずのツユミを、まるでべつな人物として発見したというそれだけのことなのだが、しかし彼を「恋する男」たちへ仲間入りさせるには充分な出来事であった。(……)いくらか虚ろな眼つきで口をすこし開けたままの、真剣さと放心が入り混じったような顔つきでいくつもの卵を割って中身を出し、腹がたつのか不器用なだけか、そのどちらともうけとれるひどくぶっきらぼうな素振りで、料理道具や食器を乱雑にあつかうのだが、できあがる5人分のオムライスはそうした粗雑さのなかにあってさえ、どこかべつの次元からとりよせたもののように見事な出来栄えで画面のなかにおさまり、だからといって……
<阿部和重;『アメリカの夜』(講談社文庫2001)>
★ 僕が小学生時代の夏休みは、暑い陽差しに首をうなだれた黄色い大きなひまわりの、原色の激しいイメージを抜きに語れない。
★ そうやって気まぐれに育てて8月――。大きな花が真夏の太陽を燦々と浴びるころ、僕は縁側に老人のようにけだるい軀を横たえ、夏が過ぎるのを、じっと待った。こうしてずっと退屈な午後を生きねばならないという漠然とした不安を、ひまわりは生命力を誇示しながら教えてくれたのだった……。
★ 僕には、僕だけでなく、似たような午後の一刻を記憶している者であれば、三島由紀夫の日常性への呪詛を否定することはむずかしい。だが、やはり彼はどこか違っているのだ。天才であること、それだけでなく、どこかが違っている。
★ 恐らく近代官僚制は、そうした不在の何かを埋め合わせるシステムなのだ。立身出世の野心に溺れた祖父、屈折した小役人でトリックスターの倅、そして三代目に三島がいる。いずれも官僚を志向するが、結局、官僚機構からの落伍者で終わった。その血脈から一筋の愚直さがこぼれ、絢爛たる文学が開化した。
<猪瀬直樹;『ペルソナ 三島由紀夫伝』(文春文庫1999)>
★ 突然、あらゆる活動が止る。あるいは、マンディの意識に入らなくなる。映像とサウンドトラックが同時に途切れ、また始まったかのようだ。サーシャはまだ演説台から滔々としゃべっている。しかしエキストラはみな叫んでいる。何重もの武装警官の輪が抗議者のまわりで狭まり、杖が盾を打つ音が雷鳴のように轟く。最初の催涙弾が炸裂する。
★ そこらじゅう怒号と殴り合いの混乱のなかで、品位らしきものを保っているのはただひとり、法官ユディットだ。驚いたことに、毛沢東のジャケットのなかから大きな野球バットを取り出し、消極的抵抗を唱えるサーシャを無視して、若い警官の真新しいヘルメットをしたたか殴りつける。そのあまりの強さにヘルメットは天からの贈り物のように警官の手に落ち、彼は馬鹿げた薄笑いを浮かべて膝から崩れ落ちる。
<ジョン・ル・カレ;『サラマンダーは炎のなかに(ABSOLUTE FRIENDS)』(光文社文庫2008)>
★ 私が『振り子』を見たのはあの時だった。
教会のドームから吊るした一本の長い糸の先端に取りつけられ、その球体は等時性を厳守しながら、ゆったりと孤を描いて揺れていた。
★ ステンドグラスを通して差しこむ夕暮れ時の太陽光線に反射して、その銅球は玉虫色の弱い光を放っていた。昔と同じように湿った砂を床に敷きつめ、重りの先端が微かに触れるようにすれば、重りは揺れるごとに砂上に軌跡を描き、その方向をごくわずかに変えながら溝を広げ、左右対称の放射線を描き続けることになるだろう。(……)いやそれはむしろ、広漠とした砂の上を際限なく移動する旅商(キャラバン)の残した足跡か、あるいは何千年もの単位でゆっくりと進む移動の歴史なのかもしれない。
<ウンベルト・エーコ;『フーコーの振り子』(文春文庫1999)>
★ 夕陽が斜面の木々を染めていた。琥珀の内側に閉ざされて時を止めたように見える場所だった。秋彦は、その場所でもう一度バスを降りた。あのトンネルの前だった。しんとした、草いきれの混じる冷えかけの空気を吸いこむと、バスからバスへ、それから二本の列車、そしてさらにバス、と何度も乗り継いでとうとうここまで来た、その間ずっと溜めてきた息もろとも、一気に吐いた。地図上でいうならそれは、衛星写真が捉えた台風の、九州という島のちょうど中心から時計回りに描く雲の影の放物線が、遠心力で自分をその外へ放り出すような行程だった。九州に暮らす者にとって、台風は荒々しい生き物だ。しかし旅程は、この山あい同様、静かすぎた。
<青山真治;『サッド・ヴァケイション』(新潮社2006)>
<注記>
以上の引用文の本は、すべて”読みかけ”です。
このなかで、どれが好きかと問われたら、最後ですね。
どれが嫌いかと問われたら、最初ですね(笑)、しかしぼくは阿部氏はこの本だけでなく(本当にいやになるまで)読み続けようと思う。
これからテレビを見て、適当に寝ます、おやすみなさい。