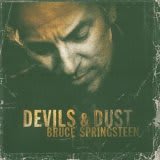 ブルース・スプリングスティーンの新譜『Devils & Dust』は、本国ではすでに発売されていて、輸入盤は店頭にも並ぶ。少しでも早く聴きたいんだけれども、仕様の問題などもあって日本版の発売を待つことにした。
ブルース・スプリングスティーンの新譜『Devils & Dust』は、本国ではすでに発売されていて、輸入盤は店頭にも並ぶ。少しでも早く聴きたいんだけれども、仕様の問題などもあって日本版の発売を待つことにした。それまでは、今回『Devils & Dust』のライナーノーツを書かれた音楽評論家/翻訳家の五十嵐さんの、もの凄くくわしくていねいな各曲紹介を愉しむ。そしてあいかわらずのBOSSの思弁とテキストワークに心を振るわせる。
アメリカという歴史の浅い国家の課題を、それに直面するマイノリティーや市井人の立ち位置から描く志は、同じ日本を描く『半島を出よ』と同じものなのだろうが、リアリティには格段の差がある。もちろん双方ともマイノリティーを描くメジャー&メガアートなわけで、極論を言えば、同じコマーシャリズムの産物といえなくもないが、おそらくBOSSは自身がメジャーであることを強く認識し、そのうえでかつマイノリティーの体験を持ち続ける力があるということだろうか。その憑依できる力が、世の中はけっして善悪ですっきり割り切れるわけではないという深く真摯な認識を生み、それゆえの苦悩への耐性を生むということだろうか(※)。まあ、楽曲を聴かないうちにあれこれ考えても不毛ですね。公式サイトで試聴しながらいろいろとイメージしてみるのがよいです。
で、そのBOSSのアコースティックソロツアーも始まっていて、そのセットリストにまた震撼する。こちらはSMEの情報から。
April 25, 2005
Detroit, Michigan
Fox Theatre
Reason to Believe
Devils and Dust
Youngstown
Lonesome Day
Long Time Comin'
Silver Palomino
For You *
Real World *
Part Man, Part Monkey
Maria's Bed
Highway Patrolman
Black Cowboys
Reno
Racing in the Street *
The Rising
Further On (Up the Road)
Jesus Was an Only Son *
Leah
The Hitter
Matamoros Banks
(encore)
This Hard Land
Waitin' on a Sunny Day
My Best Was Never Good Enough
The Promised Land
(*PIANO)
ファンの人しかわからないと思うが、このリストはそうとう鳥肌ものだ。「Racing in the Street」は、言ってしまえば僕がいちばん好きな曲で、まずパフォーマンスがあるということ自体もビビるんだけど、ピアノ弾き語りなんかやられちゃうと腰抜けるかも。それに「The Rising」「 Further On (Up the Road)」のアコースティックが続けばきっと気絶しちゃう。まあ、そもそも「Reason to Believe」のオープニングでしょうべんちびっていると思いますが。
例によって東京国際フォーラムだけでもいいから来日してほしいし、そうでない場合は、DVD化をお願いしておきますよ。SMEさん。
◆
 そのSONY MUSICのJAPANのいちおしは、知ってる人はもうかなり知っているだろうurb(アーブ)。いわゆるジャム・バンドで、ジャズなんだけど、キーボード、ギター、ベース、ドラム、、トランペットの6ピースバンドで、出自に幅広さが楽曲の幅広さにあらわれていて、とても渋くて愉しい。2002年のデビュー以来初めてのフルアルバム『afterdark』(five spot?)を、ご近所のギターウルフから借り受けていて、ようやくじっくり聴くことができたんだけど聴くほどに音楽の愉楽が実感できる。楽曲はまったく異なるがおそらくその登場感は25年前のカシオペアに通じるところがあるが、音楽に対するウィットやエスプリみたいなものはurbがちょい上か。プリンスのパープルレインなんてのを軽くカヴァーしちゃうところなんかね(そのウィットはひょっとすると芳野藤丸のSHOGUNに近いかも。もちろんテクニックも)。まあ、このあたりについては素人の戯言を聞いてもしようがないので、どこかで試聴してみてください。針が落ちた瞬間に僕の予言の正しさにご納得いただけると思います。
そのSONY MUSICのJAPANのいちおしは、知ってる人はもうかなり知っているだろうurb(アーブ)。いわゆるジャム・バンドで、ジャズなんだけど、キーボード、ギター、ベース、ドラム、、トランペットの6ピースバンドで、出自に幅広さが楽曲の幅広さにあらわれていて、とても渋くて愉しい。2002年のデビュー以来初めてのフルアルバム『afterdark』(five spot?)を、ご近所のギターウルフから借り受けていて、ようやくじっくり聴くことができたんだけど聴くほどに音楽の愉楽が実感できる。楽曲はまったく異なるがおそらくその登場感は25年前のカシオペアに通じるところがあるが、音楽に対するウィットやエスプリみたいなものはurbがちょい上か。プリンスのパープルレインなんてのを軽くカヴァーしちゃうところなんかね(そのウィットはひょっとすると芳野藤丸のSHOGUNに近いかも。もちろんテクニックも)。まあ、このあたりについては素人の戯言を聞いてもしようがないので、どこかで試聴してみてください。針が落ちた瞬間に僕の予言の正しさにご納得いただけると思います。◆
 で、最後は、ここんとこ、こればっかりのスーパーカーの『B』。シングルのカップリングを集めたベストアルバムなので、あまり期待していなかったんだけれど、結局ははまってしまった。『B』は年代順に並べた2枚組みになっており、音楽的にはその2枚の境界でばっさり寸断されているかのごとく異なる。ちょうど『FUTURAMA』あたり?そして、どちらもが紛れもなくスーパーカーであるところに、彼らの豊かさを感じる。早すぎる解散はおしい。しかし、もし彼らが今後も活動を続けたとして、この2面以上のスーパーカーを期待してしまうと、それはもうスーパーカーではないものになってしまいそうなので、そういった意味では、ここでスーパーカーが封印されるという選択肢が正しそうな気もする。
で、最後は、ここんとこ、こればっかりのスーパーカーの『B』。シングルのカップリングを集めたベストアルバムなので、あまり期待していなかったんだけれど、結局ははまってしまった。『B』は年代順に並べた2枚組みになっており、音楽的にはその2枚の境界でばっさり寸断されているかのごとく異なる。ちょうど『FUTURAMA』あたり?そして、どちらもが紛れもなくスーパーカーであるところに、彼らの豊かさを感じる。早すぎる解散はおしい。しかし、もし彼らが今後も活動を続けたとして、この2面以上のスーパーカーを期待してしまうと、それはもうスーパーカーではないものになってしまいそうなので、そういった意味では、ここでスーパーカーが封印されるという選択肢が正しそうな気もする。◆
とかいった近代的な音楽の話を、Doorsの「ストレンジデイズ」などを聴きながら書くっていう分裂気味で奇妙な一日でした。
------------------------
(※)これはけっして村上龍はダメだ、といっているわけではない。彼も見事にマイノリティに憑依していて、本来的にはこのことにもっとも自覚的な作家ではあるという点で信頼できる。ただし、精神的マイノリティーであって、社会的・経済的マイノリティへの深みにはかける。その証左として、イシハラグループのヤマダの描き方の弱さをあげてもいいかもしれない。
------------------------
↓久しぶりに本の話まったくなし。
↓不完全燃焼を解決するには
↓「本&読書のblogランキング」。











 そもそも、彼は、ロックミュージシャンの栄光と挫折を、自分自身を投影しながら客観視する楽曲が多い。そのなかには、トラベリング・バンドの哀愁を謳いあげるものもたくさん存在する。
そもそも、彼は、ロックミュージシャンの栄光と挫折を、自分自身を投影しながら客観視する楽曲が多い。そのなかには、トラベリング・バンドの哀愁を謳いあげるものもたくさん存在する。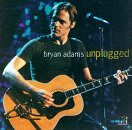 「Back to you」は、Bryanの
「Back to you」は、Bryanの (※1)
(※1)
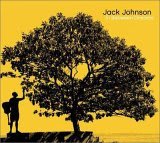 そりゃ、黄色いタワレコに黄色い一角ができれば、否が応でも(or 弥が上にも ※1)目立つので、盲目的に買い物カゴにいれてしまった人も多いかもしれませんが、わたしもまたぞろ直感で買ってしまいました。Jack Johnsonという人は、そんなに有名な人気歌手だったのだろうか。たぶん「サーフ・ミュージック」とか「癒し系」といったふれこみでプロモートされていたから、偏狭音楽趣味のぼくは知ることがなかったのだろう。
そりゃ、黄色いタワレコに黄色い一角ができれば、否が応でも(or 弥が上にも ※1)目立つので、盲目的に買い物カゴにいれてしまった人も多いかもしれませんが、わたしもまたぞろ直感で買ってしまいました。Jack Johnsonという人は、そんなに有名な人気歌手だったのだろうか。たぶん「サーフ・ミュージック」とか「癒し系」といったふれこみでプロモートされていたから、偏狭音楽趣味のぼくは知ることがなかったのだろう。




