たとえば、QfrontのTUTAYAに行くと、もの凄い枚数のカシオペアがラインアップされていて棚の前で呆然としてしまう。いったいどれを聴けばいいのか、それを判断する基準もみあたらない。僕は80年代以降、カシオペアの新譜を聞いていなかったのだけれど、90年代にいったいなにがあったんだろう。
とりわけややこしいのは「ベスト盤」と「ライブ盤」の多さだ。なかには「ベストライブ」なんかもあったりして、ややこしさに輪をかける。そこで、カシオペアこんなにあるある探検隊を呼んで調べてもらった。
2005 GIG25 【LIVE】
2004 ★MARBLE
Live & More 【ライブ】
ゴールデン☆ベスト 【ベスト】
2003 ★PLACES
2002 ★INSPIRE
2001 CASIOPEA "SINGLE" COLLECTION【ベスト】
Limited Editonal Collectors Box【ベスト?】
20th【ライブ】
★MAIN GATE
2000 ★Bitter Sweet
Best Selection【ベスト】
1999 20TH ANNIVERSARY BEST【ベスト】
★MATERIAL
★be
1998 GOLDEN WAVES 【シングル】
★Light and Shadows
TWINS~SUPER BEST OF CASIOPEA【ベスト】
1996 Schedir【ベスト】
★Flowers
work in【ベスト】
1995 work out【ベスト】
LIVE ANTHOLOGY FINE2【ベストライブ】
★freshness
1994 ★HEARTY NOTES
★ANSWERS
★ASIAN DREAMER【リメイク】
LIVE ANTHOLOGY【ベストライブ】
テイク・コレッジ【シングル】
MADE IN MELBOURNE【ライブ】
AGURI SUZUKI selected for F-1【ベスト】
1993 ★DRAMATIC
GLORY【シングル】
WE WANT MORE 【ライブ】
1992 MEMORY【ベスト】
1991 ★FULL COLORS
★active
デイブレイク&トワイライト【ベスト】
ウインド&クワイエット・ストーム【ベスト】
決定版カシオペア・ベスト・セレクション【ベスト】
1990 THE CASIOPEA (1987~1989) ~LAST MEMBERS 【ベスト】
★PARTY
SPLENDER 【シングル】
BEST OF BEST【ベスト?】
★EUPHONY
1988 WORLD LIVE'88 【ライブ】
BAYSIDE EXPRESS 【シングル】
★PLATINUM
FUNKY SOUND BOMBERS【ベスト?】
1987 CASIOPEA PERFECT LIVE LIVE II 【ライブ】
★SUN SUN
1986 ランディング・トゥ・サマー 【ベスト】
★HALLE
1985 CASIOPEA LIVE 【ライブ】
★DOWN UPBEAT
1984 THE SOUNDGRAPHY 【ベスト】
★JIVE JIVE
1983 ★PHOTOGRAPHS
Mint Jams 【ライブ】
1982 ★4×4 Four by Four
★CLOSS POINT
1981 ★EYES OF THE MIND
★MAKE UP CITY
1980 THUNDER LIVE 【ライブ】
★SUPER FLIGHT
1979 ★CASIOPEA
ネットをあちこち見ながらかき集めたらしい。なんでも、これが正解というのがなくて苦労をしたようだ。
オフィシャルサイトでは、★のオリジナルアルバムしかディスコグラフィされていないようだし、ネットショップのリストを見ると再販バージョンなども重複しており腑分がたいへんなようなだ。また公式・非公式含めたReMixもたくさんでており、したがって、これでも完璧ではないと思うんですが、というエクスキューズつきだ。
僕自身は先述したように、80年代以降、正確には
『PLATINUM』以降、聞いていなかったし、80年代のものもLPでしか所有していないので、そういう意味では、ある時期、カシオペアをまったく聞いていなかったことになる。そのためリハビリをかねて、どちらかというと古い曲を中心にいちばんバリエーションが充実していそうな、
『20TH ANNIVERSARY BEST』というのをとりあえず借りてみた。もしあいかわらず良ければ、旧版含めて買い集めようと期待をこめて。
【002】
『20TH ANNIVERSARY BEST』
■ディスク: 1/1.朝焼け 2.ブラック・ジョーク 3.ダズリング 4.ドミノ・ライン 5.ダウン・アップビート(リミックス・ヴァージョン) 6.アイズ・オブ・マインド(リミックス・ヴァージョン) 7.ファー・アウェイ 8.ギャラクティック・ファンク 9.ジプシー・ウィンド
■ディスク: 2/1.メイク・アップ・シティー 2.マリン・ブルー 3.ミッド・マンハッタン 4.ミッドナイト・ランデブー 5.ミスティ・レディ 6.サンバ・マニア 7.スパン・オブ・ア・ドリーム 8.ステップ・ドーター 9.サニーサイド・フィーリン 10.テイク・ミー 11.ザ・サウンドグラフィー

たとえ生半可なファンであっても知っている曲ばかりだ。結論をいうと、この頃のカシオペアはやはりいい(←ピンク・フロイドのときと同じ言い方になっちまった。音楽を語る語彙が少なすぎるね)。 僕はプレイヤーではないので、テクニカルなこところは「凄い」という以外にいいようないんだけれど、メロディの豊かさとか構成力みたいなものについては、聴くたびに隠し味が発見されるのがよくわかる。とりわけ、じつはファーストアルバムの「ブラック・ジョーク」や「ミッドナイト・ランデブー」があいかわらず味わい深いなのは大いなる発見だ。野呂一生が自己模倣に陥っているということを差っぴいてもあまりある。
『SUPER FLIGHT』に始まり
『MAKE UP CITY』をグニャグニャになるまで聴いた中学生の頃の記憶が甦ってきた。目覚ましに、
『Mint Jams』(※)をかけてたっけ。そういえば、何回もコンサートにいったなあ、あの頃はサクがまだ元気でワイヤレスのアンプで観客席を一周したりしてたなあ。「ドミノライン」のドミノ倒しのユニゾンとか、まだやってんだろうか。
『20TH ANNIVERSARY BEST』は、20周年といいつつも、おそらくレコード会社のからみなのか80年代の曲ばかりで、その点で、「新しいカシオペアはどうなんだ?」という僕の所期の目的は達成できていない。だけど、少なくとも昔のカシオペアは今でも充分に聴けるということがわかり、少し気分がよくなった。
今週末、ターンテーブルを結線して、昔のLPを聴いてみよう。それと、ライブのベストっていうのも何枚か借りてみよう。ああ、愉しみだ。まあ、壮大なマンネリズムなんだけどね。
------------------------
(※)幼い頃は、このノイズのクリアなアルバムの音源がLIVE録音からのもの、ということに感動したものだ。M(ukaiya)I(ssei)N(oro)T(etsuo)-J(inbo)A(kira)M(inoru)S(akurai)ってのは誰でも知ってる薀蓄ですね。
------------------------
↓いちおう本&読書のblogランキング。
↓音楽カテゴリーに変えるべきか。

 こんなブログ世界の片隅で書くことにもはやなんの意味もないし、そもそも顕在的なファンもずいぶん先細りしているような気もするので、ほとんど独りよがりな発信に過ぎない。しかしたとえそうだとわかっていても、それでもいっておきたい。ブルース・スプリングスティーンの新しいライブアルバム『Live in Dublin』はすばらしい。
こんなブログ世界の片隅で書くことにもはやなんの意味もないし、そもそも顕在的なファンもずいぶん先細りしているような気もするので、ほとんど独りよがりな発信に過ぎない。しかしたとえそうだとわかっていても、それでもいっておきたい。ブルース・スプリングスティーンの新しいライブアルバム『Live in Dublin』はすばらしい。









 斉藤和義の新しいアルバム
斉藤和義の新しいアルバム ▶WOWOWでライブのプログラムがあり、動くCOLDPLAYを初めて見た。いったい「SPEED OF SOUND」や「Clocks」のような曲がどのようなパフォーマンスで、どのように盛り上がるのか、まったくイメージできなかったのだけれど、オープニングの「SQUARE ONE」で久しぶりに鳥肌が立つくらい納得できた。めっちゃかっこいいやん、ってことだ。そして、COLDPLAYはライブだと思った。今頃気づくなんてあほだ。8ヶ月くらい前に気づいていたらなあ。WOWOWで放送されたトロントのDVDがでるとかでないとかいう噂もあるが、どうなっているのだろう。とりあえず
▶WOWOWでライブのプログラムがあり、動くCOLDPLAYを初めて見た。いったい「SPEED OF SOUND」や「Clocks」のような曲がどのようなパフォーマンスで、どのように盛り上がるのか、まったくイメージできなかったのだけれど、オープニングの「SQUARE ONE」で久しぶりに鳥肌が立つくらい納得できた。めっちゃかっこいいやん、ってことだ。そして、COLDPLAYはライブだと思った。今頃気づくなんてあほだ。8ヶ月くらい前に気づいていたらなあ。WOWOWで放送されたトロントのDVDがでるとかでないとかいう噂もあるが、どうなっているのだろう。とりあえず ▶Dexy's Midnight Runnersは、「Come On Eileen」が爆発的い流行っていた頃ですら、聞けるアルバムは
▶Dexy's Midnight Runnersは、「Come On Eileen」が爆発的い流行っていた頃ですら、聞けるアルバムは ▶しばらく
▶しばらく ▶迷った末、beckの
▶迷った末、beckの ▶ここまで、書いてきて、ようやく米国のアーティストが登場したことに気づく。僕は相変わらず、SpringsteenやJackson Browne、さらについ最近ではJohn Mellencampの蒐集リスタートを始めたほどのアメリカン・ロック好きなのだけれど、嗜好するアーティストは70年後半からほとんど減りもせず、増えもせず、つまりは成長していない。しかし、これは、現在の米国のよくわからないヒップホップが席巻しているようなヒットチャートを見ればわかるように僕が成長していないのではなく、アメリカのロックが成長していないということだろう。ほんとうにそうなのか。それを検証するために、なんかないかなあ、と思って棚を探して、とりあえずR.E.Mの
▶ここまで、書いてきて、ようやく米国のアーティストが登場したことに気づく。僕は相変わらず、SpringsteenやJackson Browne、さらについ最近ではJohn Mellencampの蒐集リスタートを始めたほどのアメリカン・ロック好きなのだけれど、嗜好するアーティストは70年後半からほとんど減りもせず、増えもせず、つまりは成長していない。しかし、これは、現在の米国のよくわからないヒップホップが席巻しているようなヒットチャートを見ればわかるように僕が成長していないのではなく、アメリカのロックが成長していないということだろう。ほんとうにそうなのか。それを検証するために、なんかないかなあ、と思って棚を探して、とりあえずR.E.Mの たとえば、
たとえば、 ①斉藤和義の
①斉藤和義の ②『俺たちのロックンロール』を買った人はこんなCDも買っています、ってのが
②『俺たちのロックンロール』を買った人はこんなCDも買っています、ってのが ③そして、そんな人がカゴにいれようかどうか1時間ほどあれこれ迷うのがPrimal Screamの
③そして、そんな人がカゴにいれようかどうか1時間ほどあれこれ迷うのがPrimal Screamの
 そういう人たち、つまりそういうぼくのような人に有効に作用するのが、彼の最近のベストアルバム
そういう人たち、つまりそういうぼくのような人に有効に作用するのが、彼の最近のベストアルバム つまり、ブルース・スプリングスティーンの
つまり、ブルース・スプリングスティーンの これはちょっとビビった。やっぱ神保はすげーや。2日の夜中のフジテレビの「メディアの苗床」。Synchronized DNAの第一歩や存在は、なんとなく知っていたんだけれど、実際に神保と則竹だけが並んで演っているのを目の前にするのは初めてで、ワールドクラス軍団とはいえ、はたしてドラムだけでうまい具合に愉しめるパフォーマンスができるのかなあ、と思って見始めた。
これはちょっとビビった。やっぱ神保はすげーや。2日の夜中のフジテレビの「メディアの苗床」。Synchronized DNAの第一歩や存在は、なんとなく知っていたんだけれど、実際に神保と則竹だけが並んで演っているのを目の前にするのは初めてで、ワールドクラス軍団とはいえ、はたしてドラムだけでうまい具合に愉しめるパフォーマンスができるのかなあ、と思って見始めた。 そこで、CDを所望しようといろいろと探してみるが、じつは、まとまった形のスタジオサイズののはまだリリースされていないようだ。カシオペアとの協演や、どちらかというと、教則的なDVDは結構あるようだが、単独のものはみつからない。とりいそぎ、
そこで、CDを所望しようといろいろと探してみるが、じつは、まとまった形のスタジオサイズののはまだリリースされていないようだ。カシオペアとの協演や、どちらかというと、教則的なDVDは結構あるようだが、単独のものはみつからない。とりいそぎ、 残念ながら、くるりは、ぼくの蝕から少しズレてしまったようだ。いやそんなことはない、と思って、
残念ながら、くるりは、ぼくの蝕から少しズレてしまったようだ。いやそんなことはない、と思って、 もちろん『NIKKI』のそれぞれの曲についても、オリジナリティは高く、おそらくずっと昔からくるりを聴きこんでいる人にとっては、たいへん貴重なものに違いない。岸田自身も、
もちろん『NIKKI』のそれぞれの曲についても、オリジナリティは高く、おそらくずっと昔からくるりを聴きこんでいる人にとっては、たいへん貴重なものに違いない。岸田自身も、 全世界的な商業的なバンドとしては初めてQueenを知って以来、バンドたるもの「全員バンド」たるべし、とこだわり続けてるんだけど、じつは後にも先にも、そんなバリエーション豊かなバンドは(ぼくの狭い音楽範囲に限れば)彼らだけなんですよね。楽器の掛け持ちといったレベルのことはあっても、曲をつくる人間、それを歌う人間はおおむね固定されていることが多いし、たまにメンバーが歌ったり作ったりすることがあったとしても、おおむね色物っぽいことが多い。商業作戦上いたしかないことであるとはいえ、一方でバンドはメインボーカリスト、メインライターの才能に委ねられることが多いのもまた事実。
全世界的な商業的なバンドとしては初めてQueenを知って以来、バンドたるもの「全員バンド」たるべし、とこだわり続けてるんだけど、じつは後にも先にも、そんなバリエーション豊かなバンドは(ぼくの狭い音楽範囲に限れば)彼らだけなんですよね。楽器の掛け持ちといったレベルのことはあっても、曲をつくる人間、それを歌う人間はおおむね固定されていることが多いし、たまにメンバーが歌ったり作ったりすることがあったとしても、おおむね色物っぽいことが多い。商業作戦上いたしかないことであるとはいえ、一方でバンドはメインボーカリスト、メインライターの才能に委ねられることが多いのもまた事実。 じゃあQueenの4人がバランスよく能力を発揮していたか?といえば、じつはそこまで完全ではないのだけれど、他のバンドに比べ、ボーカルや曲作りが分散されているのも事実で、なによりフレディの曲以外によいものが結構あったりするのが大きい。幼いころは、新譜がでるたびに、歌詞カードをみて、これは誰の曲で、誰が歌っているのか、ということを調べるのをものすごく楽しみにしていたひとりです。
じゃあQueenの4人がバランスよく能力を発揮していたか?といえば、じつはそこまで完全ではないのだけれど、他のバンドに比べ、ボーカルや曲作りが分散されているのも事実で、なによりフレディの曲以外によいものが結構あったりするのが大きい。幼いころは、新譜がでるたびに、歌詞カードをみて、これは誰の曲で、誰が歌っているのか、ということを調べるのをものすごく楽しみにしていたひとりです。 というわけで、
というわけで、 ああ、こんなふうに思考のプロセスをそのままダイレクトに書き付けていけたらいいなあと感激したり、これらの文学について何か書くべきだと焦燥していたりするんだけど、いかんせん「本は仕事をしながら読めない」という最大の障害にぶつかって、じつは思うどおりには読み進められてはいないんだ。スパッと読める
ああ、こんなふうに思考のプロセスをそのままダイレクトに書き付けていけたらいいなあと感激したり、これらの文学について何か書くべきだと焦燥していたりするんだけど、いかんせん「本は仕事をしながら読めない」という最大の障害にぶつかって、じつは思うどおりには読み進められてはいないんだ。スパッと読める あとついに
あとついに 養分?そんな中、養分どころか
養分?そんな中、養分どころか それともう一枚は宿命の浜田省吾。
それともう一枚は宿命の浜田省吾。
 先々週くらいから「音楽空白の10年を埋める企画」って言うのを始めていて、そんなこともあって、いろいろ聞いてはいるのですがright nowは、BECKの「Paper Tiger」でした。夜中に職場でPower Pointを開きながら聞く、
先々週くらいから「音楽空白の10年を埋める企画」って言うのを始めていて、そんなこともあって、いろいろ聞いてはいるのですがright nowは、BECKの「Paper Tiger」でした。夜中に職場でPower Pointを開きながら聞く、 (1)ishmaelさんとかぶってますね。最初に聞いた洋楽アルバムの最初の曲は、やはりインプリンティングされるものです。腰抜かしてましたね、きっと。この3曲の「GO→STOP→GO」のミックスダウンを1曲と解釈させていただきました。じつはロジャー・テイラーのしゃがれ声もおおいに刷り込まれています。いまやふつうのブタしゃんになっちまったけれど。
(1)ishmaelさんとかぶってますね。最初に聞いた洋楽アルバムの最初の曲は、やはりインプリンティングされるものです。腰抜かしてましたね、きっと。この3曲の「GO→STOP→GO」のミックスダウンを1曲と解釈させていただきました。じつはロジャー・テイラーのしゃがれ声もおおいに刷り込まれています。いまやふつうのブタしゃんになっちまったけれど。 (2)きっと、もうスティングには、こんなカッコいい曲はもう作れないだろうなあ。ひょっとしたらこんな思弁的な曲もつくれないかもしれない。いまでも熱狂的に聴いてます。
(2)きっと、もうスティングには、こんなカッコいい曲はもう作れないだろうなあ。ひょっとしたらこんな思弁的な曲もつくれないかもしれない。いまでも熱狂的に聴いてます。 (3)彼が、90年代にがんばった曲。ほんとうは「The Pretender」とか「Fountain Of Sorrow」なんかの方をよく聴いてるはずなんだけれど、がんばったので一票。いやそれだけでなく、ほんとにいい歌です。
(3)彼が、90年代にがんばった曲。ほんとうは「The Pretender」とか「Fountain Of Sorrow」なんかの方をよく聴いてるはずなんだけれど、がんばったので一票。いやそれだけでなく、ほんとにいい歌です。 (4)もちろんこのあとに続く「マイホームタウン」も含めて、ということで。bank bandもがんばったけれど、やっぱり「Ocian Beauty」を、はしょったらだめですね。最近では、とりわけ詞について、ことあるごとに「陳腐疑惑」が持ち上がっている浜田ですが、なかなか嫌いにはなれません。だれかライブのチケットわけてください。
(4)もちろんこのあとに続く「マイホームタウン」も含めて、ということで。bank bandもがんばったけれど、やっぱり「Ocian Beauty」を、はしょったらだめですね。最近では、とりわけ詞について、ことあるごとに「陳腐疑惑」が持ち上がっている浜田ですが、なかなか嫌いにはなれません。だれかライブのチケットわけてください。 たまさか「レコードコレクターズ」の今月号がBOSS特集。「21世紀のスプリングスティーンは名実ともに第2の黄金期に突入している」なんてエッセイも掲載されているようだけれど、「Wreck on the Highway」は、もう20年以上も前の曲ということになる。カタルシスを求めるときに必ず聴いてます。ああ、何度求めたことか。
たまさか「レコードコレクターズ」の今月号がBOSS特集。「21世紀のスプリングスティーンは名実ともに第2の黄金期に突入している」なんてエッセイも掲載されているようだけれど、「Wreck on the Highway」は、もう20年以上も前の曲ということになる。カタルシスを求めるときに必ず聴いてます。ああ、何度求めたことか。 たとえ生半可なファンであっても知っている曲ばかりだ。結論をいうと、この頃のカシオペアはやはりいい(←ピンク・フロイドのときと同じ言い方になっちまった。音楽を語る語彙が少なすぎるね)。 僕はプレイヤーではないので、テクニカルなこところは「凄い」という以外にいいようないんだけれど、メロディの豊かさとか構成力みたいなものについては、聴くたびに隠し味が発見されるのがよくわかる。とりわけ、じつはファーストアルバムの「ブラック・ジョーク」や「ミッドナイト・ランデブー」があいかわらず味わい深いなのは大いなる発見だ。野呂一生が自己模倣に陥っているということを差っぴいてもあまりある。
たとえ生半可なファンであっても知っている曲ばかりだ。結論をいうと、この頃のカシオペアはやはりいい(←ピンク・フロイドのときと同じ言い方になっちまった。音楽を語る語彙が少なすぎるね)。 僕はプレイヤーではないので、テクニカルなこところは「凄い」という以外にいいようないんだけれど、メロディの豊かさとか構成力みたいなものについては、聴くたびに隠し味が発見されるのがよくわかる。とりわけ、じつはファーストアルバムの「ブラック・ジョーク」や「ミッドナイト・ランデブー」があいかわらず味わい深いなのは大いなる発見だ。野呂一生が自己模倣に陥っているということを差っぴいてもあまりある。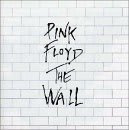 空白の10年の答えになっていないし、なにをいまさらと思われるかもしれませんが、これは久しぶりに聞くとやっぱりいい。一般的には出来が悪いとかなんとか言われているこのアルバムを好きだというのは少し複雑な感情ではあるれど。じつは、高校生や大学生のときにたまたま入手していた
空白の10年の答えになっていないし、なにをいまさらと思われるかもしれませんが、これは久しぶりに聞くとやっぱりいい。一般的には出来が悪いとかなんとか言われているこのアルバムを好きだというのは少し複雑な感情ではあるれど。じつは、高校生や大学生のときにたまたま入手していた このマルチぶりに敬意を表して、「SENRI OE CONCERT TOUR “ゴーストライター ミーツ Senri”」のライブ評にしたいところだが、残念ながらわたしは書けるほど見識と経験がある輩ではない、つまりほざく資格はないので、ライブで拾った牡丹餅について。いや牡丹餅なんて言い方はたいへん失礼だ。
このマルチぶりに敬意を表して、「SENRI OE CONCERT TOUR “ゴーストライター ミーツ Senri”」のライブ評にしたいところだが、残念ながらわたしは書けるほど見識と経験がある輩ではない、つまりほざく資格はないので、ライブで拾った牡丹餅について。いや牡丹餅なんて言い方はたいへん失礼だ。 T-SQUAREとえいば去年か一昨年か、カシオペアとの
T-SQUAREとえいば去年か一昨年か、カシオペアとの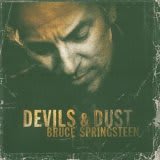 ブルースの惹句は「名盤
ブルースの惹句は「名盤