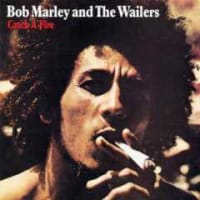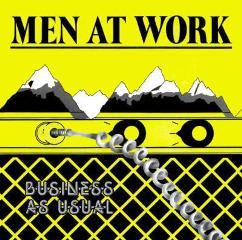
メン・アット・ワークがヒットした1980年代の前半は大きく音楽シーンが変わっていく過程にあった。ただ、それは音楽自体が大きく変化していたバロック時代とか、古典派時代からロマン派時代、十二音階とか、そういう音楽自体の変化ではなく、あくまでも音楽を取り巻く環境が変化したという言い方である。というか、商業音楽時代の1970年代から、音楽を伝えるツールと同時に音楽を保存するツールというものが大きく変わっていったのである。例えば、音楽を配給するツールが、レコードというアナログからCDというデジタルになり、ノイズが激減したり、大きさが小さくなって保存性が高まった。音楽を宣伝する情報ツールも変わってきた。ミュージックビデオの台頭である。
ミュージックビデオの進出は、音楽の概念を大きく変える要素があった。映像の効果というものは大きいがこれは何も音楽だけではなかった。例えば、漫画が映像になった場合、ヒロインの顔は同じだが、そこには声がついてしまっている。その作品がアニメ化される前のファンであれば、最初にどんな声なのかという想像力を働かせていたのだか、それより後の人は既にキャラクターやヒロインの声はこういう声だと決まっているのである。ドラえもんの声と同じである。音楽の場合もそうであって最初はステージとかスタジオ内でも演奏をしている普通にシーンが殆どだったが、例えばラヴソングだったら恋人が出てきて、パターンも恋人を思って歌っていたり、恋人と一緒に浜辺を歩いていたりなどその辺りが色々と工夫されてくる。しかし、その辺りが徐々にエスカレートしてきて、MTVなるミュージックビデオ専門のテレビ局なるものが開局した暁には、最初の内はまだ歌詞と呼応したストーリーだったのに、徐々に比喩的なものになり、更には比喩も通り越して、音楽とは全く関係ない映像が流れるようになって来たのである。だが、当時はそれも新しい音楽文化のひとつだという風潮もあったし、なにしろプロモーター側からしてみればCD以外に新しく映像商品の販売促進という新しい金脈をみつけたのだから、それは結構必死でこの分野の開拓にあたった。このメン・アット・ワークというバンドは、まさにその映像時代の黎明期に存在した。彼らのプロモーション映像は大変高い評価を受けたし、いまでもこのバンドを思い出すと、アルバムジャケットより、プロモーション映像の方が印象的に残っているので不思議である。しかし、一方で大変残念になのは、このバンドの音楽性は大変面白く、デビュー当時は英米ミュージシャンとは一線を画していたと思う。当時、オーストラリアのミュージシャンも随分クローズアップされて来たし、そのきっかけになったのもこのバンドのヒットであった。だから余計に映像バンドとしての認知が一般にも流布され過ぎてしまって、その高い音楽性は余り注目されなかった。前述したように視覚効果というのは聴覚より何倍も何十倍も人を支配できる影響を持っているものなので。
実際にプロモーションビデオを製作して有名ななったプロデューサーやディレクターが多いなかで、ミュージシャンは中々台頭してこなかった。この辺りらも映像の優位性が打ち出されていて、だとしたら、メン・アット・ワークはもっと映画音楽なんかしを担当した方が売れたのではないかとも思う。ほんの数年で終わってしまったバンドだが、私の中での印象は強い。
こちらから試聴できます