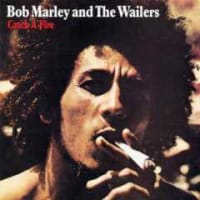U2のドキュメンタリー映画「魂の叫び」(原題"Rattle and Hum")の、ある意味サントラ盤的存在のアルバムであるが、劇中とは異なるヴァージョン、また未使用の新曲も収録され、筆者はスタジオアルバムとして"Rattle and Hum"プロジェクトのアルバム版という解釈をしている。だからこのレビューもあくまでも単独なものというスタンスで書く。新曲が9曲あり、ライブ音源が6曲、更に他のアーチストの2曲が収録されている。ご存知のようにU2は前作「ヨシュア・トゥリー」が全世界で2850万枚を売る大ヒットとなり、まさに超ビッグアーティストの仲間入りを果たした。また、いつも書くように筆者とボノは誕生日が10日しか違わないし、他のメンバーもみんな同級生みたいなものだ。だから、本当にゼネレーションがピッタリあうのはこのバンドなのである。そんな訳でU2の作品や活動は自分のことのように思っているし、今でもこのバンドが健在なのは嬉しい。だが、考えてみれば現在でもストーンズやクラプトンは第一線で活躍している訳で、我々の年代、50歳代なんて、まだまだポップ音楽に世界ではヒヨっ子なのかもしれないが、そう考えると可笑しい。
結果論で言ってしまうと、この作品は凄い位置にある。U2最大のヒットアルバムとなった「ヨシュア・トゥリー」と、U2最大の問題作である「アクトン・ベイビー」に挟まれた作品だからである。だが、この作品が発表された当時を顧みるとかなりロックの存続が危機的状態にあったのも事実である。一体この先ロックは何処へ行ってしまうのか?? そんな頃にU2は前作を、そして、スミスは「クイーン・イズ・デッド」を発表してなんとか繋ぎ止めた感があった頃だ。その一大事に、この一見すると「集大成」的な作品を発表したU2に対して筆者はかなり複雑であったことは事実である。もしかしたらU2もロックもここで終わりなんじゃないかって、そう、アイルランドから出てきた多感で発言力の強い若者たちが五線譜に乗っけて訴え続けたメッセージは、いつしかロックの主流になっていた。だから、U2が終わることは、何時しかロックが終わることとイコールになるまでの存在になっていたのである。だが皮肉にもそれを救ったのは、彼らにそれがどんな価値のあるものかどうかは別として、「プライズ」であった。前作がグラミーのアルバム賞に輝いたのは、このアルバムが発売される前のことであったが、既にこの「魂の叫び」プロジェクトは進行中であったから、このタイミングは絶妙だったかもしれないし、しかし、次作の「内容」を考えると、一体どうだったのか。その辺のことは次作のプレビューで書く。だが、このアルバム自体はU2の作品ラインナップの中にあっても、至って目立つものではない。事実、前回、スジバンのデビューアルバムの"Helter Skelter"繋がりで、あ、そういえばこの作品にレビュー書いていなかったなと思い出した程度なのである。U2好きな筆者にして、この有様である(笑)。
アルバムタイトルになっている、"Rattle and Hum"の"rattele"は「ガラガラ」、"hum"は「ブンブン」という音の声喩で、要するに騒々しい様子を表している。しかしU2の音楽も。この作品も、そしてロックという音楽も「騒々しい」だけのものではない。では一体なにが「騒々しい」のであるのか。筆者はこの段階では全く分からなかった。しかしU2はこれから後に活動において、その意味を自問自答しながら考え、丁寧にひとつずつ解き明かしていくのである。というか、やはり同年代の筆者に取ってはそうしているとしか思えないし、だからなのかもしれないが、このバンドの存在は特別である。
こちらから試聴できます