データで保存すべき記録、資料、
毎日新聞はイイタイミングで適切なインタビューを行ってくれた。菅氏の回答は率直で事実を語ろうという姿勢が読める、岡田首相よりはよほど立ち場は 客観的で、国民サイドに近いと感じる、ボクガラインを引いたところは皆さんも注目して下さい、多分彼は事実を語ろうとはしているが、間接的に、だ、放射能汚染も、福島のあと処理も事態はもっと深刻であると伝えたいはずだ、
この対談で、岡田内閣の仙谷、前原、など戦闘的な原発推進者の存在が明確にされる?
菅前首相:浜岡運転停止要請から1年 単独インタビュー
毎日新聞 2012年05月05日 11時24分
中部電力浜岡原発(静岡県御前崎市)の運転停止要請から6日で1年となるのを前に、菅直人前首相が毎日新聞の単独インタビューに応じた。主な一問一答は次の通り。
−−11年5月6日の会見で中部電への運転停止要請を発表した。判断した経緯は。
◆ずっと前から「あそこが危ない」という議論があるのは知っていた。4月の中央防災会議で、(30年以内に)87%と非常に高い確率で大きな地震が来そうだと。そういうものが重なっていった。個人的にアドバイスをくれた人もいた。
最終的にあの時点で行動したのは、5月5日に海江田万里経済産業相(当時)が浜岡原発へ自己判断で視察に行き、翌日に「話がある」と。「ここは止めた方がいい。停止要請しよう」と言われ、私が考えていたことと方向性が一緒になって「そうしましょう」と。事前に閣内で正式な表明はしていない。
−−考えた影響は。
◆福島第1原発の事故を経験して2カ月目ぐらいだった。一番厳しい時には、場合によっては首都圏まで避難が必要になるという背筋が寒くなるような思いをした。もし浜岡で同じことが起きれば、東京、大阪の太平洋ベルト地帯で新幹線も高速道路もすぐ近くにあり、その影響は福島より大きくなるという認識はあった。
−−具体的にシミュレーションはしていたのか。
◆どういう展開になるか、分からなかった。ただ、例えば福島の場合に立ち入り禁止の警戒区域となった20キロ圏を浜岡原発に当てはめてみると、日本の大動脈である東名も新幹線も引っかかる。経済的な面もあるし、住んでいる人も多い。
−−中部電は「原子力安全・保安院の評価・確認を得たときは、浜岡原発の全号機の運転が再開できることを確認したい」と確認事項を経産相との間で交わしている。政府が再稼働を保証するという議論はあったのか。
◆条件とまで言えるかは分からないが、ある種の希望が表明されたことは否定しない。一電力会社の個別の問題と、日本が原発依存を続けるかという日本のエネルギー政策の問題とは次元が違う。そこで約束できるか、できないかを超えている。福島の事故は一企業が担いきれないリスクがあることを証明した。原発事故の巨大性はスリーマイルより厳しく、チェルノブイリよりも実質大きい。国民的に判断する政策課題だ。
−−関西電力大飯原発など、再稼働への動きが加速しているように見える。
◆多少問題なのは、電力が足りないという供給側の意見が非常に強い。本当に足りないのか。国民が協力したり、企業が自己防衛を含めて自家発電したり、それらを計算してもピーク時需要に対する供給量が足りないのか。そのあたりの議論をもう少しした方がいい。この一年の経験から、個人的にはピークカットなどでしのいでいけると思う。
−−野田佳彦内閣の再稼働への動きは拙速か。
◆頂上(*脱原発)を目指しているのかが大事だ。頂上は脱原発で、それを目指す上で若干のジグザグはある。しかし、もう降りてしまおう、3・11は忘れてしまうようなことを考えてやろうとしているのか、私は国民はそこを見ていると思う。ロードマップを示すことがないまま再稼働すると、「結局どっちに行く気なんだ」と。そこが今の状況が国民的になかなか理解されない大きな要素だと思う。野田内閣も(脱原発依存を宣言した私の政権を)踏襲していると思う。だが、客観的に多くの人が疑っていることまで否定する気はない。
−−国政選挙の争点に、という話もある。
◆どういうエネルギーを使うべきかは、最終的には国民が判断すべきもの。技術的な問題やいろいろな専門的の議論があっていいが、最後は技術論を超えたところで国民が判断すべきだ。国民の選択で一番分かりやすいのが国政選挙だ。












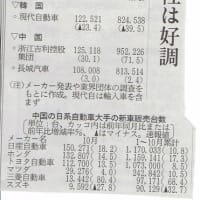


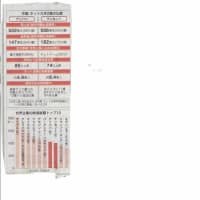
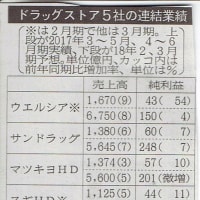

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます