厚生中央病院、整形外科、佐々木医長
蕁麻疹が2週間位前から発生していて、並行的に、左大腿部から左脹脛に掛けて、シビレが起きるようになった、いろいろ要因を考えた、1つは右脳における小さな梗塞?それで2週間前に、整形外科の佐々木先生と相談して,MRIを撮ることに決め、その結果の診断が昨日の午前9時から行われた,MRIの画像を先生と一緒に、頭からウエストまで輪切り、両サイドからみていった、どこにも問題はない、と先生はいう、ボクは余りにも影の無い濃淡の鮮明な画像で、キレイなバランスですね、という、うん、そうだね、ただし、1つ問題があるのは、シュウシ、終糸と書きます、このラインです、といって脊髄の中心の辺りを、頚部から、ウエストまでボールペンでセンをなぞってゆく、このセンのとろどころが膨らんで神経を圧迫する、それがシビレの要因でしょう、ヒドイレベルではありません、ボクはシビレが頭ではないと分かったことでとても嬉しくなったし、安心もできた、次の診療日を決めましょう、先生は言っていたが、ボクの記憶には無い、
*終糸はパッキングの役割、情報系?
*ボクのシビレにはイスの不適合もあって、イスを代えたことで大分、良くなった、安物のバネの無いいすのほうがボクにはフィットしている、
脊髄終糸症候群(せきずい しゅうし しょうこうぐん)
*ボクの終糸にも幾分か問題があることがわかった、
2)特徴
10代から30代の若い年代に多く、腰椎椎間板ヘルニアの好発年齢と重なります。症状も腰痛や下肢痛など椎間板ヘルニアと似ているため鑑別が必要です。前屈で手が床に届かないことが多く、MRIではヘルニアの所見が見られず、頻尿や便秘、下痢などの膀胱直腸障害を伴うことなどから多くの場合鑑別が可能です。最近では50歳以降で症状が出現し手術で改善する場合がありますが、生まれつき硬い終糸の人がなぜ50歳以降で症状が出るのか、まだ詳しい病態は解明されていないのが現状です。
3)治療
前かがみの姿勢を避けることで改善する場合もありますが、実際には椅子に座る、床の物を取るなどの日常動作はなかなか避けることが難しく、一度症状が出現すると多くの場合手術が必要になります。手術はまず第1仙椎の椎弓を部分的に切除し硬膜に達します。硬膜を3cmほど縦に切開してこれを糸で左右に吊り上げると硬膜の中の様子が確認できます。馬尾は黄白色から淡桃色で左右を縦に走るのに対し、終糸は正中を縦に走り、血管に富むので淡赤色から暗赤色を呈するため肉眼的に馬尾と終糸を見分けることが出来ます(図)。さらにそれぞれを微弱な電流で刺激して、馬尾では脊髄から誘発電位が出現するのに対し、終糸は通電性がないので刺激しても誘発電位が出現せず、この方法で馬尾と終糸を区別することが出来ます。終糸と確認出来たら、まず出血しないように凝固止血して、その末梢で切離します。終糸の緊張が強い場合は、伸ばしたゴム糸を切った時の様に、切離した断端が瞬時に頭側に短縮して視野から見えなくなることがあります。緊張がそこまで強くない場合でも1~2cmの短縮が見られます。これで手術の目的が達せられたので、硬膜と筋肉・皮膚をそれぞれ縫合して手術を終了します。手術創は縦に4cm程度で時間は1時間前後、出血量は10~30mlで輸血の必要はありません。術後は当日から寝返りが可能で、翌日から座位がとれ、3日ほどで歩行を開始し、約2週間で退院になります。術後の回復には個人差がありますが、私たちの経験では通常2~6か月で回復が始まり、1年ほどでほとんどの人が改善しています。手術を受けた37人の方に行った術後調査では、術後1年から8年(平均3年5カ月)の時点で46%の人が症状が消失し、52%の人が日常生活に支障ない程度まで回復し、合計98%の人で完治ないし改善が見られています。(参考文献)
1)病態
終わりの糸と書く終糸(しゅうし)という聞きなれない組織が原因で腰痛や下肢痛、頻尿などの症状を来たす疾患です。左側の図で一番下まで続いている青い線が脊髄終糸ですが、尾髄の先端から尾椎に続く長さ約25cm、太さ0.5mmほどの柔らかい糸状の組織です。私たちが体を前屈すると、脊髄は頭側に少し移動し、それに伴って終糸も頭側に引っ張られますが、通常の終糸は柔らかいゴム糸のように伸びるので、脊髄に牽引力がかかることはありません。しかし終糸が生まれつき硬い人では、前屈した時に終糸が伸びないために脊髄が牽引されてしまい、この姿勢を続けたり繰り返したりすると脊髄の中に血流の乏しい部分が生じ、前述のような症状が出ると言われています。
参考文献












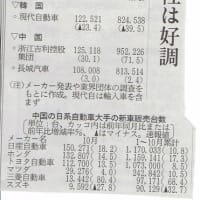


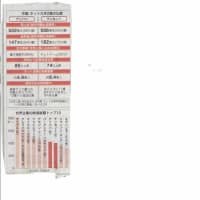
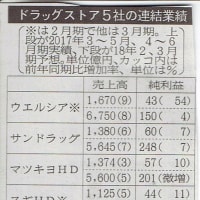

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます