東京電力福島第一原発には、6基ある原子炉建屋の使用済み燃料プールとは別に、約6400本もの使用済み燃料を貯蔵した共用プールがあり、津波で冷却装置が故障したまま、水温や水位の変化を把握できなくなっていることが、17日わかった。
*共用プールは福島だけではない、全原発現場に存在、その燃料棒はX54基、想像を絶する規模となる、
放射性物質とは何か(化学反応と核反応の違い) - アンカテ
核燃料から発生する熱は、運転中に核分裂反応から発生する熱と、運転停止後に崩壊熱として発生するものがあります。どちらも核反応なので、我々が慣れ親しんでいる化学反応(燃焼反応)と比較して、以下の点が違います。
酸素がいらない(閉じこめても熱を発し続ける)
発火点という概念がない(一時的に冷やして冷たくなっても、放置すればまたどんどん熱くなる)
逆に言えば、核反応から発生する熱には「消火」という概念がありません。つまり、化学反応から発生する熱は、酸素を奪うか低温にすることで反応を止めること、つまり「消火」ができます。
これに対し、核反応では、特定の条件が満たされる限り、閉じこめたり冷やすことで反応を止めることはできないのです。
、使用済み核燃料が出す熱は、基本的には、それがある限り一定のペースで熱を出し続けます。そして、その熱そのものを止める方法はありません。
ですから、何年、何十年もの間、冷やし続けるしかなくて、冷やすためには水をかけ続けるしかないのです。水以外の他の手段で熱を奪うことも考えられますが、少なくとも熱を奪い続ける必要があるのです。
核分裂と自己崩壊
そして、核燃料が発する熱には、原子炉の運転中に起こっている核分裂反応によるものと、それが停止してから起こる自己崩壊によるものがあります。どちらも核反応で、放射線と熱を発生しますが、以下のような違いがあります。
核分裂の方が、出すエネルギー(熱)がはるかに大きく、発電に使われるのは核分裂反応の方である
核分裂反応は、特定の条件(後述)が満たされた時に発生するが、自己崩壊は、その物質が存在するだけで必ず発生する
原子炉内で起こる核分裂反応は、ウラン235が中性子を吸収した時に起こるものだけだが、自己崩壊は多種多様な物質が多種多様な反応を起こす
核分裂反応が連続的に起こる条件とは、燃料の中にあるウラン235が中性子を吸収できることです。ウラン235は非常に稀な確率で中性子を放出しますが、この中性子が他のウラン235に吸収されると、そこからさらに中性子が出ます。この放出された中性子が間違いなく次の反応につながっていけば、倍々ゲームで中性子が放出され反応が継続します。これを臨界と言います。
臨界が起こるための条件とは以下の通りです。
自然に存在するウランの内ウラン235は0.72パーセントなので、それを濃縮する必要がある(燃料棒の中のペレットはこの状態)
もともと、事故がなくても原子力発電所の廃炉は数十年単位の時間がかかる大変な作業です。燃料が燃料棒の中に収まっていれば、時期を待って燃料を燃料棒の形で取り出すことができます。それでも、残された容器や配管の解体・撤去は大変な時間がかかるそうです。
燃料棒が破損した場合の解体・撤去の手順や、そもそもそれが可能なことかどうかについては、私は今の所具体的な言及を見つけることができていません。たぶん、専門家の方にも、前例が無さ過ぎて簡単には答えられない問題なのではないかと思います。
直感的に考えると、ペレットの形で飛び出し、場合によっては溶けてしまった燃料の回収や、超高濃度汚染水が何回も通った容器や配管の解体は、ほとんど不可能ではないかと思えます。
燃料棒に燃料が収まっているというのは、このように原子力発電所のライフサイクル全体に関連する重要な問題なのではないかと感じます。
原子炉の安全性と使用済み核燃料の問題は別
福島原発の事故について、多くの専門家が口を揃えて「これはチェルノブイリのようにはならない」と言いました。私も全く同感で、同じことを、回りに言いました。経済産業省原子力安全・保安院は、福島第1原発事故の深刻度を国際評価尺度(INES)の暫定評価で、チェルノブイリと同等、最悪の「レベル7」とすると発表しました。
なぜ多くの専門家が楽観視してしまったかと言うと、これは停止後の燃料棒の発熱の問題を軽視していたからだと思います。
使用済み核燃料の問題は、それと比較して、軽視されていたのではないかと思います。
すでに数年以上かけて冷却されているため、ただちに爆発する危険は少ないとみられるが、政府と東電でつくる福島原発事故対策統合本部は、共用プールへの対応も迫られている。
使用済み燃料、共用プールにあと6400本
福島第一では、この共用プールにある大量の使用済み燃料も大きな問題です。これは、発熱量については使用直後の燃料棒より少ないものの、冷却が止まれば熱によって燃料棒の損傷の可能性があるという点では、同じです。炉の中でなく外のプールに放置されていることや数が多いことから、今後、原子炉内の燃料棒より大きな問題となる可能性もあります。
運転中の原子炉の危険性があまりにも明白であるために、使用済み核燃料の問題は、一種のエアポケットになっているような気がします。
*特にかつては、半減期数万年の核種を数万年保管せねばならない事が、原子力発電のネックであった。しかし、最近、長半減期物質を分離して、加速器駆動未臨界炉において中性子を照射して、自然崩壊ではなく、核分裂させて、短半減期核種に変換できる見通しが立てられた。これにより500年以下の保管で天然ウラン鉱石以下の放射線に低下させて廃棄/鉛やバリウムとして一般使用が可能になるとして開発がすすめられている。
*それにしても500年は長過ぎる?












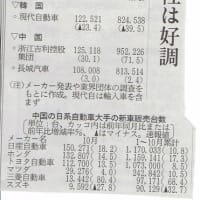


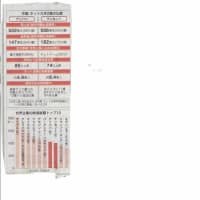
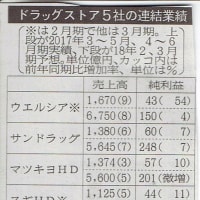

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます