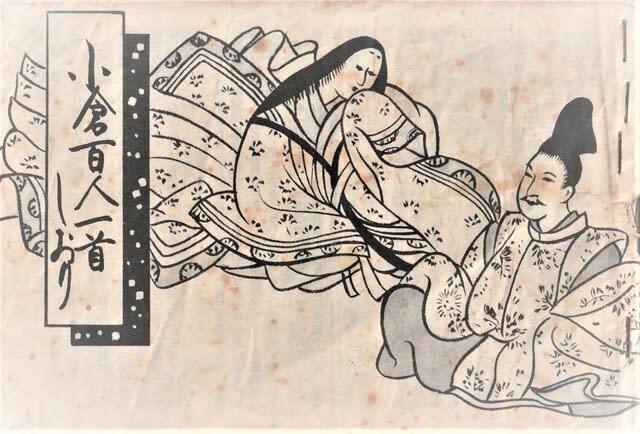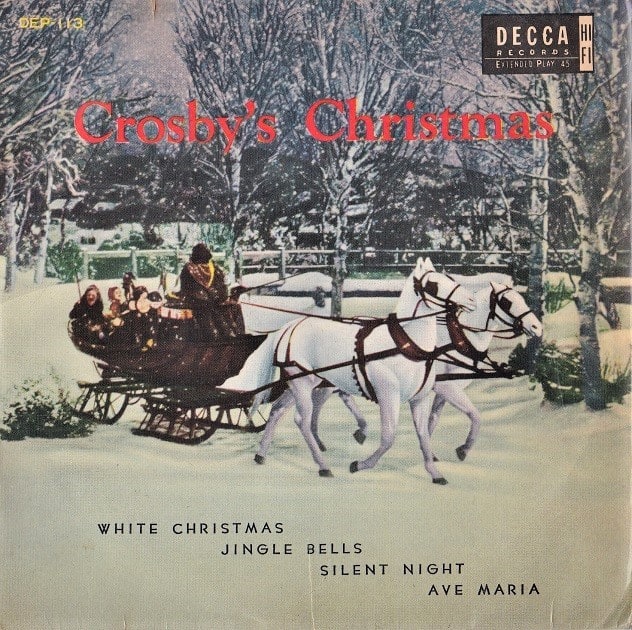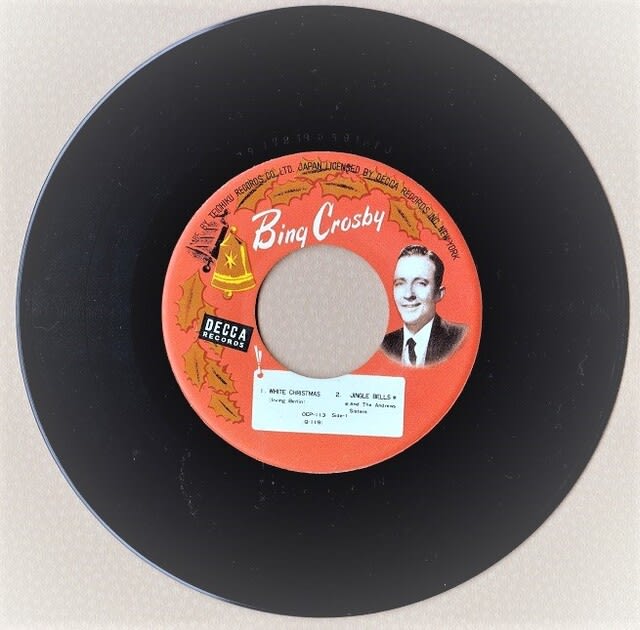gooブログの「アクセス解析」の「アクセスされたページ」欄を、時々覗くことがあるが、随分前に書き込んだ古い記事で、すっかり忘れてしまっているような記事にアクセスが有ったりすると、「エッ?」と驚くと同時に、「そう言えば・・・・」、記憶が蘇り、つい、自分もクリックし、改めて読み返してみたりすることがある。
8年前の今日、2014年12月27日に書き込んでいた記事「魔女の一撃」にアクセスが有ったことに気が付き、「おお!、懐かしい!」・・、早速、コピペ、リメイクしてみた。
そんな古い記事を、クリックひとつで引っ張り出して読んだり、加筆、訂正、修正、コピペ、リメイク等が出来るのも、ブログのメリット。従来の紙ベースの日記、日誌、備忘録、懐古録、雑記録の類では、絶対考えられないことであり、ブログを始める前までは、想像も出来なかったことである。今、出来ることは、やってみる・・、長生きした分、その時代を少しでも享受したいものだ等と、つぶやきながら・・・。
加齢と共に最大限注意しているせいもあってか、最近数年間は、腰の「ギクッ!」に襲われることが無くなっているが、当時は、しょっちゅう発症、その度に治療していたもので、改めて自戒しようと思うところだ。特に、寒くて慌ただしい年末は、要注意。
振り返り記事
8年前、2014年12月27日
「魔女の一撃」
昨日、魔女に一撃を食らいました?。
事務所のファンヒーターに給油しようとし、屋外で満杯にした、9リットルタンクを持ち上げた瞬間、「ギクッ!」。
運動不足や筋肉疲労状態で、物を持ち上げたり、身体をよじったりした時、はずみで起きるぎっくり腰。「魔女の一撃」と呼ばれています。
痛みは軽かったものの、まさに、忘れた頃に発症する、「我が腰痛問題」。
「しまった!」と思っても、遅かりしで、一晩、マッサージ、柔軟体操を試みましたが症状変わらずです。
今朝、いつもの脊椎矯正T治療院に駆け込み、所要時間約45分の施術を受けてきました。毎度のこと、1回の治療で治ってしまうのは、当方にとっては、非常に有難く助かります。施術料7000円が高いのかどうかはともかく、何日も通院して治療すること等不可能な職業柄、こんな緊急事態を、即解消してくれるT治療院は、心強い存在なのです。
靴下を履く姿勢すらもつらかった症状が、今は正常に戻っています。
通常は、4~5日「安静」にしていれば、次第に軽くなっていく場合が多い等とされていますが、 何日も「安静」にして回復を待つ余裕も無し。主な年内業務は、終了したものの残務有り。明日28日は、正月用の野菜収穫等で畑に向かう予定ですし、餅つき、大掃除等々、年内は大忙しです。高齢者とて、「のーんびり、炬燵でテレビ」も良しですが、なにかと動き回っている方が性に有っているのかも知れません。2014年も残り少な。いろいろ有りましたが、なんとか乗り切れそうで、それが何よりもうれしいこと。来年も、今の体調を維持して行けるよう願うばかりです。
振り返り記事
9年前、2013年3月24日
「ギクッ・・腰痛襲来」
1昨日、突然、「ギクッ」。またまたと言うべきか、とうとうと言うべきか、急性腰痛症(ぎっくり腰)に襲われました。特別重い物を持ち上げようとした分けでもなく、車の運転席から降りようとして、ちょこっと体を捻じった瞬間のことです。確かに、このところ、畑仕事や長距離運転が続いて、腰部にも疲労が蓄積、十分注意していたつもりですがやってしまいました。
40代から、数年に1回の頻度で襲われている 私の腰痛問題。程度の差はあるものの、「ギクッ」襲来は、もう10数回にのぼります。その都度、脊椎矯正専門のT治療院に駆け込んで治してきましたが。
腰痛治療法は、いろいろ有りますが、私にとっては、そのT治療院で受ける約40分の矯正治療が最も有効で、ほとんどの場合、ほぼ1回で、正常に戻り、帰りは、ルンルンになります。長期間の通院治療等しておれない私には、T治療院は、有り難い存在なのです。今回は、動けなくなるような重症ではなく、座った姿勢から立ち上がる際、中腰になる瞬間に、「ギクッ」と痛みが走る程度でしたが、悪化させないためにもと、昨日、T治療院に行ってきました。今日は、一応、「貼るカイロ」で温めてはいますが、痛みは全く無くなり、普通に動けます。先程、醤油類等重い買い物のぶら下げて、スーパーから戻ってきたところです。
私の場合、「腰痛(ぎっくり腰)は、忘れた頃にやってくる」という感じではありますが、今後とも、腰痛との縁は切れそうにありません。「魔女の一撃」等とも称されているようですが、治ってしまうと、「喉元過ぎれば 熱さを忘れる」性分で、どうも油断してしまいがちです。
折りしも、今日の朝日新聞の1面に、厚生労働省の調査で、「腰痛で悩んでいる人は、全国で2800万人いる」という記事が載っていました。腰痛仲間がいかに多いか、納得してしまいます。
(ネットより拝借イラスト)