今年も本屋大賞が決まった。大賞を受賞した本は、たちまちベストセラーとなり、作者の他の本にも関心が向けられ、ロングセラーとなるという。大賞候補として10冊を選ばれていて、決定後は、これらの本も売れはじめ、ここにも連鎖反応が生じるという。まさに、全国の書店員さんが選んだ「いちばん!売りたい本」の効果は予想以上の成果を挙げている。売りたいという熱意が、結実しているわけである。そこで、全国の公共図書館員は、「本のベテラン」として、どういう気持ちなのだろうかと、思うわけである。先日のテレビで、エプロン姿の男子書店員に若い女性たちが、知性とやさしさと、いろけを感じる「書店男子」なるものの姿が、放映されていた。「図書館男子」というのは、宮崎県立図書館で、イメージできそうもないが、どうだろうか。大賞本を手に手にした20人ほどの笑顔の書店男子、書店女子の輝かしい金メタルでもとったようよろこびにあふれたシーンが放映されたが、図書館司書たちは、それをみてどう感じているのだろうか。
数日前、深夜のテレビ番組で、新潮社、もう一社、これも大出版社の社長をまじえて出版社の未来についての鼎談がつづいていた。出版社の現況は、耳をうたがうほど深刻に思えるのだった。新刊書は、今7万点(冊ではない、全集でも、上・下ほんでも一点として数えて、7万種の本)出版されるというのだが、ベスト・セラーやロング・セラー本を除いて、すべて赤字だとう。新刊を書店の配本しても60パーセントは売れずに返本されるという。あとは、その中でいくらかが、時間をかけて売れていくのをまつしかない。今、出版社が経営ができるのは、なんといってもベストセラー、100万部単位のベストセラーがでると、新刊本のマイナスを補ってもらえる。そのことで、売れる売れないということと関係なくいい本を出せるのだというのだ。なるほど、そうなのかと、ため息がでる話だ。なにしろ大学生の70パーセントが一日に一冊の本も読まないという時代が、もう何十年もつづいてきているんですからなあと、二人の慨嘆が出る。そして、つづけられた言葉に、ショックを受けたのであった。
「ですから、図書館がベストセラー本を何十冊と購入して、利用者に貸し出すというは
いかがなものかとおもうのですよ。」
司会コメンテーター「しかし、住民にとって無料でおもしろ本が借りられるのありがたいわけでしょう。」
「いや、貸すな、買うなというわけではないのです。この私の図書館に聞きましたが、同じ本を127冊購入し2000人以上の貸し出し申込者に貸すわけですよね。借り手は何ヶ月もまたねばならない。もし図書館が、同じ本をこんなに買うのを、一年でも待ってもらえれば、その間に本は売れ、われわれも一息つけて、新刊を出せるのです。ベストセラーなど、いや本は買って読んでもらいたいものです。」
「というと、図書館がベスト・セラーの売れ行きを妨害しているというわけですか」
「妨害とまでとはいえないですけど、少し、購入を待ってたもらえばいいのです。」
大学生は本はよまないし、一般大衆は、本を買おうとしないし、出版社のベスト・セラー頼みの経営は切実で、胸をつまされる内実であった。しかし、公共図書館が昭和40年代から、アメリカや英国の公共図書館の活動を学び、だれにでも、どこでも、いつでも本を貸し出す、本の貸し出し、これが公共図書館のやらねばならぬ使命だと、てようやく、徹底した無料貸し出し、利用者への利便性実現、この目的に適う公共図書館が、全国的にも実現してきた。ただで、ただで、貸しまくる、そのためには、100ぺんでも頭をさげる、これが全国図書館員の魂であるとされてきた。だがしかし、今や、図書館の貸し出し活動が、出版を阻害するといわれるのだ。図書館が活動すればするほど、出版文化を破壊しかねないとは...、「本くらい自分で買って読め」で収まるのか。図書館は出版文化を阻害する。これはへりくつでもなんでもなく、現実として、わが国の文化を覆ってきている。繁栄した北京を覆う 大気汚染: PM2.5の灰色の空気が
ビルも歩道も覆うように読書環境を覆いだしている。どうすればいいのか。この社長さんたちの話には、矛盾点があるし、本屋大賞と読書とは、関係はないのが見逃されている。ここに解答があると思われる。北京からの脱出路がありそうだ。
数日前、深夜のテレビ番組で、新潮社、もう一社、これも大出版社の社長をまじえて出版社の未来についての鼎談がつづいていた。出版社の現況は、耳をうたがうほど深刻に思えるのだった。新刊書は、今7万点(冊ではない、全集でも、上・下ほんでも一点として数えて、7万種の本)出版されるというのだが、ベスト・セラーやロング・セラー本を除いて、すべて赤字だとう。新刊を書店の配本しても60パーセントは売れずに返本されるという。あとは、その中でいくらかが、時間をかけて売れていくのをまつしかない。今、出版社が経営ができるのは、なんといってもベストセラー、100万部単位のベストセラーがでると、新刊本のマイナスを補ってもらえる。そのことで、売れる売れないということと関係なくいい本を出せるのだというのだ。なるほど、そうなのかと、ため息がでる話だ。なにしろ大学生の70パーセントが一日に一冊の本も読まないという時代が、もう何十年もつづいてきているんですからなあと、二人の慨嘆が出る。そして、つづけられた言葉に、ショックを受けたのであった。
「ですから、図書館がベストセラー本を何十冊と購入して、利用者に貸し出すというは
いかがなものかとおもうのですよ。」
司会コメンテーター「しかし、住民にとって無料でおもしろ本が借りられるのありがたいわけでしょう。」
「いや、貸すな、買うなというわけではないのです。この私の図書館に聞きましたが、同じ本を127冊購入し2000人以上の貸し出し申込者に貸すわけですよね。借り手は何ヶ月もまたねばならない。もし図書館が、同じ本をこんなに買うのを、一年でも待ってもらえれば、その間に本は売れ、われわれも一息つけて、新刊を出せるのです。ベストセラーなど、いや本は買って読んでもらいたいものです。」
「というと、図書館がベスト・セラーの売れ行きを妨害しているというわけですか」
「妨害とまでとはいえないですけど、少し、購入を待ってたもらえばいいのです。」
大学生は本はよまないし、一般大衆は、本を買おうとしないし、出版社のベスト・セラー頼みの経営は切実で、胸をつまされる内実であった。しかし、公共図書館が昭和40年代から、アメリカや英国の公共図書館の活動を学び、だれにでも、どこでも、いつでも本を貸し出す、本の貸し出し、これが公共図書館のやらねばならぬ使命だと、てようやく、徹底した無料貸し出し、利用者への利便性実現、この目的に適う公共図書館が、全国的にも実現してきた。ただで、ただで、貸しまくる、そのためには、100ぺんでも頭をさげる、これが全国図書館員の魂であるとされてきた。だがしかし、今や、図書館の貸し出し活動が、出版を阻害するといわれるのだ。図書館が活動すればするほど、出版文化を破壊しかねないとは...、「本くらい自分で買って読め」で収まるのか。図書館は出版文化を阻害する。これはへりくつでもなんでもなく、現実として、わが国の文化を覆ってきている。繁栄した北京を覆う 大気汚染: PM2.5の灰色の空気が
ビルも歩道も覆うように読書環境を覆いだしている。どうすればいいのか。この社長さんたちの話には、矛盾点があるし、本屋大賞と読書とは、関係はないのが見逃されている。ここに解答があると思われる。北京からの脱出路がありそうだ。











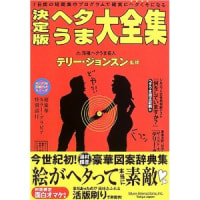











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます