ドキュメンタリー映画「靖国」は、この4月、内容に偏向ありと上映自粛が行なわれ、その後、言論・思想の自由を盾に全国各地で上映されている。「宮崎キネマ館」で、9月15日その最終回で、無事見終わった。
風評では、右にも左にも配慮した内容で、問題はないじゃないかといわれていたが、李監督の作成した靖国は、そんなあいまいなものでなく、国家権力と靖国、個人と靖国、そして国家と個人という問題を問う明快な主題を示していた。
国家権力は暴力装置だということ、その暴力を個人が徴兵義務で、遂行し、何百万人が戦死し、その霊が合祀されているのが、靖国である。そこで、その霊に拝するのは、国民として当然だとする理由で、靖国はありつづけてきた。
きわめて明快な理由である。しかし、問題はここから、発生する。国のために死んだのではなく、個人の自由を奪われて、死ななければならなかったという個人もまた、多数合祀されているということだ。
つまり国に殉じた英霊と、国家権力への怨霊も同時に靖国は宿しているわけだ。
靖国のドキュメンタリ映画としての現実感は、英霊と怨霊は逆巻く怒涛として、靖国を暗く覆っている現実を証していることである。その両者をつなぎ、妥協点を見出す言葉はないと、映像はシーンを展開して行く。
社殿前に旧日本軍人が、再現される。抜き身の日本刀である指揮刀をささげなにかを念誦する老人の異様さ、進軍ラッパに行進する小隊、ひるがえる日章旗のシーンの積み重ねに、それが、コスプレの遊びにすぎないというぼくのせせら笑う気分は次第に消されていく。なんだ、こいつらは、遊びでなく、それが自己の存立の基盤であり、モラルの根拠となっているではないかと、納得せざるをえなくなる。
19年を日本にくらしているという李さんにとって、この日本人の心象は、圧倒するような現実感を感じたのであろう。彼は映画の進行を、靖国刀を打つ現在90
歳になった刀鍛冶が、鉄を溶かし、その塊を打ち伸ばし、次第に刀の姿をととのえはじめ、ついに日本刀と完成するまでとシンクロナイズさせている。この挿入は、きわめて象徴的である。日本刀は暴力の武器でありどうじに美である。
李監督は、靖国で、この美を映像で示す。靖国は、夜の闇と光のなかに、降りしきる雨のシーンが多用されている。とくに夜、雨のなかを50人近くの神職が、木靴の音だけを発しならが、神殿に進んでいき中に消えていく光景は、靖国が観るものの意識に入っていくような存在感を発していた。これは、リドリー・スコットのブレード・ランナーの暗い現実感を連想させた。恐るべき美の存在だ。
それは、戦後60年を経ても日本人の意識を捉えていると、李監督は主張したかったのだろうか。いや、ぼくはそうではないと思う。ラストシーンでは、夜の靖国神社が捉えられ、すぐにパンして、神社はと東京の広大な都市風景に泡のひとつのように吸い込まれていくシーンで終る。靖国は日本のほんの一部というのか、それはぼくの深読みかもしれない。
しかし、付け足すなら、この伝統の美意識も、同じ日本人の美術評論家・ 椹木 野衣は、その著書「日本・現代・美術」で、それは幻想に過ぎないと否定している。もっと現実は、個々に複雑で、それを無視して美という総なめの価値基準でくくるのは、間違いだと伝統の分析をとおして説いている。人生はもっと、個別的に豊かであるのだ。
さらに国家権力の暴力は、日本だけでなく中国もロシアもアメリカもまったく同じであり、暴力は、絶えず美化されつつけている。こんな中で、戦後60年、軍事力を憲法で否定してきたのも日本である。エコノミック・アニマルといわれ、アメリカの忠犬とさげすまれても、とにかく軍事力を排除しているのも日本人なのであると、ドキュメンタリー靖国は、そのことを再確認させてくれた。この映画の普遍
性は、じつはここにある。映像は言葉でなく、この暴力否定を世界に説いている。
いやあ、憲法9条をこのドキュメンタリーにくっつけるのは、いっそうのぼくの深読みかもしれない。だが、この「靖国」を中国人である李監督が、日本の特殊な美意識と、捉えたというのでは、あまりに単純すぎよう。そのような見方は成立しないほど、世界はグローバル化され、同一の基準のもとで、国そのものも存立していける。そのとき、おのずと映画は、国家の暴力とは、その担い手である国民、個人とはなにかと考えさせられる内容を、李監督は、その映像で、生き生きと示したと思うのが、彼の評価であるといえるのではなかろうか。
風評では、右にも左にも配慮した内容で、問題はないじゃないかといわれていたが、李監督の作成した靖国は、そんなあいまいなものでなく、国家権力と靖国、個人と靖国、そして国家と個人という問題を問う明快な主題を示していた。
国家権力は暴力装置だということ、その暴力を個人が徴兵義務で、遂行し、何百万人が戦死し、その霊が合祀されているのが、靖国である。そこで、その霊に拝するのは、国民として当然だとする理由で、靖国はありつづけてきた。
きわめて明快な理由である。しかし、問題はここから、発生する。国のために死んだのではなく、個人の自由を奪われて、死ななければならなかったという個人もまた、多数合祀されているということだ。
つまり国に殉じた英霊と、国家権力への怨霊も同時に靖国は宿しているわけだ。
靖国のドキュメンタリ映画としての現実感は、英霊と怨霊は逆巻く怒涛として、靖国を暗く覆っている現実を証していることである。その両者をつなぎ、妥協点を見出す言葉はないと、映像はシーンを展開して行く。
社殿前に旧日本軍人が、再現される。抜き身の日本刀である指揮刀をささげなにかを念誦する老人の異様さ、進軍ラッパに行進する小隊、ひるがえる日章旗のシーンの積み重ねに、それが、コスプレの遊びにすぎないというぼくのせせら笑う気分は次第に消されていく。なんだ、こいつらは、遊びでなく、それが自己の存立の基盤であり、モラルの根拠となっているではないかと、納得せざるをえなくなる。
19年を日本にくらしているという李さんにとって、この日本人の心象は、圧倒するような現実感を感じたのであろう。彼は映画の進行を、靖国刀を打つ現在90
歳になった刀鍛冶が、鉄を溶かし、その塊を打ち伸ばし、次第に刀の姿をととのえはじめ、ついに日本刀と完成するまでとシンクロナイズさせている。この挿入は、きわめて象徴的である。日本刀は暴力の武器でありどうじに美である。
李監督は、靖国で、この美を映像で示す。靖国は、夜の闇と光のなかに、降りしきる雨のシーンが多用されている。とくに夜、雨のなかを50人近くの神職が、木靴の音だけを発しならが、神殿に進んでいき中に消えていく光景は、靖国が観るものの意識に入っていくような存在感を発していた。これは、リドリー・スコットのブレード・ランナーの暗い現実感を連想させた。恐るべき美の存在だ。
それは、戦後60年を経ても日本人の意識を捉えていると、李監督は主張したかったのだろうか。いや、ぼくはそうではないと思う。ラストシーンでは、夜の靖国神社が捉えられ、すぐにパンして、神社はと東京の広大な都市風景に泡のひとつのように吸い込まれていくシーンで終る。靖国は日本のほんの一部というのか、それはぼくの深読みかもしれない。
しかし、付け足すなら、この伝統の美意識も、同じ日本人の美術評論家・ 椹木 野衣は、その著書「日本・現代・美術」で、それは幻想に過ぎないと否定している。もっと現実は、個々に複雑で、それを無視して美という総なめの価値基準でくくるのは、間違いだと伝統の分析をとおして説いている。人生はもっと、個別的に豊かであるのだ。
さらに国家権力の暴力は、日本だけでなく中国もロシアもアメリカもまったく同じであり、暴力は、絶えず美化されつつけている。こんな中で、戦後60年、軍事力を憲法で否定してきたのも日本である。エコノミック・アニマルといわれ、アメリカの忠犬とさげすまれても、とにかく軍事力を排除しているのも日本人なのであると、ドキュメンタリー靖国は、そのことを再確認させてくれた。この映画の普遍
性は、じつはここにある。映像は言葉でなく、この暴力否定を世界に説いている。
いやあ、憲法9条をこのドキュメンタリーにくっつけるのは、いっそうのぼくの深読みかもしれない。だが、この「靖国」を中国人である李監督が、日本の特殊な美意識と、捉えたというのでは、あまりに単純すぎよう。そのような見方は成立しないほど、世界はグローバル化され、同一の基準のもとで、国そのものも存立していける。そのとき、おのずと映画は、国家の暴力とは、その担い手である国民、個人とはなにかと考えさせられる内容を、李監督は、その映像で、生き生きと示したと思うのが、彼の評価であるといえるのではなかろうか。











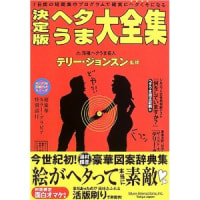












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます