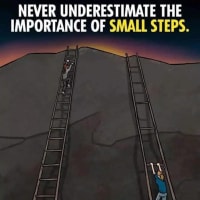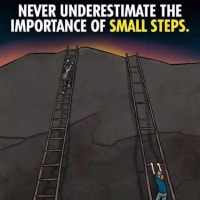とても普遍的なテーマですが、人は本質的に、自分の人生や生活の中に安心感と満足感を求めます。
安心感と満足感の両方が満たされている時、人は、幸福感を感じます。この状態が比較的安定して続いていると、その人は人生全体に対して高い幸福感を持つようになります。
余談ですが、心理学の実験において、人間の幸福度のデータを集める際に、本質的に「質的」な幸福度を数値化しなくてはならないため、便宜的に「人生の満足度」(life satisfaction)というスケールを用いるのは、興味深い事だと思います(脚注)。
つまり、人生の満足度と幸福感はそれだけ深い関連性を持っているわけです。
一方、安心感が直接的にその人の幸福度と繋がっているとは限らないようです。
もちろん、ほとんどの場合、幸福感の強い人は、安心感も満足感も高い傾向にあります。
「人生に満足してるけど不幸せな人っているじゃないですか」、と思われる方もいるかもしれませんが、本当に人生に満足している人は、幸福感も強いです。
つまりは、こうした人は、少なくとも無意識的、前意識的には人生に満足していないという可能性が考えられます。例えば、諦めている事と満足している事は違いますが、人は時にこの2つを混同します。
例によって前置きがだいぶ長くなりましたが、本題に入ります。
生活に安心感はあるけれど、満足感や幸福感がない、足りない、という人々は、実際とても多いです。
例えば、高収入で、生活レベルも高く、貯蓄もできていて、人生における不安感は低いけれど、不満は強い人を想像すると、分かりやすいと思います。
結婚生活や長期的なパートナーシップにおいて、経済的に問題なく、2人とも健康で、不貞行為や深刻な問題行動が存在しない関係性で、安心感はあるのに不満や不幸せな気持ちを抱いている方はたくさんいます。
むかしの人は、こうした人たちを「わがまま」だとか、「足るを知るべき」とか言いますが、私はそうは思いません。こうした人たちの抱える問題はそのように軽くあしらうべきでない、深刻な問題だと思っています。
恋愛関係でも、こうした事例は多いです。
今の相手とのパートナーシップに安心感はあるけれど、不満があり、あまり幸せではない、という状態です。
(これにも実際のところ、様々な理由や事情があり、一概にいうことはできないのですが、私の問題として、こうして何か書こうと思っていざ文章を書きだすと、そうした様々なケースや可能性についてどんどんいろいろな考えが出てきてその都度対処しているうちにだんだん収集つなかくなってきて文章が膨れ上がっていき、書き上げる気力が失せてしまいお蔵入り、ということがあまりにも多いので、今年はあえて簡素化してでも書き上げるように努めていきたいと思っています)
こうした人に時折見受けられる傾向として、意識ではもちろん自分にとって最善な人だと思ってお付き合いをしたり、結婚を決意したりするものの、無意識的に、そのようになりにくい人を選んでしまっているということがあります。
たとえば、幼少期の家庭環境で、親からの共感不全を慢性的に経験していた人は、親がその人と親密になることができなかったため、その人は大きくなって、親密さの課題を抱えることになります。親と親密になれなかったので、誰かと親密になる、ということがどこか居心地が悪かったり、落ち着かなかったり、恐怖であったりして、無意識的に、誰かと親密になることを回避します。こうした方たち本人は、自分が親密さを恐れている、親密さを回避している、という自覚は通常ありません。無意識の葛藤です。
こうした方たちが知らず知らずのうちに選びがちなパートナーは、性格は比較的穏やかだけれど、共感性が低い人たちです。
穏やかであることと、優しいことは、実は似ていて非なるものなのですが、こうした人たちは、穏やかさと優しさを混同します。
世の中、穏やかだけれど実はすごく冷たい人、穏やかだけれど本質的に自分にしか興味のない人、穏やかだけれど自己完結していて思いやりに欠けている人は、たくさんいます。
他者と親密になることを実は恐れている人と、穏やかだけれど共感性が低い人との組み合わせのカップルです。
こうした人たちは、自分は相手と親密になりたいと意識では思っていて、なかなか親密になれないことに不満や怒りや悲しみを経験します。
しかし彼らが気づいていないのは、もし相手にもっと強い共感性があり、うまく繋がってこれる人であったら、彼らの無意識の恐怖心は活性化され、その関係性はとても居心地の悪いものになり、関係は早期に破綻してしまうかもしれません。とても皮肉な事ですが、繋がれない相手だから一緒にいられるのです。そして、彼らは無意識的にそういう人を選んでいます。関係性が安定して、持続可能なものになる相手です。安定していて持続可能だけれど、この人たちの不幸せな気持ち、満たされない気持ちは続いていきます。こうした人たちの心の成り立ちにおいては、安心感と満足感が二律背反しています。不満と安定がセットになっています。
こうしたケースでは、相手の方にとっては、この関係性はそれなりに満足感のあるものであり、何が不満なのか分かりません。
ひとつの結婚、ひとつのパートナーシップにおいて、それが、一方においては良い関係だけれど、もう一方においては良くない関係、という事例です。
それではどうしたら、この不幸せな安定から抜けさせるのでしょうか?
そのお連れ合いと別れればいいのでしょうか?
そんな簡単な話ではありません。そして、たとえお連れ合いと別れたところで、その人が自分のテーマに無自覚であれば、そのテーマは次に選んだ「全く異なるタイプの人」と、表面的には異なっても、本質的には同じように繰り返すことになります。
それよりもまずは、自分が親密さを希求しながら、実は親密さを恐れていて、親密さを避けているのだと意識化する必要があります。
というのも、人間は、幼少期に家庭環境で形成された人間関係の無意識のテーマを、大人になってからも無意識に再現し続ける性質があるからです。そして、この無意識のテーマは無意識である限り永続します。
しかし、ひとたび本人がその無意識の動機を意識化する事ができると、その流れに歯止めをかけることができるようになります。
歯止めを掛けたら、次は、その親密さに少しずつ挑戦していく事です。小さな新しい行動をその関係性の中で試みていきます。カップルの関係性は常に動的な平衡状態にあるので、ひとりが新しい行動を取ると、一時的に平衡状態は崩れます。これがとても大事な事で、今度はパートナーはあなたの新しい行動に応じて新しい行動をとってきます。それは最初は必ずしも望ましい行動とは限りません。しかし、めげずに根気よく取り組んでいく中で、親密さに対する「耐性」ができて、次第により近くて親密な距離感で新しい動的平衡状態に達します。
親密さを回避する人が、本当の本当に親密さが嫌なのかといえば、そうではありません。本当のところでは親密である方が良いのだけれど、経験した事がない不確かで未知の領域であるため、怖いのです。その不確かで未知の領域に入っていく勇気が、本当の幸せにつながります。
(脚注)心理学は、日本では「文系」に位置付けられていますが、国際的には科学であり、理系の要素も多分に含んでいます。いわゆる「科学的」な実験が盛んに行われているのですが、ここで難しいのは、人間の心の科学という、本質的に「質的」なものを、実験ではそのプロセスで、「量的」なもの、つまり数値化する必要があります。ここに心理学の実験の限界点が常に存在しているわけですが、この限界点にどう対応していくかがまた心理学の実験のポイントでもあります。