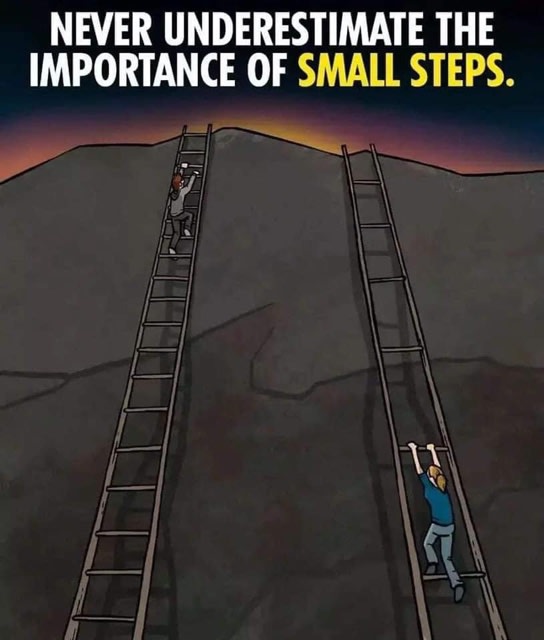タイトルにもあるように、最近、日本の政治や芸能のニュースを読んでいると、「不快に思われる方がいましたら申し訳ありません」といった言い回しをされる方が多い印象を受けます。政治家や芸能人に限らず、この言い方をする人は少なくありませんね。
そして、多くの方が、この言い回しに違和感を感じられています。
私もこの言い回しやその感覚には違和感を感じます。こういう言い方をされて気持ちが良い人はあまりいないと思います(脚注1)。
なぜなら、こういう言い方をする人は、本当に自分が悪かったと思っていないからです。
それどころか、自分は正しくて、相手の受け止め方に問題があった、と、大なり小なり思っていて、「そういうふうに感じた相手の問題だ」と、無自覚に、相手のせいにしてしまっています。「自分は悪くないから、本当は謝りたくないし、謝る必要もないと思うけれど、謝らないと収拾がつかない、あるいは良くない成り行きが予測されるから、違和感があるけれど、しかたないので謝ろう」、という心理がこの態度の背景にありそうです。
少なく言って、心から反省はしていませんし、どうして相手が傷ついたのか、理解できていません。自分の何がいけなかったのか、理解できていないので、たとえこのように「謝罪」しても、また同じことを繰り返し続けます。
こういう言い方をする人たちの典型的な特徴として、やはり、自己愛が強く、プライドが高い、ということが挙げられます。自己愛が強く、プライドが高い人は、自分の非を認めることができません。先日の兵庫県知事の斉藤元彦氏の記者会見は本当に惨憺たるものでした。どうやら彼はこの期に及んで自分が周りを傷つけていたことに気づいていないようです。
何があっても自分の非は認めない、というメンタリティは、トランプともよく似ています。
以前にもここで時々お話しましたが、自己愛の強さと自己中心性は連動し、これらが強いほどに、共感能力は低くなる相対関係があります。
絶対に正しい人などそもそもいないのですが、彼らは、「自分が正しい」という立ち位置に自分を固定してしまっているので、相対的に、常に相手が間違っていることになります。
「毒親」という言葉は個人的にはあまり馴染みませんが、そう呼ばれる人たちが、子供の失敗に対して、すごい剣幕で暴言を吐いて、その結果子供が泣いてしまったら、「なんでそんなことで泣くの?」とか、「あなたの受け止め方の問題よ」ということを言ったりします。
仕事で上司が部下に、休日や夜間をお構いなしに連絡して、相手が疲弊したら、疲弊する側が弱い、という考え方は、思いやりがなく、分かりやすいパワハラですが、どうにも元彦さんにはこの自覚がないようです。「私は厳しい知事」というスタンスで逃げ切りたいようですが、それはどうにも無理があります。彼は厳しいというよりも独善的で理不尽です。
どうして部下たちが自分のことを疎ましく思っているのか。どうして相手は嫌がっているのか。どうして相手は自分に抗うのか。どうして性行為をした相手がとても傷ついて、自分を訴えてきたのか。松本さんの、「参加された女性の中で不快な思いをされたり、心を痛められた方々がいらっしゃったのであれば、率直にお詫び申し上げます」という仮定法は被害者には響きませんし、嫌な気持ちは軽減しません。
本当に強い人は、自分の感情や主観をとりあえず傍らにおいて、相手の主張に耳を傾けます。矛盾するようだけど、これができる人は、そもそも他者を傷つけるようなことはしませんが。
いずれにしても、自分の何らかの行為で相手が傷ついてしまったら、人は、自分の自己愛と戦う必要があると思います。
自己愛と戦って、防衛的な態度をやめて、こころを開いて、相手の言い分としっかり向き合う必要があります。
「違法性がなければ」何をしても良いわけではないんです。
自分の行為で相手が困っていたら、ましてやその人たちと今後も一緒にやっていきたいのであれば、相手とちゃんと向き合う必要があります。斎藤さんは、百条委員会と向き合わなければなりません。多数決と公正な審査によって出た結論を尊重して受け入れるのが民主主義の基本ですし、それができないなら、斎藤さんは知事を続ける資格などないですし、そもそもその資質もないでしょう。
もしあなたのパートナーや大切な人が、あなたに対してこういう態度を取り続けるのであれば、その人と今後一緒にいることを続けるかどうか、再考する必要があるかもしれません。その人は、何がいけなかったのか理解していないので、遅かれ早かれ、時間の問題で、同じことであなたを傷つけるでしょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
脚注1)もちろん、例外的な状況はあります。たとえば、コーヒー屋さんに来たお客さんが、「デカフェ ブレンドコーヒー」の「デカフェ」の意味が分からないまま、この名前が気になったので注文して飲んで、いつものコーヒーと微妙に飲み心地が違う気がして、店員さんに、「『デカフェ』ってなんですか?」と聞きましたところ、店員さんが、「カフェインがほとんど入っていないものになります」と答えました。するとそのお客さんはがっかりして、しかしカスハラ的な威圧感は全く出さずに、「そうだったのですね。。カフェインが入っているのが飲みたかったです」となんだか落ち込んでしまっている様子を見せました。この時、優しくて共感的な店員さんは、自分は全然悪くないという認識でも、「ああ、そうだったのですね。。申し訳ありません。デカフェってそういうコーヒーなのですよ。まだ全国的には広まってないかもしれませんね。デカフェは、妊婦さんや、カフェインが苦手なお客様が好まれるんです。私も妊娠中よく飲みました。コーヒーが大好きなので。でもちょっと物足りないですよね」などとお詫びをするかもしれません。