池澤夏樹氏による小説。2001年から02年にかけて朝日新聞に連載され、04年に単行本として出版された。最近では文庫にもなっている。
僕はこれを単行本になって間もなく読み、その多声的な語り口と、アイヌの視点を織り込んだ位置取りに感銘を受けた。
昨年の秋、縁あってこの小説の舞台、静内を訪れた時に再読し始めた。エスノグラフィーを書く技法としてのポリフォニーを学びたいと思ったのだ。小説を読む時間は後回しになる生活の中、数か月かかってようやく読了した。人称や主体、時代、スタイルを融通無碍に変えていく語り口は、やはり面白い。そしてゆったりと物語は進んで、アイヌと共に牧場を建設しようとした開拓者・宗形三郎の人生が浮かび上がってゆく。歴史の他者の視点を取り入れたポストコロニアル文学と呼び得る小説で、日本文学史において稀有な例だといえる。
同じ時期に公開された映画「北の零年」(2005年)が、この小説とほぼ同じ設定ながら、アイヌの視点をすっぽりと脱落させていたのとは対照的である。あの代わりに、『静かな大地』が映画化されていれば、と夢想するのは私だけだろうか。しかし、そうはならなかった。一面的な歴史観に基づいた「北の零年」が鳴り物入りで製作され、管見の限りでは、さしたる批判も提起されることがなかった。「一面的」というのは、自分たちの「開拓」によって痛みを強いられた人びとがいることへの想像力を欠いているからだ。歴史観を多面化していくことに「北海道」の未来はあるはずだ。
再読してみて、挽歌や墓碑銘に接するような救いのない読後感を覚えた。それはこれが結局は宗形三郎の物語に収斂したからなのだと思う。その点で、この小説は多声的ではあっても、多主体的ではないのだ。三郎の悲劇的な死をもって遠別のチコロトイ=宗形牧場が滅んでいった後も、アイヌであることを奪い返すたたかいは続いている。今現在も。だから滅びの物語とは別の物語が必要なのだ。












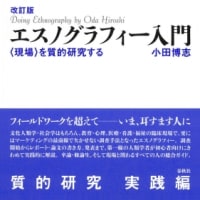








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます