(北海道新聞夕刊<魚眼図>2012年12月10日掲載)
「もちろん、ふつうの国民は戦争を望んでいません。それはどこの国であれ同じです。しかし国の指導者にとって、戦争を起こすのは簡単です。国民には『わが国は他からの攻撃にさらされている』と言い、戦争反対の平和主義者がいれば『非国民』だと非難します。これだけでよいのです。このやり方は、どんな体制の国でも有効です」
こうヘルマン・ゲーリングは戦後に語った。ナチ政権下のドイツの高官としてゲーリングは、第2次世界大戦の開始とナチの人道的犯罪に深く関与した。そのため彼は戦後、連合軍によって捕らえられ、ニュルンベルク裁判にかけられた。この裁判の通訳としてやってきたのがアメリカ人心理学者グスタフ・ギルバートである。ギルバートは、ゲーリングをはじめとするナチ政権のトップたちと個人的に話をする機会を得て、その記録を「ニュルンベルク日記」として1947年に出版した。冒頭の引用文は、ギルバートが獄中のゲーリングから直接聞いたものである。
ゲーリングの言葉は、私たちが愚かな過去を繰り返さないための戒めである。ではそこから何を教訓とすることができるだろうか。
ナチは、ラジオや映画などのマスメディアを巧みに使って、世論を操った。現代で言えばテレビであろう。テレビ報道を鵜呑(うの)みにせず、事の一面でしかないと自覚することが必要だ。特に、「他国から攻撃されている」といった扇情的な報道は、冷静に受け止めなければならない。
そして、他国を敵視し、ナショナリズムを煽(あお)り立てて、軍事化を進めようとする政治家の言葉にも、私たちは乗せられてはいけない。
「敵」はいない。その向こうには私たちと同じ人間がいるのである。
(小田博志・北大大学院准教授=文化人類学)












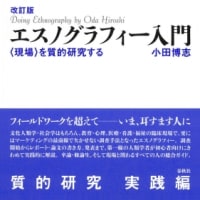







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます