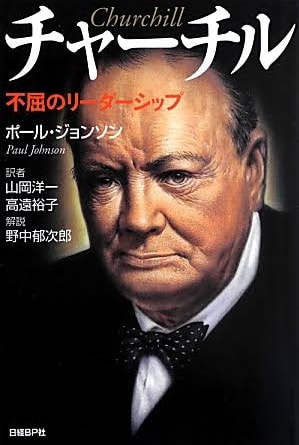@江戸末期から明治初期の混乱期でも豪商は莫大な利益を得た。幕府、大名、旗本等が幕府側か朝廷側か、尊皇攘夷派かで騒いでいた時、豪商は富をいずれかに「賭け」ながら乗り越えた。家督を継ぎその富を特定な志士を支援した豪商、戦利品から富を得た豪商など、支援はいずれも将来の日本を夢見ながらの「賭け」があった。「人」「生き様」に惚れて、見返りもなく支援した豪商、全財産と命もかけた豪商など、江戸の豪商は正に「今に生きる」のすざましい生きざまを見ることができる。今の富裕層に未来を夢見て生い立ちも判らない若者に全財産を支援するそんな金持ち・投資家がいるだろうか。未来を夢見ながら必死に生き抜いた江戸明治初期の豪商は感激に価する。
日本の新規企業投資が歪んでしまったのは将来の経済成長が余りにも低迷し、見通しが不安定だからだろうか。長期の和平=経済低迷はリスクを嫌い、無理やり変化をさせないようにしているだけなのか。 経済の「現状維持」という言葉は、経済の低迷を招いており、技術革新があっても新規導入ができない、させない環境を日本の多くの企業が真似ている。IT/IoTによる技術革新で競争力を付け突進する企業が国内に稀なのは国内大手企業の「既得権」「利権」「規制枠内保護」等に守られているからで、東南アジア諸国での革新は一部日本を大きく遅らせている現実がある。レガシーも良いが、効率化を無視した故障も、損害もない時代遅れの超老齢化システムは日本がまた「鎖国化」社会に入った原因だ。
豪商の一部を下記に抜粋
• 「高田屋喜兵衛」
1769年淡路島の農民から樽廻船屋となる
蝦夷地〜ロシア 松前藩御用達の大商人となる
1813年ロシア側との交渉で日露関係を改善
• 「濱口梧陵」
和歌山県紀州広村からのヤマサ醤油製造業、銚子、日本橋に店
1850年松代藩兵学者、佐久間象山の塾に入る
門下生の勝海舟等を支え
攘夷派(54藩中、34藩)がある中、開国派に支援
1854年の震災で海外渡航の夢はなくなり、地域貢献した
• 「13代伊藤次郎左衛門祐道」
1611年、呉服小間物店、後の松阪屋、織田信長の小姓
震災等のからの薄利多売(古着)などで巨額資産を得る
1833年天保の大飢餓で上野、名古屋での貧民に米・銭配布
震災から幕府に莫大なる上納金をし、翌年には店舗を建てた
5万5千枚のチラシで3000両の売り上げを上げた
• 「5代嘉納治兵衛尚正」
1841年、家督を相続、白鶴、菊正宗の酒酒造で富を得た
幕府の警備、台場、江戸本丸等への上納金を多くした
• 「近藤茂左衛門弘方」
1800年、飛脚、酒屋、薬屋家督をつぐ
尊王攘夷派を支援し、自らも加わった
「安政の大獄」死刑8名、島流し70名、その他100名処分
• 「白石正一郎」
奇兵隊に入隊した商人(廻船業 長州藩)
• 「山本覚馬とカールレイマン」
会津藩士、ドイツ造船技術士との取引
1867年1000丁の最新武器を契約が、新政府に取られる
• 「鴻池善右衛門幸富」
酒造業から海運業、金融業で富を築いた
1863年新撰組が結成され支えた
1877年三和銀行、その後三菱東京UFJ銀行となる
• 「8代濱崎太平次」
指宿「ヤマキ」琉球との海運業、薩摩藩を支えた
薩摩の武器調達への軍資金用達
• 「福田理兵衛」
尊王攘夷派を支援した京都の材木商
仁和寺、天龍寺の御用達
長州藩が大挙して上洛した時に支援
蛤御門の変(会津藩・薩摩藩vs長州藩)での支援
• 「飯田新七」
1803年、福井県敦賀市、呉服商の跡取り、
高島屋創業者は蛤御門の変で京が炎上古着を売り富を得た
営業方針「誠実さ」「勤勉さ」1時間も早く開店させる
「確実な品廉価にて販売し、自他の利益を図るべし」
「3方よし」売り手良し、買い手良し、世間良し
「正礼掛け値なし」現金化を実現
• 「トーマス・グラバー」
倒幕派を支援したスコットランド人
ジャーディン・マセソン商会からグラバー商会(1861年)設立
薩長同盟に貢献、武器の売買で富を得た
1872年新橋〜横浜間の鉄道開通の7年前にすでに蒸気機関車を導入
明治維新後は後のキリンビール、三菱財団の顧問となる
• 「初代伊藤忠兵衛」
近江商人(滋賀県犬上郡)紅長の呉服商
長州支援した行商からの後の伊藤忠を作った人物
長州藩の武装支援
• 「岩崎弥太郎」
1834年、土佐藩地下浪人の身分
吉田東洋の塾で学び後藤象二郎らを支えた
軍艦7隻、鉄砲、弾薬等の買い付け、会計係
三菱財閥の基盤 海運業、鉱業、金融業、造船業等を興す
• 「三野村利左衛門」
戊辰戦争、旧幕府と新政府の戦争の狭間で商機をみつけ三井番頭となる
呉服店から現在の三越百貨店を築く
• 「大倉喜八郎」
戊辰戦争等で武器の調達で富を得た富豪
大倉財閥
• 「渋沢栄一」
埼玉県深沢市、農民。 攘夷派から幕臣に返り咲き
• 「五大友厚」
薩摩藩士、官僚から民間へ
大阪の近代化を求めて奮闘 商工会議所初代会頭
• 「藤田伝三郎」
長州藩の酒造 4男
軍需品を売りさばき富を得る