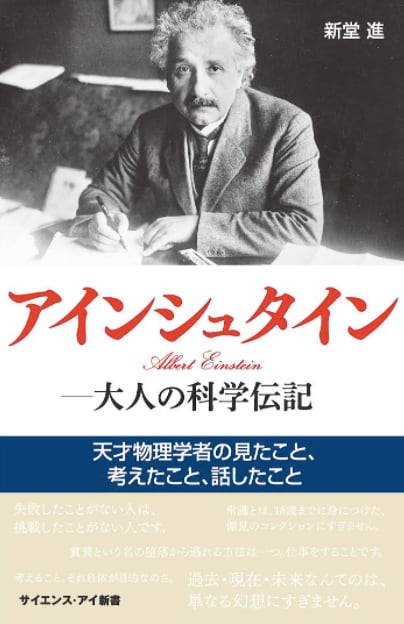@天下の悪法「生類憐れみの令」。と記述された書籍が多いが果たして悪法だったのか。生き物(鳥類・家畜類)を殺してはならぬとある部分行き過ぎた面も多かったと記されている。この令で悪用するものもあり、犬の肢体を家の前に置き去りにして、濡れ衣をかける者さえいたという。いずれにせよ、「命の尊さ」を学ぶ唯一の法で有ったとも言え、特に武士の権限で庶民等を「切り捨て御免」とした人殺しをやめる事だったともある。さて本題は、「勝者と敗者・正義と悪」である。時代劇では家督相続が特に注目に値するこの種の物語になる。だが、結局「勝者は正義」となり、「敗者は悪」となり歴史上に明確化されていることだ。最近富に「新たな謎・説」、「逆説」、「新たな古文書・資料発見」など過去を覆す新事実がでてくる事には驚きだ。(実は悪と思われた敗者が正義だった)その都度、過去の歴史記憶を消去し、新たに書き換えなければならない。これからも多くの真実が解き明かされ、過去の歴史で「勝者が悪」に覆される史実も出てくるだろう。 実際「人は最初から悪人ではない」を信じるならば、日本にある多くの銅像も「悪から正義」説で本人死後数十年後、中には数百年後というもあると言う。 ここで素朴な疑問。間違いと言われる1万円札の聖徳太子像は変更されるのだろうか?
『光圀 古着屋総兵衛 初傳』佐伯泰英
- 天下の悪法「生類憐れみの令」やゆがんだ将軍継承方針など5代将軍綱吉の大義なき政の専横ぶりに御三家定府水戸光圀(2代目水戸藩主)は憤怒を募らせる。綱吉の背後には隆光権僧正の影がちらつく。家康との約定により、表の顔は古着問屋、裏の豹は隠れ旗本として徳川守護を5代百年に亘って精勤してきた蔦沢一族。将軍家か大義か、狭間に揺れる若き総兵衛い勝頼を描く。
- 徳川家康の「隠れ旗本」本田弥八郎正純とその「影の旗本」大黒屋鳶沢一族初代成元から始まり6代目勝頼となる。徳川家を警護する為影の旗本として動く。水戸光圀との縁から勝頼は光圀を警護、光圀が育てた家臣藤井紋太夫が光圀隠居とともに3代目水戸藩主と結託、柳沢吉保と組み水戸藩内部にてこ入れ反対派を成敗、さらに光圀を葬ろうとするが、逆に光圀が家臣藤井を自らで刺殺する。それは光圀が江戸での能楽を披露する場で決行した。「千手」(一ノ谷でとらえられた平重衡を送る舞)。大老となった柳沢はその後逆襲に出てくる。赤穂浪士事件でも浅野内匠頭への即刻切腹もその仕業であり渦中の混乱を避けるべく消し去ろうとした。もし光圀が生きていれば詳細を調査させたに違いない。
- 「勝者と敗者・男と女・罪と許し・生と死・夜と朝」
- 「若者と老人・剣と扇・裏と表・虚と実・正義と悪・過去と未来」
- 時空を超えて、無常なる歴史と人生の軌跡が、記憶と想いで交差している。畢竟、人は人と出会い、愛しみ憎しみ、支え合い、心を伝えながら未来を育んでいく。