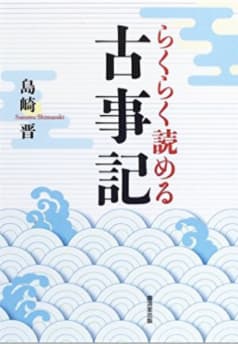@日本の「皇紀」(紀年法)はキリスト暦よりも長く継承され、神武天皇の「八紘一宇」を長く守り築いてきた。「八紘一宇」とは「天下・全世界を一つの家にすること」とある。今から2678年前にこの祝詞が発せられている事に驚きと、日本は独特の世界を最初から持った国であり自慢すべき事が多い国である事が新たな歴史資料・遺跡から続々発見されている。(文末列記)数年前のDNA解析からは、日本人と同じ人種はチベット・アンダマン諸島の人々だという事。新たに発見された遺跡等からまた日本人のルーツが中国・朝鮮・韓国からの流れではないという事実も発見されているという。
「東京裁判」「南京大虐殺」その他多くの歴史はその権力者により都合よくねじ曲げられていると著者は言う。正しい歴史認識を理解することが大切で、「歴史捏造による反日」もそれらの国はそろそろ事実から発展に阻害されるようになるであろうともある。正に日本の歴史教科書等も 隣国の捏造記事や戯言に左右される事なく、真実・事実と「日本の道徳」をもっと教育に入れ込む手法が必須だと感じた。
『欧米の侵略を日本だけが撃破した』ヘンリー・ストークス(元ニューヨークタイムズ東京支局長)
- 東京裁判「日本が罪に問われるのなら、欧米諸国のアジアへの植民地支配の方がより罪深く、アメリカ人による先住民迫害も同様に罪を問わなければならない。第2次世界大戦においては、広島と長崎に原爆を投下し、日本の各都市を空襲して多くの一般市民を虐殺した連合国側こそ責められるべきだ」
- 「従軍慰安婦問題、南京大虐殺も捏造されたプロパガンダに過ぎない」
- 「正しい歴史を検証すれば明らかで、放置しておいてはいけません。捏造された歴史が『歴史的事実』として確定してしまいかねない」
- 「グローバリズム=格差問題」
- グローバリズムは持てるものにはさらに豊かになり、持たざるものはさらに貧しくなるという格差問題が生じ、多くの国で移民敗訴や保護主義を求める声がどんどん大きくなっている
- 「北朝鮮情勢」
- 日本人はさほど危機感を感じていない(韓国はなおさら)
- 経済的制裁・外交努力は問題を解決できていない(野放し状態)
- 「戦略的忍耐」から無法国家への「正恩斬首作戦」の計画へ
- 「英雄・金日成は偽者だった」
- 英雄と呼ばれた2人の金日正(名前も経歴も詐称した)
- 中国共産党遊撃隊東北抗日連軍「キム・チャンヒ」
- 満州にて抗日武装運動ゲリラ「キム・ガンソ」
- 「日清戦争は朝鮮独立の為の戦いだった」
日本は朝鮮独立、近代化を願ったが、節操なく清、露に擦寄る
李朝鮮は清から抜け出し近代化が不可欠、日本が支援した
- その結果日清戦争が勃発、一旦は日本軍が勝利、内閣も制定、身分制度廃止、女性差別撤廃、人身売買違法とし、貨幣価値を統一、租税は貨幣で支払うようになり王室と政府の財政分離によって国家財政を立て直した。日清講和条約に「清国は朝鮮が独立自主の国であることを確認すること」で日本は朝鮮を「完全無欠なる独立」に導いた。
- 1937年、「通州事件」(北京近くで日本人居留民2百数十名が中国兵に惨殺された)ことにより朝鮮人の中国への怒りが頂点に達して朝鮮半島での皇軍志願兵が105名集まった。当時朝鮮人は日本国民であることを誇っており日本人が惨殺されたことで激情し多くの朝鮮人が皇軍に志願した。1938年に陸軍特別志願兵制度、1943年に海軍での制度が導入された。当時朝鮮人が日本の陸外軍に入隊することは士官学校を卒業、旧大韓帝国軍からの転入鹿認められなかった。当初7倍の倍率が5年後には50倍になった。
- 1938年志願者2946名中、406名合格
- 1943年志願者30万3394名中、6300名合格
- 「米ソ英による朝鮮南北分割処理」
- 1945年8月15日まで朝鮮は日本国の領土だった
- 1945年第2次世界大戦後スターリンとチャーチルの提案で北緯38度線を境に北側をソ連軍が、南側をアメリ軍が占領
- 韓国の初代大統領は抗日運動家のイ・スイマン
- アメリカの操り人形的存在となった
- 韓国人による済州島民3万人虐殺事件発生
- 現在日本にいる在日韓国・朝鮮人の多くはここからの逃れた
- 1946年、ソ連は訪日独立運動の英雄「キム・イルソン」の名を利用して33歳の運動家キム・ソンジュを政治機構の中心に置く
- 朝鮮は周辺諸国からの拉致で知識階級・専門教育を充実させた
- 「中国は歴史捏造の歴史」
- 捏造した反日教育で生まれた南京大虐殺記念館
- 「中国には国境という概念がない」が歴史を築いた
- チベット、ウイグル、南モンゴル等を侵略、中国自治区とした
- チベット:1959年3万人虐殺、パンダ・元はチベット動物
- ウイグル:1949年東トルキスタン首脳飛行機事故、無抵抗の学生含む3千人以上が虐殺、1万人以上が拘束行方不明、46回の地上核実験実行、その結果民族浄化・対抗勢力の抹殺を図った
- 周辺諸国を侵略し、冊封体制で現代の「一帯一路」につながる
- 「易姓改革」=歴史修正主義は新たな王朝が誕生するたびにその新王朝を正当化する、中国は古くから5千年史実改竄するようになった。よって前王朝は徹底的に否定されている。
- 中国の歴史・モンゴル帝国→明(朱元璋)洪武帝(1368〜1398)→永楽帝(紫禁城・1402〜1424)→清王朝(康熙帝・雍正帝・乾隆帝:1661〜1795)
- 「西欧列強による清への侵略」
- イギリスとの三角貿易からアヘン戦争勃発、南京条約、朝貢貿易禁止、香港島割譲、その他アメリカ、フランス、ロシア等からの一方的な不平等条約締結を余儀なくされた
- 1898年からフランス・ドイツ・ロシア三ヶ国干渉で遼東半島返還、その他植民地を増やした
- ロシア:満州・モンゴル・旅順・大連・関東州
- ドイツ:山東省・青島・膠州湾
- フランス:広東省・広西省・広州湾
- イギリス:長江流域・九龍半島・威海衛
- 「反日・暗黒大陸」
- 日本が経営した満州「満州は中国人にとって天国」と言われた
- 張作霖・学良父子の反日活動で満州事変勃発
- 蒋介石と毛沢東の覇権争い、最後には蒋介石は台湾へ逃亡
- 毛沢東は1949年10月1日中華人民共和国を宣言
- 「共産党王朝の本質は侵略国家」
- 1927年農民軍を組織、略奪、殺人、放火等繰り返し10万人を超える地方の有力者や富裕層を殺害。架空の「AB団」を作り上げ残虐行為を繰り返し江西地区では1万人を処刑、「AB団」狩りで7万を殺害、国民党との戦いでは約1千万人が犠牲となった。
- 1950年、北朝鮮軍をあおり38度線越え韓国ソウルを陥落
- 「中国の国境なき侵略=中国共産党帝国」
- チベット・ウイグル・南モンゴル自治区の陸統治から海へ拡大
- 1974年西沙諸島(ベトナム領土)への侵略、戦闘・略奪
- 1992年西沙諸島、南沙諸島、東沙諸島、中沙諸島へ占領
- 1995年フィリピンのミスチーフ礁占領
- 1997年第一列島線(九州・沖縄・台湾・フィリピン・インドネシアラインを海軍発展戦略設定、さらに伊豆諸島・小笠原諸島・サイパン・グアムの第2列島線の制海権を主張
- 2005年竹島を韓国領土と主張
- 2013年沖縄を中国に、沖縄中国帰属などデモ行進
- 中国の繰り返される覇権主義は限りがなく、周りの諸国に不安を与えており、世界中の人々は本音で日本がかつての道義に満ちた独立主権国家として立ち上がることを期待している
- 日本の文化、伝統は世界にあって稀な美しい遺産である。神風連、特攻隊に連なる日本的な精神性がそこにある。「日本では英雄が敗北の中から誕生する」(アイバン・モリス英国人日本研究家)
- 「アメリカに石油などの資源を止められた日本は、自衛のために戦争を余儀なくされた」(マッカーサーの上院軍事外交合同委員会発言)
- 北朝鮮はソ連が、韓国はアメリカが作った国であり独立戦争で戦ったことによる自立国された国ではない。日本の戦前は凛々しく独立権国家として毅然としており自国を守ろうとしていた。
- 「ジパング」世界が憧れた夢の国
- 「神国・神州日本」神話の国
- 日本では善悪ではなく、美しいか美しくないかで判断する
- 美しいは「真心や至誠」=ことばやしぐさ、立ち居振る舞い
- 「日本の道徳と海外のモラルの違い」
- 日本の道徳とは「人間がお互いに平和に仲良く暮らすため、かくしなければならいと言う人間の真心から自然に沸き出るもの」
- モラルは「征服者が法律・規則・組織で拘束させ大衆に守らせるもの」
- 「神道はこれからの世界の信仰となる」
- 神道は第一に大自然を信仰しているということ
- 古事記には今日の物理学者定説の「ビックバン理論」が既に宇宙創世の姿が描かれている
- 「以心伝心」高次元の世界があり相手に察してもらう会話
- 対してアメリカは多民族国家なので詳細説明が必須な国である
- 俳句や和歌で霊感的を磨き「心を通わせる」
- 日本には「言霊信仰」がある=「祝詞」神の言葉・意思疎通を計る
- 感動する事で人は心を動かせる=瞑想もその一つ、ビートルズの「イマジン」はそのいい例で神道について歌ったものと言われる
- 「東日本大震災でみた日本の道徳」
- 穏やかさ・尊厳(列に並ぶ)・能力(建築物)・気品(皆んなに配分)・秩序(整理・整頓)・犠牲的行為(作業員の役割)・優しさ(弱者への配慮)・訓練(模範)・媒体(冷静な報道)・良心(正しい行動)
- 「世界最古」日本の歴史
- 縄文時代1万5千年から3千年前の時代のDNAが現代の日本人に繋がっており、日本人男性が持つ「Y染色体」はアイヌ・沖縄=チベット・アンダマン諸島と同じ『D』を持っている
- 日本列島には9万年前の遺跡(赤城山「槍先型尖頭器」)発見
- 青森の大平山元遺跡の土器は1万7千年前
- 北海道と福井の土器1万5千年前は加熱調理の痕跡あり
- 稲作は6千7百年前日本から朝鮮に伝わったことが発見
- 青森では5千5百年前に15mもある高層建築があった
- 神武天皇の「神武東征」実証で日本書紀の初代天皇存在確認
- 「皇紀元年」日本独特の紀年法はキリスト暦よりも長く続いており、2018年は皇紀2678年となる。
- 「武」の精神は侵略とは全く関係なく「忍」である
- 「東京裁判」「南京大虐殺」その他多くの歴史はその権力者により都合よくねじ曲げられている。正しい歴史認識を理解することが大切で、「歴史捏造による反日」もそれらの国はそろそろ事実から発展に阻害されるようになるであろう。
著書「中華思想の誤解が日本を滅ぼす。徹底解明、ここまで違う日本と中国」(自由社・加瀬氏と石平氏との対談)