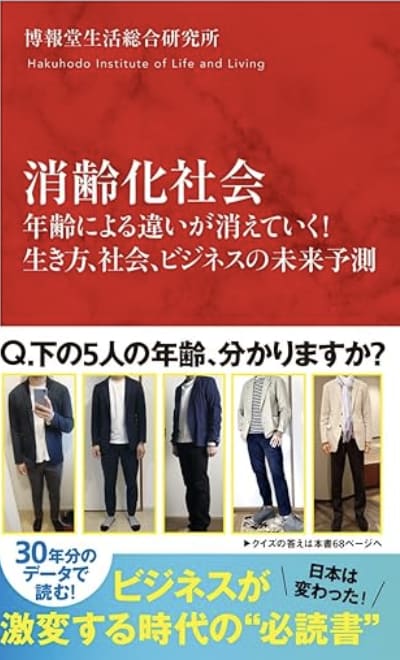@著書「After 2040」で気になったのはデジタル社会への日本国の遅れは相変わらず「古き良き時代」を妄想・堅持させる現役労働者(経営者・幹部)が多く、いつ世界の波に追いつき、ついていけるのか疑問に思った。日本の将来で気になるのは、少子化とデジタル化で教育が劇的に変化することは間違いなく、背景にあるグローバル化での正しい日本語の存在、更に一番は気候変動(温暖化)による自然災害に伴う生活環境と食問題が恐ろしく思えた。それは現在の農水産省の備蓄米問題を含め自給管理など主食・食品の異常な高騰・品不足などから全く世間を見ていない、調べもしない、胡座を描いている姿勢では災害時にはどうなるのかとても心配だ。
『After 2040』池上彰
「概要」定年後、人生の節目を迎えてなお社会や家族から見放されないためには、過去の出来事から未来を予測し、今から準備をする必要があります。とはいえ未来を考えると、暗い将来ばかりを思い描いてしまいがちです。たとえば円安がこれからさらに進み、自分の収入だけでは生活できない経済状況になってしまわないか?
ー世界のデジタル化に乗り遅れた要因とその将来
・成功体験に囚われ、新しい考え方を受け入れなかった(古い考えを捨てる)
・時代の変化にスムーズに順応できる多様な人材と好奇心次第(若手へのシフト)
・兆しをいち早く見出す事(若手経営者へのシフト・組織問題)
ー仕事編
・生成AIの普及による若手が育たない課題への早急な対応必須
・エッセンシャルワーカー(コロナ禍での仕事・医療・物流・食料品など)への重視
・人の気持ちを理解できる人間力の発揮(感情に関わる仕事が大切となる)
・期待できるのは第一次産業(農業・漁業・林業による機械化・デジタル化)
・ChatGPDは人間がいかに良い問いを立てるかがポイント(人間力)
生成AIに対して優れた指示を出すプロンプトエンジニア(質問力)
企業ごと専門知識や個性を持った生成AIトレーナー(創造力)
・日本の自動車メーカーは部品等の下請け企業になる(部品製造へと変化する)
・アニメ・漫画も中国の下請け企業になる(市場の格差、賃金格差など)
・退職金がなくなり雇用の不安定、人材の流動性が高くなる(プロジェクト毎雇用)
・スキルの陳腐化に加速(リスキリング)、優秀な人材が企業を選ぶ時代へ
ー教養編
・オンライン教育(通信制学生の急増)日本の教育問題「飛び級」への加速必須
詰め込め式教育から論理的思考能力を鍛え判断できる教育(討論・議論する場)
先生は教えることに専念(雑用など他の人材が支援)ICT教育への広がり
教育格差の広がり(都心と地方、私立と公立)が階級社会につながる
・人間力が問われる時代(人脈コミュニティー力)
・生涯使える技術(寿司職人、宮大工、養殖技術職など)
ー自然災害編(温暖化対策必須「パリ協定」最大国中国、アメリカ)
・南からの暖流がなくなることでヨーロッパが寒冷化する
・海水温度の上昇で日本では渇水と大雨災害が多発する(土砂災害・巨大台風)
・夏は日没後に外出する生活が始まる
・食料の最適な産地が南から北に移動
・蚊の危険性が高まり感染症が拡大する(デング熱、マラリア)
・林業の衰退で森林火災が頻発する(高温熱波の来襲)
・「水」利権の紛争が増える(特に中国、中近東など)
・原発事故の処理は2050年まで続く(脱原発:使用済み燃料処理問題)
・太陽光パネルの廃棄問題(2040年まで続く・ペロブスカイトへの移行)
・巨大地震の予測(2040年までに南海トラフ・首都圏直下・富士山噴火)
ー暮らし編
・物価上昇が混乱を招く円安傾向、だが、大手企業の収益は回復(内部保留問題)
・値上げから賃上げへの動きが遅い、もしくは停滞、購買力の低下、不景気から抜け出せない
・インバウンド経済へ移行、だがオーバーツーリズムへの対処が遅い(渋滞・ゴミ・騒音問題)
・少子化社会は厳しい競争社会となる(GDP低迷)中福祉・低負担国になる
・金利上昇の容認で円安が是正されるが、国の赤字国債返済金額増える
日銀が紙幣を多く発行で買える安倍理論崩壊・世界で2番目の借金国となった
財政への不安、破綻は日本国債の大暴落へとつながる
・労働者不足で夫婦共働きが今以上の膨れ上がる(少子化問題=人口減少=消費減)
配偶者控除・扶養控除など専業主婦=ケアする人などの形態が崩れる
完全フレキシブル労働環境が生まれ、多くの人はリスキリングに励む
ジェンダーギャップが低くなり男女間格差の縮む
移民受け入れが増える(介護・技能実習)、定住を認める
・年金破綻論が言われるが国が存続する以上金額が低迷しても続く
・マイナンバーで純資産への課税が始まる(富裕税など)
ー健康編
・テクノロジーの進化で病気を早期発見、早期治療でがんは治る
・遠隔地での遠隔手術への道が開け過疎地でも手術可能となる
・3Dプリンターで臓器などを作成、再生医療が飛躍的に伸びる
・体外受精、遺伝子検査などで妊娠から出産までの監視、デザイナーベイビーへ飛躍
・医療費の高騰化で格差が生まれる(医療費負担の増額、年齢制限など)
・AIの普及で健康管理、高齢者施設での介護ロボなど進化する
ー次への不安
・人脈を築き、教養を高める、できれ現役で働き続ける素地を作っておく