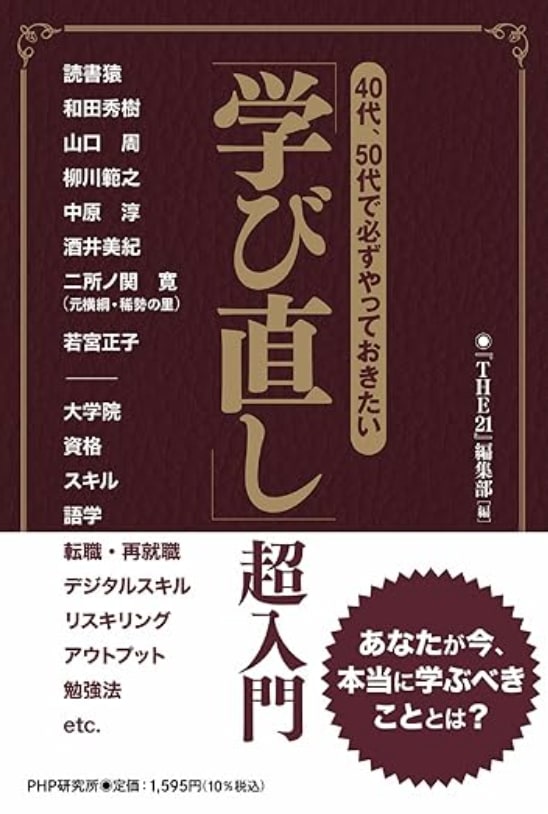@様変わりし始めた都市開発、特に人口減少に伴う各都市の利便性を生かした工夫が生まれ始めた。大都市では地権者の持ち出しなしで補助金に頼らない建築から、地方都市ではタワマンの規制と住居環境を重視した環境整備などさまざまだ。人口減少は今後さらに深刻となり数年前にブームとなった郊外ニュータウンなども老朽化と共に住人の老齢化でリノベーションが難しくなっている。そこで新たな動きは住人の環境を工夫し充実した施設を優先し、公共施設+商業施設+分譲へと順番に付加価値建築へと変化している。
『人口減少時代の再開発』NHK取材
「概要」明治神宮外苑の再開発について反対の声が相次ぎ、議論を呼んでいることは多くの人の知るところとなった。3棟の高層ビルが建てられる計画など、その開発スキームは高層化によって「保留床」を生み出し、得られた収益などで神宮球場を含む一帯の再開発にかかる事業費を補填するというものだ。ほかにも福岡、秋葉原、中野、福井など、今まさに変わろうとしている都市を現地で徹底取材することで、再開発の裏側に迫ってゆく。高層化ありきのスキームとなっていないか、街の個性や住民目線を置き去りにしてはいないか、そして、次世代に引き渡せるものとなっているのか――多面的な側面から検証する。
ー「なぜ全国の都市で高層ビルによる再開発事業が進むのか」
・東京は日本全体が人口減少傾向にあっても増加し続けている例外的な都市「選ばれる都市」
・「変化し続けないと街として生き残れない」危機感がある東京ー地上げ屋による値上げが続く
・老朽化した建物の更新から、地権者の持ちなしで建設可能「権利床・権利交換」=「魔法の杖」
・地権者の3分の2のトリック(土地を分割し地権者数を意図的に増やす)で建設に着手
・想定外が噴出(物価高騰で工事費・労賃等が増加による)延期・減築・組換え問題
ー高層ビル物件・集客ビル
・千代田区秋葉原(電気街からアニメ街)高層ビルで変貌・貸店舗に入居数が激減
・福岡「天神ビックバン」高さ制限(空港近く)+福岡大名ガーデンシティ(集客力)
・福井(新幹線開通に伴う街開発)建設費高騰・持ち出しなしで計画された物件に難題
ー課題
・補助金依存を強めた計画が不安定
・資材建材、工事費等の高騰化による工事の延期、施設変更
・都市での施設変更はオフィスや分譲マンションになるが地方では難しい
・資金調達をPFI(プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)で公募、賄う方法
ーさいたま市(人口増)
・転入者数2023年には7631人(転出を引いた数)全国で六番目に増加都市
・0歳から14歳以下の子供の転入超過数は988人(9年連続一位)市民税は500億増
・学校施設不足・教室不足(ある小学校は生徒数1200人、12から24クラス増)
・医療不足・緊急医療説不足
ー東京・湾岸エリア
・高層ビルでの空室率上昇(オフィスビル)
渋谷1.36%、丸の内大手町2.25%、新橋虎ノ門7.09%、北品川東品川11.91%
・都内の100mを超える超高層ビルは525棟、20年で3倍に膨れた
ーユニークなまちづくり
・世田谷区下北沢(文化や歴史を継承)小田急線地下の分割利用・起業家支援
・岩手県紫波町(補助金に依存しない施設)住居環境を整える(歩いて10分以内施設完備)
公民連携で土地・建設費等を分担、住民に住んでもらう工夫
・神戸市でのタワマン規制(高さ制限を街に設け乱立させない・災害時避難対策も考慮)
・「郊外のオールド・ニュータウン」の再構築・リノベーション「面」整備
・利便性重視(交通機関・格安運賃・公共性を持った街機能)・条例緩和・強化策
ー開発のポイント(生きるための施設重視)
・普遍的集客装置を作る(商業施設・図書館・運動場など住民の集客施設)
・テナント賃料を蹴ってしてから施設を建築(テナント重視・優先させた逆算)
・エリアの機能が充実してから分譲地の販売(補助金を頼りにしない施設を確保)