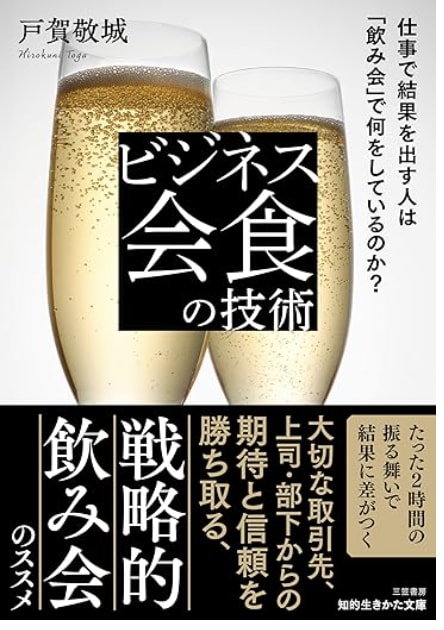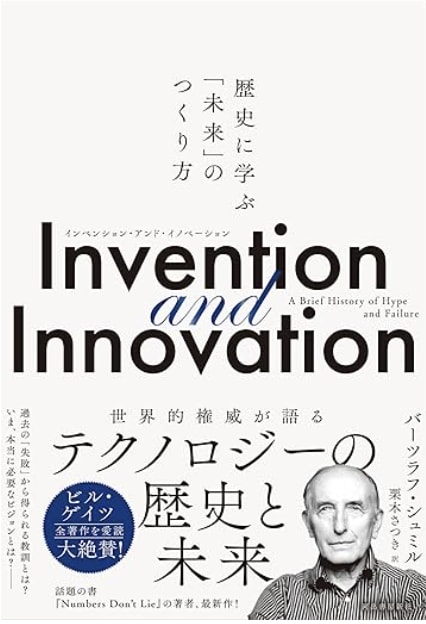@仕事に、人生に誰もが「行き詰まり」を感じることがある。そこに必要なことは「明日は今日と違う自分になる」「遊び感覚で色々やって、成り行きを見守る」「成功とは右に倣えをしないこと」、成功はチャンスを如何に「気付く」、と言うこと。コカコーラ、リーバイスなど成功はきっかけを如何に捉え、ビジネスチャンスに変えるかなのだ。「失敗」と認める前に3つのポイント(ミスした点・問題点・今の現状)を書き出すだけでも「反省」から新たな「挑戦」へのチャンスを掴むことができるという。成功した人の真似ではいつまで経っても成功しないと言うことだ。
『仕事は楽しいかね?』ディル・ドーテン
「概要」出張の帰りに、大雪のため一昼夜空港のロビーに足止めされた「私」。そこで出会ったある老人に、つい仕事で鬱積(うっせき)した感情をぶつけてしまう。老人は実は、企業トップがアドバイスをほしがるほどの高名な実業家。その含蓄ある言葉に「私」はしだいに仕事観を揺さぶられていく。
ーくだらないことが繰り返されている
・目標の設定=自分の人生をきちんと管理することができる
・生きる姿勢を変える=新しい自分を築く=毎日毎日違う自分になること=「試すこと」
・わかりきっていることを手間かけてやり直すことはない=良くなろうとすること
・試すこと、日々変化が必要であること、偶然を見落としていること…
・適切な時とか完璧な機会なんてものはない=遊び感覚でいろいろやって、成り行きを見守る
・失敗した理由はあらゆる試すことをしなかった=アイデアは偶然・ラッキー・幸運
・世の中は変わったことで興味を持つお客が増えた=真似では人は興味を持たない
・うまくいっていないのはどうしてなのか=試すことは簡単だが、変えるのは難しい
・アイデアの為の3つのリスト:ミスした点・問題点・今やっている点
そこから「試すこと」を見出すこと
「コカコーラの由来:薬屋の頭痛薬を水で割って飲んでいたことから発想、ソーダで割ったこと
「リーバイス・ジーンズの由来:帆船の帆販売からズボンがないかと言われ帆をズボンに」