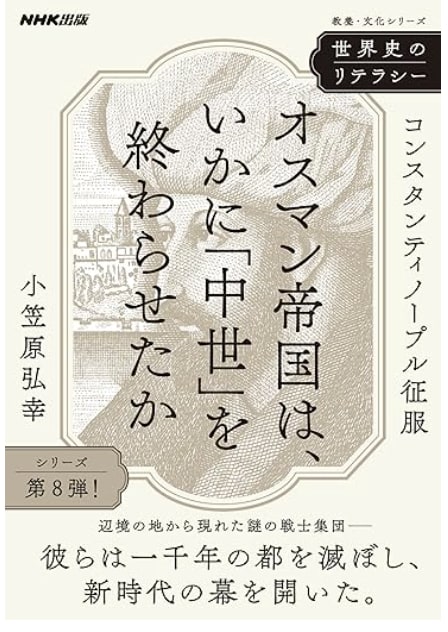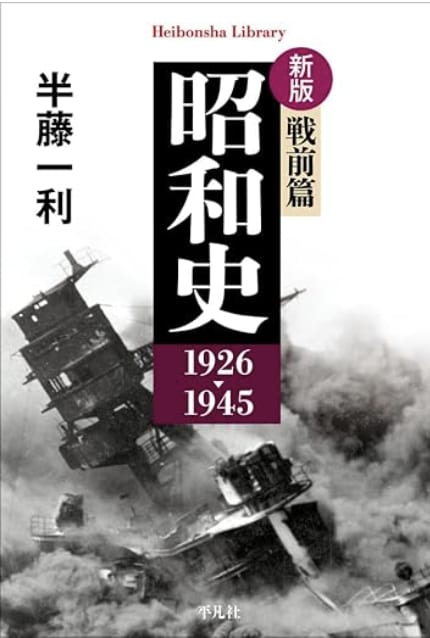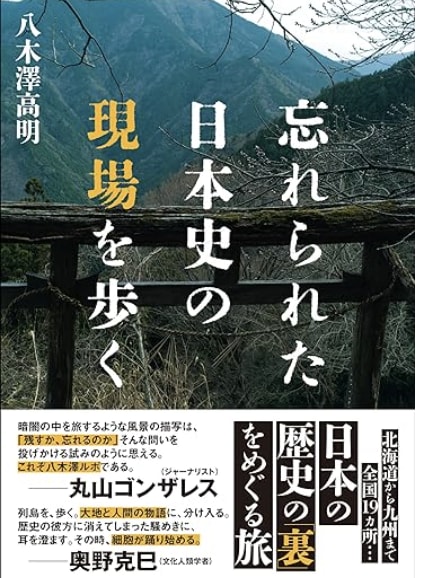@1926年から満州・上海での一連の事件・戦争は前線陸軍の単独行動と暴走(天皇・元帥の命令なしで行動「統師権干犯」)軍の陰謀から満州事変へと発展、更に分派(統制派と皇道派)との争いから、皇道派による2.26事件(政治腐敗や農村貧困を訴えた)により国政は軍事一色へと大きく傾いた。結局、現在でも置かれた環境の機運で事が悪くても進めざるを得なくなる政治体質は変わっていないと感じた。史実で昭和天皇への報告は偽りが多く、当初内閣、軍隊官僚が事件発端の軍人行動を軍律で押さえ付けられなかった怠慢責任は重大で且つ致命傷で、その後の第2次世界大戦への火蓋は、近衛文麿首相など強力なリーダーシップのない人物が祭り上げられ米国の戦争への引き金(日米の最終交渉に望みを捨てた行動)を許したことは決して許されるものでは無い。歴史から学べることは多く、戦前の二の舞を踏まないように近隣諸国との交渉を持ち、米国頼りからの脱皮が必須とされる時期が来たと感じる。
本書の歴史から学べる事柄:
1、時の勢いに駆り立てられてはいけない(周りから判断し慎重に行動するべし、選択・判断力)
2、過剰な自信とエゴは方向を見誤る(思い上がり、うのぼれなどエゴと自信過剰に注意)
3、課題・問題対処を先送りせず、責任の所在等を明確に、対処する(問題処理と説明責任)
4、最新・近代化へ目配りから先を読む努力と時の政策を打ち出す(最新情報の収集と予測・展開)
『昭和史1926~1945』半藤一利
「概要」授業形式の語り下ろしで「わかりやすい通史」として絶賛を博した半藤一利さんの「昭和史」シリーズ戦前・戦中篇。日本人はなぜ戦争を繰り返したのか――。すべての大事件の前には必ず小事件が起こるもの。国民的熱狂の危険、抽象的な観念論への戒めなどがある。
ー昭和史の根底には“赤い夕陽の満洲”があった(5大強国への慢心)
・ポーツマス条約により満州の利権を持つ(当初1万人の関東軍が最終的に70万人に増加)
・資源(鉄、石油、錫、亜鉛)を求め植民地化
・日本国人口問題(流出先として選択)満州には40万人から50万人が移住した
・清国の孫文、蒋介石の辛亥改革勃発、中華民国へと動き中国共産党軍との衝突(満州事変)
・第一次世界大戦後の戦勝国(27カ国)、ベルサイユ条約を経て国際連盟で軍縮となる
・日本の劣勢(中国における利権保護を廃棄され)国際連盟を脱退、独自の外交を進む
ー昭和は“陰謀”と“魔法の杖”で開幕した(最前線の陸軍人たちの陰謀による暴発)
・辛亥革命後に張作霖爆殺事件を陸軍が故意に実施
・「統師権干犯」(魔法の杖)天皇に周りの人間が虚い報告(軍師は北一輝と言う)
・軍人石原莞爾らが中国軍張学良の仕業に見せかけ鉄道を爆破、満洲事変につながる
・新聞・ラジオ等での報道で関東軍擁護に戦争を煽ったことで国民も火がつく
国家予算:昭和8年度22億3千8百万円の巨額
・分派(統制派と皇道派)による軍内部の混乱が勃発(首相・大臣の交代)
・皇道派による政治腐敗や農村貧困を訴えた二・二六事件で国政は軍事一色へと傾く
ー日中戦争・旗行列提灯行列の波は続いた(危惧した高級幹部・国家総動員法・日中戦争へ)
・蒋介石の国民政府軍と毛沢東の中国共産党軍の内乱から対日本軍へと(抗日民族統一戦線)
・盧溝橋での中国軍による銃撃事件で日本軍と中国軍が戦闘状態になり(1937年)南京事件へ
最初の1発目は中国の抗日は学生か共産分子の仕業(第三者による双方に発砲の陰謀)
南京虐殺(30万人)は無かった(30万も存在せず中国軍逃亡者3万人があった事実)
・政府も軍部も強気一点張り、そしてノモンハンでソ連軍との対峙(1939年失敗の連続となる)
巨大戦艦5隻建造計画大和と武蔵(4万m飛ぶ主砲)=低水準の火力能力・気力のみ
関東軍の強気でソ連との国境紛争(4千km)に独自行動(双方の不法侵入で言いがかり)
(日本軍5万8925人の内3分の1が死傷、大敗したvsソ連2万4992人)
1939年ドイツとソ連が不可侵条約締結(日本との3国同盟間近)
ー第2次大戦の勃発があらゆる問題を吹き飛ばした
・日独伊の三国同盟に反対したのが海軍大臣米内光政、次官山本五十六、軍務局長井上成美
・陸軍の「他人の褌で相撲を取る」(対ソ連)同盟に賛同、海軍の対米英協調論が消える
山本五十六の遺言「戦場で死ぬのも内地で銃後で死ぬのも同じだ、むしろ戦場で弾に当たって死ぬほうが易しい。自分の思いを貫き、いかなる俗論にも負けずに『斃れてのち止む」方がよほど難しい。この身は滅んでもいい、しかしこの志は奪う事はできない」
・北シナ方面山下奉文「矢はすでに弦を離れた。もはや容疑者の引き渡しで終わるものでは無い。イギリス租界官憲が日本との建設に合意する新政策を高く掲げるまで武器を捨てる事はない」日本の報道は一斉に「イギリスよ日本の言うことを聞け」等宣言報道を出した。
・1939年9月1日ヒトラーによる第一号命令書にサイン、ポーランド進撃開始(第2次世界大戦)
1940年パリ陥落で日独伊3国同盟締結、近衛文麿首相で更に戦争悪化と混沌
・1940年日米通商航海条約を破棄により米国は敵対行動を開始する(米国の輸出規制強化)
同年米国は原子爆弾の製造への道を開く・日本は零戦闘機配置
・ドイツの選択(ソ連との不可侵条約)はソ連による英仏との接近を恐れた
ソ連は対日本軍にノモンハンへの強力部隊派遣・「見れど見えず」状態へ
天皇は英米に対して協調しなくてはならないと主張していた
吉田海相は三国同盟は米国を敵に回すと最後まで断固反対した(米内・山本・井上含め)
・山本五十六「海軍内部の統制に完全服従するが、三国同盟で英米勢力圏からの資材調達失い、どう変更するべきか聞かせて欲しい」と参議官等に問うが誰も返答無し。海軍は陸軍と違い戦闘機および戦艦の多くの原料が必要であり調達先が不明のまま、軍事行動せざるを得なかった。そこで生まれたのが「奇襲攻撃:ハワイの軍艦・空母」だった。
・山本の親友堀悌吉中将「内乱では国は滅びない。戦争では国が滅びる。内乱を避けるために、戦争に賭けるとは、主客転倒も甚だしい」
ー御前会議から戦争開始への決議
・近衛首相は米国との最後の交渉会議を諦め辞任、開戦を迫った東條内閣を推奨
・開戦強行派らの内閣、松岡外相の断固たるアジアでの南北への開戦を進めた
・米国国務長官コーデル・ハル「ハル・ノート」は一才日本の条件は承認せず
米国は既に日本の暗号解読から事前に了解していた(日本の資源不足と開戦決議)
ー開戦前の日本vs米国戦力(米国の7割を確保できる予測で、「戦争にノー」と言わなかった)
・飛行機:3800機vs 米国5500機、戦艦:10隻vs17隻、航空母艦:10隻vs8隻、
重巡洋艦:18vs18、軽巡洋艦:20vs19、駆逐艦:112vs72、潜水艦:65vs111
総艦艇数:235隻・97万5793トンvs345隻・138万2026トン
・海軍は最後の最後まで日米交渉の前途を思い、奇襲作戦はギリギリまで待機した
・最後通牒での不手際は米国外務省の職員の怠慢で攻撃30分前となった
米国は日本からの暗号解読で完全に読み取っており、日本の先制攻撃が必須だった
ルーズベルト大統領は「侮辱の日」「騙し討ち」と非難した声明文を国民に発表
ーハワイ奇襲(12月8日)
・飛行機353機、米国の太平洋艦隊を攻撃、空母はいなかった
・日本として「自存自衛のためにやむを得ずして立ち上がる」として報道
・ミッドウエー海戦からガダルカナル島へ敗北への道
「運命の5分間」攻撃用の魚雷と陸の爆弾の積み替え作業のロスで艦隊惨敗
海軍の勝ちに驕り、うのぼれのぼせで敵の監視をしていなかったのが主の理由
・米国の大規模な上陸作戦に兵器、食糧不足(米国輸送船など輸送路を抑えが逆転)
・山本五十六長官の戦闘機攻撃を受け戦死(暗号解読で尾行)
・無謀で個人的な野望のインパール作戦で3万人戦死(病気・食糧不足)
後方支援なし、補給なしの無謀な牟田口中将の勲章欲50日戦略
・サイパン島玉砕から特攻隊「志願兵」(250k爆弾抱えた戦闘機)が開始
神風:敷島隊(5機)、大和隊(6機)、朝日隊(2機)、山桜隊(2機)
B29爆撃機がサイパンから東京上空へ発進(1944年11月)
闇取引など国内では物価が10倍以上値上がり(非国民告発運動)
ー日本降伏ーヤルタ会談
・1945年ルーズベルト・チャーチル・スターリン領土占領・制空権獲得
・当初ソ連は樺太南半分、千島列島、大連、旅順、南満州鉄道を返して欲しいと嘆願
・8月15日以降にソ連は無力の日本へ侵入、できるだけ領土獲得を狙った
戦死者8万人、57万4538名が捕虜としてソ連に連行(帰還者は47万2942人)
・ロシアの日本への貪欲な奪回戦略を知った米国は日本を早く降伏させようと原爆投下計画
焼夷弾で焼き尽くすことかでの攻撃開始(原爆投下計画は1945年4月23日決定)
・戦艦大和は米軍380機で沈没、2740人が戦死、その他巡洋艦等で980人も戦死
・最後の内閣鈴木貫太郎が「最後の一兵まで戦う」と宣言
・1945年4月13日ルーズベルト死去、4月28日ムッソリーニ銃殺、4月30日ヒトラー自殺
1943年9月イタリア降伏、1945年5月7日ドイツ降伏、ポツダム宣言7月24日
・1945年8月6日広島、9日長崎原爆投下、ソ連が日本へ侵攻開始
ポツダム宣言受諾、「米国制限下におかる」とした連行最高司令官判断となる
天皇の「聖断」に対する軍部は納得し得なかった(8月10日軍部クーデタ計画あり)
14日連合国へ通達、9月2日ミズーリ艦船上で「降伏の調印」となる
ー占領後の軍隊・国民(各国の軍隊配置9ヶ月)
・米軍85万人本土統治(関東・中部・近畿に31万5千人配置)
・英国軍16万5千人(中国・九州)
・中国軍13万(四国・近畿)
・ソ連軍21万(東北・北海道)
ー3百10万人の戦死者
8月15日ラジオ放送で天皇自らが終戦をつげる
1926年から1945年までに戦死者3百万人以上
戦争末期での特攻隊では海軍2632人、陸軍1983人が戦死した
ー歴史に学べ
・国民的熱狂を作ってはいけない(時の勢いに駆り立てられてはいけない:三国同盟など)
・抽象的な観念論を非常に好み、具体的な理性的な方法論を全く検討しない(勝手な論理)
・日本型蛸壷社会における集団主義の弊害(エリート集団のエゴと過剰な自信)
・降伏は正式な調印がなければ宣言だけでは認証されない(国際常識)
・ことに対する対処療法的でその場その場を誤魔化し処理する(複眼的な考えを持たない)
ーノモンハン事件から学ぶ(1万7700人の戦死者)
・思いあがり「敵は日本軍が出動すれば退却する」
・敗北を素直に認めない(更なる敗北へとつながる・反省しない)
・旧式銃で対抗(本営での近代化兵器への開発・戦略・努力不足)
・最前線での事実・結果を参謀等が正しく伝えない(天皇への報告も偽り)
・軍律の怠慢人事・配置など(失敗した服部・辻参謀を再採用、敗戦への再編と無責任)