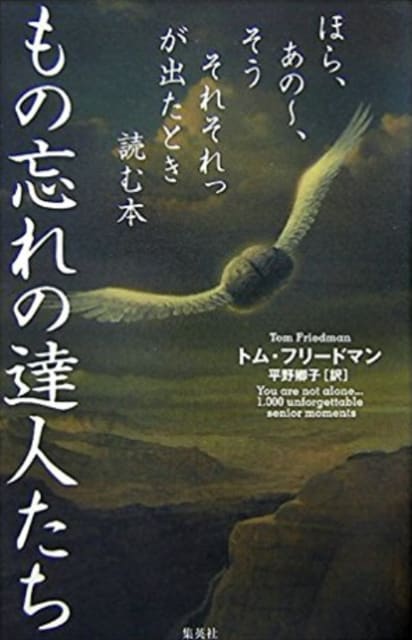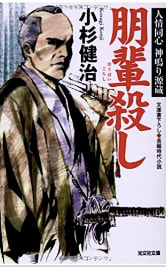@退職すると「肩書き」が消える。消えると周りが変わって見える。仕事上の情報、人、金回りなど一切が変わる、それほど「肩書き」は社会に通用する「勲章」のような物だ。問題はその「肩書き」がない世界(退職後)に入って何をするかである。「人生100年時代」は退職後の生活がさらに20年〜30年はある。では最初に何をするか?この書で一番気になったことは「捨てる」という事。「勿体無い」或いは「物持ち」の世代だから物は多い。シンプルに生きることは、シェアー・共有・リサイクル文化など物を持たない世代文化に見習った方が良いかもしれない。「勿体無い」は物がない時代に育った、教わった教訓でいつかは使う、利用すると思いつつ保管しておくが、殆どが使われず奥にしまったままで、新たに購入したものがその上に積み重ねられている。「捨てる」は意外に勇気がいる。「想い出」もあるからだが、やはり「捨てる」を勇気を持って一気にすべきだろう。遺された遺産整理など誰も見たくもない物が多いし、「ゴミの塊」だ。それこそ家族に迷惑、負担をかけないで済む。それをこなした後、また新たな夢・趣味を持ち、物・事にこだわるのもいいかもしれない。この書の最後にある言葉「幸福とは生きた長さではなく、自分の夢をどこまで追い求めることができたか、それだけのこと」が印象深かった。
『持たない!生き方』米山公啓
- 「気楽でシンプルな人生の勧め」
- 「捨て去ることで喪失感はなくなる。守ろうとするから、喪失感が起こるのであって、求めていくならそんなことは全くない。肩書きも持たず、物も所有しない潔さこそ、新しい人生の生き方である。」
- 「大きな家を持たない」
- 賃貸生活か持ち家か?所有・持たないを優先した方が良い
- 老後の引っ越しはしない
- 子供と同居しない
- こまめに体を動かす(週三回ほどの歩行で脳の活性化・健康)
- 10分の運動を1日3回、30分くらいの運動
- 人に任せない生き方(自分から動く)
- 都会の一人暮らしが理想
- 「健康神話を持たない」
- 好きなものを楽しく食べる(食事を楽しむこと)
- 低カロリー3割減で寿命3割伸びるより
- 60歳を超えたら豊かな食生活にすること
- 食べれないストレスは体・脳に影響する
- 塩分を控え、カリウムを含む食品をとる
- 甘いものが体に悪いのではない
- 糖尿病は遺伝子と高カロリー高脂肪の食事
- 砂糖・ブドウ糖は脳にとって必要
- 楽しく食べるか、節制で長生きか(美味しい料理)
- 脳を元気にするには歩くこと「最強の健康法」
- 骨を守るには自分の体重をかけること(かかと落とし)
- ダイエットの最短は食べるものを減らす事だが
- 体調の異常とリバウンドが起こる
- 「肩書きを持たない」
- 全く新しいものへの挑戦
- 大人の脳はリスクを好まなくなっていく
- 教わるではなく学び取る姿勢が大事
- 苦手な事は脳にとって良い(右脳への刺激)
- 左脳:計算・事務系
- 右脳はデザイン・芸術・音楽・文章を書くなど
- 芸術家はいつまでの若さを保つ
- 子供の頃に体験、知ったことを再挑戦する
- 感覚で挑戦・五感をフル活用(感覚への刺激)
- 新しい情報を常に、新しい事に好奇心を持つ事
- 同じ仲間との交流は大きな刺激とはならない
- 若い人との話に昔の話はほどほどに
- 過去を語らない事こそ若さの証明
- 病気は自慢するのではなく、どんな健康法をしているか
- 「孤独な時間を持たない」
- 社会との繋がりを持つ事(仕事を常に持つ)
- 教える楽しさ、面白さを知る
- 右脳の刺激に評価・尊敬、褒められるは脳を元気にする
- 愛情・恋愛でも脳が元気になる(ドーパミン)
- 自分史を書く・遺す事
- 「余分な金を持たない」
- 自分のためにお金を使い切る
- ローンは組まない(銀行への投資となるだけ)
- 「老いる前にやるべき6つのこと」
- 「時間を忘れる時間を持つ事」(趣味を広げる)
- 「定年までの服を捨てる事」(派手な演出をする)
- 「既成のものを拒否する事」(こだわりを持つ)
- 「形のあるものを遺す」(自分史を作る)
- 「友人に会っておこう」(同窓会等へ出かける)
- 「世界1周を試みる」(別世界を知る・感動を与える)