
ようやく疑問が解決しました。
(∩´∀`)∩ ワショーイ
『河北新報』1906年1月20日「凶作地方教育費県債」(原文に句読点追加)
東北凶作地に於ける教育費県債募集の件は文部、内務、大蔵の三省にて協議中なるが、文部省側の意見は目下同地方の教員は、俸給支払延滞の為め非常なる苦痛を感じつゝあり。或地方の如きは現に三箇月、五箇月の未払と成り居り、此等は税金の集まり次第、按分比例にて分与さるゝも、其額僅かに一円乃至二円位宛にて、何れも弊衣破袴肉落ち色青ざめて、而も熱心に教授する有様見るも甚だ哀れなり。尤も俸給支払の延滞は、町村役場吏員等も同様ながら、此等は土着の中等民にして何れも相応の資材を有し、且つ俸給は租税と相殺し居れば、苦痛を感ずるものは少かる可きも、教員は多くは土着の者にあらずして、僅かに十二円十五円の俸給を唯一の生活費充て居る有様なれば、企業等の如き手段にては此急を救ふに足らず、此際是非共県債を募集するの外、道なかる可しとの意向あり〔後略〕
戦前の日本においては、しばしば教員の給与未払いが社会問題になりました。
それは給与を支払うべき市町村、とくに小規模な町村の財政が危機的な状況にあったため、とされています。
ただし、町や村が財政難であったなら 教員以外の給与も払えなかったんじゃね? というのが素朴な疑問だったわけです。
ここで紹介した新聞記事では、以下のように状況を報告しております。
①半年近くお給料をもらえない教員は大変ですよ。
②町村役場の職員は、その土地のボンボンだから余裕がありますよ。
③しかも、お給料がない代わりに、税金を納めなくても大丈夫なんですよ。
④ゆえに、赴任地と縁の薄い先生たちだけが 肉が落ちて青ざめる わけですね。
わかってしまえば、なるほどなー、という話でした。
役場の職員たちは土地のお金持ちであっただけでなく、租税と不足する給料とを「相殺」する、なんて対応もしていたんですね。
いろいろと勉強になりました。
_○/\_ ハハァ-! ...
ちなみに「弊衣破袴(へいいはこ)」というのは、ぼろぼろの衣服と破れた袴、すなわち ヨレヨレの身なり のことですね。
どちらかというと「幣衣破帽(へいいはぼう)」の方が、よく使われているような気がします。
写真は、引き続き学習発表会の様子。
家で繰り返し練習していた通り、ハキハキと話しておりましたよ。
(∩´∀`)∩ ワショーイ
<11月の新刊コーナー>
11月4日、この音とまれ!(10)
11月16日、花のズボラ飯(3)
11月20日、いとしのムーコ(8)
11月20日、きのう何食べた?(11)
11月20日、聖☆おにいさん(12)
11月27日、よつばと(13)
11月30日、しあわせアフロ田中(1)
11月30日、あさひなぐ(17)
よつばとの最新刊が、ようやく出ますね。
ただ、リアルの15巻は難しそうな気配です。ざんねん。










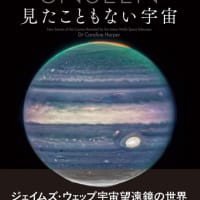














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます