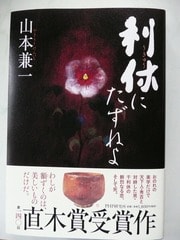←今日もまた頑張って更新いたしますので、「ブレンド日記」を応援してやってください。
←今日もまた頑張って更新いたしますので、「ブレンド日記」を応援してやってください。クリックよろしくです。
≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁≁
 私が愛してやまない太宰治の「走れメロス」の話を土台にしてあったので、とくに入り込みやすかったということもあるが、面白かったと思う。
私が愛してやまない太宰治の「走れメロス」の話を土台にしてあったので、とくに入り込みやすかったということもあるが、面白かったと思う。勿論甘納豆で読ませてもらったのだけど、久々の社会派ミステリーかな。
「雪冤」とは無実の罪をすすぎ晴らすことだそうです。こんな言葉初めて知りました。
まさしく冤罪のことなのです。
推理小説の醍醐味(だいごみ)はトリックをどう楽しむかにある。謎を仕掛ける作家に対し、その手のうちをどこまで読めるかは読書の楽しみであり、スリルを味わうことでもある。だが、物語が予想通りの展開になると、読者はがっかりする。読み手をどこまで騙(だま)せるかは作品の成否を握る鍵で、作家は読者の心理を予見し、その推理を出し抜かないといけない。かといって、彼らの「やる気」を挫(くじ)いてはならない。不即不離の状態が望ましいが、読者をその気にさせるのは簡単なことではない。その点で、この小説は成功している。毎日新聞書評に書いてあった。
ううむ、この若かりし頃はサスペンスおたくだった、経験豊富なおその姐さんをも騙すとは、新人ながらあっぱれ!といいたい。(少々偉そう?)どんでん返しがこの小説を最後まで、飽きさせなかった。
そうは言うもののこの本の真のテーマは死刑は是か、非かということで、その論争がこの本の中で展開されるけれど、それが一番読み応えのある部分でありまた著者の訴えたかった事なのではないかと思う。
そして、裁判員制度の導入によって、現在司法の問題が広く注目を集めているが、書名が示す通り、この小説は冤罪問題を題材にしている。
無実の罪で逮捕された息子の死刑が確定された後も、息子の無実を信じ再審を求める父親を軸に書かれているのだけど、無残にも最愛の息子の死刑が執行されてしまう。その苦しみに耐えながら、父親は真相解明に立ち上がったのだ。
手の込んだミステリを通じて死刑制度に疑問を投げかける。死刑賛成派・反対派の意見をふんだんに織り込んでいてミステリとしても二転三転する真犯人に何度も騙されてしまう。
ただ読んだあと、あまりに凝った作りのため、ここまで混ぜくらなくてもとの読みづらさの印象も拭えませんが・・・。
でもう一冊。
リビドヲ・・弐藤水流著(光文社)
 この小説正直言って あまり好みではない。
この小説正直言って あまり好みではない。そう言ったら「あんたの好みで本を買っているのではない。」といわれましたけど。
そんなわけで斜め読みしました。
残虐連続殺人事件が発生。凶器、被害者同士の関連、不明。妻を残し失踪した男が捜査線に浮上するが、彼には人を殺す理由がない。失踪した男の妻。男の旧友の元精神科医。覇気のない年下の相棒に苛立ちながら捜査する刑事。それぞれが探るうちに、男は失踪直前、未完成のままお蔵入りした昭和30年代の映画を観ていたことが判明。映画黄金時代の撮影現場で何が起こったのか?バブル期の東京で、誰が、何の目的で、殺人を続けるのか?―しかし、これらは恐怖の幕開けに過ぎなかった。この物語の結末を見届けるのは誰だ。(「 BOOK」データベースより)
作中の未完成映画は阿部定事件を扱ったものらしく、主役の男優が次第に憑かれたような感じになって行くのが印象的だった。
久々の晴れ 30℃