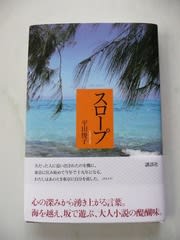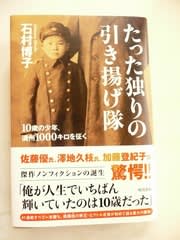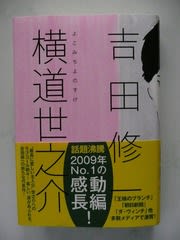←毎度お手数おかけします。クリックお願いできますか?励みになります。
←毎度お手数おかけします。クリックお願いできますか?励みになります。たまった、たまった、ブックレビューが・・
早く書かないと、というわけで今日は本の話です。
 この本はなんでも、『第2回 ばらのまち福山ミステリー文学新人賞』受賞作品らしい。
この本はなんでも、『第2回 ばらのまち福山ミステリー文学新人賞』受賞作品らしい。『現在では、昔の猫間川は、下水管にして地下に埋めて道路となり、
「源ケ橋」の姿はありませんが、生野本通商店街の入口にあたり、
源ケ橋交差点の付近です。
ここには、千年以前の昔から「猫間川」がありました。
南から流れてきた水が、北の旧淀川に合流していてのです。
さて、このあたりに、古い伝説があります。
200年も昔、江戸は、文化と言われる頃のことです。
「猫間川」の渡し守をしている「源」という悪党がいました。
通行人から暴力で金品をまきあげきあげて生活をしていたのです。
或る日、例のように、一人の旅人からみぐるみ剥いで殺してしまいました。
ところが、この人が、長年行方を捜していた、我が子だったのです。
さすがの悪党の「源」も深く悲しんで悔やみました。
思い悩んだ末、ついに罪滅ぼしをしようと決意します。
自分の身代をすべてなげうち、「猫間川」に橋を架けることにしたのです。
この橋は、すごい橋でした。それは香木に使われる「伽羅」で出来ていたのです。
この香り高い伽羅香木の橋は、源さんの悔いを表して、あまりあるものでした。
人々は、善人になった「源さん」に因んで、「源ケ橋」と名づけて呼んだのでした。 』
表紙をめくるとこの昔話が書いてある。
さて、面白かったのかというと、ううーん・・・正直サクサク読めたけど、内容的サスペンスとしては どんでん返しがあるわけではなし少し平凡かな。でも力作ではあったと思うが。
それというのも 今までの大好きな推理作家のデビュー作は どれもこれも、読むうちにすっかり入りこみ、感嘆とため息しか出なかった記憶、舌を巻くほどだったのに比べて、この作品は単純なのだ。
たとえば 水上勉の「海の牙」、松本清張「目の壁」、高木彬光「刺青殺人事件」、内田康夫「死者の木霊」・・・
ずーっと昔に読んだにもかかわらず覚えているほど素晴らしかったので。
介護保健施設の職員・四条典座(しじょうのりこ)は、
認知症の老人・安土(あど)マサヲと出会い、その凄惨な過去を知る。
昭和二十年八月十四日、大阪を最大の空襲が襲った終戦前日、マサヲは夫と子供二人を殺し、首を刎ねたという・・
穏やかそうなマサヲが何故そんなことをしたのか?
典座は調査を進めるうちに彼女の無実を確信し、冤罪を晴らす決意をする。
死んだはずの夫からの大量の手紙、犯行時刻に別の場所でマサヲを目撃したという証言、大阪大空襲を描いた一編の不思議な詩……
様々な事実を積み重ね、典座にある推理が浮かんだそのとき、大阪の町を未曾有の災害・阪神大震災が襲う――!!
まず、名前が変わっている。
なにもそこまで変わった名前にしなくてもいいのにと、それに違和感を覚えた。
そして冤罪を晴らすために典座は仕事が終わってから、調査しキチンと立証していくのだ。
冤罪を晴らそうという正義感と情熱には脱帽するも、読み終えた最後、お疲れさん!といいたくなった。
雲りのち雨 15℃