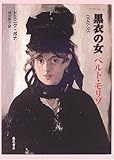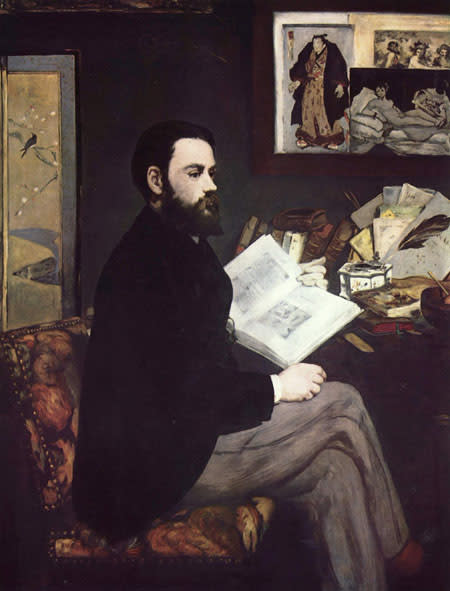「龍馬史」が描く坂本龍馬の続きでしょうか。
あるいは、桐野利秋と龍馬暗殺 前編、後編の続きかも、なんですが、「木漏れ日に命を!」のノブさまのご著書を、読ませていただきました。
 | 龍馬暗殺の黒幕は歴史から消されていた 幕末京都の五十日 |
| 中島 信文 | |
| 彩流社 |
私、いわゆる龍馬暗殺黒幕ものは、ほとんど読んでおりません。
歴史の謎、といいますものは、さまざまに設定が可能です。
素人は素人でも私は変人ですから、一般にはほとんど興味を持たれていないモンブラン伯爵の維新における活躍なんぞといいますものに、多大な関心を抱いたりしているのですけれども、通常でいいますならば、昔邪馬台国、今龍馬暗殺かなあ、と思ったりします。
そういえば、最近あまり、邪馬台国関係の出版物を見かけなくなりましたねえ。
あれこそ、史料があまりにも少なくって、素人が簡単に取り組める歴史の謎でしたから、乙女の頃の私は、あれこれと他人様のご著書を拝読しては、なるほどー、そうかもー、いやまってー、こうかもーと、推測するのを楽しんだものでした。
しかし、龍馬暗殺について言いますと、アーネスト・サトウと龍馬暗殺に書いておりますが、故・西尾秋風氏のご高説に、お口ぽっかーんとあきれてものがいえない状態になってしまいまして以来、馬鹿馬鹿しくって、読むのは時間の無駄、と思ってまいりました。
邪馬台国とちがいまして、史料がないわけではありません。
あるんです。それなりに。
実のところ私、西尾秋風氏のご高説も、詳しく承知しているわけではなくって、おそらく最初の頃と後の方では、お説にちがいがでてきていたのでは、と思うのですが、少なくとも私が知っていた範囲では、中村半次郎(桐野利秋)だということでして、これが実に馬鹿馬鹿しい話なのです。
桐野利秋と龍馬暗殺 後編に、龍馬の甥、高松太郎が事件の二ヶ月後に、龍馬の兄夫婦へ宛てた手紙を引用しております。以下、必要部分を再録。
僕六刀を受けて斃る。十六日の夕方落命。次に才谷を斬る。石川氏同時の事、然れども急にして脱力にいとまもなく、才谷氏は鞘のまま大に防戦すると雖、終にかなわずして斃る。石川氏亦斃る。石川氏は十七日の夕方落命す。衆問ふといえども敵を知らずといふ。不幸にして隊中の士、丹波江州、或は摂津等四方へ隊長の命によりて出張し京師に在らず。わずかに残る者両士、しかれども旅舎を同うせず。変と聞や否や馳せて致るといえども、すでに敵の行衛知れず、京師の二士速に報書を以て四方に告ぐ。同十六日牛の刻に、報書の一つ浪花に着く。衆之を聞き会す。すなわち乗船17日朝入京、伏見より隊士散行す。
高松太郎は、大阪にいて、16日の夜中に事件の知らせを受け取り、11月17日の朝には入京しています。そして、中岡慎太郎(石川)が落命したのは17日の夕方で、慎太郎は「知らない奴らにやられた」と語り残していた、というんです。
私は、平尾道雄氏の「海援隊始末記」から孫引きしてこのときのブログ記事を書いていまして、私が参照しましたのは古い版のものですが、いまでは、下のように文庫本で出ていますので、簡単に手に入ります。
 | 坂本龍馬 - 海援隊始末記 (中公文庫) |
| 平尾 道雄 | |
| 中央公論新社 |
下の「陸援隊始末記」もそうなのですが、龍馬と中岡慎太郎について、平尾道雄氏のご著書は、基本中の基本だと思うのですね。
 | 陸援隊始末記―中岡慎太郎 (中公文庫) |
| クリエーター情報なし | |
| 中央公論新社 |
桐野にとって、元治元年からつきあいのある慎太郎と、寺田屋事件の後に薩摩で新妻とともにもてなしたこともある龍馬と、大詰めを迎えての二人の死は、なんとも口惜しいことであったと思いますし、それは、慎太郎ファンでもある私にとってもそうなのです。
しかし、犯人さがしについて言いますならば、平尾道雄氏が述べられておられます基本線につけ加えることは、ほとんどないのではないか、といいますのが、正直なところです。
にもかかわらず、今回、ノブさまのご著書を拝読させていただきましたのは、「犯人の狙いは龍馬ではなく、実は慎太郎が本命だったのではないか」という憶測には、私も少々関心がありましたし、ノブさまが当初ブログに書かれておりましたのは、そういうようなお話だったからです。
ただ、慎太郎本命説には、難点があります。殺された場所が、龍馬の居所の近江屋であったことと、慎太郎が即死していなかったこと、です。
即死していなかったことにつきましては、犯人は死んだと思ったけれども、昏倒していた慎太郎が一時蘇生したのではないか、とは、十分に考えられますし、慎太郎は「知らない奴らだった」と言い残しているわけですから、犯人にしてみましたならば、虫の息があったにしても正体がわかるわけがない、という安心感があったのではないか、という推測も成り立つでしょう。
しかし、事件の場所が龍馬の居所の近江屋であった、につきましては、慎太郎とともにやはり龍馬も狙われていたのだろう、としなければ説明のつき辛いことでして、今回、ノブさまがそういう観点からご著書を出されたのは、卓見だと思います。
それでー、ご著書の内容なのですが、大筋ではけっこう説得されます。
といいますか、もし、一会桑サイドではなく黒幕がいる、としましたら、この線ならまあ考えられなくはないのかなあ、と思ってしまう、常識的なお話をされていまして、声を失いますような奇説、珍説とは、一線を画しておられます。
それについては、ご著書の「はじめに」で、ノブさまはこう述べておられます。
今までに論じられていた諸説に対して、論議の前提や思考方法にどこか違和感を感じていた。というのは、江戸時代や幕末、そして、現代にしても、人間の行動や思考は大きくは変わらず、龍馬らの暗殺も現代に通じる事件ではないかと考えたからである。そういったことから、当時の幕府や諸藩の動きを洗い直し、現代における会社組織などの動きや人間の行動と比較検討が必要ではないかと思った。
「時代は変わっても人間の行動や思考は大きくは変わらない」という信念を基本に持っておりました歴史家として、『近世日本国民史』の徳富蘇峰がおります。彼は、そういう目で歴史を見、現実も見ておりましたので、敗戦後にはいち早く、アメリカが日本を助ける方向に舵をきるだろうと見極めた、鋭い観察眼を示していたりします。
基本的には、ノブさまのおっしゃる通りなんです。
ですけれども、しかし……、です。
時代は変わりますし、その時代の風潮に、人間は大きく影響されるものである、とも、私は思っています。
例えば、暗殺という行為に対します評価です。
幕末・明治と現代では、受け止め方が、まったくちがうと思うのです。
古い記事ですが、慶喜公と天璋院vol2に大筋のところは書いてあるのですが。
まずは桜田門外の変。
幕府の側からしますならば、大老が公道で浪士に襲われ、殺されたのですから、まぎれもないテロです。
しかし、井伊大老は安政の大獄という政治的な大弾圧を行っていましたので、弾圧されました側からは、この暗殺は義挙でした。
弾圧された側には、高位の公卿・大名もあり、土佐の山内容堂などは、「首を失って負けたおまえが成仏できるものかな。おまえの領地は犬や豚にくれてやれ」というものすごい漢詩を作って大喜びしています。
まあ、しかし、です。当時の状況としましては、密かに漢詩を作っていただけなのですから、自分を失脚させた政敵が殺されて、表面ではお悔やみを言いながら日記に罵詈雑言を書き残すくらいのことは、現在でもありえそうなのですけれども。
しかし、ですね。
いつのまにかテロが正義となり、堂々と天誅がまかり通ったあたりは、どうでしょうか。
「京の天誅の最初の一石となった島田左近暗殺には島津久光のひそかな指示があったのではないか」と書いたことについて、私はいまもそうであったのではないか、と思っています。久光に「あいつが怖いんですのやー」と訴えた近衛忠房は、島田が無事殺されたと知って「希代希代珍事、祝すべし、祝すべし」と喜んだというのですから。
大会社の会長がですね、提携する政治家から「ライバルの用心棒が怖いんやー」と訴えられたので部下に暗殺を命じるって、現代ではまず、ありえんですわね。
これに証拠があるのか、といえば、状況証拠しかないわけですけれども、確実なところでいけば、例えば久光の命令による上意討ちであった方の寺田屋事件、です。大会社の会長がですね、社員が勝手に他者の社員と連携して事を起こそうとしているからって、「やめろというわしの命令に従わないなら殺せ」って部下に命じるなんてこと、現代ではありえないですわね。書きかけなんですけれども、寺田屋事件と桐野利秋 前編は、時代相に即して、事件を追おうとしたつもりです。
暗殺といっても、それは自分の命をかけてするものですし、命がけですることは賞賛される時代だったのだと、私は思います。
それはしかし、当時においては日本だけのことではなく、世界的にもそうだったのではないでしょうか。
例えば、イタリア統一運動にかかわっていましたカルボナリ党のフェリーチェ・オルシーニですけれども、もともとはカルボナリ党であったにもかかわらず、フランスの皇帝となってからのナポレオン三世がイタリア統一に背を向けたと見られたことから、皇帝の馬車に爆弾を投げつけるというテロを決行するのですけれども、失敗に終わって皇帝は軽傷。しかし、周囲のなんの関係もない一般フランス人がまきこまれて、死者十数人、負傷者百名以上という、大惨事になってしまいます。
しかし、大義に殉じようとするオルシーニの裁判での態度がりっぱだということで、一般のフランス人もけっこう同情しますし、結果、ナポレオン三世は、イタリア統一に力を貸す決意をします。
ちょっと、現代ではありえない話ですよね。
もしかしましたら近デジにあるかな、と思うのですが、明治32年発行の「尚武養成 軍隊必読」という読み物があります。古今の武勇談を集めた読み物なんですが、新撰組の近藤勇が一人で龍馬と慎太郎を斬り殺したことになっていまして、その武勇が賞賛されていたりします。
「龍馬死に臨み慎太郎を呼び起し、幕府末運に臨むもかかる武士あり。未だ侮るべからずと語り、嗟嘆して死す」って、現代ではちょっと理解し辛い価値観、ではないでしょうか。
まあ、明治42年、伊藤博文を暗殺しました安重根を、日本人が義士と称えるような風潮もあったわけですし。
と、まあ、そういうような観点からしまして、ですね、ノブさまの描写されます時代の様相が納得がいくかといいますと、ちょっとちがうかな、と感じるんです。例えば、以下です。
京都の街自体は、緊張感は以前とは比べものにならないほど高揚してはいたが、それが逆に街の安全や治安に効いており、表面上は台風の目の中にいるような、ひと時の奇妙な静けさを持った、治安もかなり守られていた街だったのだ。笑い話だが、慶喜に大政奉還を建白した土佐藩要人などは、坂本龍馬らが斬殺された日、仲間と朝から芝居見物を暢気に楽しんでいたという話も残っているくらいである。
えーと、まず芝居見物については、ですね。
例えば一会桑側が、です。れっきとした土佐藩要人を襲ったのでは、それで黙っていては土佐の藩としての面目が立たず、確実に土佐藩そのものを敵にまわしてしまいますし、そんなことをば一会桑側も望むわけがないですから、別に土佐藩要人の身に危険はないわけです。
一方、龍馬と慎太郎は、といえば、です。現実に二人が殺された後、犯人は新撰組だと噂されましたが、むしろ土佐藩邸は、二人を関係ないものとして扱うことで面目を保ち、それで一会桑の敵にまわるということもなかったのですから、殺したところで大問題とはならず、ひるがえって考えると、彼らは危険にさらされていたわけです。
危険か危険でないかは立場によってちがった、ということでして、桐野利秋と龍馬暗殺 後編に書きました以下の部分を訂正する必要を、私は感じておりません。
慶応三年十月、大政奉還が公表された当時の京は、殺伐とした空気を濃くしていました。
昨日もご紹介しましたが、10月14日、大政奉還のその日、京在海援隊士・岡内俊太郎から、長崎の佐々木高行への手紙の最後は、この文句で結ばれています。
「新撰組という奴らは私共の事に目をつけ、あるいは探偵を放ちある由にて、河原町邸(土佐藩邸)と白川邸(陸援隊)との往来も夜中は相戒め居候次第に御座候」
新撰組のやつらはぼくたちに目をつけて、探偵にさぐらせていたりして、ここ白川邸と河原町藩邸とを行き来するのも、夜はやめておこうと気をつけているほどなんだよ。
10月28日の桐野の日記には、そんな殺伐とした状況をうかがわせる記事があります。
桐野の従兄弟の別府晋介と、弟の山之内半左衛門が、四条富小路の路上でいどまれ、「何者か」というと、「政府」との答え。「政府とはどこか?」とさらに聞けば、「徳川」とのみ答え、刀をぬきかかったので、別府が抜き打ちに斬り、倒れるところを、半左衛門が一太刀あびせて倒した、というのです。
大政奉還があった以上、薩摩藩士は、すでに幕府を政府とは思っていません。
一方で、あくまでも徳川が政府だと思う幕府側の人々にとって、大政奉還は討幕派の陰謀なのです。
そして………、土佐藩在京の参政、神山佐多衛の日記です。
11月14日
薩土芸を会藩より討たずんば有るべからざると企これあるやに粗聞ゆ。石精(中岡)の手よりも聞ゆ
「会津藩は薩摩、土佐、安芸藩を討つべきだということで企てがあるという。中岡慎太郎も同じ事を言っていた」というんですね。
神山佐多衛の日記などを読んでいますと、あきらかに、この時期の京都土佐藩邸要人は、おびえています。なににおびえているかといいますと、白川の土佐藩邸にいる陸援隊と新撰組の間で騒動が起こり、それに土佐藩そのものがまきこまれるかもしれないことに、です。
一橋慶喜や松平容保のレベルの話では、ないんです。
幕府にしろ会津藩にしろ、新撰組の動きを確実にコントロールできているわけではないですし、陸援隊にしろ海援隊にしろ、浪士の集まりなんですから、土佐藩がコントロールできたわけでは、決してありません。
もう一つ。
倒幕派と佐幕派と、あるいは土佐藩士と会津藩士と、自由に会っていたについて、なんですけれども、いや、桐野利秋と龍馬暗殺 後編、そして中井桜洲と桐野利秋をご参照いただきたいのですが、脱藩薩摩人で、海援隊に席をおいておりました中井桜洲は、です。倒幕派の桐野利秋・永山弥一郎と非常に親しく(このことは、後世のものになりますが、中井の書簡で確かめられます)、西郷・大久保・小松が討幕の密勅を奉じて国元に帰りました直後に、永山とともに桐野を訪ねているんですね。桐野の日記によれば、桐野は西郷から密勅の写しを見せてもらっていて、なぜ京都薩摩藩邸の要人三人がそろって国元に帰ったのか、真相を知っています。中井は、密勅について、桐野から聞き知っていた可能性が非常に高いんですね。
しかし、かなり自由にいろいろな陣営の人物と会って、土佐藩邸要人の情報源になったりもしています。どこまで中井がしゃべっていたかは、謎なんですけれども。
あと、ですね。
詳しくはfhさまのところの2007.08/16 [Thu]「備忘 寺島宗則19」にありますが、いわゆる王政復古のクーデターのその日、その首謀者といっていい大久保利通のブレーンだった寺島宗則が、なんでだか知りませんが、慶喜の側のブレーン西周に会おうとしていたりするんですね。寺島の自叙伝によれば、西周と榎本武揚に会おうとしていたことになっていまして、「西家略譜」『西周夫人升子の日記』でも、それは確かめられることなんです。
寺島宗則は幕府の蕃書調所にいた人ですから、もともと西周とは親しく、えーと、このとき大阪の薩摩藩邸には五代とともにモンブランがいますし、モンブラン伯は維新回天のガンダルフだった!? vol2で書いておりますが、フリーメーソンに加盟した西周は、オランダ留学帰りにパリにより、モンブランのもとを訪ねていたりするんですね。
私といたしましては、寺島ママンはモンブラン・五代と西周を会わせて、そうですね、慶喜に対して、開港地を朝廷に渡して外交権を手放すことを勧めてもらおう、とか、考えていたんじゃないだろうか、と妄想したくなります。
ま、あれです。治安がどうだろうが、会うべきと思えば、敵陣営の人物でも会おうとしてしていたりするもの、と、私は思うのです。
それで、ですね。
肝心要な部分、なんですが、最初に述べましたように、大筋では、ノブさんのなさっているような推理も、なりたたなくはない、と、私は思っています。
土佐藩の史料をあまり読んでいないものですから、勉強させていただいたことも多々あります。
しかし、そのご推測に関して、証拠はありません。証拠と思われたのでしたら、それは誤読、だと思います。
思います、といいますのは、私は直接「寺村左善道成日記」を読んでいませんので、断言はできないんです。
しかし、ちょっとネタバレになるかもしれませんが、慶応三年九月二十四日の「寺村左善日記」について、寺尾道雄氏が「陸援隊始末記」でこう記していると述べておられます部分を、以下、引用します。
「相談の上、(陸援)隊士を白川邸から放逐することにしたが、命しらずのものが、うかつに処分するとどんな大事をおこすかも知れない。ついに後藤の裁断で壱千両を投げだし、おだやかに出すことにした」
えーと、ですね。
このもとの文章がどういうものなのか、私は読んでいないのでわからないのですが、ノブさまが引用しておられますこの日の日記の末尾、「吾邸内ヲ出ス事ニ決シタリ」が、平尾氏が要約しておられます冒頭の「(陸援)隊士を白川邸から放逐することにした」に呼応していると思われるんですね。
で、この「吾邸内ヲ出ス事ニ決シタリ」を、ノブさまは「白川土佐藩邸にいた陸援隊や海援隊の隊長(巨魁)である坂本龍馬と中岡慎太郎を飢寒の徒で何をするか分からない危険な浪士であるので排除したい」と訳しておられるんですけれども、この意訳を平尾氏の解釈とくらべましたとき、大きく意味がちがっていますし、平尾氏の解釈の方が、原文に素直なものではないのか、という気がするんですね。
平尾道雄氏は、「(土佐)藩邸でも佐幕派の連中は、この陸援隊を厄介視していた。幕府や会津の猜疑をおそれ、薄氷を踏む気持ちである」とも述べておられまして、「海援隊始末記」をあわせ読みますと、土佐の佐幕派が、海援隊も陸援隊も、同じように厄介視ししていたことは、大前提なんですね。
そこまでは変わらないんですけれども、では陸援隊と海援隊を土佐藩から切り離すためにどうしようというのか、というところで、平尾氏とノブさまの解釈は変わってきています。そしてノブさまのように、龍馬と慎太郎を排除するというような解決法は、成り立たないのではないでしょうか。
現実に、龍馬と慎太郎が暗殺されました後、海援隊・陸援隊の隊員の一部が、紀州藩士三浦休太郎と新撰組を襲う天満屋事件を起こしていまして、平尾氏の解釈のように「命しらずのものが、うかつに処分するとどんな大事をおこすかも知れない」という心配が大きかったと思います。
先に述べましたように、佐幕派が陸援隊、海援隊を厄介視していましたのは、自分たちのコントロールできない浪士集団であり、彼らが勝手に暴れかねないことでして、そんな集団が土佐藩の白川藩邸に巣くっていたのでは、自分たちに災難をもたらしかねないから、です。
以上を踏まえまして、ノブさまが引用しておられます「寺村左善道成日記」慶応3年10月5日の「白川邸浪士所分之事」を解釈しますと、これはもう素直に、そして平尾氏の解釈通りに「陸援隊士を白川邸から放逐すること」でまちがいはなく、「龍馬と慎太郎を暗殺すること」と解釈いたしますのは、不可能です。
結論からいいまして、平尾氏が書いておられます通りに、陸援隊を白川邸から放逐したい、という、寺村左善の望みはかないませんでした。そして、なぜその当時、左善が切実にそう思ったのか、というような分析に関しまして、ノブさまのご推測は、非常に説得力のあるものなのです。
いったいなぜ、慎太郎が龍馬とともに襲われたのか。
ノブさまの他のご推測の部分、実は新撰組も関係していたのではないか、とか、考えさせられる部分は多かったですし、ご労作、楽しんで読ませていただきました。
人気blogランキングへ