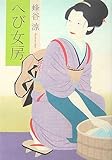広瀬常と森有礼 美女ありき14の続きです。
内容の上からは、今回も広瀬常と森有礼 美女ありき10と広瀬常と森有礼 美女ありき11の続報になります。
現在までのところ、慶応3年以降の広瀬寅五郎の動静がわかります史料に、私はめぐりあっていません。
広瀬寅五郎=冨五郎、広瀬常の父であったと仮定して話を進めますと、冨五郎は「静岡県士族」とされているわけですから、一度は静岡へ行ったものと推測されます。
おそらく、静岡では生活が成りたたなかったのでしょう。
明治5年の開拓使「女学生徒入校願」によれば、広瀬冨五郎は娘の常とともに、「第五大區小三區下谷青石横町加藤泰秋長屋」に住んでいます。
元大洲藩上屋敷、加藤泰秋邸の門長屋です。
「力石本加藤家譜」によりますと、明治4年2月23日、大洲藩知事・加藤泰秋は上京していたようです。
同年7月14日(1871年8月29日)、廃藩置県。
元大洲藩上屋敷と中屋敷の処置について、以下、「力石本加藤家譜」より、fhさまに解読していただきました。
同年同月廿三日右之通願書差出ス
邸地振替願書
今般諸県上邸被仰出候ニ付下谷和泉橋通大洲県邸地建家共私邸ニ拝領仕度依テ同所私邸右為代リト家作共奉還仕候間別紙絵図面二通相添右振替之儀御聞済被下置候様此段奉願候以
上
明治四年辛未十月廿三日 位 名
東京府御中
書面下谷和泉橋通私邸家作共可致返上同所大洲県元邸家作共引替下賜候事
辛未十月 東京府
明治4年9月、東京府は旧大名屋敷をすべて収公することになりましたが、元知事(藩主)に、一つは屋敷を下げ渡していたんですね。
私、加藤泰秋は最初から元上屋敷を私邸にもらっていたのだと思い込んでいて、上の文章の意味がうまくとれなかったのですが、fhさまのご教授によりまして、最初、東京府から下げ渡されたのは元中屋敷であった、と考えれば、筋が通るのだと気づきました。
goo古地図 江戸切絵図 東下谷-1
上の切り絵図で見るとわかるのですが、元大洲藩上屋敷と中屋敷は、路地を隔ててすぐそばにあります。
江戸時代の上屋敷を、明治になって私邸にした大名はほとんどいないようですから、あるいは一応、上屋敷は差し出すことにでもなっていたのでしょうか。
もちろん、上屋敷の方が敷地が広く、建物もりっぱだったでしょうから、東京府の意向が中屋敷を私邸に、ということだったとしますと、加藤家としては承服できなかったでしょう。
まず、加藤家から東京府への「邸地振替願書」の解釈です。
「今般、諸県に江戸屋敷を差し出すようにと仰せがありましたが、下谷和泉橋通にある大洲県邸地と建物(上屋敷)を拝領したいと思います。これに代えまして、同所にある現在の私邸(中屋敷)を、地内の家作(貸家)とともに返還いたしますので、別紙の絵図面2通を添えて、振替許可をお願いいたします。
これに対する東京府の返事です。
「書面にある下谷和泉橋通の私邸及び家作を返上すれば、同所の大洲県元邸と家作をその引替として下賜する」
大名屋敷には、長屋がたくさんありましたから、維新以降、大洲藩では、関係者で望む者に貸したりしていたんでしょうね。
そして、どうも加藤家では、中屋敷も手放したくなかったらしいのです。
翌11月、改めて中屋敷の払い下げを願っています。
同年同月八日願書差出ス
元私邸地御払下ケ願
前月私邸振替ノ儀奉願候所御聞済被下置難有仕合奉存候就テハ又候私邸三千七百七十八坪余ノ地所別紙図面ノ通別段御用ノ筋無之候得者開拓ノ上地味相応ノ物品植付申度候間相当ノ価ヲ以御払下ケ被下度此段奉願候 以上
十一月八日 位 氏 名
東京府御中 図面此ニ略ス
別紙地所払下ケ願ハ当時見合申尤場所姓名懸ニ留メ置書面差戻申候追テ一定ノ規則相立候上可及沙汰候此段申入候也
十一月十四日 東京府
「先月(10月)、私邸振替を願い出ましたところ、お聞き届けくださり、有難い幸せと存じます。つきましてはまた、私邸3778坪余の地所(中屋敷)について、別紙の図面の通り、別に官でご利用の予定がなければ、開拓して地味にふさわしいものを植えつけたいと思いますので、相当の価格でもって払い下げられますことを、このたびお願いいたします」
これに対する東京府の回答は、拒否でした。
別紙の地所払い下げについての願出は、今のところ見合わせ、当該の場所と(請願者の)姓名は、東京府の担当係(宅地係)に記録した上で、願書は差し戻す。追って(収公した土地についての)一定の規則が定まった上で、沙汰することを申し入れる」
どうもこれは危ないと、加藤家では思ったみたいです。
おそらく、なんですが、中屋敷のブロックの右隣、秋田藩佐竹氏の大きな上屋敷は、明治8年の地図では「陸軍造兵司御用地」になっていまして、一帯を陸軍省が狙っている、という情報をつかんでいたんじゃないでしょうか。
誰から情報が入ったかって……、武田斐三郎からです。
一ヶ月あまりの後、明治4年のうちに、加藤家は対策を講じています。
竹門もと私邸昨冬御払下ケ願書差出ノ所当年ニテハ願意御採用難相成趣ニ付武田成章ヘ示談ノ上同人ヨリ願書差出ス但入用ノ節ハ引受候筈
下谷和泉橋通名元私邸先般邸相成候由ニ付御用無之候得者私へ御払下ケ被成下度則図面相添此段奉願候、已上
十二月廿三日 武田陸軍中佐
東京府 邸宅懸御中
願之家作金百八十五両二部二朱永五十五文八歩ニテ払下ケ候条当二月ヨリ十六ヶ月ニ割合可被致上納右地所ハ更ニ拝借相済候事但上納方相滞候節ハ仮令自費修繕相成候共地所家作其儘取揚可申事
明治五年壬申正月
竹門の元私邸(中屋敷)について、昨冬に払い下げ願いを提出したところ、当年は願いは採用されないとの趣旨だったので、武田成章(斐三郎)へ示談の上、武田から願書を提出した。もっとも経費についてはこちらで引き受ける予定である。
下谷和泉橋通名の元私邸(中屋敷)について、先般収公されたそうですが、官でご利用の予定がなければ、私へ払い下げてくださるよう、図面を添えてお願いします。 12月23日 武田陸軍中佐
東京府 邸宅懸御中
中屋敷の家作、つまり借家人は、武田斐三郎だったんです。
以前に書きましたが、大洲藩の上屋敷と中屋敷は隣にありながら、実は町名がちがい、明治8年の住所で、上屋敷は徒町、中屋敷は竹町です。明治以前の切り絵図でも、徒町は徒町なのですが、竹町は竹門になっています。佐竹藩邸の西門の扉が竹でできていたため、中屋敷のあるブロックと佐竹邸一帯は、竹門と呼ばれていたそうです。
つまり、中屋敷は下谷和泉橋通を冠して呼ばれるゆえんはないのですが、振替と払い下げを有利に運ぼうとしたためでしょうか、中屋敷が上屋敷の付録であるかのように、東京府への願書では、上屋敷と同じく下谷和泉橋通の名を被せていたのではないでしょうか。加藤家の内部文書で、初めて「竹門」をだしてきてくれてまして、おかげで、これが中屋敷であることがはっきりします。
陸軍中佐になっていました借家人の武田斐三郎に願書を出させて、費用を加藤家が出すことで、実質的に中屋敷も手元に残そうとしたんですね。
この企ては、うまくいきました。以下、東京都の回答部分です。
払い下げを願い出た家作が、金185両2歩2朱・永55文8歩で払い下げとなったことについて、この2月から16ヶ月の月賦にして上納させることで、右地所は再び拝借済みとする。ただし、上納が滞ったときには、たとえ自費で修繕をしていたとしても、地所および家作はそのまま取り上げる。明治五年壬申正月
広瀬一家は、この明治4年、おそらくは廃藩置県の前後に、静岡を引き払って、江戸へ帰ったのではないでしょうか。
冨五郎は、旧知の武田斐三郎を頼り、斐三郎は陸軍省に勤めて、中屋敷を借りて住んでいたようですから、当初は、中屋敷の長屋に住まわせてもらったのでしょう。
そして、この大名屋敷収公に出くわし、斐三郎を通じて、加藤家に知恵を貸したのではないかと思われます。
斐三郎が中屋敷すべてを使うことはなかったでしょうし、多数あっただろう長屋は、そのまま借家にもなったでしょう。
実は広瀬冨五郎は、娘の常が森有礼と結婚した後、森家の土地の売り買いに、かかわっているんです。
森有礼夫人・広瀬常の謎 後編上に書いていますが、有礼は特命全権公使として清国にいる間に、木挽町の屋敷を引き払い、新しく外務省から払い下げを受けて、麹町区永田町1丁目14蕃地の大邸宅に引っ越す手配をしているのですが、この土地の取得、不用地の売却を、広瀬冨五郎がしているようなのです。
明治10年の有礼の家族宛書簡には、「永田町も広瀬様御配慮にて追々片付候趣」(1月24日付)とか、「永田町東方二三千坪賈払之儀広瀬氏へ頼入候」(2月15日付)とかの文言が見えて、冨五郎が不動産の扱いに長けていたことを、裏付けてくれます。
当初、斐三郎の居候であった広瀬一家は、冨五郎が加藤家の財産管理にかかわったことで、明治5年当時、加藤家の私邸となった上屋敷の門長屋に無料で住まわせてもらえることになったのではないか、というのが、私の推測です。
このシリーズ、続きます。
人気blogランキングへ


内容の上からは、今回も広瀬常と森有礼 美女ありき10と広瀬常と森有礼 美女ありき11の続報になります。
現在までのところ、慶応3年以降の広瀬寅五郎の動静がわかります史料に、私はめぐりあっていません。
広瀬寅五郎=冨五郎、広瀬常の父であったと仮定して話を進めますと、冨五郎は「静岡県士族」とされているわけですから、一度は静岡へ行ったものと推測されます。
おそらく、静岡では生活が成りたたなかったのでしょう。
明治5年の開拓使「女学生徒入校願」によれば、広瀬冨五郎は娘の常とともに、「第五大區小三區下谷青石横町加藤泰秋長屋」に住んでいます。
元大洲藩上屋敷、加藤泰秋邸の門長屋です。
「力石本加藤家譜」によりますと、明治4年2月23日、大洲藩知事・加藤泰秋は上京していたようです。
同年7月14日(1871年8月29日)、廃藩置県。
元大洲藩上屋敷と中屋敷の処置について、以下、「力石本加藤家譜」より、fhさまに解読していただきました。
同年同月廿三日右之通願書差出ス
邸地振替願書
今般諸県上邸被仰出候ニ付下谷和泉橋通大洲県邸地建家共私邸ニ拝領仕度依テ同所私邸右為代リト家作共奉還仕候間別紙絵図面二通相添右振替之儀御聞済被下置候様此段奉願候以
上
明治四年辛未十月廿三日 位 名
東京府御中
書面下谷和泉橋通私邸家作共可致返上同所大洲県元邸家作共引替下賜候事
辛未十月 東京府
明治4年9月、東京府は旧大名屋敷をすべて収公することになりましたが、元知事(藩主)に、一つは屋敷を下げ渡していたんですね。
私、加藤泰秋は最初から元上屋敷を私邸にもらっていたのだと思い込んでいて、上の文章の意味がうまくとれなかったのですが、fhさまのご教授によりまして、最初、東京府から下げ渡されたのは元中屋敷であった、と考えれば、筋が通るのだと気づきました。
goo古地図 江戸切絵図 東下谷-1
上の切り絵図で見るとわかるのですが、元大洲藩上屋敷と中屋敷は、路地を隔ててすぐそばにあります。
江戸時代の上屋敷を、明治になって私邸にした大名はほとんどいないようですから、あるいは一応、上屋敷は差し出すことにでもなっていたのでしょうか。
もちろん、上屋敷の方が敷地が広く、建物もりっぱだったでしょうから、東京府の意向が中屋敷を私邸に、ということだったとしますと、加藤家としては承服できなかったでしょう。
まず、加藤家から東京府への「邸地振替願書」の解釈です。
「今般、諸県に江戸屋敷を差し出すようにと仰せがありましたが、下谷和泉橋通にある大洲県邸地と建物(上屋敷)を拝領したいと思います。これに代えまして、同所にある現在の私邸(中屋敷)を、地内の家作(貸家)とともに返還いたしますので、別紙の絵図面2通を添えて、振替許可をお願いいたします。
これに対する東京府の返事です。
「書面にある下谷和泉橋通の私邸及び家作を返上すれば、同所の大洲県元邸と家作をその引替として下賜する」
大名屋敷には、長屋がたくさんありましたから、維新以降、大洲藩では、関係者で望む者に貸したりしていたんでしょうね。
そして、どうも加藤家では、中屋敷も手放したくなかったらしいのです。
翌11月、改めて中屋敷の払い下げを願っています。
同年同月八日願書差出ス
元私邸地御払下ケ願
前月私邸振替ノ儀奉願候所御聞済被下置難有仕合奉存候就テハ又候私邸三千七百七十八坪余ノ地所別紙図面ノ通別段御用ノ筋無之候得者開拓ノ上地味相応ノ物品植付申度候間相当ノ価ヲ以御払下ケ被下度此段奉願候 以上
十一月八日 位 氏 名
東京府御中 図面此ニ略ス
別紙地所払下ケ願ハ当時見合申尤場所姓名懸ニ留メ置書面差戻申候追テ一定ノ規則相立候上可及沙汰候此段申入候也
十一月十四日 東京府
「先月(10月)、私邸振替を願い出ましたところ、お聞き届けくださり、有難い幸せと存じます。つきましてはまた、私邸3778坪余の地所(中屋敷)について、別紙の図面の通り、別に官でご利用の予定がなければ、開拓して地味にふさわしいものを植えつけたいと思いますので、相当の価格でもって払い下げられますことを、このたびお願いいたします」
これに対する東京府の回答は、拒否でした。
別紙の地所払い下げについての願出は、今のところ見合わせ、当該の場所と(請願者の)姓名は、東京府の担当係(宅地係)に記録した上で、願書は差し戻す。追って(収公した土地についての)一定の規則が定まった上で、沙汰することを申し入れる」
どうもこれは危ないと、加藤家では思ったみたいです。
おそらく、なんですが、中屋敷のブロックの右隣、秋田藩佐竹氏の大きな上屋敷は、明治8年の地図では「陸軍造兵司御用地」になっていまして、一帯を陸軍省が狙っている、という情報をつかんでいたんじゃないでしょうか。
誰から情報が入ったかって……、武田斐三郎からです。
一ヶ月あまりの後、明治4年のうちに、加藤家は対策を講じています。
竹門もと私邸昨冬御払下ケ願書差出ノ所当年ニテハ願意御採用難相成趣ニ付武田成章ヘ示談ノ上同人ヨリ願書差出ス但入用ノ節ハ引受候筈
下谷和泉橋通名元私邸先般邸相成候由ニ付御用無之候得者私へ御払下ケ被成下度則図面相添此段奉願候、已上
十二月廿三日 武田陸軍中佐
東京府 邸宅懸御中
願之家作金百八十五両二部二朱永五十五文八歩ニテ払下ケ候条当二月ヨリ十六ヶ月ニ割合可被致上納右地所ハ更ニ拝借相済候事但上納方相滞候節ハ仮令自費修繕相成候共地所家作其儘取揚可申事
明治五年壬申正月
竹門の元私邸(中屋敷)について、昨冬に払い下げ願いを提出したところ、当年は願いは採用されないとの趣旨だったので、武田成章(斐三郎)へ示談の上、武田から願書を提出した。もっとも経費についてはこちらで引き受ける予定である。
下谷和泉橋通名の元私邸(中屋敷)について、先般収公されたそうですが、官でご利用の予定がなければ、私へ払い下げてくださるよう、図面を添えてお願いします。 12月23日 武田陸軍中佐
東京府 邸宅懸御中
中屋敷の家作、つまり借家人は、武田斐三郎だったんです。
以前に書きましたが、大洲藩の上屋敷と中屋敷は隣にありながら、実は町名がちがい、明治8年の住所で、上屋敷は徒町、中屋敷は竹町です。明治以前の切り絵図でも、徒町は徒町なのですが、竹町は竹門になっています。佐竹藩邸の西門の扉が竹でできていたため、中屋敷のあるブロックと佐竹邸一帯は、竹門と呼ばれていたそうです。
つまり、中屋敷は下谷和泉橋通を冠して呼ばれるゆえんはないのですが、振替と払い下げを有利に運ぼうとしたためでしょうか、中屋敷が上屋敷の付録であるかのように、東京府への願書では、上屋敷と同じく下谷和泉橋通の名を被せていたのではないでしょうか。加藤家の内部文書で、初めて「竹門」をだしてきてくれてまして、おかげで、これが中屋敷であることがはっきりします。
陸軍中佐になっていました借家人の武田斐三郎に願書を出させて、費用を加藤家が出すことで、実質的に中屋敷も手元に残そうとしたんですね。
この企ては、うまくいきました。以下、東京都の回答部分です。
払い下げを願い出た家作が、金185両2歩2朱・永55文8歩で払い下げとなったことについて、この2月から16ヶ月の月賦にして上納させることで、右地所は再び拝借済みとする。ただし、上納が滞ったときには、たとえ自費で修繕をしていたとしても、地所および家作はそのまま取り上げる。明治五年壬申正月
広瀬一家は、この明治4年、おそらくは廃藩置県の前後に、静岡を引き払って、江戸へ帰ったのではないでしょうか。
冨五郎は、旧知の武田斐三郎を頼り、斐三郎は陸軍省に勤めて、中屋敷を借りて住んでいたようですから、当初は、中屋敷の長屋に住まわせてもらったのでしょう。
そして、この大名屋敷収公に出くわし、斐三郎を通じて、加藤家に知恵を貸したのではないかと思われます。
斐三郎が中屋敷すべてを使うことはなかったでしょうし、多数あっただろう長屋は、そのまま借家にもなったでしょう。
実は広瀬冨五郎は、娘の常が森有礼と結婚した後、森家の土地の売り買いに、かかわっているんです。
森有礼夫人・広瀬常の謎 後編上に書いていますが、有礼は特命全権公使として清国にいる間に、木挽町の屋敷を引き払い、新しく外務省から払い下げを受けて、麹町区永田町1丁目14蕃地の大邸宅に引っ越す手配をしているのですが、この土地の取得、不用地の売却を、広瀬冨五郎がしているようなのです。
明治10年の有礼の家族宛書簡には、「永田町も広瀬様御配慮にて追々片付候趣」(1月24日付)とか、「永田町東方二三千坪賈払之儀広瀬氏へ頼入候」(2月15日付)とかの文言が見えて、冨五郎が不動産の扱いに長けていたことを、裏付けてくれます。
当初、斐三郎の居候であった広瀬一家は、冨五郎が加藤家の財産管理にかかわったことで、明治5年当時、加藤家の私邸となった上屋敷の門長屋に無料で住まわせてもらえることになったのではないか、というのが、私の推測です。
このシリーズ、続きます。
人気blogランキングへ