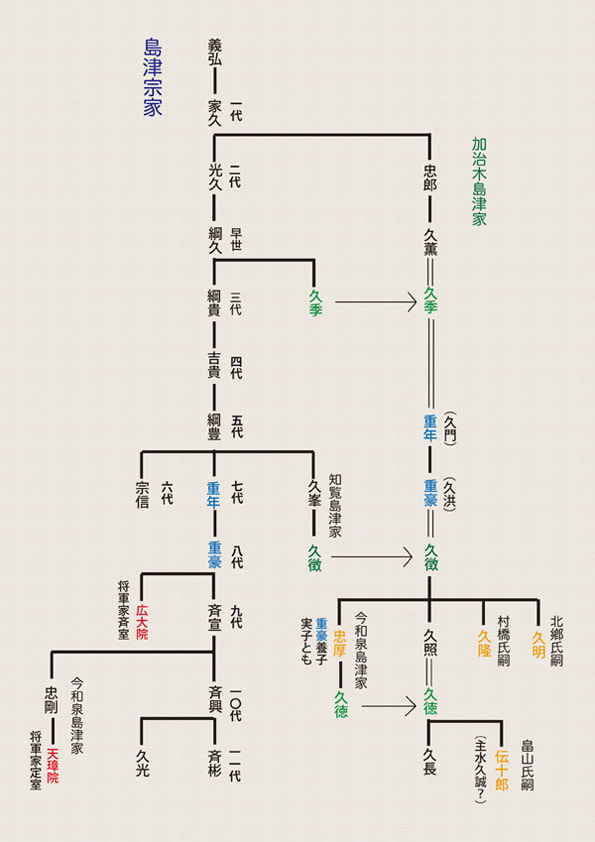春の嵐が過ぎ去りまして、桜と菜の花が、美しく輝く今日このごろ。
高杉晋作の従弟・南貞助のドキドキ国際派人生 中の続きです。
明治維新のとき貞ちゃんは二十歳。
まだまだ若いですし、再びイギリスへ!という夢を抱いていたらしいのですが、明治4年(1871年)、東伏見宮(小松宮)の英国留学に随従する、という機会がめぐってきます。
今回もまた、主な参考書は小山騰氏の下の著作です。
 | 国際結婚第一号―明治人たちの雑婚事始 (講談社選書メチエ) |
| 小山 騰 | |
| 講談社 |
貞ちゃんの今回の目標は、法学修行です。
あのオリファントと、そして今度はハリー・パークスの尽力もあり、ロンドンの法律学校リンカーンズ・インに入学がかないました。
ところが、ですね。
このとき貞ちゃんは、アメリカまわりでイギリスへ行っているのですが、小山氏は、すでにイギリスに着きます前に貞ちゃんは、チャールズ・ボウルズなる詐欺師まがいのアメリカの金融業者と、船中ででも知り合っていたのではないか、と推測なさっています。
ともかく、貞ちゃんの自叙伝によりますと、リンカーンズ・インで法律を学ぶうち、「イギリスの法律は、商習慣に関係するものが多いので、実地見習いが必要だと教師にいわれ、チャールズ・ボウルズに相談したところ、最近設立したうちの子会社ナショナル・エージェンシーはさまざまな商業に関係しているから株主になって勉強すればいい、といわれた」ということでして、ナショナル・エージェンシーなる子会社は、岩倉使節団がヨーロッパに渡るのにあわせるかのように設立されていまして、勘ぐりますと、最初から日本人詐欺をもくろみまして、貞ちゃんを株主に誘ったのではないか、という疑いももたれるんです。
チャールズ・ボウルズは、兄弟たちとともに、ニューヨーク、ボストン、ロンドン、パリ、ニースなど、各地に店を持つボウルズ兄弟社銀行を運営する、金融業者でした。
当時としましては、非常に新しい形の総合経営をしていまして、アメリカ人旅行者に、物品の購入や送付などを代行したり、旅行代理店のようなサービスを行い、それに金融をからめていましたから、けっこう繁盛してはいたらしいんですね。
ただ、経営がずさんでして、資金繰りは苦しく、顧客からの預かりものを勝手に抵当に入れ、他の銀行から金を借りるなどの不法行為を行ったりもしていました。
明治5年(1872年)、貞ちゃんはチャールズ・ボウルズに誘われまして、ナショナル・エージェンシーの株主になり、同時に取締役になります。当時、やはりロンドンに留学していました尾崎三良の自叙略伝には、次のようにあるそうです。
南は取締役として月給二百ポンド、すなわち我今の二千円を受け、倫敦(ロンドン)に宏壮なる家屋を借り、英人を妻となし随分贅沢の活計を為し、たまたま日本の書生などが訪問すると客室へ招じ葡萄酒などを饗し、妻諸共出で来り挨拶を為し(後略)
貞ちゃんの英人の妻とは、ロンドン近郊の庭師の娘、ライザ・ピットマンでした。
明治6年、貞ちゃんがライザを連れて帰国しましたとき、「まいにちひらがなしんんぶんし」の記事は、「我国始つてよりこのかた、珍しき縁組なり」と述べ、ライザが貞ちゃんと結婚した理由について、「ライザが南を大金持ちと誤解したから」という噂を伝えているのだとか。
まあ、ライザは、初等科の教師が務まる程度の教育は受けていたようなのですが、ロンドン近郊の庶民の娘さんが、極東の小さな島国がどんな国やら知るわけないですし、東洋の大金持ちの御曹司だと誤解したといいますのは、ありえる話ではないんでしょうか。
後年の自叙伝によれば、なんですが、貞ちゃんの方も「自分は人種改良論者だったので、日英の混血の子供が欲しかったのだ」なんぞとのたまっていまして、一応、日本人の国際結婚第一号とされるのですが、まったくもって、ロマンティックではありません。
ナショナル・エージェンシーは貞ちゃんに、豪邸で大金持ちのように暮らせるほどの給料をなぜ払っていたのか、あっという間に種は明かされます。
先にも書きましたが、ナショナル・エージェンシーは、岩倉使節団の便宜をはかり、一行の日本人から金をまきあげるために、設立されたような会社です。実際に貞ちゃんは、岩倉使節団がイギリスの造船所や兵器工場を訪問する手続きに奔走しておりまして、同時に、ナショナル・エージェンシーへ預金するよう、日本人を勧誘してまわっているのです。
ナショナル・エージェンシーは、親会社ボウルズ兄弟社のロンドン支店に同居していまして、その支店がまた、トラファルガー広場のすぐそば、チャーリング・クロス駅の真ん前の角地に、堂々と建っていたのだそうです。
現在も、Google地図チャーリング・クロス駅前でストリートビューをしますと、真正面に丸っこい建物があるんですが、これ、もしかして、当時のままなんでしょうか。ちがっていたにしましても、当時もロンドンの一等地ですし、りっぱな建物だったんでしょうし、騙されてしまいますよねえ。
なにしろ、岩倉使節団は動く日本政府のようなものでしたから、多額の公金をうずんでいましたし、随行員の手当の額も破格で、それを私金として溜め込んでいる人間も多数いました。
貞ちゃんはまず、私金を預けるように誘い、ついで公金にも勧誘の手をのばしていました。
英語がぺらぺらで、今をときめく長州閥の御曹司が取締役を務める銀行が、いろいろと便宜もはかってくれるわけですし、安全な上に利子がつくという話なのですから、預かってもらった者は多く、金額も膨らみました。
ところが、まだ使節団がイギリス滞在中の明治5年11月、突然、ロンドンのボウルズ兄弟社とその子会社のナショナル・エージェンシーはともに閉鎖され、預けたお金が引き出せなくなってしまうんです。
ナショナル・エージェンシーは、日本人から集めた金をすべて親会社ボウルズ兄弟社に貸していまして、ボウルズ兄弟社の資金繰りが悪化しましたために、ほとんどの幹部がアメリカに引き揚げてしまい、貞ちゃんの知らないところで、閉鎖、倒産という事態になってしまったんです。
なにしろ岩倉本人からして、1127ポンドという多額の金を預けていましたし、副使の大久保利通、木戸孝允、山口尚芳、みんな私費を預けていたらしく、パニックです。
しかし、使節団の公金は、会計主務の青山伯(田中光顕)が、文久遣欧使節団参加経験者の福地源一郎の忠告を入れ、貞ちゃんの勧誘を拒絶しましたことが、林董の回顧録「後は昔の記」(近デジにあります)に見えます。
 | 後は昔の記 他―林董回顧録 (東洋文庫 (173)) |
| 林 董,由井 正臣 | |
| 平凡社 |
公金を預けることを拒んだといいますと、もう一人、やはり文久遣欧使節団に参加していました人で、寺島宗則がいます。
寺島は薩摩藩の密航使節&留学生の一員でもありましたが、慶応2年3月28日(1866年5月12日)に帰国しておりますので、貞ちゃんが幕末に一千両使ってイギリスにたどり着きましたときには、もういませんでした。
そして寺島は、先に述べましたように、外務大輔としてガルトネル開墾条約事件の後始末にかかわっているわけでして、私、思いますにこのとき、「相当なうっかり屋だな、こいつ。信用ならん」と、鋭くにらんでいたにちがいありません。
しかし、その寺島の外務省薩摩閥の後輩に、公金をもっていかれてしまいました超うっかり屋が、いました。
2677ポンドを失った鮫ちゃん、鮫島尚信です。この事件の最大の日本人被害者でした。
寺島も鮫ちゃんも、岩倉使節団のメンバー、というわけでは、ありませんで、広瀬常と森有礼 美女ありき5で、以下のように書いた通りです。
鮫ちゃんと有礼は、日本が海外へ送り出す最初の日本人駐在外交官となりました。鮫ちゃんは普仏戦争最中の欧州へ、有礼はアメリカへ、20代半ばという若さで、日本を代表する少弁務使(代理公使)としての赴任です。鮫ちゃんは、イギリスでは拒否され、フランスに落ち着きます。何度か書きましたが、イギリスの外交官は官僚ではなく、貴族かジェントリーの子弟が自腹をきって奉仕するものでして、まあ世界の一等国イギリスとしましては、公使をよこすなら、せめて大名の一門とか、名門で、なおかつ経験豊かな年輩の者をよこせ、ということなんですね。
しかし、手探りで外交デビューする日本側にしてみましたら、条約改正問題もありますし、日本のお殿様は通常、「よきにはからえ」で大人しく祭られていることをよしとしていて、イギリスの貴族のように英才教育を受けてリーダーシップがとれるようには育てられていませんし、海外事情もなにもさっぱりわからないでは、手探りのしようさえないわけなのです。それでイギリスには結局、名門の条件は満たしていませんが、幕末からの外交経験を買われて、寺島宗則が赴任することになります。
鮫ちゃんのフランス赴任につきましては、普仏戦争と前田正名シリーズで、もう一度ちゃんと書くつもりでおりますが、ともかく、鮫ちゃんは駐仏公使館を開設する費用など、公金を貞ちゃんの会社に預けていたんです。
これってやっぱり、ハリスつながりの濃い絆なんじゃなかったんでしょうか。
明治元年の京都で、貞ちゃんはフェアリーのようにやさしく、ハリスの祝福を受けて帰国しました鮫ちゃんと有礼を迎えてくれたのでしょう。
薩摩と欧米しか知りませんで、突然、様変わりの京都へ迷いこみました鮫ちゃんにとりまして、魂の伴侶であります有礼をのぞけば、まわりにいる人間、みんなが宇宙人のようだった中、ただ一人貞ちゃんは、心を許せる友だったりしたかもしれません。いや、客観的に見ますならば、鮫ちゃん、貞ちゃん、有礼のハリス教団三人組の方が、宇宙人だったんですけれども。
そして鮫ちゃんは、気が大きくて素っ頓狂な貞ちゃんの人柄をこよなく愛し、信頼していたにちがいないのです。
公金としましては他に、尾崎三良が預かっていましたイギリス公費留学生たちの費用、2198ポンドも消えてなくなりました。この尾崎三良というお方も、イギリス人女性と結婚しておりますが、これがまたいいかげんなものでして、私、まだろくに調べてはいないのですけれども、相当な素っ頓狂仲間のようではあります。あんまりかわいげがなさげで、調べる気にならないのですけれども。
結局のところ、このボウルズ銀行倒産騒ぎの解決には22年という長い時間がかかりまして、被害額の四分の一を返してもらえることになりましたが、そのときには、日本人被害者にも、死んでしまった者があり、鮫ちゃんもその一人でした。
まあ、あれです。
貞ちゃんも、被害者ではあったわけですけれども、こう、ですね。突然株主にしてやるだとか、富豪のような多額の給料をくれるだとか、なんかおかしいなと立ち止まるような性格では……、なかったんですね。
しかし、まあ、これも当然のことなのですが、貞ちゃんをかばいましたのは、長州閥の頭領・木戸孝允のみでして、明治6年(1873年)春、貞ちゃんは、妻のライザとともに、ひっそりと帰国します。
えー、いくら貞ちゃんが、まったくもって悪気があったわけではなかったといいましても、欧州日本人使節団が被りました巨額金銭詐欺被害は、貞ちゃんのせいであるにはちがいないのですが、帰国後の活動を見ますかぎり、高杉晋作の従弟にして義弟、といいます、今をときめく長州閥の御曹司ブランドは強かった、と思わざるをえません。
帰国して間もなく、貞ちゃんは、内外用達会社を立ち上げ、やがてこの会社を、一応ちゃんとした形式の株式会社にします。
業務内容は、日本と海外との仲介で、書簡や電信の翻訳、訴訟や商売のための通訳、海外への荷物の送付・受け取り、外国為替の取り扱い、海外取り引きの代理、などなどでした。
株主には、渋沢栄一もいたようですし、民間の海外取り引きが少なかった当時、官の引き立てなくして、この事業はできなかったでしょう。
しかし、それでも事業は失敗し、貞ちゃんは、明治14年には会社を投げ出し、官界に復帰します。
木戸はすでに世を去っていましたが、伊藤もいれば、井上もいましたし、なにしろ、高杉晋作の従弟にして義弟ですし、素っ頓狂ではありましたけれども、語学力はたいしたものですし、社交的で、物怖じしない人柄です。物怖じしなさすぎで、困ったものなんですけれども。
どうも、ですね。
官界に帰りました翌年、明治15年あたりから、貞ちゃんとイギリス人妻ライザとの仲は、極端に悪化したようです。
貞ちゃんは、ライザをイギリスに放っておいたりはしませんで、ちゃんと日本に連れ帰りました。
行き当たりばったりの貞ちゃんだったからこそ、ともいえますが、見方をかえますと、実のところは、とても愛していたのかもしれませんし、そして、内外用達会社の設立は、なんとかイギリスにいたときと同じように、不自由のない生活をライザにさせてやりたかったがゆえの貞ちゃんの奮闘であった、と見ることも可能でしょう。
しかし、おそらく、貞ちゃんにとっての最大の不満は、子供が生まれなかったことだったでしょう。
そこへもってきまして、貞ちゃんが官界に復帰しまして最初の仕事は、明治9年に日本領となりました小笠原諸島に出向き、欧米系島民を帰化させること、でした。
あるいは、貞ちゃんは事業の失敗で多額の負債をかかえ、離島、小笠原への赴任を引き受けたのかもしれませんし、ライザが小笠原諸島へ行ったとは思えません。貞ちゃんの実家・南家や、あるいは高杉家の人々といっしょに暮らすことになったりしたのではなかったでしょうか。
明治16年、二人は離婚し、ライザはイギリスへ帰りますが、その離婚理由といいますのがなんと!、妻ライザの暴力です。
貞ちゃんは、井上聞多宛の書簡で、妻の暴力について、以下のように述べているそうです。
「その残酷なるは、拙官の愛する実父および実伯父母兄弟などに対し、残酷無礼を行い、ともにその残酷を受けること数度なり。よって実父は同居を去り、他家において死し、その他拙官の面部および手足を負傷せしめたること数度なり。明治15年2月に至りては、日本刀をもって切りかかり、酷してこれを脱し、実伯父の家にいたり、衣類などの扶助を乞ひ、あるいは官吏の家に潜伏すること数日、すでに告発し法律に訴えんとせしも、英国人親友の仲裁によって、別紙乙号約定書をもって誓いをなすにつき、こんどかぎり勘弁を加え候ところ、その後一月も過ぎず三月中、重ねてほとんど同様の挙動これあり候。故離縁の義申渡し候ところ、英国へ送り帰しくれ候様申出候故、同年四月上旬横浜出帆為致候」
「ライザは、ぼくの愛する父や伯父(晋作さんの父親です。おそらく)、母や兄弟などに対して、残虐無礼で、家族といっしょにぼくも暴力を受けたことが数回あって、父は家を出て、よその家で死んでしまったんだよ。ぼくの顔や手足に傷を負わせることもたび重なり、ついに明治15年2月、日本刀で斬りかかってきたので、必死になって逃げて、伯父さんの家に駆け込み、衣類なども都合してもらって、部下の家に隠れて数日、法に訴えようとしたのだけれど、イギリス人の親友が仲裁に入ってくれて、二度と暴力はふるいませんというライザの誓約書をとったところが、一ヵ月もたたないうちに、ほとんど同じようなことをやらかしたので、離縁すると宣言したら、ライザはイギリスへ帰してくれ、と言うので、四月上旬に横浜から出航させたんだよ」
えー、小山騰氏がおっしゃることには、この手紙を書きましたとき、貞ちゃんは一年勘違いしていまして、明治15年ではなく、これは翌16年のことなんだそうです。
それにいたしましても………。
異国で、おそらくは貞ちゃんの会社がつぶれまして以来、生活が激変し、ライザの鬱屈は募ったのでしょうけれども、晋作さんの従弟が妻に虐待されて離婚って、なんだか呆然としますよね。
その後貞ちゃんは、日本女性と再婚して子供も生まれ、明治24年には、官界での自分の処遇が不満で受け入れなかったものですから、首になりました。
その年に、貞ちゃんのアイデアで、渋沢栄一などが資金を出し、蜂須賀茂韶を会長に担いで、「外国から日本へ観光客を呼ぼう!」ということを目的にしました「貴賓会」が立ち上がります。
蜂須賀茂韶は元阿波藩主ですが、戊辰戦争の最中に先代が急死して藩主となり、明治5年にイギリス留学しまして、貞ちゃんとライザの結婚の立会人を務めた人です。
貞ちゃんが名誉書記になりましたのは、三年後のことだそうですが、実務は最初から貞ちゃんが担当していたようです。
数年後、明治35年、貞ちゃんは55歳にして名誉書記を辞しまして、翌年、海外から日本へ来た旅行者、日本から海外へ行く旅行者にサービスを提供する旅行代理会社を立ち上げます。
なんと、ですね。その資金作りには、15歳の自分の娘を尾崎三良のもとへ頼みに行かせるなど、家族ぐるみ作戦を展開し、ついにこの生涯最後の事業に、貞ちゃんは成功したようです。
大正元年、貞ちゃんは長男に事業をゆずって引退し、書道と和歌をたしなんで、大正4年、68歳で世を去りました。
なんといえば、いいのでしょうか。
長州高杉晋作ブランドで若くして密航留学し、語学もできて、数学もできて、それなりの才はあったはずですのに、素っ頓狂で、失敗続きの人生でしたけれども、いつもまわりに助けられまして、結局はやりたいことをやり、最後にはそれなりに成功して、子孫に後を託し、畳の上で往生。
とても幸せな人生だったんじゃないんでしょうか。
しかし、ね。西からの光はやはり、美しくも身を焼く業火であったのだと思います。
要は使い方で、見方によれば貞ちゃんは、しゃにむにがんばって命を縮めたりもしませんで、うまく綱渡りのバランスをとって、渡りきったのだとも、いえると思うのですけれども。
自分の身代わりに貞ちゃんを西洋へ送り出し、西洋近代文明と激突した日本の変革のために、炎のように燃えつきました晋作さんの人生。
貞ちゃんとともに密航して間もなく、おそらくは貞ちゃんに自分のぶんまでの望みもたくし、はかなく異国の土となりました山崎小三郎。
貞ちゃんを愛し、ともに騙され、最初の日本人海外駐在外交官としましての奮闘のあげくに、体を壊してパリに客死しました鮫ちゃん。
最後はやはり、これでしめたいと思います。
ザ・バンド with ボブ・ディラン アイ・シャル・ビー・リリースト
They say ev'rything can be replaced
Yet ev'ry distance is not near
So I remember ev'ry face
Of ev'ry man who put me here
I see my light come shining from the west unto the east.
Any day now, any day now, I shall be released.
すべての物事は、やがて変わっていくだろう。
しかしそれは、容易なことじゃないんだ。
そしておれは、去っていったみんなの顔を思い出す。
おれがいまここにいるのは、先に逝ったみんなのおかげなのだから。
西から東へ、届く光がきらきらとおれを照らす。
いつの日か、いや今すぐにでも、おれは自由になれるだろう。
舞い散る桜の花びらを見つめていますと、先に逝った人々も、そして後に残った貞ちゃんも、みんなみんな、その営みが、とても愛おしく脳裏によみがえってまいります。
私、次は……、次こそは、普仏戦争と前田正名に立ち返ります。
クリックのほどを! お願い申し上げます。