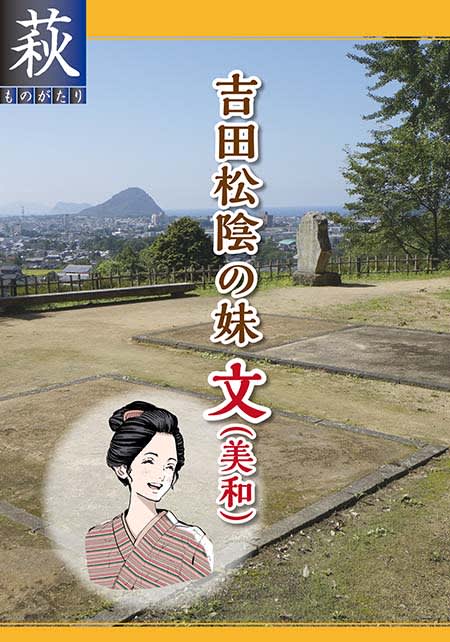珍大河『花燃ゆ33』と史実◆高杉晋作挙兵と明暗の続きです。
 | 花燃ゆ メインテーマ |
| クリエーター情報なし | |
| VAP |
本題に入ります前に、私のこのブログ、簡単なアクセス解析がついています。どのページにどの程度のアクセスがあったかはわかるのですが、どういう経過でアクセスされたのかは、結局、よくわからない解析です。
で、ここのところ、少しづつなのですが、薩摩スチューデント、路傍に死すへのアクセスがありましたのを不思議に思い、「村橋久成 テレビ」で検索をかけてみましたところ、北海道新聞の「村橋久成、大河ドラマに 撮影誘致へ会設立 札幌に開拓使麦酒醸造所」という記事が出てきました。
うちのコメント欄にもこられました『残響』の著者・田中和夫氏が中心になられて、誘致運動が行われるみたいです。

実は去年、中村さまにおつきあい願い、鹿児島県いちき串木野市羽島の「薩摩藩英国留学生記念館」のオープンセレモニーに出かけました。
関連の催しで、神田紅さんの講談があったのですが、やはり、村橋久成を題材に選んでおられました。劇的な生涯、ですものね。
 | 薩摩藩英国留学生 (1974年) (中公新書) |
| 犬塚 孝明 | |
| 中央公論社 |
昔、乙女のころ、犬塚孝明氏の「薩摩藩英国留学生」を読みまして、もっとも心引かれましたのが、村橋久成と英国へ渡った土佐郷士の流離で書きました高見弥一(大石団蔵)でした。
しかし、ですね。村橋久成一人では弱い気がしまして、薩摩スチューデントと開拓史がらみの集団劇ならけっこうおもしろいし、美形オンパレードなんだけどなあ、と思ったんですが、あえて誰かを主人公にするなら、村橋と森有礼と、対照的な二人中心でやればどんなでしょう。
森有礼につきましては、広瀬常と森有礼 美女ありき5が一番略歴がわかりやすいんですが、日本初の女学校、開拓史女学校へ通っていた広瀬常と結婚し、これが鹿鳴館スキャンダルにつながりますし、有礼の留学仲間で魂の伴侶、鮫島尚信は、東京大学教養学部附属博物館所蔵の肖像画でみますと、ものすごい美形ですわよ。
高杉晋作の従弟・南貞助のドキドキ国際派人生 下で見ていただけたら、と思うのですが鮫ちゃんは、高杉晋作の従弟で、素っ頓狂な貞ちゃんとも無二の親友っぽいですし、美形同士で絵になります。
江戸は極楽であるに書いております、有礼と吉田清成の国際的大喧嘩も、二人とも若くていい男ですから、これまた絵になります。
モンブラン伯爵とグラバーの大喧嘩も出して、町田兄弟から岩下、新納少年、そしてもちろん五代友厚を出す必要がありますが、いくら来期の朝ドラが五代がらみとはいえ、朝ドラとはまったくちがって、善悪相半ばする桁外れな発想力の持ち主として、描けると思うんですね。パリ万博が出てきて、外交をやっていた岩下方平が帰国した途端に京都で王政復古。高見弥一を出しますと、龍馬と中岡慎太郎も出してこれますし、村橋にからめて、箱館戦争で幕府海軍と新撰組も登場。薩長土、幕府、全部ひっくるめて、幕末維新が描けますわよ。
これね、薩摩・長崎(小菅修船場は薩摩が造ったものです)の明治近代産業遺産にも関係しますし、ぜひ、ボクサーパトロンや薩摩バンドの話も出していただければ、と。
シナリオはジェームス三木あたりかな。
去年の薩摩藩英国留学生記念館オープンの関連催しで、薩摩近代産業遺産の世界遺産登録についての報告もあったのですが、舞台に立たれたどなただったかが、「この前の会議では、安倍さんがまるで幕末の近代化は長州が中心、みたいな話をされた」と、ご不満をもらしておられました(笑) どう考えても、近代化産業では薩摩・佐賀の方が上なのですが、いかんせん、現在の政治力は、長州の方がはるかに上ですわねえ。まあ、明治からそうなんですが。
北海道もあまり政治力はなさそうですが、ぜひ、鹿児島と組んで、運動すべきだと思います。
さて、本題ですが。
またまた、脚本が金子ありさ氏です。
とっぱなから、興丸のお小姓を決めねば、とか、奥とはそれほど関係のなさそうな話を奥でしてしていまして、あげくの果てに銀姫さまいわく、「征長軍が再びさしむけられるであろう。裏にはあの薩摩がー」です。
どや顔美和さんに関しましては、すべて出来の悪い嘘話なのでどーでもいいのですが、馬鹿が、なにを考えているんだか。 なんの得にもならず、金がかかるばかりの征長を、なんで薩摩がやりたがったことにしてしまっているんだろ。これまでの西郷の描き方が妙ちきりんなので仕方ないけど、それにしても調子外れだわさと、そっぽを向きたい気分満点。
どこまでが金子ありさ氏の責任かは、判然としませんが、公卿の描き方のひどさも絶好調。
どや顔小田村が、大宰府の五卿の元を訪れた、までは史実ですが、「幕府と戦う? (長州)たった一藩で? 正気の沙汰とは思えん」なんぞと、三条侯がそんな暢気なこと、言うわけがないでしょうが、糞馬鹿!!!です。
史実としまして、小田村は藩命を受けて、五卿に長州藩の時事を知らせるために大宰府入りし、坂本龍馬に会いましたのは、慶応元年(1865年)5月24日のことです。
すでにこの三ヶ月以上前、2月に、ですね。三条側近の土佐脱藩士・土方久元と中岡慎太郎は、薩摩藩士の吉井幸輔と共に上京するつもりで、船待ちの間、下関の白石正一郎宅で、報国隊(乃木希典が属していた長府藩の有志隊)隊長や白石正一郎の実弟・大庭伝七、赤禰武人とともに、薩長和解を謀り懇談(土方久元「回天実記」より)していまして、あきらかに土方、中岡は、ともに三条の意を受けて、上京の後も薩長和解に動いているんですね。
薩摩に身をよせていました龍馬は、京で土方と会い、鹿児島へ入った後、三条に会いに来ているんです。
ところが、ですね。このキチガイドラマのくたびれ果てた龍馬は、小田村に向かって、「どうやったかの? お公家さんらは? この国の大事を語る相手としてはちっくとものたらんろ」なんぞと、「そこまで三条を馬鹿にしてるんなら、あんた、なんのために大宰府にいるのさ!」と怒鳴りつけてやりたくなるようなことを、平気でぬかすんですのよ。
そして、さらに龍馬は続けます。
「昔会うたとき、久坂さんは言いよった。幕府も公家も大名も顧みるに価せん。草莽の志士がこの国を変える。草莽崛起じゃと。それを聞いて胸が熱うなって、わしは脱藩ー(以下略)」
だ・か・ら、いまさらそんなことを言うなら、ちゃんと久坂が草莽崛起を語り、龍馬が胸を熱くする場面を描いとけよっ!!!!!と、もう、私、あきれ果てました。
唖然呆然長州ありえへん珍大河『花燃ゆ』で書きましたが、第18回「龍馬!登場」で、肝心要のこの久坂の見せ場をまったく描かないで終わらせたのは、金子ありさ氏です。いまさら、くたびれ龍馬になんと語らせたところで、このキチガイドラマの久坂のイメージは、ぼーっとしたでくの棒のまま、ですわ。
今回、私、久坂について、少し語りたいと思います。
 | 高杉晋作と奇兵隊 (幕末維新の個性 7) |
| 青山 忠正 | |
| 吉川弘文館 |
青山忠正氏の「高杉晋作と奇兵隊 」に、村塾生だった渡辺蒿蔵(天野清三郎)の次のような回想が載っています。
「久坂と高杉の差は、久坂には誰もついてゆきたいが、高杉にはどうもならんとみな言うほどに、高杉の乱暴なりやすきには人望少なく、久坂の方人望多し」
にもかかわらず、ですね。 昨今、高杉晋作はトリックスターとしてもてはやされます一方、久坂が悪く言われるのはなぜか、といえば、モンブラン伯と「海軍」をめぐる欧州の暗闘vol3で書いております加徳丸事件が大きいでしょう。
これ、一坂太郎氏が「長州奇兵隊」で書かれて、一般に知られるようになったのですが、一坂氏も文中で述べておられますように、もとはといえば、井上勝生氏の「幕末維新政治史の研究―日本近代国家の生成について」に書かれていることなのですね。
 | 長州奇兵隊―勝者のなかの敗者たち (中公新書) |
| 一坂 太郎 | |
| 中央公論新社 |
 | 幕末維新政治史の研究―日本近代国家の生成について |
| 井上 勝生 | |
| 塙書房 |
一坂氏は、基本的には、中原邦平の「忠正公勤王事蹟」
私、あらためて、できるだけ原本にあたりつつ、検討してみたのですが、この事件処理にまつわる悲劇の責任を久坂におわせるのは、はっきり言いまして無茶苦茶でしょう。
まず、ですね。加徳丸事件の先例として、長崎丸事件があるんですが、この二つの事件は、似ているようでいて、まったくちがっています。
長崎丸は、薩英戦争で蒸気船が足りなくなりました薩摩藩が、幕府の長崎製鉄所所属の老朽船を借り受け、自藩士を乗せて藩の商用に使っていました。
文久3年12月、繰綿などの商品を積んで、長崎丸は兵庫から長崎に向かって航行していまして、下関において、砲撃を受けます。
砲撃したのは、長州奇兵隊ですが、薩摩船だと認識していたかどうかは、定かではありません。折からの濃霧で、長崎丸が掲げた明かりを目標に砲撃していた、というのですが、一寸先も見えない瀬戸内海の濃霧を経験したことがあります私としましては、薩摩藩の船印なんぞ確認しようもなかっただろう、としか思えません。
砲撃が命中した、というわけではなかったようなのですが、なにしろ老朽船ですし、砲撃を受けて回避行動をとるうち、蒸気機関が火を噴き、綿に燃え移ったんだそうなんです。乗り組んでいた68人のうち、28人が死亡しました。以前に書きましたが、その中には前田正名の実兄もいます。おそらく、蒸気機関が爆発したのではないんでしょうか。
死亡者のほとんどは薩摩藩士ですし、長州としましても、これはひたすら謝るしかない事件です。
一方、加徳丸の船主は、実は長州藩上関に近い、田布施別府の住人でした。つまり、長州の民間の船だったわけです。
長崎丸事件から一月後の元治元年一月、その民間船を、薩摩商人が雇い、大阪で買い集めた繰綿を長崎へ運ぶ途中、船の母港・田布施別府に停泊していましたところ、地元上関の攘夷有志隊・上関義勇軍の数名に襲われ、船は積み荷ごと焼き捨てられ、同乗していました薩摩商人・大谷仲之進は斬り殺されました。
つまり、積み荷の綿は薩摩商人のもので、綿でしたら結局取り引きに薩摩藩もかかわってはいたでしょうけれども、焼き捨てられました船は薩摩のものではありませんし、乗組員も薩摩人ではありません。
おそらく、薩摩藩の船印をかかげたりはしていなかった、と思われますのに、なぜ襲われたか、といえば、地元の船でしたから、上関義勇軍隊士が噂を聞きつけたわけなのでしょう。
これまでに幾度か書いてきたのですが、アメリカの南北戦争で、南部の綿花輸出が止まり、値段が高騰したんですね。
グラバー(ジャーデン・マセソン)を中心とした在日商人たちが綿花を求め、薩摩藩はそれに応えて、大阪で買い占めを行っていました。
薩摩商人の買い占めはすさまじいばかりで、材料が入らなくなりました日本の綿織業は、操業ができなくなり、怨嗟の声が上がります。
油などの買い占めも行われ、物価が急上昇し、それが海外交易のせいだということは、火を見るよりも明らかでしたから、それにたずさわる商人は憎まれることとなり、攘夷のために結成されました上関義勇隊では、襲うことが正義、という気分が盛り上がっちゃったんでしょうね。
なんと、上関義勇隊では、隊員二人に斬り落とした薩摩商人の首をもたせて、大阪まで行き、さらそうとします。
これは別に二人だけの判断ではなく、隊としての行動でしたから、後ろめたさはなにもなかったわけなのです。
ここで、久坂が出てきます。以下、野村靖の「追懐録」(マツノ書店復刻版)より、です。
「久坂など今回、永井など(船を焼き討ちした上関義勇隊員)の軍令を犯したることを聞きて、痛く規律の緩慢に流れたるあらんことを憂い、品川弥二郎および余(野村靖)をしてこれを処理せしむ」
つまり、久坂など、在京の長州藩政務役の命令で、野村靖たち(他に杉山松介、時山直八)は、隊の規律違反だとして、二人に自裁を迫ったんですね。二人にしてみましたら思いもよらないことで、逃げ出して、上関に帰りますが、野村と品川弥二郎はそれを追いかけ、山口の政庁に処分を計って、藩の決定により、大阪まで二人を連れ帰り、自刃させます。
その自刃が、薩摩商人の首をさらしたそばで行われましたことは、異常といえば異常なんですが、これって、長州が藩として、決定したことですわね。
長州人の船主にしてみましたら、船を焼かれるなど財産権の侵害ですし、船の乗組員も職を失ったわけですし、地元から苦情が上がっていた、と見るべきではないでしょうか。
なお、このとき、二人が自刃すべきだと決定を下した山口の政庁には、政務役として高杉晋作がいますし、久坂が政務役となっていましたのは、おそらくは高杉の引き立てですし、なんでこの事件の処理で、久坂ばかりが悪くいわれなければならないのか、私にはさっぱりわかりません。
次は、ちゃんと小倉口の戦いをやってくれるのでしょうかね。
クリックのほどを! お願い申し上げます。