また、ちょっと脱線します。
大河の「篤姫」なんですが、将軍家定が、実は馬鹿ではなかった!設定になったあたりから、堺雅人の好演も手伝って、「なかなか、やるじゃないの」と思って見ていましたが、夫が死んで、篤姫が未亡人になってからというもの、あるわけない………とあくびが出るほど、ホームドラマ部分がつまらなくなってしまい、そうするといやでも史実を描いた部分の方へ目がいってしまいまして、まあ、当然なんですが、これがまたあるわけない………の連続で、最初の印象、「まあ、小松帯刀の名が世に知れわたるだけでもいいんでないかい」という境地に、落ち着いてまいりました。
にしても前回は、実にひどかった、としか。小松帯刀、似合わなすぎ!です、総髪が。
つーか、事実としては病気のときの「さかやき剃らなくていいですか」願いをたてに、外国人に髷が珍しがられてうるさいから総髪って、馬鹿馬鹿しすぎ!です。帯刀は外国に行っているわけじゃないんですから。
アーネスト・サトウやミットフォードやグラバーやボードウィンなどが、髷を珍しがるわけがないでしょうがっ!!! 日本にいるんですから。
だいたい、総髪は王政復古の象徴なんです。その昔、武士が政権をとる以前、朝廷に実権があった古代には、さかやきなどなくって総髪だったのだからと、勤王の志士は総髪を好んだんです。みんなでお公家さんのまねをしようってことで、外国人は関係ありません。
まあ、文句をいえばきりがなく、例えばですね、家茂の実母・実成院が、酒好きで、賑やかなことの好きな人だった、という話を、本寿院におっかぶせていましたが、そもそも実成院を出していないのですから、仕方がないといえば仕方がないんですが、ますます本寿院が、あんまりにもありえない……状態。
しかし、そんなことよりもなによりも、家茂将軍が勝海舟に抱かれて死んだ!!!という呆然とするような作り話に、心底うんざりしたのは、やはり、昔これを読んで、思わず松本良順に感情移入し、まあ、なんとおいたわしい上さま……と、ほろっとした記憶が鮮明だったせいでしょう。
松本良順は、将軍家の奥医師で、蘭方医です。勝海舟が長崎でオランダ海軍伝習を受けていたと同時期に、やはり長崎で、オランダ海軍軍医だったポンペ・ファン・メーデルフォールトから、医学伝習を受けました。
実父は佐倉藩の蘭方医だった佐藤泰然で、日英同盟時のイギリス公使だった林董は、実の弟です。
林董は、幕末のイギリス留学生で、帰国後、榎本武揚の脱走艦隊に身を投じて、函館戦争に参加していますが、兄の松本良順は幕府の脱走陸軍の治療にあたり、会津入りしています。良順は、結局、土方歳三とともに会津を出て仙台まで行き、そこから横浜へ帰ります。
そもそもは、近藤勇が良順のもとを訪れて親交がはじまり、京都では良順が新撰組の屯所を訪れて土方にも会いましたし、良順は後年、この二人の顕彰に心を尽くしましたので、新撰組ファンには必読の自叙伝です。
しかし、この自叙伝でどこが最も感動的かというと、将軍家茂の最後を看取る場面です。
大阪城で病の床に伏した、21歳(満20)の若き将軍家茂は、無能な老中にかこまれ、次々に入る第二次征長の敗戦の報に心痛ひとかたならず、赤子が母親にすがるように良順をひきとめます。奥医師が、2時間ごとに交代でそばにつめることになっていたのですが、良順は三週間の間、ずっとつめきりで、その間、横になって眠ることはできませんから、朦朧としてきて、ついに「1,2時間の休息を賜え」と家茂に願います。しかし家茂は、良順がそばからいなくなることを怖れ、「ここに入っていっしょに眠れ」と、良順を自分の寝床に入れたんだそうです。
良順は、「恩命の重き、辞することあたわず」、将軍の寝床に入りましたが、もちろん、眠れるわけがありません。
「君上と同衾するの苦は、百日眠らざるよりくるしかりし」
それから2、3日のうちに、良順に看取られながら、家茂はこの世を去りました。
「これ順が終天無窮の恨事にして、公に尽くせし最後のことなり」
そして、松本良順は、こうも記しています。
「予は将軍家茂公に仕え、恩遇をこうむり、最も心を尽くしければ、そのことおのずから内殿に伝わり聞こえ、天璋院殿大いに予を信ぜられたり」
つまるところ、実成院の逸話を本寿院のことにしてしまうと同時に、松本良順の回顧録を妙なぐあいに脚色して、勝海舟のことにしてしまったわけなのですが。
なお、この場面は、司馬遼太郎氏が、実にみごとな脚色で、「胡蝶の夢〈第3巻〉」 (新潮文庫) において、描かれています。
において、描かれています。
クリックのほどを! お願い申し上げます。
 にほんブログ村
にほんブログ村
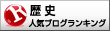 歴史 ブログランキングへ
歴史 ブログランキングへ
大河の「篤姫」なんですが、将軍家定が、実は馬鹿ではなかった!設定になったあたりから、堺雅人の好演も手伝って、「なかなか、やるじゃないの」と思って見ていましたが、夫が死んで、篤姫が未亡人になってからというもの、あるわけない………とあくびが出るほど、ホームドラマ部分がつまらなくなってしまい、そうするといやでも史実を描いた部分の方へ目がいってしまいまして、まあ、当然なんですが、これがまたあるわけない………の連続で、最初の印象、「まあ、小松帯刀の名が世に知れわたるだけでもいいんでないかい」という境地に、落ち着いてまいりました。
にしても前回は、実にひどかった、としか。小松帯刀、似合わなすぎ!です、総髪が。
つーか、事実としては病気のときの「さかやき剃らなくていいですか」願いをたてに、外国人に髷が珍しがられてうるさいから総髪って、馬鹿馬鹿しすぎ!です。帯刀は外国に行っているわけじゃないんですから。
アーネスト・サトウやミットフォードやグラバーやボードウィンなどが、髷を珍しがるわけがないでしょうがっ!!! 日本にいるんですから。
だいたい、総髪は王政復古の象徴なんです。その昔、武士が政権をとる以前、朝廷に実権があった古代には、さかやきなどなくって総髪だったのだからと、勤王の志士は総髪を好んだんです。みんなでお公家さんのまねをしようってことで、外国人は関係ありません。
まあ、文句をいえばきりがなく、例えばですね、家茂の実母・実成院が、酒好きで、賑やかなことの好きな人だった、という話を、本寿院におっかぶせていましたが、そもそも実成院を出していないのですから、仕方がないといえば仕方がないんですが、ますます本寿院が、あんまりにもありえない……状態。
しかし、そんなことよりもなによりも、家茂将軍が勝海舟に抱かれて死んだ!!!という呆然とするような作り話に、心底うんざりしたのは、やはり、昔これを読んで、思わず松本良順に感情移入し、まあ、なんとおいたわしい上さま……と、ほろっとした記憶が鮮明だったせいでしょう。
 | 松本順自伝・長与専斎自伝 (東洋文庫 386)松本 順,長与 専斎,小川 鼎三平凡社このアイテムの詳細を見る |
松本良順は、将軍家の奥医師で、蘭方医です。勝海舟が長崎でオランダ海軍伝習を受けていたと同時期に、やはり長崎で、オランダ海軍軍医だったポンペ・ファン・メーデルフォールトから、医学伝習を受けました。
実父は佐倉藩の蘭方医だった佐藤泰然で、日英同盟時のイギリス公使だった林董は、実の弟です。
林董は、幕末のイギリス留学生で、帰国後、榎本武揚の脱走艦隊に身を投じて、函館戦争に参加していますが、兄の松本良順は幕府の脱走陸軍の治療にあたり、会津入りしています。良順は、結局、土方歳三とともに会津を出て仙台まで行き、そこから横浜へ帰ります。
そもそもは、近藤勇が良順のもとを訪れて親交がはじまり、京都では良順が新撰組の屯所を訪れて土方にも会いましたし、良順は後年、この二人の顕彰に心を尽くしましたので、新撰組ファンには必読の自叙伝です。
しかし、この自叙伝でどこが最も感動的かというと、将軍家茂の最後を看取る場面です。
大阪城で病の床に伏した、21歳(満20)の若き将軍家茂は、無能な老中にかこまれ、次々に入る第二次征長の敗戦の報に心痛ひとかたならず、赤子が母親にすがるように良順をひきとめます。奥医師が、2時間ごとに交代でそばにつめることになっていたのですが、良順は三週間の間、ずっとつめきりで、その間、横になって眠ることはできませんから、朦朧としてきて、ついに「1,2時間の休息を賜え」と家茂に願います。しかし家茂は、良順がそばからいなくなることを怖れ、「ここに入っていっしょに眠れ」と、良順を自分の寝床に入れたんだそうです。
良順は、「恩命の重き、辞することあたわず」、将軍の寝床に入りましたが、もちろん、眠れるわけがありません。
「君上と同衾するの苦は、百日眠らざるよりくるしかりし」
それから2、3日のうちに、良順に看取られながら、家茂はこの世を去りました。
「これ順が終天無窮の恨事にして、公に尽くせし最後のことなり」
そして、松本良順は、こうも記しています。
「予は将軍家茂公に仕え、恩遇をこうむり、最も心を尽くしければ、そのことおのずから内殿に伝わり聞こえ、天璋院殿大いに予を信ぜられたり」
つまるところ、実成院の逸話を本寿院のことにしてしまうと同時に、松本良順の回顧録を妙なぐあいに脚色して、勝海舟のことにしてしまったわけなのですが。
なお、この場面は、司馬遼太郎氏が、実にみごとな脚色で、「胡蝶の夢〈第3巻〉」 (新潮文庫)
クリックのほどを! お願い申し上げます。



















