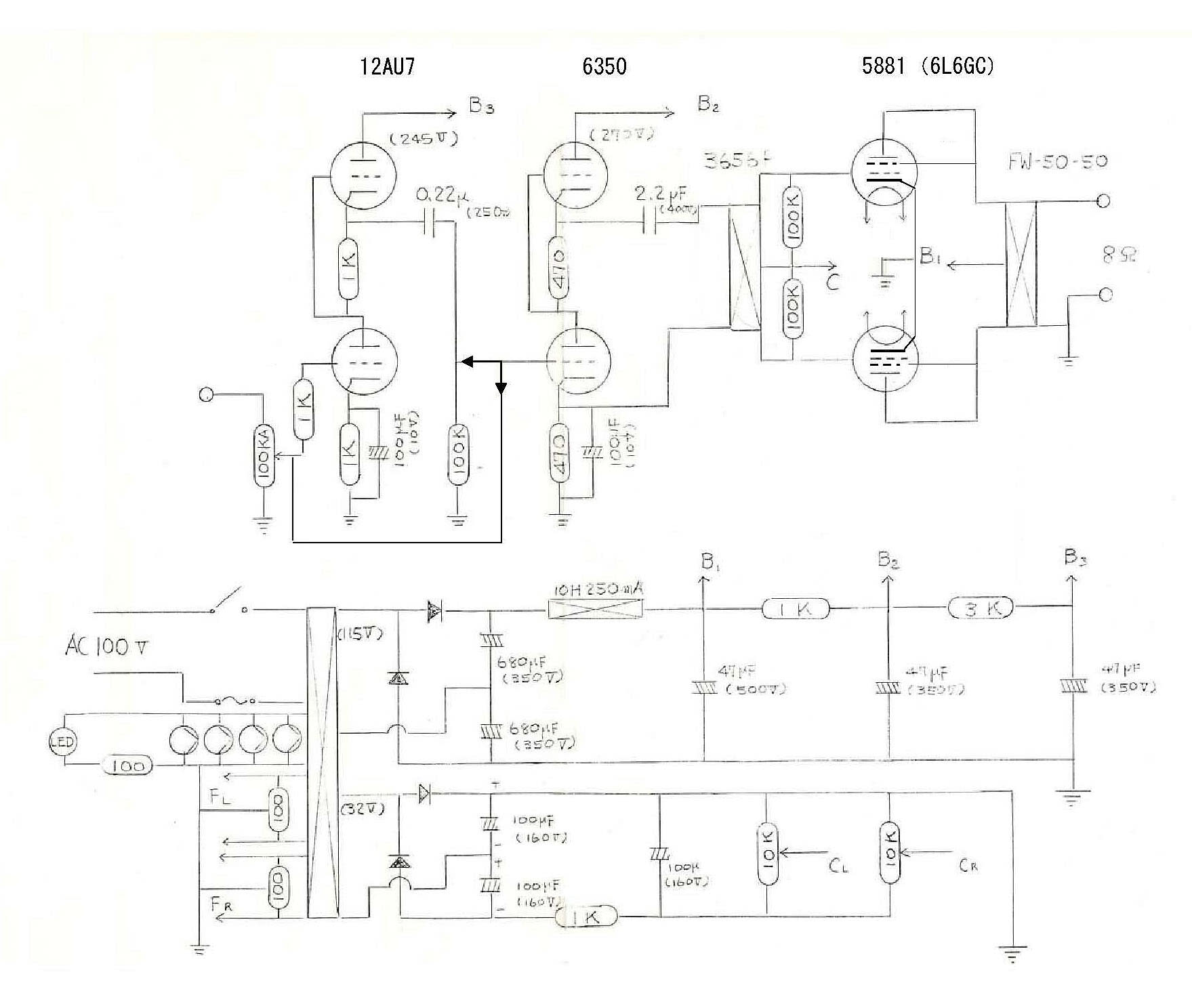長年オーディオのメインシステム用アンプは真空管式にこだわってきました。
今、私の使っている1980年代に入手したJBLスピーカーは当時アメリカGAS社のアンプジラという製品と相性が良いという定評がありましたが、このアンプは50万円以上するもので入手も難しく、自作派を通してきました。
しかし一度はアンプジラを聴いてみたいと思い続けていましたが、最近オークションでアンプジラがお値打ち相場で出ていたのでチャンスとばかり落札してしまいました。それが今日入荷し早速数枚のCDを試聴するとやはり評判通りの再生音で感激しました。
ただしこれまで指摘されていた「電源投入時数秒間回路が安定するまでスピーカ端子に微小電圧の発生」「トランスのうなり」「ファンの音」「無音時に微小ハム音(入力がシールド線でなく撚り線使用、Tr類の磁界影響あり」など改善課題、未完成部分も確認できました。


音は、低域はしまりがあって力ずよくかつ雄大です。サックスやペットの音もリアルで良い表現をしました。
人の声も非常にしっかりしていますが、声の柔らかさは自作の真空管アンプの方が優れていると思いました。
ひとしきり試聴評価が出来たので、メータランプが点灯しない原因をチェックした結果ランプ電源配線の抵抗が腐食断線していました。さっそく交換し、めでたく修理が完了しました。

早速修理後再度試聴をと思い「アンプジラON⇒プリアンプON」の順に電源を入れてしまったのです。
そうすると片チャンネメータが振り切れ、アンプ異常の赤ランプが点灯してしまいました。解放して中を見ると回路中のヒューズが切れて少し煙も出ていました。
実はこのアンプは、保護回路が省略されていて上流のプリが不安定状態のとき電圧変動をそのまま増幅してしまうため必ず「プリアンプON⇒アンプジラON」の手順を守る必要があったのです。
音を良くする一つの対策として保護回路を省いているため慎重に扱う必要があるアンプなのです。
結局入荷して数枚のCDを聴いて壊してしまいました。残念・・・・。