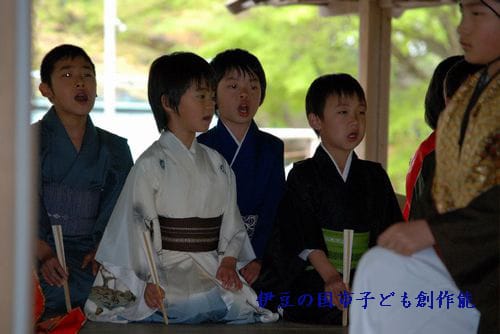ぬえの解釈。。これは能楽師だから考えること、かもしれませんが、稽古をしてみて実際の舞台進行に即して持った印象なのですが。
つまり、この場面。。というよりこの能の前半部分はツレ小宰相の物語なのであって、いうなればツレが主人公であって、漁翁のシテは、「主役」ではあっても「主人公」ではないのではないか、というものです。
ぬえの解釈によれば、入水の場面で小宰相の袖にすがって止めるのは、通盛の化身ではなく、やはり乳母なのです。
それは例えば、次のような、舞台に現れる小さな事象を積み重ねてきたときに考えられるのではないかと思います。いわく、入水を止める場面での言葉。。「この時の物思ひ君一人に限らず。思し召し止り給へ」が、夫の遺言を背いてまで彼の後を追おうとする妻の決意を翻すには、あまりに薄っぺらな説得であること。。これは小宰相の入水に対する通盛思いではなく、やはり乳母の言葉と解すべきでしょう。
そもそも、すでに先に討ち死にしている通盛が、同じく入水自殺を遂げた妻を 今さら引き止める、という構図そのものに違和感があります。僧に対して懺悔のために自分たちの死の有様を仕方話に演じているのだとしても、妻の死に夫の動作は介在できないはずですし。
それから、もしこの能の前場での主人公がシテではなくツレだと考えると、正面に向けて出された舟の先の方にツレが立ち、シテはその後ろに立つことでツレの陰に隠されて客席から見えにくい事も説明がつきます。もちろん、舟を漕ぐのは後ろに乗る人の役目ですし、そこに男性のシテが立ち、女性であるツレがお客さんのようにその前に立つのは当たり前のことです。そうして、もしもシテが前に立ってしまったら、それこそ主役に隠されたツレはまったく舞台に登場した存在意義がなくなってしまう。さらにはそのような位置関係では小宰相が死去したこの場所で彼女の最期を物語るには圧倒的に不利。。というか不可能でしょう。
そんな事からシテが後ろに、ツレが前に立つのは当然なのですが、これによって終始、シテの姿は正面から見えづらい事になります。ところが、この前場の核心となる部分は小宰相の最期です。そうであれば物語はその化身であるツレの口から語られるのが自然ですし、最も効果的であります。そのためにはツレ一人に観客の注目が集まる方が、その効果を最大に高めることができるのです。
現に、ワキ僧から鳴門で死亡した平家の事を問われたシテは「中にも小宰相の局こそ。。」と言いかけて、あえてツレに「もろともに御物語り候へ」と発言を求めます。そうしてこれ以後、ずっとシテとツレとの連吟になるのですが、その中でシテは「こゝだにも都の遠き須磨の浦」の1句を謡うのみで、これに対してツ
ツレは「さる程に平家の一門。。」「さる程に小宰相の局乳母を近づけ。。」「さるにてもあの海にこそ沈まうずらめ。。」と、多くの説明をみずからの口によって行います。
この場面で語り手は明らかにツレ小宰相なのであって、シテは「主役」という立場上、連吟の主導を執るけれども、内容としてはむしろ「もろともに」と言うよりはツレの一人語りと考えるべきでしょう。シテは、舞台への登場からワキ僧との問答など、舟の所有者として、ツレよりも年長者として、一定の主導権は執るけれども、ワキに問われて「鳴門で死去した平家一門」を物語るとき、その話題はおのずから小宰相の悲劇にならざるを得ないです。ですから「や。もろともに御物語り候へ」とシテが言うとき、物語の「主人公」はシテの手を離れてツレに移った、と考えることができると思います。
そうであれば、「乳母泣く泣く取り付きて」と地謡が謡うときにツレの袖にすがって引き止めたのは、やはり通盛の霊ではなくて、「乳母」であったのだと思います。それは、乳母の霊が登場したのでも、また通盛が乳母の役を演じたのでもなく、ただ、そういう光景がその夜に繰り広げられた、ということを視覚的に説明する、演出上の方便として行われるのであろうと考えています。この場面。。ツレが入水を決意するところから、それを乳母が引き止めようとする場面、そしてツレの入水までは、シテは「主人公」であることをツレに譲って、その演技の補助的な役割を勤めているのだと思います。
そしてツレの入水の場面にはまた特筆すべき演出が施されてあります。
それは、ツレが乳母の制止を振り切って、舟から<左側>に下りて膝をつくのに対して、シテは反対側。。<右側>に向いて、ツレの姿を見失った体で海面を見回して呆然とした表情を見せるのです。(注:右・左は演者から見た方向ですので、客席からは逆に。。ツレは向かって右側の舞台中央の方向に舟を下りて膝をつき、シテは向かって左側。。脇正面の客席の方にその姿を探す型をします)
一瞬のことではありますが、シテとツレが あべこべの方向を向いて演技をするので、お客さまには混乱があるかもしれませんね。
これは、舟の作物がシテ柱の先、舞台の右側いっぱいに出されているので、ツレは物理的に舟の右側には下りられない(舞台から落ちてしまう)、という理由もあります。けれどもこの動作の理由はそれだけではないのです。
現に、ツレは入水する直前に「さるにてもあの海にこそ沈まうずらめ」と謡うとき、その後に実際に舟を下りる方向ではなく、やはり<右側>に向くのです。この曲では阿弥陀如来がおわす西方浄土を、ツレから見て<右側>に設定しているのは明らかで、入水した後にシテがツレの姿を探す方向とも一致しています。
それなのにツレはそれとは反対側の<左側>に向かって入水する型を見せるわけですが、つまりこれは、小宰相が入水した、という「事実」あるいは「動作」だけを抽出して見せているのだと思います。「こうして海に飛び込んだ」という動作が観客の目に入れるのが目的で、ツレは舟から下りて膝をつくと、すぐに立ち上がって、後見座に後ろ向きに着座してしまいます。能では常套手段の演出で、この役者はもう舞台上には存在しない、という事を意味する約束事です。そうして、ツレに袖を振りきられたシテ。。乳母は、あわてて「小宰相が飛び込んだ方角」である<右側>の海面を目で探し、それが得られないと分かると呆然と中空を見上げます。このとき、シテ。。乳母が探す方向にツレの役者の身体があってはならないはずです。
ずっと動作が少ない能であるからこそ、この一瞬の動きはとても目に鮮やかに飛び込んできますね。一瞬のうちに観客は舟の<左側>に小宰相が入水した、という「事実」を見、すぐさまその姿を見失った「残された者」。。乳母の悲嘆を<右側>に見るのです。これに気づいた ぬえは、大変優れた演出だと感嘆しました。
付け加えて言えば、ツレを見失ったシテは激しく右左に面を動かして(これを「面を切ル)と言います)海面にツレの姿を求めますが、このとき(役はあくまで乳母であるけれども)、シテが掛けている老人の面。。わけても『通盛』の前シテに使う「笑尉」や「朝倉尉」という面は、面を切ルと大変効果が出る面なのです。ほかにも面を切ルのが利く面には「泥眼」や「般若」がありますが、作者がその効果まで計算に入れて、『通盛』の前シテを、通盛本人が若くして死んだにもかかわらず、あえて老人に設定したのだとしたら。。
先ほど「シテは『主人公』であることをツレに譲って、その演技の補助的な役割を勤めている」と書きましたが、もちろんそのまま「主人公」であることを放棄したままでは終わりません。
ツレの姿を見失って呆然とした有様は、それを制止し得なかった乳母の心でもありましょうし、同時に愛妻を失った(ことを冥土で知った)通盛の悲しみでもあります。シテは自然に乳母から通盛本人へとその主体を移し、喪失感を漂わせたまま、ツレと同じように舟から下りると、正面を向いたまま力なく後ろに下がると、やはり膝をついて座ります。
ツレが一瞬で海に飛び込んだ様子とは対照的に、シテは静かに 静かに膝をつくことで、ずぶずぶと海の中に姿を消した事を表現します。
かくしてワキ僧はここに至って、はじめてこの漁師たちが生きた人間でないことを悟ったでしょう。そうしてシテが再び立ち上がって、これも静かに幕に姿を消したとき、舞台上には二人が登場する前と同じように舟がポツンと取り残されるのです。誰も乗っていないままに波間を漂う舟。。ちょっと怖いですね。
今回は笛が森田流のため、シテが橋掛リを歩んで幕に向かうとき、彩りの笛を吹いてくださいません。無音の中を歩むのはなかなか難しいですが、緊張の糸がとぎれる事がないように歩みたいです。
つまり、この場面。。というよりこの能の前半部分はツレ小宰相の物語なのであって、いうなればツレが主人公であって、漁翁のシテは、「主役」ではあっても「主人公」ではないのではないか、というものです。
ぬえの解釈によれば、入水の場面で小宰相の袖にすがって止めるのは、通盛の化身ではなく、やはり乳母なのです。
それは例えば、次のような、舞台に現れる小さな事象を積み重ねてきたときに考えられるのではないかと思います。いわく、入水を止める場面での言葉。。「この時の物思ひ君一人に限らず。思し召し止り給へ」が、夫の遺言を背いてまで彼の後を追おうとする妻の決意を翻すには、あまりに薄っぺらな説得であること。。これは小宰相の入水に対する通盛思いではなく、やはり乳母の言葉と解すべきでしょう。
そもそも、すでに先に討ち死にしている通盛が、同じく入水自殺を遂げた妻を 今さら引き止める、という構図そのものに違和感があります。僧に対して懺悔のために自分たちの死の有様を仕方話に演じているのだとしても、妻の死に夫の動作は介在できないはずですし。
それから、もしこの能の前場での主人公がシテではなくツレだと考えると、正面に向けて出された舟の先の方にツレが立ち、シテはその後ろに立つことでツレの陰に隠されて客席から見えにくい事も説明がつきます。もちろん、舟を漕ぐのは後ろに乗る人の役目ですし、そこに男性のシテが立ち、女性であるツレがお客さんのようにその前に立つのは当たり前のことです。そうして、もしもシテが前に立ってしまったら、それこそ主役に隠されたツレはまったく舞台に登場した存在意義がなくなってしまう。さらにはそのような位置関係では小宰相が死去したこの場所で彼女の最期を物語るには圧倒的に不利。。というか不可能でしょう。
そんな事からシテが後ろに、ツレが前に立つのは当然なのですが、これによって終始、シテの姿は正面から見えづらい事になります。ところが、この前場の核心となる部分は小宰相の最期です。そうであれば物語はその化身であるツレの口から語られるのが自然ですし、最も効果的であります。そのためにはツレ一人に観客の注目が集まる方が、その効果を最大に高めることができるのです。
現に、ワキ僧から鳴門で死亡した平家の事を問われたシテは「中にも小宰相の局こそ。。」と言いかけて、あえてツレに「もろともに御物語り候へ」と発言を求めます。そうしてこれ以後、ずっとシテとツレとの連吟になるのですが、その中でシテは「こゝだにも都の遠き須磨の浦」の1句を謡うのみで、これに対してツ
ツレは「さる程に平家の一門。。」「さる程に小宰相の局乳母を近づけ。。」「さるにてもあの海にこそ沈まうずらめ。。」と、多くの説明をみずからの口によって行います。
この場面で語り手は明らかにツレ小宰相なのであって、シテは「主役」という立場上、連吟の主導を執るけれども、内容としてはむしろ「もろともに」と言うよりはツレの一人語りと考えるべきでしょう。シテは、舞台への登場からワキ僧との問答など、舟の所有者として、ツレよりも年長者として、一定の主導権は執るけれども、ワキに問われて「鳴門で死去した平家一門」を物語るとき、その話題はおのずから小宰相の悲劇にならざるを得ないです。ですから「や。もろともに御物語り候へ」とシテが言うとき、物語の「主人公」はシテの手を離れてツレに移った、と考えることができると思います。
そうであれば、「乳母泣く泣く取り付きて」と地謡が謡うときにツレの袖にすがって引き止めたのは、やはり通盛の霊ではなくて、「乳母」であったのだと思います。それは、乳母の霊が登場したのでも、また通盛が乳母の役を演じたのでもなく、ただ、そういう光景がその夜に繰り広げられた、ということを視覚的に説明する、演出上の方便として行われるのであろうと考えています。この場面。。ツレが入水を決意するところから、それを乳母が引き止めようとする場面、そしてツレの入水までは、シテは「主人公」であることをツレに譲って、その演技の補助的な役割を勤めているのだと思います。
そしてツレの入水の場面にはまた特筆すべき演出が施されてあります。
それは、ツレが乳母の制止を振り切って、舟から<左側>に下りて膝をつくのに対して、シテは反対側。。<右側>に向いて、ツレの姿を見失った体で海面を見回して呆然とした表情を見せるのです。(注:右・左は演者から見た方向ですので、客席からは逆に。。ツレは向かって右側の舞台中央の方向に舟を下りて膝をつき、シテは向かって左側。。脇正面の客席の方にその姿を探す型をします)
一瞬のことではありますが、シテとツレが あべこべの方向を向いて演技をするので、お客さまには混乱があるかもしれませんね。
これは、舟の作物がシテ柱の先、舞台の右側いっぱいに出されているので、ツレは物理的に舟の右側には下りられない(舞台から落ちてしまう)、という理由もあります。けれどもこの動作の理由はそれだけではないのです。
現に、ツレは入水する直前に「さるにてもあの海にこそ沈まうずらめ」と謡うとき、その後に実際に舟を下りる方向ではなく、やはり<右側>に向くのです。この曲では阿弥陀如来がおわす西方浄土を、ツレから見て<右側>に設定しているのは明らかで、入水した後にシテがツレの姿を探す方向とも一致しています。
それなのにツレはそれとは反対側の<左側>に向かって入水する型を見せるわけですが、つまりこれは、小宰相が入水した、という「事実」あるいは「動作」だけを抽出して見せているのだと思います。「こうして海に飛び込んだ」という動作が観客の目に入れるのが目的で、ツレは舟から下りて膝をつくと、すぐに立ち上がって、後見座に後ろ向きに着座してしまいます。能では常套手段の演出で、この役者はもう舞台上には存在しない、という事を意味する約束事です。そうして、ツレに袖を振りきられたシテ。。乳母は、あわてて「小宰相が飛び込んだ方角」である<右側>の海面を目で探し、それが得られないと分かると呆然と中空を見上げます。このとき、シテ。。乳母が探す方向にツレの役者の身体があってはならないはずです。
ずっと動作が少ない能であるからこそ、この一瞬の動きはとても目に鮮やかに飛び込んできますね。一瞬のうちに観客は舟の<左側>に小宰相が入水した、という「事実」を見、すぐさまその姿を見失った「残された者」。。乳母の悲嘆を<右側>に見るのです。これに気づいた ぬえは、大変優れた演出だと感嘆しました。
付け加えて言えば、ツレを見失ったシテは激しく右左に面を動かして(これを「面を切ル)と言います)海面にツレの姿を求めますが、このとき(役はあくまで乳母であるけれども)、シテが掛けている老人の面。。わけても『通盛』の前シテに使う「笑尉」や「朝倉尉」という面は、面を切ルと大変効果が出る面なのです。ほかにも面を切ルのが利く面には「泥眼」や「般若」がありますが、作者がその効果まで計算に入れて、『通盛』の前シテを、通盛本人が若くして死んだにもかかわらず、あえて老人に設定したのだとしたら。。
先ほど「シテは『主人公』であることをツレに譲って、その演技の補助的な役割を勤めている」と書きましたが、もちろんそのまま「主人公」であることを放棄したままでは終わりません。
ツレの姿を見失って呆然とした有様は、それを制止し得なかった乳母の心でもありましょうし、同時に愛妻を失った(ことを冥土で知った)通盛の悲しみでもあります。シテは自然に乳母から通盛本人へとその主体を移し、喪失感を漂わせたまま、ツレと同じように舟から下りると、正面を向いたまま力なく後ろに下がると、やはり膝をついて座ります。
ツレが一瞬で海に飛び込んだ様子とは対照的に、シテは静かに 静かに膝をつくことで、ずぶずぶと海の中に姿を消した事を表現します。
かくしてワキ僧はここに至って、はじめてこの漁師たちが生きた人間でないことを悟ったでしょう。そうしてシテが再び立ち上がって、これも静かに幕に姿を消したとき、舞台上には二人が登場する前と同じように舟がポツンと取り残されるのです。誰も乗っていないままに波間を漂う舟。。ちょっと怖いですね。
今回は笛が森田流のため、シテが橋掛リを歩んで幕に向かうとき、彩りの笛を吹いてくださいません。無音の中を歩むのはなかなか難しいですが、緊張の糸がとぎれる事がないように歩みたいです。