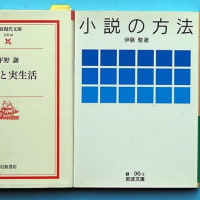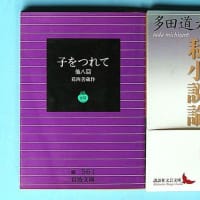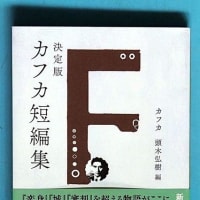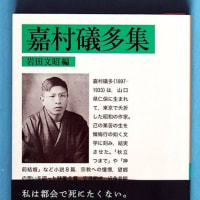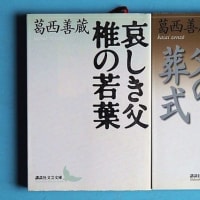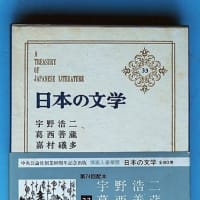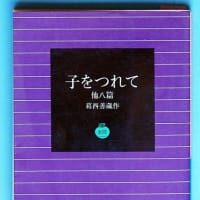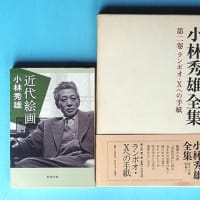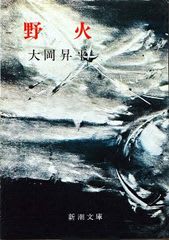
1
これまで「野火」に対しては、わたしはたいへん高い評価を与えてきた。
「野火」は、明治、大正、昭和を通じて、わが国最高の文学的達成のひとつである、と。
いや、わたしばかりでなく、本書を読む者の多くが、ここに見られる見事な小説的言語空間に、心をゆさぶられるに相違ない、と確信する。
それに関連して、あるエピソードを思い出す。
<私はこの小説を面白ずくや娯楽として読んだのじゃない。人生永遠の書の一つとして心読したつもりである。>
「人生永遠の書」とは、正宗白鳥が深沢七郎の「楢山節考」をさしていったことばである。
ところが、それに対し、深沢は「あれは道楽で書いた小説だ」といってはばからなかったそうである。
ところで、「野火」である。本書はわたしにとっては、まさに「人生永遠の書」なのであるが、あの世にいる大岡さんにそれを告げたら、著者はなんていうだろうかと、考えてみたのだ。「あんなもの、きみ、ただのレトリックじゃないか。ぼくの作としては、たまたまうまくいった方だな」
そういった辛辣な返事が返ってきそうに思えるのである。
2
「野火」は、いわゆる戦後文学の傑作である。これに比肩しうるものがあるとすれば、それは唯一武田泰淳の「司馬遷~史記の世界」のみであろう。わたしはずっとそう考えてきた。このたび読み返して、大筋ではその評価はゆるがなかったが、いくつか、大きな疑問が残ったので、そのことを書いておこう。
それはまず、本書が狂人の手記という体裁をとっていることについてである。作者はなぜ、「狂人の手記」という設定にしたか。
わたしは読み返すにあたっていくつかの仮説を立ててみた。
(1)これはハムレットのように佯狂ではないか?
(2)著者が出版社、読者の「良序公俗」に遠慮した結果ではないか?
(3)著者自身が、自分に対して、殺人を犯し、人肉を食った田村一等兵を「狂人」としてしか、容認できなかったのではないか?
(4)上記3つ以外の理由が考えられるとしたら、それはなにか?
田村はハムレット型の人間である。わたしがいちばんスリリングな設定と期待した「狂気を装っている」という読み筋は、表層ではあまり目立たないが、作者は「三八 再び野火に」の章において、それを示唆している。換言すれば、主人公は、むしろ「狂人になりたがっている病者」なのである。本書「野火」には、トラウマ(外傷後ストレス障害または、精神的外傷などと訳される)について学ぼうとするものには、格好のテキストともいえるような側面があるが、この元一等兵の主治医は本人には「あなたは離人症である」と告げている。
すぐれた作品はすべてそうだが、本書は地層のように、いくつかの層から成り立っているので、(3)の仮説も、また(4)の「それ以外の理由」が隠れているという感触も捨てがたいものがある。
この作品は終わりが近づくにつれ、謎のようなことばがかなり断片的に鏤められ、読者の想像力を刺激する仕掛けになっている。作者がそういう書き方を意識的にやっているのである。こういった暗示的な手法を大胆に取り入れて成功した事例を、わたしは日本の小説ではほかに知らない。また、たいへん喚起力の強いこういった文体は、わずかに「俘虜記」(のち「捉まるまで」)に共通性が見られはするものの、その後影をひそめてしまったので、「野火」は大岡の作品系列において、文体的には孤立した作品にみえる。
復員兵田村は、戦後という日常をあるがまま容け入れることができず、生活が「戦場をさまようこと」と同義になってしまった男である。
<汝の右手のなすことを、左手をして知らしむる勿れ>
<私は怒りを感じた。もし人間がその飢えの果てに、互いを食い合うのが必然であるならば、この世は神の怒りの跡にすぎない。>
<私は私の心を人に隠すのに、興味を覚えるようになった。>
<戦争を知らない人間は、半分は子供である。>
<どうでもよろしい。男がみな人食い人種であるように、女はみな淫売である。各自そのなすべきことをなせばよいのである。>
こういったエピグラムが、読者の心を射抜く。
聖書などに出典のあることばもあるようであるが、作者は、たんなる知識としてではなく、生きたことばとして、小説の末尾にいたってじつに効果的に使っている。わたしは若き日にはじめて「野火」を読んで以来、こういった一節をほとんど忘れたことがない。
「凄い小説があったものだ」と、素直に感動したというより、むしろ恐れを感じたというべきであろう。平和な日常では隠れているものが、戦場という極限状況下で、露出しただけ、・・・世界とは、こういった構造のものだという認識は、いまでもわたしを怯えさせ、息苦しいまでのにがにがしい感情で心を満たす。
3
つぎに、本書の際立った特徴をあげるとすれば、こうである。
いわゆる地の文と会話の部分の著しい対比。
これは、そのまま「聖と俗」の対比ととらえることができる、とわたしは考えている。孤独でいるときは、彼は自分を「聖化」できるし、詩人ですらあるのだが、仲間と出会った瞬間、人間関係が復活し、と同時に世間の掟にとらえられるのである。集団のなかに身をおき、またその仲間と別れて、単独者にかえり、山中を彷徨するのだが、「野火」においては、この転換は驚くほど鮮やかである。人はひとりでは生きられない、というのは、感傷的な意味ではないのだ。明日をも知れぬみじめな飢えた敗残の徒となって、比島山中をはいずりまわる兵士と兵士のあいだにある「世間」あるいは「渡世」の苦の世界・・・、それを大岡はすでに冒頭から「会話」によってみごとに象徴的に描き出している。
さらに、もうひとつ、本書を特徴づけているもの。
それは、こうである。
主人公田村は、ドストエフスキーやベートーベンに思いをはせる、当時としてはなかなの知識人なのであるが、奇妙なことに、自分の周辺環境を地政学的な眼でたえず観察し、そこでつぎにどう行動すべきかの理非を判断している。彼はひとりになると、時間の観念はすぐに脱落してしまうのだが、空間の把握力は、むしろ先鋭さを増す、というふうに描き出される。彼は払暁と夕刻をしばしば間違える。「あれから、どのくらいの時間が経過」したか、混乱をきたしているが、まるで見えない羅針盤をかかえた人間のように、自身の位置を、ことばによって、正確に記述しつづける。
「野火」の文体の正確さとは、第一にこのことである。
これがなにを意味するのか? いまのわたしにはよくわからないが、「聖と俗」を、「ひとりと集団」に置き換えたとき、それが空間性となって、この小説の構造を決定している、と思われる。いつ敵があらわれるかわからない戦場をさまようとき、人間は野生動物としての勘を取り戻すのだろうか。
4
<夜は暗かった。西空に懸かった細い月は、紐で繋がれたように、太陽の後を追って沈んで行った。めいめい雨衣をかぶり、雑嚢を枕に横になった。強い光を放つ大きな蛍が、谷間を貫く小さな流れに沿って飛んで来て、或いは地上二米(メートル)の高さを、火箭のように早く真直に飛び、或いは木立の葉簇(はむら)の輪郭をなぞって、高く低くめまぐるしく飛んだ。そして果ては一本の木にかたまって、その木をクリスマス・トリーのように輝かした。>(6 夜)
ここは本書でもよく知られた、美しい場面である。
丸谷才一は、「文章読本」のなかで、ここの描写を「文学的誇張」であると揶揄しているのだが、はたしてそうか?
ところが先日、大岡が「歩哨の眼」において、比島の蛍は、日本の蛍より三倍の大きさがあるといっているのに気がついた。
<(たくさんの蛍が)一本の木にかたまって、その木をクリスマス・トリーのように輝かした>
このイメージは鮮やかで美しいが、いかにもおおげさな比喩だと受け取られ、それに対して、作者が、いや、そうではない、と反論をこころみたのである。
丸谷さんもほかの大方の読者も、蛍といえば、せいぜい日本の「ゲンジボタル」しか知らないのである。ミンドロ島に「わが国の蛍の三倍」もの蛍がいたとしても、なんら不思議ではない。
ここから理解できるのは、本を読むとは、結局のところ、読者の経験と知識のなかで、あれこれ想像力をはたらかせながら読むほかない、という、あたりまえの事実である。
20歳で読むのと、40歳で読むのとでは、あるいは、男性が読むのと、女性が読むのとでは、しばしばまったく違った印象をうけるのは、むしろ当然というべきであろう。
丸谷才一はさきにあげた「文章読本」の「文体とレトリック」の一章を、すべて「野火」の分析と紹介にあてていて、「野火」が、表現のあらゆるテクニックを駆使して書かれた日本文学史上稀有な作品であることを、シェークスピアと比較しながら、さまざまに実証している。
これはいうまでもなく、側面からの「野火」へのオードなのである。
5
35歳の老兵大岡昇平は、暗号手として、フィリピン戦線へと派遣される。
年譜を見ると、青春期に中原中也と交友し、小林秀雄にフランス語の手ほどきを受け、フランス文学、なかでも、スタンダール研究家として、訳書や論考を発表していたが、それだけでは生活できず、神戸で会社員となって勤務する一方、結婚して二児をもうける。そいう彼のもとへ、召集令状が届くのである。
九死に一生を得て帰国した彼は、のちに「俘虜記」としてまとめられることになる、戦場体験をつづった短編を次つぎと発表、小説家としての道を歩みはじめる。この戦場体験がなかったら、彼はいくらかは知られたスタンダール研究家として、陋巷にうもれたことであろう。図らずも小説家となった彼は、「武蔵野夫人」「花影」などを書いて、一時流行作家となる。わたしは彼のこういった作品も好きである。
しかし、大岡昇平の真骨頂は、なんといっても、鎮魂作家としての業績であろう。あの大部の「中原中也」「レイテ戦記」を読むものは、著者の執念に圧倒されずにはいない。
生き残ってしまった人間の文学。
流行作家でありつづけることを断念したあと、彼の仕事は過去へ遡及する。そして、無常観だとか、もののあわれといったような伝統美の世界をめざすのではなく、「事実はどうであったか」を掘り下げ、あくなき検証をくわえるのである。人がどういった考えをいだいて生き、どのように死んでいったかを「知る」ことで、鎮魂をはたそうとするこういった大岡の著作は、むろん「記録」と不可分のものであった。
<そして私は死を怖れなくなった。私はスタンダールに倣って自分の墓碑銘を選び、ノートの終りに書きつけた。「孤影悄然」というのである>(「俘虜記」)
後年、石原吉郎という詩人を知ったとき、わたしは「孤影悄然」ということばに、もう一度めぐりあった。
大岡昇平「野火」新潮文庫>★★★★★
(1909-1988)東京生れ。京都帝大仏文科卒。帝国酸素、川崎重工業などに勤務。1944(昭和19)年、召集されてフィリピンのミンドロ島に赴くが、翌年米軍の俘虜となり、レイテ島収容所に送られる。1949年、戦場の経験を書いた『俘虜記』で第1回横光利一賞を受け、これが文学的出発となる。小説家としての活動は多岐にわたり、代表作に『武蔵野夫人』『野火』(読売文学賞)『花影』『レイテ戦記』(毎日芸術大賞)などがある。1971年、芸術院会員に選ばれたが辞退。(新潮社ホームページより)
これまで「野火」に対しては、わたしはたいへん高い評価を与えてきた。
「野火」は、明治、大正、昭和を通じて、わが国最高の文学的達成のひとつである、と。
いや、わたしばかりでなく、本書を読む者の多くが、ここに見られる見事な小説的言語空間に、心をゆさぶられるに相違ない、と確信する。
それに関連して、あるエピソードを思い出す。
<私はこの小説を面白ずくや娯楽として読んだのじゃない。人生永遠の書の一つとして心読したつもりである。>
「人生永遠の書」とは、正宗白鳥が深沢七郎の「楢山節考」をさしていったことばである。
ところが、それに対し、深沢は「あれは道楽で書いた小説だ」といってはばからなかったそうである。
ところで、「野火」である。本書はわたしにとっては、まさに「人生永遠の書」なのであるが、あの世にいる大岡さんにそれを告げたら、著者はなんていうだろうかと、考えてみたのだ。「あんなもの、きみ、ただのレトリックじゃないか。ぼくの作としては、たまたまうまくいった方だな」
そういった辛辣な返事が返ってきそうに思えるのである。
2
「野火」は、いわゆる戦後文学の傑作である。これに比肩しうるものがあるとすれば、それは唯一武田泰淳の「司馬遷~史記の世界」のみであろう。わたしはずっとそう考えてきた。このたび読み返して、大筋ではその評価はゆるがなかったが、いくつか、大きな疑問が残ったので、そのことを書いておこう。
それはまず、本書が狂人の手記という体裁をとっていることについてである。作者はなぜ、「狂人の手記」という設定にしたか。
わたしは読み返すにあたっていくつかの仮説を立ててみた。
(1)これはハムレットのように佯狂ではないか?
(2)著者が出版社、読者の「良序公俗」に遠慮した結果ではないか?
(3)著者自身が、自分に対して、殺人を犯し、人肉を食った田村一等兵を「狂人」としてしか、容認できなかったのではないか?
(4)上記3つ以外の理由が考えられるとしたら、それはなにか?
田村はハムレット型の人間である。わたしがいちばんスリリングな設定と期待した「狂気を装っている」という読み筋は、表層ではあまり目立たないが、作者は「三八 再び野火に」の章において、それを示唆している。換言すれば、主人公は、むしろ「狂人になりたがっている病者」なのである。本書「野火」には、トラウマ(外傷後ストレス障害または、精神的外傷などと訳される)について学ぼうとするものには、格好のテキストともいえるような側面があるが、この元一等兵の主治医は本人には「あなたは離人症である」と告げている。
すぐれた作品はすべてそうだが、本書は地層のように、いくつかの層から成り立っているので、(3)の仮説も、また(4)の「それ以外の理由」が隠れているという感触も捨てがたいものがある。
この作品は終わりが近づくにつれ、謎のようなことばがかなり断片的に鏤められ、読者の想像力を刺激する仕掛けになっている。作者がそういう書き方を意識的にやっているのである。こういった暗示的な手法を大胆に取り入れて成功した事例を、わたしは日本の小説ではほかに知らない。また、たいへん喚起力の強いこういった文体は、わずかに「俘虜記」(のち「捉まるまで」)に共通性が見られはするものの、その後影をひそめてしまったので、「野火」は大岡の作品系列において、文体的には孤立した作品にみえる。
復員兵田村は、戦後という日常をあるがまま容け入れることができず、生活が「戦場をさまようこと」と同義になってしまった男である。
<汝の右手のなすことを、左手をして知らしむる勿れ>
<私は怒りを感じた。もし人間がその飢えの果てに、互いを食い合うのが必然であるならば、この世は神の怒りの跡にすぎない。>
<私は私の心を人に隠すのに、興味を覚えるようになった。>
<戦争を知らない人間は、半分は子供である。>
<どうでもよろしい。男がみな人食い人種であるように、女はみな淫売である。各自そのなすべきことをなせばよいのである。>
こういったエピグラムが、読者の心を射抜く。
聖書などに出典のあることばもあるようであるが、作者は、たんなる知識としてではなく、生きたことばとして、小説の末尾にいたってじつに効果的に使っている。わたしは若き日にはじめて「野火」を読んで以来、こういった一節をほとんど忘れたことがない。
「凄い小説があったものだ」と、素直に感動したというより、むしろ恐れを感じたというべきであろう。平和な日常では隠れているものが、戦場という極限状況下で、露出しただけ、・・・世界とは、こういった構造のものだという認識は、いまでもわたしを怯えさせ、息苦しいまでのにがにがしい感情で心を満たす。
3
つぎに、本書の際立った特徴をあげるとすれば、こうである。
いわゆる地の文と会話の部分の著しい対比。
これは、そのまま「聖と俗」の対比ととらえることができる、とわたしは考えている。孤独でいるときは、彼は自分を「聖化」できるし、詩人ですらあるのだが、仲間と出会った瞬間、人間関係が復活し、と同時に世間の掟にとらえられるのである。集団のなかに身をおき、またその仲間と別れて、単独者にかえり、山中を彷徨するのだが、「野火」においては、この転換は驚くほど鮮やかである。人はひとりでは生きられない、というのは、感傷的な意味ではないのだ。明日をも知れぬみじめな飢えた敗残の徒となって、比島山中をはいずりまわる兵士と兵士のあいだにある「世間」あるいは「渡世」の苦の世界・・・、それを大岡はすでに冒頭から「会話」によってみごとに象徴的に描き出している。
さらに、もうひとつ、本書を特徴づけているもの。
それは、こうである。
主人公田村は、ドストエフスキーやベートーベンに思いをはせる、当時としてはなかなの知識人なのであるが、奇妙なことに、自分の周辺環境を地政学的な眼でたえず観察し、そこでつぎにどう行動すべきかの理非を判断している。彼はひとりになると、時間の観念はすぐに脱落してしまうのだが、空間の把握力は、むしろ先鋭さを増す、というふうに描き出される。彼は払暁と夕刻をしばしば間違える。「あれから、どのくらいの時間が経過」したか、混乱をきたしているが、まるで見えない羅針盤をかかえた人間のように、自身の位置を、ことばによって、正確に記述しつづける。
「野火」の文体の正確さとは、第一にこのことである。
これがなにを意味するのか? いまのわたしにはよくわからないが、「聖と俗」を、「ひとりと集団」に置き換えたとき、それが空間性となって、この小説の構造を決定している、と思われる。いつ敵があらわれるかわからない戦場をさまようとき、人間は野生動物としての勘を取り戻すのだろうか。
4
<夜は暗かった。西空に懸かった細い月は、紐で繋がれたように、太陽の後を追って沈んで行った。めいめい雨衣をかぶり、雑嚢を枕に横になった。強い光を放つ大きな蛍が、谷間を貫く小さな流れに沿って飛んで来て、或いは地上二米(メートル)の高さを、火箭のように早く真直に飛び、或いは木立の葉簇(はむら)の輪郭をなぞって、高く低くめまぐるしく飛んだ。そして果ては一本の木にかたまって、その木をクリスマス・トリーのように輝かした。>(6 夜)
ここは本書でもよく知られた、美しい場面である。
丸谷才一は、「文章読本」のなかで、ここの描写を「文学的誇張」であると揶揄しているのだが、はたしてそうか?
ところが先日、大岡が「歩哨の眼」において、比島の蛍は、日本の蛍より三倍の大きさがあるといっているのに気がついた。
<(たくさんの蛍が)一本の木にかたまって、その木をクリスマス・トリーのように輝かした>
このイメージは鮮やかで美しいが、いかにもおおげさな比喩だと受け取られ、それに対して、作者が、いや、そうではない、と反論をこころみたのである。
丸谷さんもほかの大方の読者も、蛍といえば、せいぜい日本の「ゲンジボタル」しか知らないのである。ミンドロ島に「わが国の蛍の三倍」もの蛍がいたとしても、なんら不思議ではない。
ここから理解できるのは、本を読むとは、結局のところ、読者の経験と知識のなかで、あれこれ想像力をはたらかせながら読むほかない、という、あたりまえの事実である。
20歳で読むのと、40歳で読むのとでは、あるいは、男性が読むのと、女性が読むのとでは、しばしばまったく違った印象をうけるのは、むしろ当然というべきであろう。
丸谷才一はさきにあげた「文章読本」の「文体とレトリック」の一章を、すべて「野火」の分析と紹介にあてていて、「野火」が、表現のあらゆるテクニックを駆使して書かれた日本文学史上稀有な作品であることを、シェークスピアと比較しながら、さまざまに実証している。
これはいうまでもなく、側面からの「野火」へのオードなのである。
5
35歳の老兵大岡昇平は、暗号手として、フィリピン戦線へと派遣される。
年譜を見ると、青春期に中原中也と交友し、小林秀雄にフランス語の手ほどきを受け、フランス文学、なかでも、スタンダール研究家として、訳書や論考を発表していたが、それだけでは生活できず、神戸で会社員となって勤務する一方、結婚して二児をもうける。そいう彼のもとへ、召集令状が届くのである。
九死に一生を得て帰国した彼は、のちに「俘虜記」としてまとめられることになる、戦場体験をつづった短編を次つぎと発表、小説家としての道を歩みはじめる。この戦場体験がなかったら、彼はいくらかは知られたスタンダール研究家として、陋巷にうもれたことであろう。図らずも小説家となった彼は、「武蔵野夫人」「花影」などを書いて、一時流行作家となる。わたしは彼のこういった作品も好きである。
しかし、大岡昇平の真骨頂は、なんといっても、鎮魂作家としての業績であろう。あの大部の「中原中也」「レイテ戦記」を読むものは、著者の執念に圧倒されずにはいない。
生き残ってしまった人間の文学。
流行作家でありつづけることを断念したあと、彼の仕事は過去へ遡及する。そして、無常観だとか、もののあわれといったような伝統美の世界をめざすのではなく、「事実はどうであったか」を掘り下げ、あくなき検証をくわえるのである。人がどういった考えをいだいて生き、どのように死んでいったかを「知る」ことで、鎮魂をはたそうとするこういった大岡の著作は、むろん「記録」と不可分のものであった。
<そして私は死を怖れなくなった。私はスタンダールに倣って自分の墓碑銘を選び、ノートの終りに書きつけた。「孤影悄然」というのである>(「俘虜記」)
後年、石原吉郎という詩人を知ったとき、わたしは「孤影悄然」ということばに、もう一度めぐりあった。
大岡昇平「野火」新潮文庫>★★★★★
(1909-1988)東京生れ。京都帝大仏文科卒。帝国酸素、川崎重工業などに勤務。1944(昭和19)年、召集されてフィリピンのミンドロ島に赴くが、翌年米軍の俘虜となり、レイテ島収容所に送られる。1949年、戦場の経験を書いた『俘虜記』で第1回横光利一賞を受け、これが文学的出発となる。小説家としての活動は多岐にわたり、代表作に『武蔵野夫人』『野火』(読売文学賞)『花影』『レイテ戦記』(毎日芸術大賞)などがある。1971年、芸術院会員に選ばれたが辞退。(新潮社ホームページより)