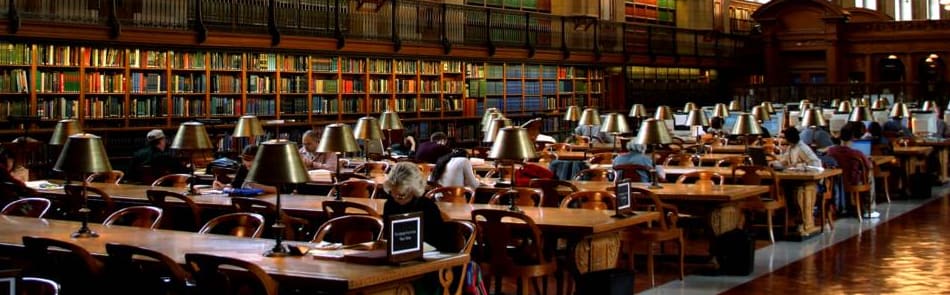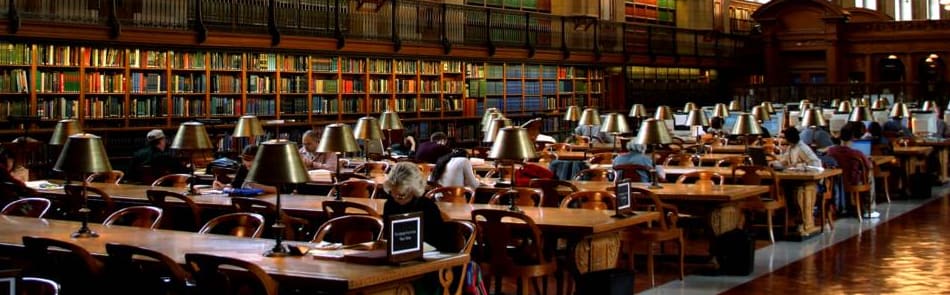
(明眸社HPより
http://meibousha.com/)
さて、カタカムナはしばらくお休みして、かさこ塾のプレゼンで紹介した通り、
明眸社とコラボして、自分史を書くお手伝いをしたい、と思っていまして、自分史について少し書いていきたいと思います。
(2016.7.31 の記事「明眸社のエッセイクラブ」/ 2017.3.26 の記事「自分史出版のお手伝い」参照)
自分史とは何か、どう書けばいいのか?
とはいえ、正直なところ、私はまだ自分史のお手伝いをしたことがありません。
若い頃、若干それに似た仕事をしたことはありますが、
(インタビューや取材したものを文章にまとめる、あるいは、そうしたものを基にして小説仕立ての本にする等、ゴーストライターの仕事です)
経験不足は否めません。その力量があるかどうかもわかりません。
ただ、70年近く生きてきて、いい時代も苦しい時代も経験しているので、
それだけが強みです。
そこで、自分史を書くとはどういうことなのか、
最初から、皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。
今、私の手元には、
「自分史の書き方」立花隆著(講談社)
という本があります。
前にも紹介しましたが、とてもいい本なので、
これから自分史を書こうと思っている方はぜひ読まれるといいと思います。
これを一冊読めば、何をどう書けばいいのか大体わかるので、
私があえて述べるまでもないのですが、
ただ、
立花隆氏とは少し違う視点もあるかなとは思っています。
五年ほど前(明眸社を立ち上げる前)明眸社を主宰しているSさんがこんなことを話してくれました。
「出版社を立ち上げたいと思っているんだけど・・歌集や自費出版の本を格安で出版できる出版社があるといいと思うし、自分史の本も出せるといいなと思って。あなたも書いてみない?」
そこで、私は、
自分史って何? と思いました。
自分史を書くということは、過去を振り返るということ。
今さら振り返ってどうする?
ようやく通り抜けてきたのに、大変な思いをして通り抜けてきたのに、
また振り返るなんて、しかもそれを文章にするなんて、
勘弁してほしい・・
それが私の正直な気持でした。
振り返るより、未来を見ていたい。
振り返っても過去は変わらない。ならば、変えることのできる未来をこそ見ていたい。
いってみれば、まあ、
恐ろしかったのですね。
振り返るたびに、その時代に引き戻されそうで、
過去の自分に向き合うのが怖い。
自分史を書こうという人たちは
きっと幸せな人生を生きてきた人たちなのだろう。
そう思っていました。
でも、
いくら私でも、苦しいことばかりではありませんでした。
楽しい時代もあったし、幸せな時代もありました。
禍福は糾える縄の如し。
まさにその通りの人生でありました・・
って、まだ終わってないけど。
明眸社のエッセイクラブに所属し、これまでに50本近いエッセイを書いてきました。
その中には、子ども時代のことや過去の記録等もあります。
そして、文章にすることによって、過去が鮮明に立ち上がってくる、という事実を目の当たりにして、書くという行為はなかなかのものではないか、と思うに至りつつあります。
つまり、過去は変えられないけれど、過去に対する見方は変えられるのですね。
見方を変えると、人生そのものも違って見えてきます。
これは一種のセラピーといってもいいかと思います。
何より驚いたのは、私に限らず、過去のことを書き始めると記憶が鮮明に蘇ってくることです。
よく覚えているね、そんな細かいことまで。
とよく言われますが、誰でもそうなります。
書き始めると、記憶装置にスイッチが入り、海馬の奥底にしまいこまれていた記憶の断片が少しずつ引き出されていき、そういえばこんなこともあった、あんなこともあったと、次から次へと忘れていた思い出がよみがえってくるのは驚くほどです。
皆さんも試してごらんになるといいと思います。
過去の出来事について、
ひと夏の思い出について、
書きだしてみてください。
びっくりするほど記憶がよみがえってきますから。
そして、
自分を客観視することが出来るようになります。
そして、また、
他人に見てもらうということ、
これも大事です。
自分だけではなく、同時代を生きた人々の記録にもなるし、
時代背景も浮かんできます。
ひいては、歴史そのものの見方にも変化が現れるかもしれません。
書いていくうちに、必ず自分の中で何かが変わっていきます。
その変化を見る楽しみもあります。
自分史にはいろんな方法や使い道があり、使い方によっては大きな人生の転換をもたらす契機にすらなるかもしれません。
というわけで、自分史に興味を持っていただけると嬉しいです。