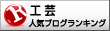呉須に少量のCMC(合成糊)を入れたので、その上に撥水剤を塗ってもにじまず成功。
これで、この模様の製作手順確立。
▼下部は、透明釉による模様。
思いついた時はドキッとしたのに、窯出しでご対面した時はドキッとはしなかった。
ほんのりと言えば、ほんのりと言えなくもない。
うるさいと言えば、うるさいと言えなくもない。
微妙な出来。
でも、うまく描けない。
だから、ライフワークぐらいのつもり。
▼写真は、下記を終えた蛸唐草。
①エンピツで下書き
②陶画用ゴム液(薄いピンク色)を塗る
③ゴムの周りに撥水剤(青色)を塗る
▼これから、ゴムを剥がして、そこに京呉須を流し込む。
ゴムの跡(薄いピンク色)が青くなり、
撥水剤(青色)は本焼きで飛んで白くなる。
▼面倒だけど、ゴムは意図しない輪郭を作ってくれるので、お気に入りの手法のひとつ。
気に入らなくて消しゴムで消した。
偶然できた消し跡が気にいる。
でも、適当に消したもんで、気に入ったのは一部分。
▼という事で、もう一度挑戦したのが写真。
だめだ気に入らない。
またやり直そう。
もう煮詰まったので、後日。
p.s. 偶然性に頼りすぎず、マスキングを使うか。
模様は、カップの上部だけとした。
すると、下部が物足りなく感じた。
▼②簡単に思い浮かぶ模様は、上下がマッチしないものばかり。
そして、本日思いついた。
上の模様を透明薬で浮かばせる案。
さっそくエンピツで下書き。
▼③これは、黒御影に透明釉で模様を描く試作品。
蚤の市での評判は上々だった。
この手法を②に適用したら、白い土の場合は、透明釉の線がほんのり浮かび上がるのでは?
▼ほんのり出たら、お洒落では。
失敗でも、成功でもアイデアが出た時は、心高鳴る。
それは、学生の頃に練習問題で解を導き出して、答え合わせをする前に似ている。
インパクトがあった。
それは、マジンガーZの敵役の”あしゅら男爵”
▼その影響か?
左右を2色で塗り分ける事が結構多い私。
写真は、飴釉、ルリ釉薬の2色。
回転させると、印象が変わるのも面白い。
上下に模様を入れる範囲を描いて、
その中に花びらみたいな文様。
▼描ける範囲は帯状で狭い。
よって、線描は途中で切れる。
これがいい感じ。
模様が広がるような感じがして。
▼ マイ・フェイバリット・パターンズになりそうな気がする。
(マイ・フェイバリット・ソングスを真似てみた)
(むむ、個展のサブタイトルにいいかも)