
3月1日(日)、第1回奄美大島検定があった。
-奄美の「宝」である自然や文化について学び、奄美の魅力を紹介できるように、観光に対する知識を身につけよう-
ということで、最近全国的に流行っている「ご当地検定」の奄美版。
「
奄美しちもんにゃ?」というクイズ本の問題などを参考にして作られた奄美大島に関する問題に挑戦し、正答率7割以上の合格者には「マスター」の資格が与えられるというものだ。
「奄美しちもんにゃ」の本も大好きで、クイズと言えば飛びつく長女と2人で挑戦した。
こちらの記事にもある通り、この検定に関しては地元紙には載っていたものの、ネット検索してもまともな情報がヒットしない。申し込み時にもらったプリントが見つからず、「何時からだっけー?」と思ってもわからないし、そもそもそんな試験があることがネット上でわからないのは困った。
(お陰で、何がなんでもプリントを探さねばならず、家がちと片付いた。...で、見つかった^^;;)
昨日の新聞を見ると名瀬会場と瀬戸内会場、全部で133名受験者がいたそうだ。
地元紙に何度か紹介されていたので、受験者は結構集まったものの、試験会場を見渡すと、私よりもさらにご年配とお見受けする方々が受験者の大半。「しちもんにゃ?」の本は子供向けにも書かれているのに、若い受験者は本当に少ないなぁと思った。もうちょっと小中学生がいるかな、と思ったのに...。
「ドキドキしますねー。」「試験受けるのなんて、ン十年ぶりですからねー。」なんて隣の人と話しながら開始を待つ。
1週間前に、「事前研修」なるものがあった。「受けたほうが有利ですよー。」と申し込みの時に市役所の紬観光課の人に言われたのだが、夜だったので参加できず。
そこで配られたと思われる本を直前まで広げて勉強している人がたくさん。わ~受験会場っぽーい。
やっぱり事前研修受けておいたほうがよかったかな?
でも、問題用紙を配られるとすぐに、あれほど「時間まで開けないで下さい。」と言われていたのに開いて注意されるおじさんあり。こういうところは、受験といっても入試などと違ってピリピリ感はなく、和む(^^)
さて、問題は三択式の50問。
第1問。奄美大島の祭り「八月踊り」に欠かせない楽器・クサビ締めの太鼓を何と呼んでいるか。
①チヂン ②サンバラ ③ティル
なぁんだ!簡単♪ なんて始めていったが、
『奄美大島の中心地として発展した名瀬市(当時)の人口が、最も多かったときの国勢調査における人口は、何人であったか。』
5万人くらいいた、ということは知っていたが、選択肢は
①49,021人 ②49,765人 ③49,962人
...って、これみんな「5万人くらい」じゃ~ん... (~_~) こういうときは勘でエイッ!
マングローブの植物や鳥の話題から、島の方言に伝統行事、そして名越左源太に島尾敏雄、幅広い分野の問題が出ていた。
(※上の問題の答えは①チヂンと②49,765人)
「しちもんにゃ」の本は、漢字にふり仮名がついているのだが、試験にはそんなものがないので長女は漢字にかなり苦労したようだ。
でも、しちもんにゃからの問題もたくさん出ていたし、三択だった上、時間もたっぷりあったので、全て解答して会場を出た。
問題用紙は持ち帰ってよく、会場を出るとすぐに受付で詳しい解説付きの模範解答も下さった。
待ちきれず、駐車場ですぐに自己採点。
私は...いっぱい間違えているが合格ラインが7割と低いので、なんとかなりそう?!
でも娘は、「何て書いてきたか、ちゃんと覚えてない。」
あのねー、問題用紙も持ち帰っていいって最初に言われたんだから、こういう時はそこにちゃんと自分の答えを書いておくものよーと説教しつつ記憶をたどると、こちらはなんとも微妙なライン。こりゃ、結果がくるまでわからんなー。
=========================
すると昨日、なんと試験の翌日だというのに、もう結果が来た!
当日じゅうに、採点、結果の印刷、そしてそれをポストに入れて下さったとは、島では考えられないスピーディーな運び!
ドキドキしながら封筒を開けると...

我が家に合格通知2枚!
いやぁ~ これは嬉しかった♪
でも、今朝地元紙見たら、133人中128人合格したそうな(^^;;
合格してよかったーというよりは、落ちなくてよかったーというべきか。
次のステップであるグランドマスターはもっと難易度をあげるかも?などと新聞にはあったけれど、難易度というより合格ラインを上げた方がよいのかも?だって3択式で合格ラインが7割ということは、実質的には6割わかればよいということだ。わからなかった残り4割の3分の1は「当たる」わけで、それで7割越えだもんねー。
それにしても、奄美のことで知らないことがまだまだ山のようにあるなぁと親子で改めて実感。またこれからも、歩きまわって、本も読んで、たくさん勉強しようと思った楽しいひとときだった。
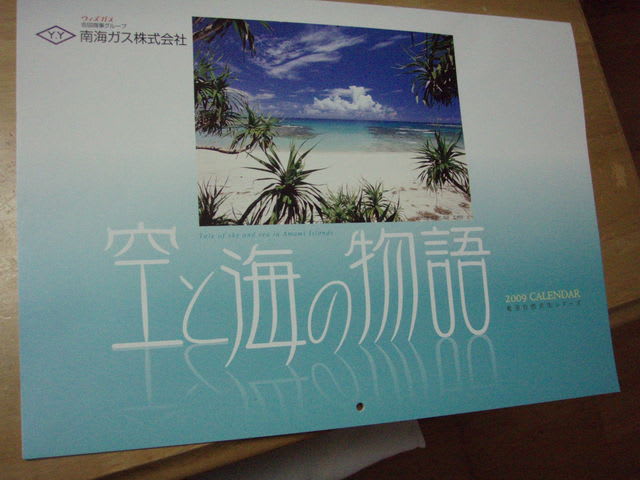 ポストに、来年のカレンダーが入っていました。
ポストに、来年のカレンダーが入っていました。 ですが、これは浜田太さんのカレンダーでした。
ですが、これは浜田太さんのカレンダーでした。












 )や、クイズ本のように簡単で面白いものの断片的なものだったりで、簡単に、ざーーーっと奄美の歴史を学べるものはないかなぁと日々探していますが、見つけました!
)や、クイズ本のように簡単で面白いものの断片的なものだったりで、簡単に、ざーーーっと奄美の歴史を学べるものはないかなぁと日々探していますが、見つけました!





 タン
タン 」
」


 四月も後半になり、毎日汗ばむほどの陽気になってきたので、先日、息子の頭を刈った。
四月も後半になり、毎日汗ばむほどの陽気になってきたので、先日、息子の頭を刈った。



