~まずは「あまみこ物語」~


うちの駐車場に咲いています。左の白い花は何かな...。右はリュウキュウコスミレです。スミレの方は、先月くらいから咲き始めこれから増えていきます。
えーと、新聞なら「本文と写真は関係がありません。」と載せられちゃうところでしょうが、今の時期にこういうお花が見られる奄美が大好きです。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
奄美に来た時から、何と表現したら良いかわかりませんが、何かとても不思議な感覚に囚われました。
外国に来たような新鮮な驚きと、幼い頃の時代・昭和に戻ったような懐かしい感じと。遅れているとかそういう意味ではなく、風景とか人とか、うまくいえませんが、でもやっぱり表現すれば「懐かしい」です。
「奄美」というものを全く知らなかったので、なんだか毎日が発見の連続というか...。
そして、その複雑な歴史もだんだんと知るようになったのですが、知れば知るほど興味深く、しかし難しく。好奇心が刺激されて楽しく、でも自分の無知と記憶力の無さが悲しく。
奄美のことを知りたい、といろいろな本を手に取ったりしますが、とても細かくて私のようなものではまさに「格闘」しないといけないもの(そしてたいてい敗北

)や、クイズ本のように簡単で面白いものの断片的なものだったりで、簡単に、ざーーーっと奄美の歴史を学べるものはないかなぁと日々探していますが、見つけました!
(前置きが長すぎ

)
奄美小学校のホームページにある「
あまみこ物語」。
これは私レベルでも、よくわかる!(脳が小学生レベルであることの証明か?!)
子ども向けに書かれているので表現が平易ですし、「奄美の歴史」については、その前の目次から入れてもたったの38ページです。
日本書紀の時代の日本と奄美の関わり、なぜ「あまみ」なのか、琉球・薩摩の関わりなどなど、あぁこうやって噛み砕いて書いて下されば私にもわかったのよーと思うことばかりです。
全国どこにでもありそうな、「みどり公園」だって、奄美の場合はそんじょそこらの「みどり」じゃなかった。
「屋仁川」(やんご)といえば、今は奄美ではイコール「飲み屋街」ですが、大間違い。
「御殿浜」と書いて「うどんばま」と読むあそこは、どんな殿様が来たのかしらんと思っていましたが、そういうことだったのか...。
...相も変わらず「へぇ」を連発しながら読み返しています。
これは学校ではどのように活用されているのかわかりませんが、(多分これに割く時間など、今の小学校にはほとんど無いのでしょうね)簡単とはいえ、ちょっと小学生には難しいかもしれません。
まずは、先生方に読んでもらいたいと思いました。
全国の人は私も同様だったように、奄美の歴史というのを全く知らないでしょうが、本土鹿児島の人でさえ同様です。習わないのだと思います。知っているのは、歴史好きな一部の人だけのようです。実際、娘の教科書にも、薩摩藩の圧制のことなどありません。今更、同じ県内でそのようなことがあったというのを蒸し返さないほうがよいという配慮なんでしょうか。
もっとも、4年生では日本の歴史というのを習っていないので、いきなり奄美の歴史から入ってもわけがわからないので無理なんでしょうね。5-6年生になると、今度は全国のことを習うのでいっぱいになって、奄美に触れる時間が無いのでしょう。
奄美の学校の先生は、必ずしも奄美の人でなく、鹿児島本土から転勤でやってくる人が多いのです。先生方も「奄美の歴史」というものを、あまりご存知無いのだと思います。習ってこなかったんですから...。
だからまずは先生方に知ってもらいたい。そして奄美の子ども達に、鹿児島の子ども達に教えてもらいたい。
ゆくゆくは、奄美の歴史が日本の歴史の一部としてもう少し取り上げられていったらいいなと思います。今奄美が教科書に出てくるといえば、西郷さんが島流しされた先、ということぐらいですもんね。

奄美小学校の校長先生は、お名前から察すると奄美ご出身の方なんでしょうか。校長先生の業務のかたわら急にやってできることではないともいますが、長く研究してこられたんでしょうか。
前書きの部分にあるのが、まさに私が思っていたことです。奄美に関する著書や研究論文はたくさんあっても難しく、教科書では奄美の独自性はわからない-。
I部の歴史編については、あとがきを読むと、奄美の歴史といえばこの人という弓削政己氏や博物館館長の中山清美氏・ヤコウガイの歴史一人者の高梨修氏の協力ということで、平易ながらも本格派です。
「奄美ってそんなに他と違うの?」と思われた方、ハイハイ、これも何かのご縁です。
今夜からチビリチビリと歴史編を読んでみて下さいね⇒
こちら
 ...と、語る奄美パークのおじい...。
...と、語る奄美パークのおじい...。
















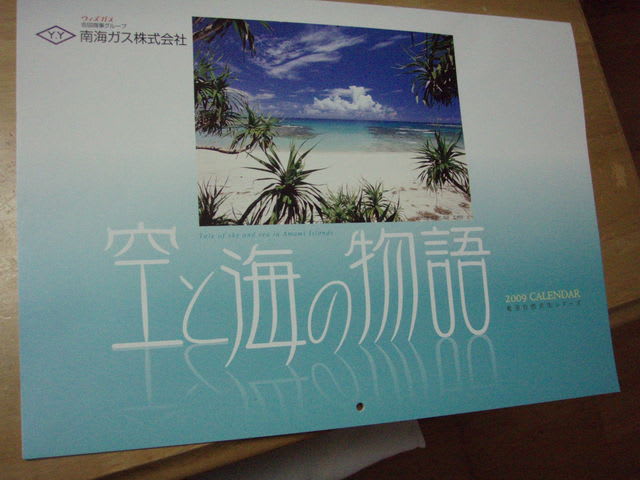





 )や、クイズ本のように簡単で面白いものの断片的なものだったりで、簡単に、ざーーーっと奄美の歴史を学べるものはないかなぁと日々探していますが、見つけました!
)や、クイズ本のように簡単で面白いものの断片的なものだったりで、簡単に、ざーーーっと奄美の歴史を学べるものはないかなぁと日々探していますが、見つけました!

 )
)
