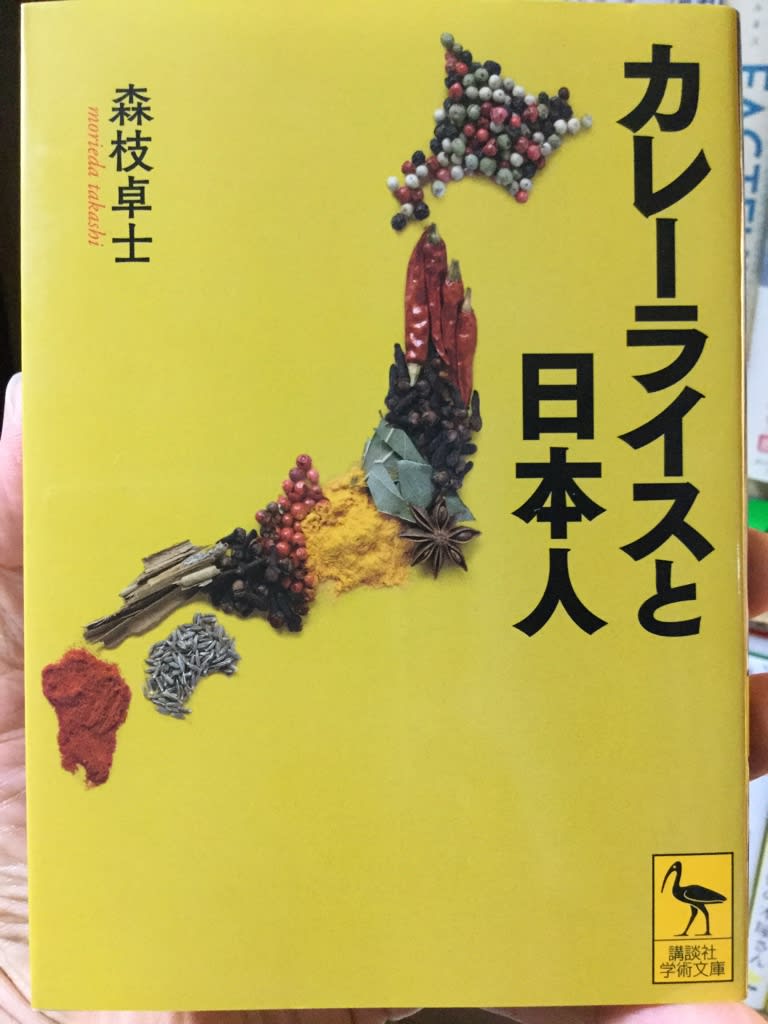
『カレーライスと日本人』
森枝卓士著、講談社(講談社学術文庫)、2015年
(原本は1989年に講談社現代新書として刊行)
一見小難しそうに見える本ばかりではなく、じつは食に関する書物も多い講談社学術文庫。子どもも大人もみんな大好きなカレーライスについての本も、2冊入っております。
一冊は、以前当ブログでご紹介した『カレーライスの誕生』(小菅桂子著)、そしてもう一冊が、今回取り上げる『カレーライスと日本人』です。1989年に講談社現代新書として刊行された元本に、その後の取材で明らかとなった事柄を盛り込んだ「補遺」と、カレーに関する書籍紹介を加えて文庫化したものです。1989年に現代新書版で出て間もない頃に買って読んで以来、30年ぶりの再読となりますが、あらためて興味深く、面白く読むことができました。
『カレーライスの誕生』が、豊富な文献資料をもとにしてカレーの日本伝来から現代までの歴史を辿った〝文献探究型カレー本〟だとするなら、東南アジアを中心に食文化についての取材を続けている写真家・ジャーナリストの森枝卓士さんによる本書は、いってみれば〝行動探究型カレー本〟。カレーのルーツを探るため、インドやイギリスへと足を運ぶなどの実地取材と検証から、カレーと日本人との関わりを探っていきます。
インドではさまざまな家庭を訪問して、実際にカレーが作られ、食されるところを取材します。そこでまずなされることは、マサーラ(スパイス)を調合して、石臼もしくはミキサーでそれらをすり潰すこと。インドにおいては、「どんなスパイスを選ぶか、どう調合するか、そしてすりつぶしぐあいといった一連の作業がもっとも重要なプロセス」なのだといいます。
使われるスパイスの量はかなり多いとはいえ(とある家庭では「店でも開こうっていうのかしら」と思うほどの多さだったとか)、それは辛さを強調するためではなく、あくまでも香りを強調するため。また、小麦粉でとろみをつけることもせず、「西洋料理のソースのようなものがからんだ肉や野菜の料理であるか、汁状のもの」のいずれかであって、日本のカレーと似ているか近いと感じられるものは見られなかったとか。これらのことから森枝さんは、インドのカレーは日本のカレーの御先祖様ではあっても、直系の親戚か祖先というより「昔は血のつながりもあったらしい」というほどのかなり遠い親族ではないか、と考えるに至ります。
それほどまでに違うインドと日本のカレー事情ですが、ためしにさまざまなインドの人々に日本式のカレーを食べてもらったところ、「味は悪くない」「美味しい」という反応が圧倒的だったそうな。なんだか妙にウレシイ話でありました。
日本で記録の残る最古のカレー調理法である、カエルの肉を使ったカレー(明治5年刊の『西洋料理指南』に出てきます)。その明確なイメージを掴もうと、当時のレシピを参考にしながら、カエルカレーを実際に作ったりするところも、まさしく〝行動探究型〟である本書の面目躍如です。カエル肉の入手にはずいぶん苦労したようですが(結局は川魚専門店で入手)、味のほうは「まずいものではなかった」とのこと。このカエルカレー自体、インドというより英国、ヨーロッパの流れを汲んだ〝西洋料理〟としてのカレーを日本化したものであるといいます。
日本におけるカレーの歴史を辿った記述で興味深かったのは、明治31年に出された『日本料理法大全』という、文字通り日本料理のオンパレードである書物の中にも、カレーの作りかたが登場しているということ。かなり早い時期から、カレーはれっきとした「日本料理」だったわけなんですねえ。
本書の後半では、カレーが「日本料理」として受容されていった理由についての考察がなされます。国を根底からゆるがすような歴史的大転換が、この一世紀ほどの間に集中する中で勢いのあった日本の国民が、外に対して開放的になり何でも受け入れていく時期に、カレーもまた受容されていったのでは・・・などと。
森枝さんは、日本料理の代表のようにいわれるテンプラや寿司も、そのルーツを辿れば外国へと行きつくことを指摘して、外国からさまざまなものを受容しながら独自に発展させていく日本文化のありようを評価し、次のように述べています。
「テンプラや寿司は日本料理で、カレーやコロッケはちがうという発想にみなおちいりがちだ。しかし、それはちがうということである。偏狭な国粋主義では何もみえてこない。テンプラやカレーも同じ次元で考えなくてはならない。ここまでみてきたカレーの物語が、ほかの食べ物にも同じように存在したのではないかということである。そういった意味では、カレーが日本で受け入れられたことは、それほど大変な変化ではなかったということではないだろうか」
国単位の狭い視野で見るのではなく、海外から伝わったことも受け入れながら発展していった過程に目を向けることで、日本の食の世界はより一層豊かな形を持って見えてくるのではないか・・・そんなことを教えてくれる一冊であります。
【関連おススメ本】
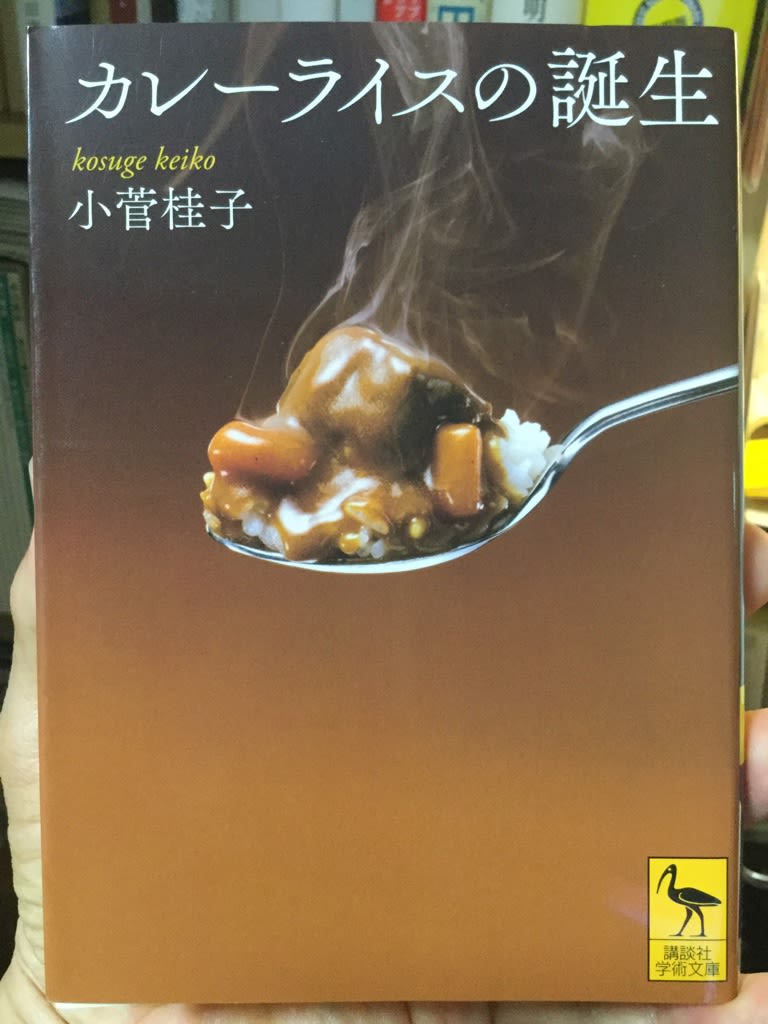
『カレーライスの誕生』
小菅桂子著、講談社(講談社学術文庫)、2013年(原本は2002年に講談社選書メチエとして刊行)
講談社学術文庫のもう一冊のカレー本であり、学術文庫版『カレーライスと日本人』巻末のカレー関連書籍紹介でも触れられているのが、こちら。日本最古のカレーレシピであるカエルカレーについてのお話を含めた、日本におけるカレーの歴史が網羅的に記されていて、とても勉強になります。当ブログのレビューはこちらを。→ 【読了本メモ的レビュー】『カレーライスの誕生』



















