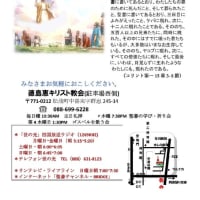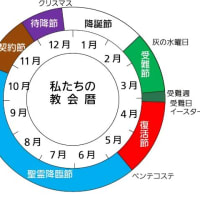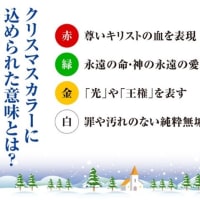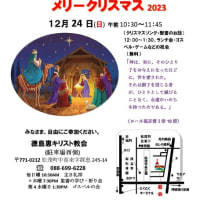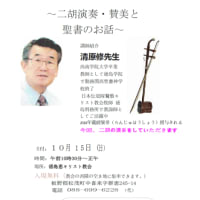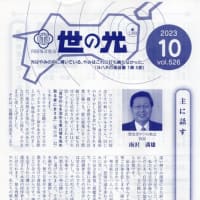【 ヨハネ福音書21章1-17節】
21章は付録の部分と言われます。書き足りなかったことを示されて追加されたのです。奇妙なことは二度も復活の主に出会ったのに、ガリラヤに帰って、琵琶湖の4分の一ほどのなつかしい湖で漁をしていることです。
もしかしたら、主の復活の噂を聞いても信じられずにエマオの村に急いだあの二人の弟子のように、エルサレムにいる危険性を覚えて逃げる思いで里帰りしたのかもしれません。
ペテロは主に出会ったはずですが、それでも確信が持てなかったと考えることもできます。本名は、風に揺らぐ「葦」の意味で、すぐ信じても、次の瞬間は疑うという弱さを持っていたようです。
主に倣って水の上を歩んでも、波を見て恐ろしくなりズブズブ沈みかけたこともありました。一番弟子を自負しながら十字架を前にした主を知らないと三度も裏切りました。
復活は人間の世界や経験を超えた、創造主の世界ですから容易には理解できません。
ヤゴは水中で生まれ育ち、やがて空中に挙げられて翼をもつトンボになりますが、水の中にいる限り陸のことはわかりません。
多分半信半疑の思いの弟子たちは、以前からの漁に戻りました。いつどこに網を降ろしたら、網にかかるか、長い経験で知っていました。しかし、一晩労苦しても一匹の魚も獲れません。
夜が明け始めて岸辺に立つ誰かが「子たちよ、獲物はありませんね」、「船の右側に網を降ろしてごらんよ。」と叫びました。
その声に従ったところ、おびただしい数の魚が網にかかりました。
主はずっと岸辺で見守っておられたのだと現在完了形で記されています。
復活の主は、いつでもどこでも共にいてくださるのですが、弟子たちは世と自分の働きだけに夢中になって、一番大切な方をすっかり見失っていたのでした。
私たちも自力だけに頼って、内住の聖霊様を軽視すると、霊の目が曇り仰ぐべき復活の主を見落としてしまいます。
この弟子たちの経験は、やがて主の働きをすることになる、伝道と牧会の教訓でもありました。
神からご覧になると、この世界はご自分から離反し霊的に死んだ状態です。
ガリラヤ湖は地中海よりも水位が低く、盆地の中にありますから、突風が吹いて大荒れになると非常に危険になりました。
そのような死の海から、引き揚げて救い出すのが伝道であり、救いであります。ヨナは大魚の胃の中で僅かな酸素を吸ってかろうじて生き延びましたが、水中では呼吸できませんから窒息死します。
息(ルーアッハ)がないと肉体が死滅するように、神の息がないと霊的に生きてゆけません。
「人間をすなどる漁師にしてあげよう」(マタイ4・5)と、かつて主は約束されましたが、それは罪と死に沈んでいる人々が悲惨な闇の淵から引き揚げられて、聖霊の息吹によって霊のいのちによみがえる働きにたずさわることを意味します。新生(神生)して永遠の神の子にされるのです。
そして主はパンと魚で共に食事をされました。
神との交わりのなかで、神の子は成長(聖化)します。人間としての誕生と成長があるように、神の子は聖霊によって生まれ、聖霊によって成長して主の働き人にされます。聖霊によって新生したのですから、聖霊によって聖化されます。聖霊は、十字架の贖いの血を通して私たちの不信仰と罪を絶えず洗い清めて、主との永遠の交わりに導かれます。三度、主はペテロに「私を愛するか」と語られます。シモンからペテロ(岩)に改名されたのは、信仰告白による新生のときでしたが、自分に失望し悲しむことによって、かえって主を仰ぎそのみ言葉に頼りはじめたときに文字通りゆるぎない羊飼い、牧者として建てられてゆきました。