http://www.k-kawasaki.info/2010/02/201023.html
の引用です。
「国際科学振興財団TRACE研究プロジェクト幹事・今井弥生氏は、ルベン・アルカレイ編『ヘブル・英語大辞典』(Reuben Alcalay"The Complete Hebrew-English Dictionary")で、学んだことをもとに、ヘブル語と日本語の類似性に関する膨大なリストを公表している。
そして、その中でこう述べている。
「日本語の中心にあるヤマト言葉は主として、ヘブライ語の単語により、ウラル・アルタイ系(古代朝鮮語やツングース系)の語順に当てはめて形成されている。」 (『日本語の起源に関する調査研究報告書』国際科学振興財団内、日本語の起源研究会発行) 」
今井氏は「日本語の起源に関する調査報告書」というタイトルで1995年5月に68ペ-ジに及ぶ研究報告を財団法人国際科学振興財団「日本語の起源研究会」で発表されました。
氏は川守田英二によるヘブル語と日本語の研究を評価しつつ、ウラル・アルタイ系の言語との合成という仮説を提起している。
「文法の異なる言語の混成語」において
「インドやイランの言葉やイ-ディッシュ(ドイツ系ヘブライ語)、ラディ-ノ(スペイン系ヘブライ語)のように、民族の移動に伴い、文法のまるで異なる混成語の研究にも力を入れるべきで、まさに、日本語の場合、そのような視野で見る時、日本語の起源が解けてくる。混成語の例として、インドの古語サンスクリットは、先住民のドラヴィダ人の言語の形に、移動してきて先住民を征服したア-リア人の言語が主として入り、合成されて自然発生的に形成されていった言語である。インドのドラヴィダ語、サンスクリット、ペルシャ語、シュメ-ル語等は大雑把にいえば、日本語のように、ウラル・アルタイ系の言語と同じような語順をしている。それなのにサンスクリットは、インド・ヨ-ロッパ言語と呼ばれ、ヨ-ロッパ系統の言葉の仲間入りで分類されている。それは、中身の単語がヨ-ロッパ起源のものが多いためである。その意味では、日本語は、日本・ヘブライ語と呼んで分類し得る。日本語の中心にある大和言葉は主として、ヘブライ語の単語により、ウラル・アルタイ系(古代朝鮮語やツング-ス系)の語順に当てはめて形成されている。」と述べ、以下のように推察されています。
「B.C.700年ごろ古代南ユダより東の果ての海の島々をめざして、移住してきた一団の人々は、通って来た国々の言語の単語も少しづつ取り入れたとみられ、様々の国と少しづつ同じ単語が(身体語等)日本語に入っている。ユダヤ→イラン→インド→河南(ビルマ語系)→日本先住民族 →漢字→オランダ語・ポルトガル語→英語等、(河南ビルマ語系統の身体語、数詞、代名詞、植物名等)。」

















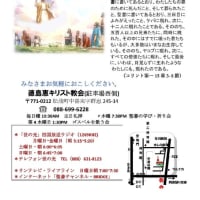
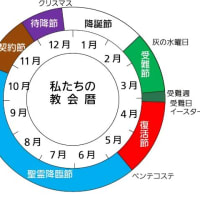
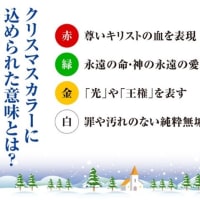







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます