一昨日の水曜日、再び川内村に行ってきました。
第2回 「川内村若者ふるさと再生検討会」 です。
第1回のときは福島民友新聞が記事に取り上げてくれました。
あのときは検討会そのものの時間は45分くらいしか取れなかったのですが、
それでもいくつか皆さんから大事な論点を出してもらうことができました。
今回は平日夕方からの開催で、会の終了後には懇親会も予定されていましたから、
たっぷり時間を取って話し合うことができました。
場所は、「いわなの郷」 の 「幻魚亭」。
「いわなの郷」 は釣り堀や体験交流館、コテージなどがある、
川内村のなかで現在稼働している数少ない観光スポットのひとつです。
この日も釣り堀に来ている人はけっこういましたし、
週末になると多くの人が県内外から訪れているそうです。
そのなかにあるお食事処で、座敷で膝付き合わせるアットホームな形で検討会は催されました。
会の冒頭、参加者の方から 「そもそもこの検討会は何を目指しているのか?」、
「いったい何をどこまで話し合えばいいのか?」 という厳しい問いかけがあり、
座長である私がたじたじとなるなか、参加者のなかのひとりの方が中心となって、
むしろ座長役を乗っ取られるような形で話し合いは進んでいきました。
座長は何をやってるんだという感じですが、私にとってはむしろこのほうが好ましいことで、
川内の若者の皆さんが自ら主導しながら、さまざまな問題が語り合われました。
話は多岐にわたりましたが、例えば、未だに避難している村民の皆さんや、
川内村の外部の人たちに対して、今の川内の様子や生活、リアルタイムな情報などを伝える、
手作りの情報発信を、行政ではなく自分たちの手で行っていったほうがいいのではないかとか、
子どもたちが思いっきり外遊びできる公園や施設を作ってもらえないかとか、
若者たちや村外避難者が率先して参加できるようなイベントを企画できないか等、
自分たちでもできそうなことから、けっこう大がかりなプロジェクトまで、
さまざまなアイディアが出されました。
あと1、2回の予定ですが、おそらく実現可能な案がまとまりそうな気配でした。
検討会終了後、同じ 「幻魚亭」 でいわな料理などを頂きながら懇親会を行いました。
川内村の若い人々と一緒に飲めるということで私はけっこう期待していたのですが、
会場に近づくにつれて、みんなここにどうやって来てどうやって帰るんだろうかと、
ちょっと心配になっていた私の予感はみごとに当たり、
参加者全員クルマで来ているので、誰もアルコールを飲むことはできず、
けっきょく飲んだのは私と県職員の方2名だけでした。
皆さんはシラフで、私はビールを遠慮しながらいただきつつ、
岩魚をはじめとする地の料理に舌鼓を打ち、
すっかり打ち解けたみんなのぶっちゃけ話に酔い痴れたのでした。
解散後、旅館に着いてからは、県職員の方々と軽く反省会と言いながら、
けっきょく黒霧島を一本、熱燗を四合、越の寒梅をグラスで一杯空け、
日が変わるまで川内と福島の未来について語り合ったのでした。
翌朝はすっきり目覚め、朝食と朝風呂をいただいたあと、
川内村のいくつかの施設を回ってきました。
役場では福島大学うつくしまふくしま未来支援センターのサテライトに顔を出し、
その後、野菜工場 「KiMiDoRi」 を訪問しました。
こちらは川内村がこの春に誘致したばかりの株式会社で、
無菌の工場内でLEDなどの人工光を使って野菜を育てています。
まさに野菜工場です。
各種のレタスをはじめとして30種くらいの野菜を栽培しているそうです。
中をちらっと見せていただきましたがこんな感じです。

青と赤のLEDを使っていて工場内全部、紫というかピンク色の感じです。
原発事故のおかげで農業が大打撃を受けた福島において、
ちょっと寂しい感じもしますが、今後はこうした形での農業の再生もありうるのかもしれません。
「KiMiDoRi」 の若手社員の方も今回の検討会に参加してくださっていますので、
会にこちらで採れた野菜を差し入れしてくださいました。

これは私がお土産にもらってきたもので、右側はフリルレタス、
左側は数種のレタスの詰め合わせパックです。
無菌の栽培室で農薬も使わず育てられていますので、このまま洗わずに食べられます。
続いて 「かわうち保育園」 におじゃましました。
こちらの保育士さんも検討会のメンバーに加わってくださっています。
着いた瞬間、園庭の広いことに感銘を受けました。


よく考えてみると幼稚園って行ったことありますが、保育園って初めてです。
保育園ってどこでもこんなの広いわけじゃないんですよね?
私の見た感じ、規模のデカイ幼稚園って感じでした。
保育園は幼稚園と違って外遊びなどできない施設なのかなと思っていましたが、
ここはそんじょそこらの幼稚園なんか太刀打ちできないほどの敷地を有しています。
夏になると草むしりが大変と保育士さんが嘆いておられました。
ちなみに線量は0.136μSv/h。
福島大学と変わらないレベルです。
建物はこちら。

震災前は60人以上の子どもたちがこちらに預けられていたそうですが、今は10人。
でもみんな元気に歌を歌ったり体操をしたりしていました。
ここがまた子どもたちの元気な声で一杯になることを期待したいと思います。
続いて向かったのは廃校になった小学校跡地です。
校庭は草が伸び放題、校舎もさびれた感じです。

その右手に体育館がありました。

ここが現在は、「手づくり家具工房 ニングル」 になっているのです。
こちらも昨夏に川内村に進出してきた企業です。
廃校となった小学校の体育館をそのまま使って工場としました。

奥には入学式、卒業式用の演台もあってまさに体育館です。

バスケットゴールもそのままです。
そんななかに巨大な工作機具を置いて家具づくりに精を出しておられます。

先ほどの 「KiMiDoRi」 といいこちら 「ニングル」 といい、
川内村の窮状を知ってわざわざ進出してきてくださった企業です。
こちらの工場長さんも検討会のメンバーに加わってくださっています。
人を増やしたいのに住宅が不足していて人を呼ぶことができない、
という問題を前回指摘してくださったのも、こちらの工場長さんでした。
川内村に生まれ川内村に戻ってきた若者たち、
企業進出等に伴い新たに川内村に入ってきた若者たち、
彼らみんなの意見を汲んで、川内村の再生に向けてほんのわずかでも、
なにか新しい提案をしていくことができたらいいなと思いつつ、
二度目の川内村を後にしたのでした。
第2回 「川内村若者ふるさと再生検討会」 です。
第1回のときは福島民友新聞が記事に取り上げてくれました。
あのときは検討会そのものの時間は45分くらいしか取れなかったのですが、
それでもいくつか皆さんから大事な論点を出してもらうことができました。
今回は平日夕方からの開催で、会の終了後には懇親会も予定されていましたから、
たっぷり時間を取って話し合うことができました。
場所は、「いわなの郷」 の 「幻魚亭」。
「いわなの郷」 は釣り堀や体験交流館、コテージなどがある、
川内村のなかで現在稼働している数少ない観光スポットのひとつです。
この日も釣り堀に来ている人はけっこういましたし、
週末になると多くの人が県内外から訪れているそうです。
そのなかにあるお食事処で、座敷で膝付き合わせるアットホームな形で検討会は催されました。
会の冒頭、参加者の方から 「そもそもこの検討会は何を目指しているのか?」、
「いったい何をどこまで話し合えばいいのか?」 という厳しい問いかけがあり、
座長である私がたじたじとなるなか、参加者のなかのひとりの方が中心となって、
むしろ座長役を乗っ取られるような形で話し合いは進んでいきました。
座長は何をやってるんだという感じですが、私にとってはむしろこのほうが好ましいことで、
川内の若者の皆さんが自ら主導しながら、さまざまな問題が語り合われました。
話は多岐にわたりましたが、例えば、未だに避難している村民の皆さんや、
川内村の外部の人たちに対して、今の川内の様子や生活、リアルタイムな情報などを伝える、
手作りの情報発信を、行政ではなく自分たちの手で行っていったほうがいいのではないかとか、
子どもたちが思いっきり外遊びできる公園や施設を作ってもらえないかとか、
若者たちや村外避難者が率先して参加できるようなイベントを企画できないか等、
自分たちでもできそうなことから、けっこう大がかりなプロジェクトまで、
さまざまなアイディアが出されました。
あと1、2回の予定ですが、おそらく実現可能な案がまとまりそうな気配でした。
検討会終了後、同じ 「幻魚亭」 でいわな料理などを頂きながら懇親会を行いました。
川内村の若い人々と一緒に飲めるということで私はけっこう期待していたのですが、
会場に近づくにつれて、みんなここにどうやって来てどうやって帰るんだろうかと、
ちょっと心配になっていた私の予感はみごとに当たり、
参加者全員クルマで来ているので、誰もアルコールを飲むことはできず、
けっきょく飲んだのは私と県職員の方2名だけでした。
皆さんはシラフで、私はビールを遠慮しながらいただきつつ、
岩魚をはじめとする地の料理に舌鼓を打ち、
すっかり打ち解けたみんなのぶっちゃけ話に酔い痴れたのでした。
解散後、旅館に着いてからは、県職員の方々と軽く反省会と言いながら、
けっきょく黒霧島を一本、熱燗を四合、越の寒梅をグラスで一杯空け、
日が変わるまで川内と福島の未来について語り合ったのでした。
翌朝はすっきり目覚め、朝食と朝風呂をいただいたあと、
川内村のいくつかの施設を回ってきました。
役場では福島大学うつくしまふくしま未来支援センターのサテライトに顔を出し、
その後、野菜工場 「KiMiDoRi」 を訪問しました。
こちらは川内村がこの春に誘致したばかりの株式会社で、
無菌の工場内でLEDなどの人工光を使って野菜を育てています。
まさに野菜工場です。
各種のレタスをはじめとして30種くらいの野菜を栽培しているそうです。
中をちらっと見せていただきましたがこんな感じです。

青と赤のLEDを使っていて工場内全部、紫というかピンク色の感じです。
原発事故のおかげで農業が大打撃を受けた福島において、
ちょっと寂しい感じもしますが、今後はこうした形での農業の再生もありうるのかもしれません。
「KiMiDoRi」 の若手社員の方も今回の検討会に参加してくださっていますので、
会にこちらで採れた野菜を差し入れしてくださいました。

これは私がお土産にもらってきたもので、右側はフリルレタス、
左側は数種のレタスの詰め合わせパックです。
無菌の栽培室で農薬も使わず育てられていますので、このまま洗わずに食べられます。
続いて 「かわうち保育園」 におじゃましました。
こちらの保育士さんも検討会のメンバーに加わってくださっています。
着いた瞬間、園庭の広いことに感銘を受けました。


よく考えてみると幼稚園って行ったことありますが、保育園って初めてです。
保育園ってどこでもこんなの広いわけじゃないんですよね?
私の見た感じ、規模のデカイ幼稚園って感じでした。
保育園は幼稚園と違って外遊びなどできない施設なのかなと思っていましたが、
ここはそんじょそこらの幼稚園なんか太刀打ちできないほどの敷地を有しています。
夏になると草むしりが大変と保育士さんが嘆いておられました。
ちなみに線量は0.136μSv/h。
福島大学と変わらないレベルです。
建物はこちら。

震災前は60人以上の子どもたちがこちらに預けられていたそうですが、今は10人。
でもみんな元気に歌を歌ったり体操をしたりしていました。
ここがまた子どもたちの元気な声で一杯になることを期待したいと思います。
続いて向かったのは廃校になった小学校跡地です。
校庭は草が伸び放題、校舎もさびれた感じです。

その右手に体育館がありました。

ここが現在は、「手づくり家具工房 ニングル」 になっているのです。
こちらも昨夏に川内村に進出してきた企業です。
廃校となった小学校の体育館をそのまま使って工場としました。

奥には入学式、卒業式用の演台もあってまさに体育館です。

バスケットゴールもそのままです。
そんななかに巨大な工作機具を置いて家具づくりに精を出しておられます。

先ほどの 「KiMiDoRi」 といいこちら 「ニングル」 といい、
川内村の窮状を知ってわざわざ進出してきてくださった企業です。
こちらの工場長さんも検討会のメンバーに加わってくださっています。
人を増やしたいのに住宅が不足していて人を呼ぶことができない、
という問題を前回指摘してくださったのも、こちらの工場長さんでした。
川内村に生まれ川内村に戻ってきた若者たち、
企業進出等に伴い新たに川内村に入ってきた若者たち、
彼らみんなの意見を汲んで、川内村の再生に向けてほんのわずかでも、
なにか新しい提案をしていくことができたらいいなと思いつつ、
二度目の川内村を後にしたのでした。










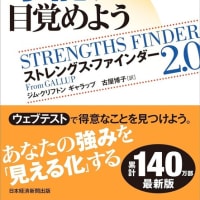









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます