(本稿は掲示板書き込みのコピペです。後日整形します)
「天津飯の謎」 投稿者:管理人 投稿日:2018年12月 2日(日)16時36分43秒
そうそう。昨日は同期生から著書をいただいたのでした。

自費出版本で(文春新書みたい!)、彼がのたまうに、天津飯という料理が本場中国にはないことは知っていると思う(>知りませんでした)(汗)。その名前の由来についてはネットでもあまた説が出ているが、全部間違いである。本書はそれを質し、ある仮説を提出したもの、とのこと(^^;
面白そう(^^)。『ランドスケープと夏の定理』を読み終わったら、さっそく着手しようと思います!
Re: 「天津飯の謎」 投稿者:雫石鉄也 投稿日:2018年12月 3日(月)09時59分32秒
この本、面白そうですね。
天津飯、確かに日本生まれだそうですね。
天津飯があんねんから、天津ラーメンもあってもええやろと
思って作りました。
https://blog.goo.ne.jp/totuzen703/e/50f562aaa6244c91fcba8d477da1319a
おいしかったですよ。
Re: 「天津飯の謎」 投稿者:管理人 投稿日:2018年12月 3日(月)19時12分53秒
雫石さん
>天津飯があんねんから、天津ラーメンもあってもええやろと
雫石さんのと同じかどうかわかりませんが、天津麺もうまいですよね。
ところで冒頭を下に掲げますが、著者の疑問はカツ丼みたく[材料+ごはん]という命名が一般的な中で、[米産地+ごはん]はいかにも不自然というのが出発点だったみたいですね。
そこで、雫石さんの書き込みの、天津麺(天津ラーメン)です。天津飯の「天津」が米産地から来ているのなら、天津麺は[米産地+麺]ということになり、まったく意味が通らなくなってしまいますよね(^^;
これは通説が誤りであることの強力な傍証になるのではないでしょうか。もしかしたら著者は気がついてないかもしれません。今度教えてあげようと思います!

あ、アマゾンに反映されていました→ 〔amazon〕
〔amazon〕
「天津飯の謎」に着手 投稿者:管理人 投稿日:2018年12月 8日(土)22時33分19秒
という次第で、『天津飯の謎』に着手しました。
冒頭です。
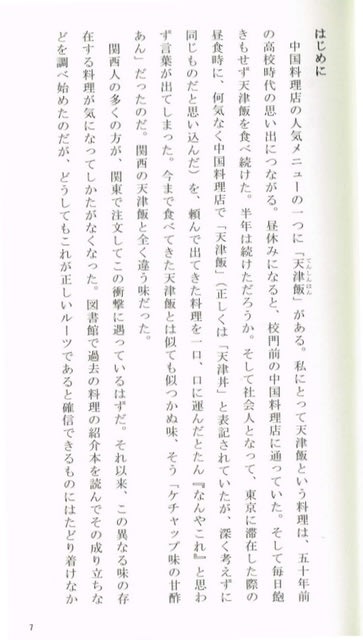
ちょっとびっくりしました。この店、私もよく利用していたのです。著者と一緒に行った記憶はありませんが、私も行けば必ず天津飯を注文していたと思います。
というか、この店ではじめて天津飯なる中華料理を知ったというべきでしょう。そのことについては、以前、当掲示板に書き込んだ記憶があり、検索したのですが発見できず。掲示板の欠点は検索性の悪さなんですよね。書き込みにおいて管理人と訪問者の差別がないところが気に入っていて、それでブログに移行せず使いつづけているのですが。
話が端からそれてしまいました。この店の天津飯がうまかったというのは、実は先日のクラブOB会でも出まして、してみますとこの中華店、よほど天津飯がおいしい店だったのかもしれませんね。
今はもう建物ごとありません。ゼロ年代にはまだ店はありましたが、営業していなかったかも。いずれにしろ、もはやその味を検証できないのです。残念です(^^;
さて本書ですが、天津産の小站米が輸入されていたかどうかを調査しています。この部分、本格的でして、事実上戦前戦後の日本の米輸入史といってよいほど。
結論だけいえば、ジャポニカ米である小站米は当時の天津近辺の在留日本人だけで消費されてしまって、日本本土に輸出する余分はなかったようです。逆に言えば、それだけ日本人が軍人民間人合わせて大量に北京天津辺に進出していたということなんでしょうね。
上田早夕里『破滅の王』で通州事件が描かれていましたが、現地の人にすれば、もともと有数の人口地帯に、大量の日本人の到来は、邪魔で邪魔で仕方なかったんだろうな、とこの事実からでも想像されます(満蒙開拓団も、実は満蒙の荒蕪地を自分らで開拓したのではなく、既に農耕地となっている土地の住民をそっちに追い出し、居座ったというのが事実で、おそらく通州辺りでもそういうことをしていたのだろうと思いますね)。
今でこそ米余りの日本ですが、実は戦後、昭和29・30年をピークに、昭和34年まで米は輸入されていたとのこと。多くは東南アジアからの輸入で、つまりインディカ米だったわけです。平成5年の米の緊急輸入でタイ米が嫌われて売れなかったことはいまだに記憶に新しいですが、わずか数十年で過去を忘れてしまう日本人の驕りは、ほんと、どうしようもないですね。
「天津飯の謎」(2) 投稿者:管理人 投稿日:2018年12月 9日(日)17時38分34秒
第二章は「天津飯は誰が作ったのか」。
まずウィキペディア記載の「発祥」の二説が、「記述の論理的検証」によって退けられます(まずウィキペディアの記述をお読み下さい)
「来々軒説」について、この記述中のどこにも、この料理に「なぜ天津という名前が付くのか」「この部分の説明がまったくない」ことを指摘する。たしかにこれでは説明になっていませんね。著者は親切にも「天津の根拠は前述の、米の名前から名づけられたということなのかもしれない」と好意的に推測しますが、たとえそうだとしても、天津から米が輸入されたことがないという著者の調査の結果から、この説は否定されます。
「大正軒説」についても、「天津の食習慣である「蓋飯」」という記述が疑われる。なぜなら江南ならぬ華北(河北)で「米食(飯食)」が習慣であった事実がないからです。かれらの主食は「米ではなくトウモロコシや小麦」なんですからねえ。
その派生として、華北内蒙古からの引揚者が、船待ちの天津で食べた料理説があり(たしか梅棹忠夫も天津から引揚げたと記憶しています。北満外蒙古からの引揚者はナホトカに集約されましたが。華北方面は天津がそういう港だったんでしょうね)、しかし著者は、困窮した引揚者にそんなものを食う金銭的余裕はなかったはずといいます。たしかに、「黒パン俘虜記」でも主人公はすべてを港で奪われ、着の身着のままでようやく乗船するのですし、配給される食事は(ロシアですから)黒パン。天津でも米作りはそもそも日本人農民が従事していたはずで、彼らも引揚げに大童で農耕などしているはずがない。配給されるのはアワとかヒエとかムギの携帯食で、というのは想像ですが、少なくとも米の白ご飯にかに玉をのせたあんかけ料理なんて夢のまた夢だったのではないでしょうか。てことでこの説もX。
「天津飯の謎」(3) 投稿者:管理人 投稿日:2018年12月 9日(日)23時19分48秒
いよいよ天津飯そのものに話は向かいます。
もっとも著者は常に「そもそも」から解き明かしていきますので、まずは「そもそも中国料理はいつから日本で食べられはじめたか」が調べられる。
当然江戸時代ということになります。鎖国日本は唯一長崎出島でオランダと通商していたわけですが、実はもう一つ窓口があり、それが中国貿易だった。同じ長崎に「唐人屋敷」が建てられ規模はオランダ人の出島より大きかった(年間5千人が利用した)。唐人屋敷ができる以前は船宿と呼ばれる民家に散宿していたので、日本人とも交流があり、そのときに中国料理が、まあ初めて伝えられたとされているようです(とはいえそれ以前に宣教師が「南蛮料理」を伝えています)。
しかし本格的に入ってきたのは開国後。各地にできた「居留地」にやってくる外国人は、実質中国(香港、広東、上海)からの貿易商人なので、それに付随して中国人が船乗りやコックとして(同時に漢字筆談できるので通訳として)やってき、居留地に隣接する土地に住みつく。最初は中国人向けの料理店だったのが、居留地が廃止(1899)されてからは一般日本人相手の店となる。「中華街」のはじまりですね。(強引に約めた要約です。きちんと知りたい人は本書で確認下さい)
「天津飯の謎」(4) 投稿者:管理人 投稿日:2018年12月10日(月)18時56分43秒
初期の中国料理店は、現在の梅田の新北京のような、大人数が円卓を囲み、宴会場として利用する体の店だったようで、1882年(明治15)開店の日本橋の偕楽園がその嚆矢だった。以降、続々と類似店が生まれたのですが、日清戦争勃発(1894年)で多くの中国人が帰国してしまう。
その結果、在留中国人向けではない、日本人むけの中国料理店が増加します。これらは宴会目的ではない、小規模な一般客相手の店です。たぶん現在日本各地津々浦々にある「中国料理」店をイメージすればいいのではないでしょうか。こうして中国料理が国民に広く知られるようになります。
さらに日清戦争が終結し、日本は台湾を獲得すると共に、天津や漢口、杭州、上海※などに日本人租界を認めさせたのでしたが(上海租界は日清戦争以前、南京条約で獲得)、空前の中国料理(支那料理)ブームが起こり、家庭で作られる料理となっていく。
そういう次第で、この時代は中国料理レシピ本が多く出版された。著者はそれらも調査していて、当時の中国料理レシピ本を見る限りでは、天津飯に当てはまる料理は紹介されていなかったとします。
「やはり天津飯は、戦前には存在せず、戦後に生まれたものかもしれない」
それでもなお、後の天津飯につながるものはないかと、「蟹」や「蝦」や「卵」を使った料理をピックアップします。
そのレシピが具体的に紹介されていますので、料理に興味ある方は、掲載のレシピにもとづいて、戦前日本における家庭むき中国料理を作って見られるのも一興かと思います(^^;
※追記。そういえば、日本人租界があった天津、漢口、杭州、上海って、広義に見ればいわゆる中華料理の大きな流派、北京料理・四川料理・広東料理・上海料理の原産地ですよね(^^;
「天津飯の謎」(5) 投稿者:管理人 投稿日:2018年12月11日(火)00時32分51秒
著者は一々のレシピを丹念に確認していくのですが、これは多分に著者の趣味ですね(>おい)。私は作るほうにはさほど興味がないのでその要約は割愛させていただきます。
結局、「明治の終わりから大正にかけて、既に蟹と卵を使う料理は、家庭料理として一般的な料理となっていたと推測される」のですが、しかしそれらはどうみても「オムレツ」の変種なんですね(ケチャップやソースをかけたりする)。
そこで著者は、この時代の蟹と卵を使う中華料理は、実は西洋料理の影響下に日本で生まれたのではないかと考えているようです。「西洋料理の支那化」
よくいわれるように、日本のカレーはインド料理の日本化です。同じことがここでも起こったのではないでしょうか。支那料理を日本風にアレンジするに際して西洋料理が利用されたのではないか。これは本書に(ここまでのところでは)明示的ではなく、私の想像であることをお断りするのですが(でも、著者もたぶん内心そう考えているように、私には読めるのですけどね)、もしそれが正しいとしますと、当時の本場の中国料理に、西洋のオムレツ的な料理があったのかなかったのか、それを確認しなければなりません。そこまで深入りする気はないので、今度著者に会ったとき訊ねてみようと思います(^^;
さて、大正14年に至りますと、ようやく「現在の「芙蓉蟹(フーヨーハイ)」として知られるレシピと、あんの有無以外は大変よく似ている」調理法が現れます。料理名も「芙蓉蟹」です。昭和2年発行の本にも紹介されており、「この頃にはよく知られた料理になっていたと思われる」。
さらにその10年後、昭和12年の本で紹介されている「芙蓉蟹粉」という料理は、卵焼きの上から「あん」のかかったもので、これは現在のそれに最も近いものになっていたようです。
「天津飯はどの料理の紹介本にものっていなかったが」「その具にあたる「芙蓉蟹」は多くの本で紹介されており、この料理は多くの人に広く知られた存在となっていたようだ」
以下更に考証は続くのですが、省略。ここでは、天津飯の具に当たる料理が大正末期には存在していたことのみ確認して、次に進みます。
「天津飯の謎」(6) 投稿者:管理人 投稿日:2018年12月14日(金)03時47分10秒
さて気を取り直して薀蓄篇。いや私じゃなくて著者の薀蓄ですよ(^^;
著者によれば、中国料理は(漢字の特性上)その料理名を見ただけで、どんな料理(調理)か一目瞭然になっているのだといいます。
たとえば「炒」は「強火で炒める」という意味です。したがって炒飯は、「ご飯を強火で炒める」料理法だとわかる。実際は炒飯とだけ表現される料理はない。ご飯だけ炒めても料理にはなりません。他の食材とあわせて「鶏丁炒飯」や「蟹肉炒飯」という形で表されます。
「鶏丁炒飯」とは、「鶏肉」を「さいの目に切って」「強火で炒めた」「ご飯」という意味です。(たしかに豆腐は一丁二丁と数えますね。さいの目に切ってあるからなんでしょうね)
「絲」は「千切り」の意味です。したがって「青椒牛肉絲」(チンジャオロース)は「牛肉細切りピーマン炒め」となる。

なるほどねえ。まさに一目瞭然で意味が頭に入ってきます。あ、これって、ディープラーニングと同じ原理ですよね。としますと中国人は、古来、AIのように思考していたのでしょうか(^^;
いやまあそれはそれとして、コルトレーンの「Selflessness」は漢字なら「無私」となるわけで、表音文字より数倍理解が早くなるのは間違いなさそうですね。山田正紀の「神語」は、関係代名詞を重層させることで理解のスピードアップ化をはかるものだったと思いますが、「漢語」も負けてないような(^^;
お話もどして――
それでは芙蓉蟹(フーヨーハイ)はどうでしょう。著者の考察の過程はすっ飛ばして、結論をいいますと、「芙蓉」は元来花の名前で、白い花です。芙蓉蟹のレシピにはふたつの流派(?)があって、ひとつは卵白を使う調理法、もうひとつは全卵を使う調理法。
現在の天津飯の具である芙蓉蟹は、後者ですね。
著者は調査の結果、前者の記述は本場中国での調理法で、後者は日本でアレンジされた家庭料理としての調理法だろうと結論します。
家庭料理では、卵白料理だと黄身が余ってしまう。黄身を使う別の献立を考えなければならない。料理店ならいろいろ使い道があるでしょうが、家庭ではなかなかそうは行きません。
棄ててしまうようなそんな無駄はできないから、本来白身あんかけであった芙蓉蟹を全卵で作るようになったのではないかというのが著者の推理で、その結果、漢語としての「芙蓉」の意味が歪められてしまった。
逆に言えば、漢語の意味が歪められたことから、この芙蓉蟹が日本でのアレンジであることが確定されるのですねえ!
ちなみに黄身であんを作る場合は、本場では「桂花」と呼ぶらしいです(桂花は木犀の花の意味)。漢語は厳密なんですね。
「天津飯の謎」読了 投稿者:管理人 投稿日:2018年12月15日(土)22時13分20秒
天津飯の天津とは何かを調べる著者ですが、なかなか核心に迫れません。
芙蓉蟹という料理があることはわかりました。しかし戦前のそれは、いわゆるかに玉で、あんはかかっていなかった(むしろ西洋のオムレツに近いものだった)。
そんなとき、著者は銀座アスター開店当時のメニュー表を入手します。
銀座アスターは現在も続く中華料理の老舗銘店です。創業は1926年(昭和元年)です。そのメニュー表に、なんと「天津麺」という料理が載っていたのです! 天津飯の前に、天津麺が文献調査によって見つかったわけです。
そのお品書きの「天津麺」の下には、「蟹・玉子入りそば」と説明書きがあったのですが、いかんせんメニュー表ですから詳しいレシピが判明したわけではありません。
その後、一年前の1925年(大正14)の、当時のミシュランガイド的な本に、日本橋本石町の海曄軒が紹介されていて、評判の品として「天津麺」が挙げられていることも分かりました(但しレシピは不明)。
何はともあれ、大正末年から昭和初年にかけて、「天津麺」という料理が確かに存在していたわけです。
しかし、その後は再び、天津麺の品名は、当時の文献から姿を消してしまうのですね。そして次に天津麺が文献に現れるのは、それから30年ちかくあいた戦後の1952年(昭和27)でした。
著者は考えます。昭和初年には存在した料理が途中姿を消し、昭和27年に再び世に現れる。そこには何か外在的な原因があるはずだ。
天津飯ではなく天津麺ですから、米は関係ありません。麺か卵か蟹です。また逆に天津飯という料理が現在あるわけですから、麺も消去です。では卵なのか、それとも蟹なのか……
天津とあるからには、卵にしても蟹にしても、天津産のそれでなければなりません。
まず蟹。調べたところ天津から蟹が日本に輸出されたという記録は存在しなかった。消去。
では卵か?
ピンポン!
戦前の天津の「在留邦人職業別統計」によって、「鶏卵輸出業」の会社が4社存在したことが判明したのです。
卵は日本に輸出されていました。卵みたいな足の短い食材が、戦前戦後の、航空便などあるはずもない、船便で日本に送られてきて大丈夫なのか。これは私も目からうろこでした。大丈夫だったのです。それには日本の商社の営業努力があった。現地に一時保管用の製氷冷蔵庫を設置し、日本への配送に冷蔵船まで手配したとのこと。
もちろんそこまでするのは、儲かったからですね。そこまでやっても日本産の卵より安価に販売できた。最盛期には、実に日本人の消費量の3分の1を中国からの輸入でまかなっていたと著者は書いています。
当初は上海産が主力だったのですが、大正8年に関税が撤廃されてからは、天津産に比重が移った。ピークは大正12年で、この頃は卵といえば天津卵を日本人はイメージしたのかもしれません。しかし国内業者を圧迫したため、翌年(大正13)関税が復活、採算が合わなくなり1931年(昭和6)に鶏卵の輸入は停止します。
上記したように天津麺は大正14年と昭和元年にその存在が確認されましたが、その後はぱったりと記事を見なくなります。
これは天津卵の輸入の消長と軌を一にしているといえる。つまり天津卵のおかげで卵が安価だったとき、天津麺という日本的にアレンジされた中華料理が創案されたのだけれど、輸入卵が関税で高くなった結果、メニュー自体がなくなってしまったと考えると平仄が合う。
以後は卵は高級食材となります。たしかに、当板をご覧の皆さんは経験あると思いますが、卵は運動会のときとか、風邪を引いたときしか口にできなかったじゃないですか(^^;。
卵が今日のように安価に手に入るようになるのは、1962年(昭和37)に大暴落して一個17円(ワンパック170円)になってからです。以後は安値安定で現在に至るわけですが、昭和27年ですでにぐんと値下がりしてますよね。
上記のように昭和27年に天津麺が復活したのは、やはり卵の価格が、ようやく芙蓉蟹を供するに適当な価格(あくまで料理店的には、ですが)にまで下がってきた結果だろうと著者は推理します。

こうして、天津麺という日本アレンジ料理が、生まれるや否や姿を消し、30年後に復活するに至った理由と、なぜ「天津」なのかの謎が解明されたことになります。
いや天津麺じゃなくて、天津飯の謎じゃなかったのかって?
だから、雫石さんがおっしゃっているではないですか。
「天津飯があんねんから、天津ラーメンもあってもええやろ」
実際は逆で、「天津麺があんねんから、天津飯もあってもええやろ」だったわけですね(^^; いずれにしましても、アレンジ好きの日本人なら当然考えつきますよね。
著者は、「天津飯が誕生したのは1960年代(昭和35年~昭和44年)」とします。やはり卵大暴落の昭和37年前後からということですね。
当感想文の冒頭に記しましたように、私が生まれて初めて天津飯なる中華料理を食したのが、高校に入学した昭和46年です。それまで食べたことがなかったのもむべなるかな。出来立てのほやほやの料理だったのですね(^^;
さて、江戸時代に始まり現代に至る、天津飯の謎をめぐるながいながい旅も、愈々終わりに近づいてきました。
あ、いま気が付きましたが、芙蓉蟹があんかけになった経緯を書き忘れていますね。いまさら書き足すのも面倒なので、ぜひ本書に当たって確認してください。
ということで、早川貴正『天津飯の謎』(2018)、読了です。
 【Amazon】
【Amazon】
「天津飯の謎」 投稿者:管理人 投稿日:2018年12月 2日(日)16時36分43秒
そうそう。昨日は同期生から著書をいただいたのでした。

自費出版本で(文春新書みたい!)、彼がのたまうに、天津飯という料理が本場中国にはないことは知っていると思う(>知りませんでした)(汗)。その名前の由来についてはネットでもあまた説が出ているが、全部間違いである。本書はそれを質し、ある仮説を提出したもの、とのこと(^^;
面白そう(^^)。『ランドスケープと夏の定理』を読み終わったら、さっそく着手しようと思います!
Re: 「天津飯の謎」 投稿者:雫石鉄也 投稿日:2018年12月 3日(月)09時59分32秒
この本、面白そうですね。
天津飯、確かに日本生まれだそうですね。
天津飯があんねんから、天津ラーメンもあってもええやろと
思って作りました。
https://blog.goo.ne.jp/totuzen703/e/50f562aaa6244c91fcba8d477da1319a
おいしかったですよ。
Re: 「天津飯の謎」 投稿者:管理人 投稿日:2018年12月 3日(月)19時12分53秒
雫石さん
>天津飯があんねんから、天津ラーメンもあってもええやろと
雫石さんのと同じかどうかわかりませんが、天津麺もうまいですよね。
ところで冒頭を下に掲げますが、著者の疑問はカツ丼みたく[材料+ごはん]という命名が一般的な中で、[米産地+ごはん]はいかにも不自然というのが出発点だったみたいですね。
そこで、雫石さんの書き込みの、天津麺(天津ラーメン)です。天津飯の「天津」が米産地から来ているのなら、天津麺は[米産地+麺]ということになり、まったく意味が通らなくなってしまいますよね(^^;
これは通説が誤りであることの強力な傍証になるのではないでしょうか。もしかしたら著者は気がついてないかもしれません。今度教えてあげようと思います!

あ、アマゾンに反映されていました→
 〔amazon〕
〔amazon〕「天津飯の謎」に着手 投稿者:管理人 投稿日:2018年12月 8日(土)22時33分19秒
という次第で、『天津飯の謎』に着手しました。
冒頭です。
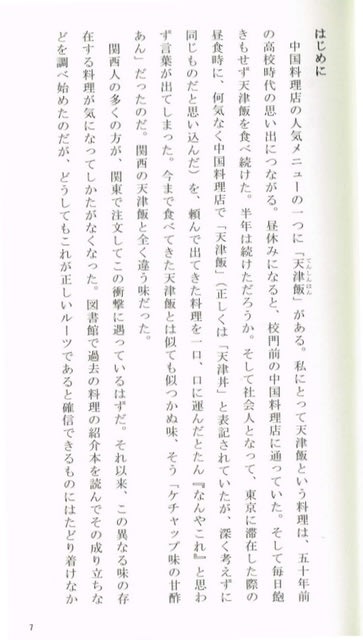
ちょっとびっくりしました。この店、私もよく利用していたのです。著者と一緒に行った記憶はありませんが、私も行けば必ず天津飯を注文していたと思います。
というか、この店ではじめて天津飯なる中華料理を知ったというべきでしょう。そのことについては、以前、当掲示板に書き込んだ記憶があり、検索したのですが発見できず。掲示板の欠点は検索性の悪さなんですよね。書き込みにおいて管理人と訪問者の差別がないところが気に入っていて、それでブログに移行せず使いつづけているのですが。
話が端からそれてしまいました。この店の天津飯がうまかったというのは、実は先日のクラブOB会でも出まして、してみますとこの中華店、よほど天津飯がおいしい店だったのかもしれませんね。
今はもう建物ごとありません。ゼロ年代にはまだ店はありましたが、営業していなかったかも。いずれにしろ、もはやその味を検証できないのです。残念です(^^;
さて本書ですが、天津産の小站米が輸入されていたかどうかを調査しています。この部分、本格的でして、事実上戦前戦後の日本の米輸入史といってよいほど。
結論だけいえば、ジャポニカ米である小站米は当時の天津近辺の在留日本人だけで消費されてしまって、日本本土に輸出する余分はなかったようです。逆に言えば、それだけ日本人が軍人民間人合わせて大量に北京天津辺に進出していたということなんでしょうね。
上田早夕里『破滅の王』で通州事件が描かれていましたが、現地の人にすれば、もともと有数の人口地帯に、大量の日本人の到来は、邪魔で邪魔で仕方なかったんだろうな、とこの事実からでも想像されます(満蒙開拓団も、実は満蒙の荒蕪地を自分らで開拓したのではなく、既に農耕地となっている土地の住民をそっちに追い出し、居座ったというのが事実で、おそらく通州辺りでもそういうことをしていたのだろうと思いますね)。
今でこそ米余りの日本ですが、実は戦後、昭和29・30年をピークに、昭和34年まで米は輸入されていたとのこと。多くは東南アジアからの輸入で、つまりインディカ米だったわけです。平成5年の米の緊急輸入でタイ米が嫌われて売れなかったことはいまだに記憶に新しいですが、わずか数十年で過去を忘れてしまう日本人の驕りは、ほんと、どうしようもないですね。
「天津飯の謎」(2) 投稿者:管理人 投稿日:2018年12月 9日(日)17時38分34秒
第二章は「天津飯は誰が作ったのか」。
まずウィキペディア記載の「発祥」の二説が、「記述の論理的検証」によって退けられます(まずウィキペディアの記述をお読み下さい)
「来々軒説」について、この記述中のどこにも、この料理に「なぜ天津という名前が付くのか」「この部分の説明がまったくない」ことを指摘する。たしかにこれでは説明になっていませんね。著者は親切にも「天津の根拠は前述の、米の名前から名づけられたということなのかもしれない」と好意的に推測しますが、たとえそうだとしても、天津から米が輸入されたことがないという著者の調査の結果から、この説は否定されます。
「大正軒説」についても、「天津の食習慣である「蓋飯」」という記述が疑われる。なぜなら江南ならぬ華北(河北)で「米食(飯食)」が習慣であった事実がないからです。かれらの主食は「米ではなくトウモロコシや小麦」なんですからねえ。
その派生として、華北内蒙古からの引揚者が、船待ちの天津で食べた料理説があり(たしか梅棹忠夫も天津から引揚げたと記憶しています。北満外蒙古からの引揚者はナホトカに集約されましたが。華北方面は天津がそういう港だったんでしょうね)、しかし著者は、困窮した引揚者にそんなものを食う金銭的余裕はなかったはずといいます。たしかに、「黒パン俘虜記」でも主人公はすべてを港で奪われ、着の身着のままでようやく乗船するのですし、配給される食事は(ロシアですから)黒パン。天津でも米作りはそもそも日本人農民が従事していたはずで、彼らも引揚げに大童で農耕などしているはずがない。配給されるのはアワとかヒエとかムギの携帯食で、というのは想像ですが、少なくとも米の白ご飯にかに玉をのせたあんかけ料理なんて夢のまた夢だったのではないでしょうか。てことでこの説もX。
「天津飯の謎」(3) 投稿者:管理人 投稿日:2018年12月 9日(日)23時19分48秒
いよいよ天津飯そのものに話は向かいます。
もっとも著者は常に「そもそも」から解き明かしていきますので、まずは「そもそも中国料理はいつから日本で食べられはじめたか」が調べられる。
当然江戸時代ということになります。鎖国日本は唯一長崎出島でオランダと通商していたわけですが、実はもう一つ窓口があり、それが中国貿易だった。同じ長崎に「唐人屋敷」が建てられ規模はオランダ人の出島より大きかった(年間5千人が利用した)。唐人屋敷ができる以前は船宿と呼ばれる民家に散宿していたので、日本人とも交流があり、そのときに中国料理が、まあ初めて伝えられたとされているようです(とはいえそれ以前に宣教師が「南蛮料理」を伝えています)。
しかし本格的に入ってきたのは開国後。各地にできた「居留地」にやってくる外国人は、実質中国(香港、広東、上海)からの貿易商人なので、それに付随して中国人が船乗りやコックとして(同時に漢字筆談できるので通訳として)やってき、居留地に隣接する土地に住みつく。最初は中国人向けの料理店だったのが、居留地が廃止(1899)されてからは一般日本人相手の店となる。「中華街」のはじまりですね。(強引に約めた要約です。きちんと知りたい人は本書で確認下さい)
「天津飯の謎」(4) 投稿者:管理人 投稿日:2018年12月10日(月)18時56分43秒
初期の中国料理店は、現在の梅田の新北京のような、大人数が円卓を囲み、宴会場として利用する体の店だったようで、1882年(明治15)開店の日本橋の偕楽園がその嚆矢だった。以降、続々と類似店が生まれたのですが、日清戦争勃発(1894年)で多くの中国人が帰国してしまう。
その結果、在留中国人向けではない、日本人むけの中国料理店が増加します。これらは宴会目的ではない、小規模な一般客相手の店です。たぶん現在日本各地津々浦々にある「中国料理」店をイメージすればいいのではないでしょうか。こうして中国料理が国民に広く知られるようになります。
さらに日清戦争が終結し、日本は台湾を獲得すると共に、天津や漢口、杭州、上海※などに日本人租界を認めさせたのでしたが(上海租界は日清戦争以前、南京条約で獲得)、空前の中国料理(支那料理)ブームが起こり、家庭で作られる料理となっていく。
そういう次第で、この時代は中国料理レシピ本が多く出版された。著者はそれらも調査していて、当時の中国料理レシピ本を見る限りでは、天津飯に当てはまる料理は紹介されていなかったとします。
「やはり天津飯は、戦前には存在せず、戦後に生まれたものかもしれない」
それでもなお、後の天津飯につながるものはないかと、「蟹」や「蝦」や「卵」を使った料理をピックアップします。
そのレシピが具体的に紹介されていますので、料理に興味ある方は、掲載のレシピにもとづいて、戦前日本における家庭むき中国料理を作って見られるのも一興かと思います(^^;
※追記。そういえば、日本人租界があった天津、漢口、杭州、上海って、広義に見ればいわゆる中華料理の大きな流派、北京料理・四川料理・広東料理・上海料理の原産地ですよね(^^;
「天津飯の謎」(5) 投稿者:管理人 投稿日:2018年12月11日(火)00時32分51秒
著者は一々のレシピを丹念に確認していくのですが、これは多分に著者の趣味ですね(>おい)。私は作るほうにはさほど興味がないのでその要約は割愛させていただきます。
結局、「明治の終わりから大正にかけて、既に蟹と卵を使う料理は、家庭料理として一般的な料理となっていたと推測される」のですが、しかしそれらはどうみても「オムレツ」の変種なんですね(ケチャップやソースをかけたりする)。
そこで著者は、この時代の蟹と卵を使う中華料理は、実は西洋料理の影響下に日本で生まれたのではないかと考えているようです。「西洋料理の支那化」
よくいわれるように、日本のカレーはインド料理の日本化です。同じことがここでも起こったのではないでしょうか。支那料理を日本風にアレンジするに際して西洋料理が利用されたのではないか。これは本書に(ここまでのところでは)明示的ではなく、私の想像であることをお断りするのですが(でも、著者もたぶん内心そう考えているように、私には読めるのですけどね)、もしそれが正しいとしますと、当時の本場の中国料理に、西洋のオムレツ的な料理があったのかなかったのか、それを確認しなければなりません。そこまで深入りする気はないので、今度著者に会ったとき訊ねてみようと思います(^^;
さて、大正14年に至りますと、ようやく「現在の「芙蓉蟹(フーヨーハイ)」として知られるレシピと、あんの有無以外は大変よく似ている」調理法が現れます。料理名も「芙蓉蟹」です。昭和2年発行の本にも紹介されており、「この頃にはよく知られた料理になっていたと思われる」。
さらにその10年後、昭和12年の本で紹介されている「芙蓉蟹粉」という料理は、卵焼きの上から「あん」のかかったもので、これは現在のそれに最も近いものになっていたようです。
「天津飯はどの料理の紹介本にものっていなかったが」「その具にあたる「芙蓉蟹」は多くの本で紹介されており、この料理は多くの人に広く知られた存在となっていたようだ」
以下更に考証は続くのですが、省略。ここでは、天津飯の具に当たる料理が大正末期には存在していたことのみ確認して、次に進みます。
「天津飯の謎」(6) 投稿者:管理人 投稿日:2018年12月14日(金)03時47分10秒
さて気を取り直して薀蓄篇。いや私じゃなくて著者の薀蓄ですよ(^^;
著者によれば、中国料理は(漢字の特性上)その料理名を見ただけで、どんな料理(調理)か一目瞭然になっているのだといいます。
たとえば「炒」は「強火で炒める」という意味です。したがって炒飯は、「ご飯を強火で炒める」料理法だとわかる。実際は炒飯とだけ表現される料理はない。ご飯だけ炒めても料理にはなりません。他の食材とあわせて「鶏丁炒飯」や「蟹肉炒飯」という形で表されます。
「鶏丁炒飯」とは、「鶏肉」を「さいの目に切って」「強火で炒めた」「ご飯」という意味です。(たしかに豆腐は一丁二丁と数えますね。さいの目に切ってあるからなんでしょうね)
「絲」は「千切り」の意味です。したがって「青椒牛肉絲」(チンジャオロース)は「牛肉細切りピーマン炒め」となる。

なるほどねえ。まさに一目瞭然で意味が頭に入ってきます。あ、これって、ディープラーニングと同じ原理ですよね。としますと中国人は、古来、AIのように思考していたのでしょうか(^^;
いやまあそれはそれとして、コルトレーンの「Selflessness」は漢字なら「無私」となるわけで、表音文字より数倍理解が早くなるのは間違いなさそうですね。山田正紀の「神語」は、関係代名詞を重層させることで理解のスピードアップ化をはかるものだったと思いますが、「漢語」も負けてないような(^^;
お話もどして――
それでは芙蓉蟹(フーヨーハイ)はどうでしょう。著者の考察の過程はすっ飛ばして、結論をいいますと、「芙蓉」は元来花の名前で、白い花です。芙蓉蟹のレシピにはふたつの流派(?)があって、ひとつは卵白を使う調理法、もうひとつは全卵を使う調理法。
現在の天津飯の具である芙蓉蟹は、後者ですね。
著者は調査の結果、前者の記述は本場中国での調理法で、後者は日本でアレンジされた家庭料理としての調理法だろうと結論します。
家庭料理では、卵白料理だと黄身が余ってしまう。黄身を使う別の献立を考えなければならない。料理店ならいろいろ使い道があるでしょうが、家庭ではなかなかそうは行きません。
棄ててしまうようなそんな無駄はできないから、本来白身あんかけであった芙蓉蟹を全卵で作るようになったのではないかというのが著者の推理で、その結果、漢語としての「芙蓉」の意味が歪められてしまった。
逆に言えば、漢語の意味が歪められたことから、この芙蓉蟹が日本でのアレンジであることが確定されるのですねえ!
ちなみに黄身であんを作る場合は、本場では「桂花」と呼ぶらしいです(桂花は木犀の花の意味)。漢語は厳密なんですね。
「天津飯の謎」読了 投稿者:管理人 投稿日:2018年12月15日(土)22時13分20秒
天津飯の天津とは何かを調べる著者ですが、なかなか核心に迫れません。
芙蓉蟹という料理があることはわかりました。しかし戦前のそれは、いわゆるかに玉で、あんはかかっていなかった(むしろ西洋のオムレツに近いものだった)。
そんなとき、著者は銀座アスター開店当時のメニュー表を入手します。
銀座アスターは現在も続く中華料理の老舗銘店です。創業は1926年(昭和元年)です。そのメニュー表に、なんと「天津麺」という料理が載っていたのです! 天津飯の前に、天津麺が文献調査によって見つかったわけです。
そのお品書きの「天津麺」の下には、「蟹・玉子入りそば」と説明書きがあったのですが、いかんせんメニュー表ですから詳しいレシピが判明したわけではありません。
その後、一年前の1925年(大正14)の、当時のミシュランガイド的な本に、日本橋本石町の海曄軒が紹介されていて、評判の品として「天津麺」が挙げられていることも分かりました(但しレシピは不明)。
何はともあれ、大正末年から昭和初年にかけて、「天津麺」という料理が確かに存在していたわけです。
しかし、その後は再び、天津麺の品名は、当時の文献から姿を消してしまうのですね。そして次に天津麺が文献に現れるのは、それから30年ちかくあいた戦後の1952年(昭和27)でした。
著者は考えます。昭和初年には存在した料理が途中姿を消し、昭和27年に再び世に現れる。そこには何か外在的な原因があるはずだ。
天津飯ではなく天津麺ですから、米は関係ありません。麺か卵か蟹です。また逆に天津飯という料理が現在あるわけですから、麺も消去です。では卵なのか、それとも蟹なのか……
天津とあるからには、卵にしても蟹にしても、天津産のそれでなければなりません。
まず蟹。調べたところ天津から蟹が日本に輸出されたという記録は存在しなかった。消去。
では卵か?
ピンポン!
戦前の天津の「在留邦人職業別統計」によって、「鶏卵輸出業」の会社が4社存在したことが判明したのです。
卵は日本に輸出されていました。卵みたいな足の短い食材が、戦前戦後の、航空便などあるはずもない、船便で日本に送られてきて大丈夫なのか。これは私も目からうろこでした。大丈夫だったのです。それには日本の商社の営業努力があった。現地に一時保管用の製氷冷蔵庫を設置し、日本への配送に冷蔵船まで手配したとのこと。
もちろんそこまでするのは、儲かったからですね。そこまでやっても日本産の卵より安価に販売できた。最盛期には、実に日本人の消費量の3分の1を中国からの輸入でまかなっていたと著者は書いています。
当初は上海産が主力だったのですが、大正8年に関税が撤廃されてからは、天津産に比重が移った。ピークは大正12年で、この頃は卵といえば天津卵を日本人はイメージしたのかもしれません。しかし国内業者を圧迫したため、翌年(大正13)関税が復活、採算が合わなくなり1931年(昭和6)に鶏卵の輸入は停止します。
上記したように天津麺は大正14年と昭和元年にその存在が確認されましたが、その後はぱったりと記事を見なくなります。
これは天津卵の輸入の消長と軌を一にしているといえる。つまり天津卵のおかげで卵が安価だったとき、天津麺という日本的にアレンジされた中華料理が創案されたのだけれど、輸入卵が関税で高くなった結果、メニュー自体がなくなってしまったと考えると平仄が合う。
以後は卵は高級食材となります。たしかに、当板をご覧の皆さんは経験あると思いますが、卵は運動会のときとか、風邪を引いたときしか口にできなかったじゃないですか(^^;。
卵が今日のように安価に手に入るようになるのは、1962年(昭和37)に大暴落して一個17円(ワンパック170円)になってからです。以後は安値安定で現在に至るわけですが、昭和27年ですでにぐんと値下がりしてますよね。
上記のように昭和27年に天津麺が復活したのは、やはり卵の価格が、ようやく芙蓉蟹を供するに適当な価格(あくまで料理店的には、ですが)にまで下がってきた結果だろうと著者は推理します。

こうして、天津麺という日本アレンジ料理が、生まれるや否や姿を消し、30年後に復活するに至った理由と、なぜ「天津」なのかの謎が解明されたことになります。
いや天津麺じゃなくて、天津飯の謎じゃなかったのかって?
だから、雫石さんがおっしゃっているではないですか。
「天津飯があんねんから、天津ラーメンもあってもええやろ」
実際は逆で、「天津麺があんねんから、天津飯もあってもええやろ」だったわけですね(^^; いずれにしましても、アレンジ好きの日本人なら当然考えつきますよね。
著者は、「天津飯が誕生したのは1960年代(昭和35年~昭和44年)」とします。やはり卵大暴落の昭和37年前後からということですね。
当感想文の冒頭に記しましたように、私が生まれて初めて天津飯なる中華料理を食したのが、高校に入学した昭和46年です。それまで食べたことがなかったのもむべなるかな。出来立てのほやほやの料理だったのですね(^^;
さて、江戸時代に始まり現代に至る、天津飯の謎をめぐるながいながい旅も、愈々終わりに近づいてきました。
あ、いま気が付きましたが、芙蓉蟹があんかけになった経緯を書き忘れていますね。いまさら書き足すのも面倒なので、ぜひ本書に当たって確認してください。
ということで、早川貴正『天津飯の謎』(2018)、読了です。
 【Amazon】
【Amazon】
















