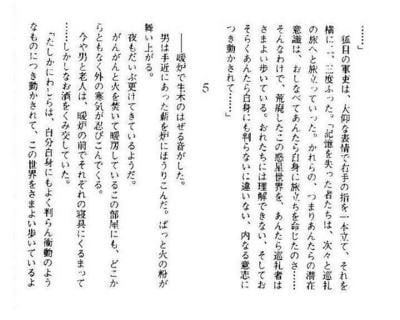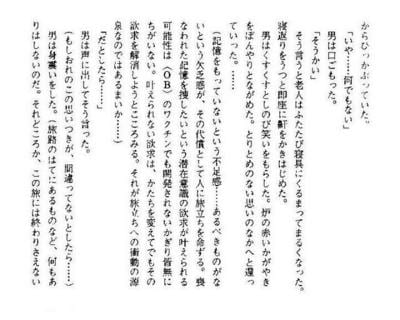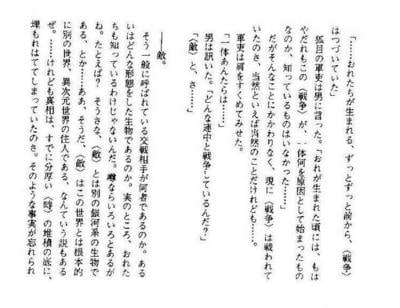木田元『哲学の余白』(新書館、00)
哲学者の木田元が、1997年から1999年にかけて発表した哲学以外の「雑文・書評のたぐい」をまとめたものとのことで、私も気楽に読み始めた。
各種の雑誌に発表された短い文章が「昔を懐かしむということ」、「読書について」、「少しばかり哲学の話も」、「書評のたぐい」、「なんと、山田風太郎を解説する」の5つの章題のもとに纏められている。
最初の「昔を懐かしむということ」には、「専ら鑑賞する方」という趣味の俳句にひっかけた身辺雑記風の文章が並んでいて、軽く読める。ただ軽いといってもそこは木田元の文章である。そこここに著者の思索の片鱗が垣間見られるわけで、たとえば、世にはサルトル・芭蕉型とメルロ=ポンティ・蕪村型の二種類の在り方があるらしい。
前者は過去を振り返らない、というか振り捨てて生きる。後者は過去にとらわれる。「自分は比類のない幼年期からついに癒えないでしまった」(メルロ=ポンティ)。楽園喪失が原体験。
例として芭蕉と蕪村の句を並べて、彼らふたりの対照的な時間性(時間意識?)が示される。
ふるさとや臍の緒に泣としのくれ 芭蕉
遅き日のつもりて遠きむかしかな 蕪村
なるほど。芭蕉にとって過去は痛みなしには振り返られないのに対し、蕪村はのほほん(?)と過去のセピア色を心地よく振り返っている。最初私は後者の句の方を好いと感じたのだったが、初読から数日たった今現在、芭蕉の句の方がずっとすぐれていると思わざるを得ない。前者の鋭さに比べれば後者の感興はやはり凡庸だ。
なぜ最初蕪村の句をよいと感じたのか、それは明らかで、この類型に従えば、私は典型的に後者なのだ。だからSFMを読むと昔のSFMの方がよかったと思うし、今のSFを読むと70年代のSFはよかったなあと懐かしまないではいられない。それが事実かどうかは関係ない。過ぎにし過去にユートピアを「仮構」して、そうして亡くした・追放された楽園を恋しがっている。一事が万事私の意識はそのように働いている。
著者はサルトル・芭蕉型だそうだが、おそらく福島正実もそうだったに違いない。逆にメルロ=ポンティ・蕪村型の人は比較的めぐまれた幼年期を送った人が多いのではないだろうか。前者は過去を忘れたい、ないことにしたい、その意識をバネに前へ前へと進んでいく。それに対して後者の過去は回想の中でどんどん純化され美化されていく。 その意味で今の時代、殆どの人は後者かもしれない。そういえば中学生の子が小学校の卒業アルバムを見て懐かしんでいるらしいではないか。
「読書について」では主に原文を読むことや翻訳について所感が述べられていて、これも興味深い。
「昔は分からないのは自分の頭が悪いからだと思っていたが、近頃はたいていの場合、翻訳が悪いせいだという程度のことは分かるようになった。誤訳というよりは、全体としての文意がつかめないのである。今は辞書も格段によくなったし、語学力も向上しているはずなのに、翻訳が悪くなるとはいうのはどういうことであろう」(85p)として、その理由として、日本語の表現力の衰え、そして仕事に対する怖れ、律儀さがかけているのではないかと指摘する。
なるほどなあ。これは海外SFの翻訳にも当て嵌まる指摘であるな。
さらに続けて、翻訳もひとつの技術であるから、しかるべき訓練が必要で、できればすぐれた訳者の下訳をし添削してもらいながら、正確に読み的確に表現する訓練を一度は受けたほうがよいともおっしゃっている。
しかし一番の問題は「編集者」だと断言する。
「翻訳の良否を判定できる編集者が少なくなったことであろう。昔、組みあがった翻訳に納得できず、一部分を自分で訳して第三者の判定を求め、訳者を替えた編集者がいた。むろん今でも、全文原文と読み合わせ、過不足なく訳文をチェックしてくれる編集者はいる。そうした人間に担当してもらうと、確かによい翻訳ができるものである」(86p)
この編集者の問題は重要だと私も思う。私は英語は読めないけど、そんな私ですら翻訳文を読んでいてこれは誤訳してるんとちゃうか、と思うことがたまにある。最近では『グリュフォンの卵』や 『遺す言葉、その他の短篇』にそれを感じたものだ。具体的にはリンクをたどって確認していただきたいのだが、これらの訳文に私が感じた不満や疑問は、編集者がきちんと仕事をしておりさえすれば防げたものだ。しかも両書は海外文学に強いはずの早川書房からの上梓なのだから、問題は深い。
話がそれた。つづく「少しばかり哲学の話も」には、かなり本格的な論文が収められている。
この章で著者は、哲学とは普遍的な学問だという先入観があるけど、それは違うといっている。これは面白い。
著者によれば、近代哲学の父デカルトの「理性」概念は(我々の日常概念の理性とはぜんぜん違うもので)、実はキリスト教神学の「神」概念と同じ思考様式に属する。どちらもプラトン的「イデア」が変換したものに過ぎない。かかる三者は(外在的な)或る「超自然的」(即ちメタ・フィジックな)原理を設定し、それを参照しながら自然を見るというその思考様式においては同じものだと著者は言う。
この原理から「物質的自然観」が成立し、近代ヨーロッパ文化が(科学的思考も)形成される。
このように「哲学」は人間一般を扱うものに見えて、実は「特殊西欧的」な思考様式に過ぎず、ハイデガーによればそれはたかだかプラトンに始まり下限即ちその終焉もある「歴史的存在」なのだそうだ。
だとすればフーコーの仕事なんて実はハイデガーによって既にやり遂げられていたことになるのではないか? 面白い。
で、著者によればハイデガーは(メルロ=ポンティも)そのような「哲学」を「ぶっこわそう」としていたらしい(反哲学)。SFでいえばニュウェーブであるな。
「私は<反哲学>も含めた広い意味での<哲学>を、現実の外に引かれる補助線のようなものではないかと思っている。それ自体は現実のうちに確たる座を占めることはできないが、それが引かれることによって、現実がまったく違ったふうに見えてくるといったような補助線である。フィクションと言いたければそう言ってもいい。しかし、それは、そのうちに据えることによって現実が思いがけない見え方をしてくるフィクティヴな全体図である」(127p)
この文の「哲学」を「SF」と言い換えれば、まさにSFの本質を言い表した文となる。SFはやはり原理的に「哲学小説」なのだろう。
「書評のたぐい」は文字どおり、新聞や雑誌に掲載された書評集で、本業の哲学から趣味だというミステリまで、幅広く作品が取り上げられている。これが滅法面白い。やはりお座なりな、最大公約数的な書評でなく、著者が読み、そこから触発されたところを自由自在にというか自分の視点で評価しているから、書評だけ読んでも面白いのだろう。
「なんと、山田風太郎を解説する」は、なんと『山田風太郎明治小説全集』(愛蔵版)全巻に著者が書いた解説の集成。ミステリファン、風太郎ファン必読ではなかろうか。
哲学者の木田元が、1997年から1999年にかけて発表した哲学以外の「雑文・書評のたぐい」をまとめたものとのことで、私も気楽に読み始めた。
各種の雑誌に発表された短い文章が「昔を懐かしむということ」、「読書について」、「少しばかり哲学の話も」、「書評のたぐい」、「なんと、山田風太郎を解説する」の5つの章題のもとに纏められている。
最初の「昔を懐かしむということ」には、「専ら鑑賞する方」という趣味の俳句にひっかけた身辺雑記風の文章が並んでいて、軽く読める。ただ軽いといってもそこは木田元の文章である。そこここに著者の思索の片鱗が垣間見られるわけで、たとえば、世にはサルトル・芭蕉型とメルロ=ポンティ・蕪村型の二種類の在り方があるらしい。
前者は過去を振り返らない、というか振り捨てて生きる。後者は過去にとらわれる。「自分は比類のない幼年期からついに癒えないでしまった」(メルロ=ポンティ)。楽園喪失が原体験。
例として芭蕉と蕪村の句を並べて、彼らふたりの対照的な時間性(時間意識?)が示される。
ふるさとや臍の緒に泣としのくれ 芭蕉
遅き日のつもりて遠きむかしかな 蕪村
なるほど。芭蕉にとって過去は痛みなしには振り返られないのに対し、蕪村はのほほん(?)と過去のセピア色を心地よく振り返っている。最初私は後者の句の方を好いと感じたのだったが、初読から数日たった今現在、芭蕉の句の方がずっとすぐれていると思わざるを得ない。前者の鋭さに比べれば後者の感興はやはり凡庸だ。
なぜ最初蕪村の句をよいと感じたのか、それは明らかで、この類型に従えば、私は典型的に後者なのだ。だからSFMを読むと昔のSFMの方がよかったと思うし、今のSFを読むと70年代のSFはよかったなあと懐かしまないではいられない。それが事実かどうかは関係ない。過ぎにし過去にユートピアを「仮構」して、そうして亡くした・追放された楽園を恋しがっている。一事が万事私の意識はそのように働いている。
著者はサルトル・芭蕉型だそうだが、おそらく福島正実もそうだったに違いない。逆にメルロ=ポンティ・蕪村型の人は比較的めぐまれた幼年期を送った人が多いのではないだろうか。前者は過去を忘れたい、ないことにしたい、その意識をバネに前へ前へと進んでいく。それに対して後者の過去は回想の中でどんどん純化され美化されていく。 その意味で今の時代、殆どの人は後者かもしれない。そういえば中学生の子が小学校の卒業アルバムを見て懐かしんでいるらしいではないか。
「読書について」では主に原文を読むことや翻訳について所感が述べられていて、これも興味深い。
「昔は分からないのは自分の頭が悪いからだと思っていたが、近頃はたいていの場合、翻訳が悪いせいだという程度のことは分かるようになった。誤訳というよりは、全体としての文意がつかめないのである。今は辞書も格段によくなったし、語学力も向上しているはずなのに、翻訳が悪くなるとはいうのはどういうことであろう」(85p)として、その理由として、日本語の表現力の衰え、そして仕事に対する怖れ、律儀さがかけているのではないかと指摘する。
なるほどなあ。これは海外SFの翻訳にも当て嵌まる指摘であるな。
さらに続けて、翻訳もひとつの技術であるから、しかるべき訓練が必要で、できればすぐれた訳者の下訳をし添削してもらいながら、正確に読み的確に表現する訓練を一度は受けたほうがよいともおっしゃっている。
しかし一番の問題は「編集者」だと断言する。
「翻訳の良否を判定できる編集者が少なくなったことであろう。昔、組みあがった翻訳に納得できず、一部分を自分で訳して第三者の判定を求め、訳者を替えた編集者がいた。むろん今でも、全文原文と読み合わせ、過不足なく訳文をチェックしてくれる編集者はいる。そうした人間に担当してもらうと、確かによい翻訳ができるものである」(86p)
この編集者の問題は重要だと私も思う。私は英語は読めないけど、そんな私ですら翻訳文を読んでいてこれは誤訳してるんとちゃうか、と思うことがたまにある。最近では『グリュフォンの卵』や 『遺す言葉、その他の短篇』にそれを感じたものだ。具体的にはリンクをたどって確認していただきたいのだが、これらの訳文に私が感じた不満や疑問は、編集者がきちんと仕事をしておりさえすれば防げたものだ。しかも両書は海外文学に強いはずの早川書房からの上梓なのだから、問題は深い。
話がそれた。つづく「少しばかり哲学の話も」には、かなり本格的な論文が収められている。
この章で著者は、哲学とは普遍的な学問だという先入観があるけど、それは違うといっている。これは面白い。
著者によれば、近代哲学の父デカルトの「理性」概念は(我々の日常概念の理性とはぜんぜん違うもので)、実はキリスト教神学の「神」概念と同じ思考様式に属する。どちらもプラトン的「イデア」が変換したものに過ぎない。かかる三者は(外在的な)或る「超自然的」(即ちメタ・フィジックな)原理を設定し、それを参照しながら自然を見るというその思考様式においては同じものだと著者は言う。
この原理から「物質的自然観」が成立し、近代ヨーロッパ文化が(科学的思考も)形成される。
このように「哲学」は人間一般を扱うものに見えて、実は「特殊西欧的」な思考様式に過ぎず、ハイデガーによればそれはたかだかプラトンに始まり下限即ちその終焉もある「歴史的存在」なのだそうだ。
だとすればフーコーの仕事なんて実はハイデガーによって既にやり遂げられていたことになるのではないか? 面白い。
で、著者によればハイデガーは(メルロ=ポンティも)そのような「哲学」を「ぶっこわそう」としていたらしい(反哲学)。SFでいえばニュウェーブであるな。
「私は<反哲学>も含めた広い意味での<哲学>を、現実の外に引かれる補助線のようなものではないかと思っている。それ自体は現実のうちに確たる座を占めることはできないが、それが引かれることによって、現実がまったく違ったふうに見えてくるといったような補助線である。フィクションと言いたければそう言ってもいい。しかし、それは、そのうちに据えることによって現実が思いがけない見え方をしてくるフィクティヴな全体図である」(127p)
この文の「哲学」を「SF」と言い換えれば、まさにSFの本質を言い表した文となる。SFはやはり原理的に「哲学小説」なのだろう。
「書評のたぐい」は文字どおり、新聞や雑誌に掲載された書評集で、本業の哲学から趣味だというミステリまで、幅広く作品が取り上げられている。これが滅法面白い。やはりお座なりな、最大公約数的な書評でなく、著者が読み、そこから触発されたところを自由自在にというか自分の視点で評価しているから、書評だけ読んでも面白いのだろう。
「なんと、山田風太郎を解説する」は、なんと『山田風太郎明治小説全集』(愛蔵版)全巻に著者が書いた解説の集成。ミステリファン、風太郎ファン必読ではなかろうか。










 〈装幀〉中島靖侃
〈装幀〉中島靖侃