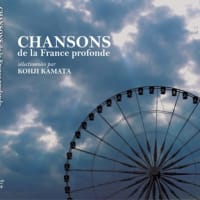クラウディオ・アッバードというと、1981年にスカラ座のカンパニーを引き連れて来日した折りの名演が忘れられない。イタリア・オペラはそれまでにもNHKが何度か上演を主催していて、レナータ・テバルディ、マリオ・デル・モナコといった大物歌手の来日もあったのだが、オーケストラ、コーラスともども名門歌劇場がそっくりやってくる引っ越し公演は、あのときが初めてだった。
アッバードの指揮で『シモン・ボッカネグラ』『セビーリャの理髪師』、カルロス・クライバーの指揮で『オテッロ』『ラ・ボエーム』の4作が上演された(ほかにヴェルディの『レクイエム』も)。プラーシド・ドミンゴ、ミレッラ・フレーニ、ピエーロ・カップッチッリら当時最高ランクの名歌手が参加していた。日本がバブルに向かって急成長を続けていた時代の、いまは夢の贅沢。
世評がいちばん高かったのはクライバーの『オテッロ』だったが、手許に残った録音テープを聴くと、アッバードの『理髪師』が歌手の顔ぶれに凹んだところがなく、オーケストラ、コーラスとも生気にみちあふれ、一分の隙もない超名演だったことが分かる。
リズムは常に前ノリで生き生きと弾み、すべての音が朝日を受けた海の波のようにキラキラ光っている。早世した名メッゾ・ソプラノ、ルチーア・ヴァレンティーニ=テッラーニが藍色のビロードのような声でE難度の技巧的装飾楽句を軽やかに歌ってのける。
この演奏を聴いた後は、もはやどんな『理髪師』の録音も死んだような演奏に聞こえてしまう。マリア・カラス主演の全曲盤は無論、アッバード自身のスタジオ録音も例外ではない。アッバードはライヴ演奏ではすばらしいノリを示すが、スタジオに入ると途端にカミシモ着けたような演奏をする人だったのだ。ていねいで羽目を外さない。『理髪師』だけではなく、『シモン』も『アイーダ』もそう。
ともあれ、ベッリーニやヴェルディ初期のカンティレーナの美しさをあれだけ理解し、あれだけ洗練された形で呈示できた指揮者はそれまでいなかった。今後も出てこないんじゃないかな。晩年はムソルグスキーとかベルクとか、つまんないオペラばかり取り上げていたが。
なお、アバドという呼び方は日本独特で、こんな発音をしても外国人には通じない。多分、アッバード本人にも通じなかっただろう。ゲーテのひそみに倣えば、アバドとは俺のことかとアッバード言い、だ。
日本の音楽界は、映画界でも同じだが、外国人名をだれかが最初に適当に、いい加減に読んで表記すると、レコード会社、プロモーター、評論家から雑誌、新聞、ネットまで、あらゆるメディアがその適当な読み方に追随してしまう。朝日、NHKなどのマスコミが率先してこれをやる。世間で通用している読み方だから、ではなく、真剣勝負でアーティストを評価する気構えを欠いているからだ。
こうした怠慢、思考停止型大勢順応に敢然と抵抗したのが、故・中村とうよう氏だった。
アッバードの指揮で『シモン・ボッカネグラ』『セビーリャの理髪師』、カルロス・クライバーの指揮で『オテッロ』『ラ・ボエーム』の4作が上演された(ほかにヴェルディの『レクイエム』も)。プラーシド・ドミンゴ、ミレッラ・フレーニ、ピエーロ・カップッチッリら当時最高ランクの名歌手が参加していた。日本がバブルに向かって急成長を続けていた時代の、いまは夢の贅沢。
世評がいちばん高かったのはクライバーの『オテッロ』だったが、手許に残った録音テープを聴くと、アッバードの『理髪師』が歌手の顔ぶれに凹んだところがなく、オーケストラ、コーラスとも生気にみちあふれ、一分の隙もない超名演だったことが分かる。
リズムは常に前ノリで生き生きと弾み、すべての音が朝日を受けた海の波のようにキラキラ光っている。早世した名メッゾ・ソプラノ、ルチーア・ヴァレンティーニ=テッラーニが藍色のビロードのような声でE難度の技巧的装飾楽句を軽やかに歌ってのける。
この演奏を聴いた後は、もはやどんな『理髪師』の録音も死んだような演奏に聞こえてしまう。マリア・カラス主演の全曲盤は無論、アッバード自身のスタジオ録音も例外ではない。アッバードはライヴ演奏ではすばらしいノリを示すが、スタジオに入ると途端にカミシモ着けたような演奏をする人だったのだ。ていねいで羽目を外さない。『理髪師』だけではなく、『シモン』も『アイーダ』もそう。
ともあれ、ベッリーニやヴェルディ初期のカンティレーナの美しさをあれだけ理解し、あれだけ洗練された形で呈示できた指揮者はそれまでいなかった。今後も出てこないんじゃないかな。晩年はムソルグスキーとかベルクとか、つまんないオペラばかり取り上げていたが。
なお、アバドという呼び方は日本独特で、こんな発音をしても外国人には通じない。多分、アッバード本人にも通じなかっただろう。ゲーテのひそみに倣えば、アバドとは俺のことかとアッバード言い、だ。
日本の音楽界は、映画界でも同じだが、外国人名をだれかが最初に適当に、いい加減に読んで表記すると、レコード会社、プロモーター、評論家から雑誌、新聞、ネットまで、あらゆるメディアがその適当な読み方に追随してしまう。朝日、NHKなどのマスコミが率先してこれをやる。世間で通用している読み方だから、ではなく、真剣勝負でアーティストを評価する気構えを欠いているからだ。
こうした怠慢、思考停止型大勢順応に敢然と抵抗したのが、故・中村とうよう氏だった。